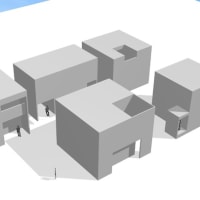最近は外壁を左官仕上げとする場合、その下地に合板が使われるが、ここでは昔ながらの「木ずり」下地としている。
木ずり下地とは、杉板を隙間を空けて打ち付けてゆくものだが、昔は「通気工法」というものがなかったので、軸組の上にそのまま木ずりを打って、アスファルトフェルト、ラス網、モルタルという感じで仕上げて行った。断熱などあまり考えていなかった時代はこれで問題はなかった。
今は通気胴縁を打って、その上に合板を張り、塗り下地とするのが一般的である。しかし、窓廻りなど通気が塞がり易い箇所では通気胴縁を切って横に流れる様に対処するが、実際には通気が塞がってしまう箇所が多々発生する。そういう箇所は湿気の逃げ道がないので次第に腐食菌やカビが発生し、木造住宅の寿命を縮めてしまうことになる。
通気胴縁の上に木ずり下地とした場合、常に縦横に通気が取れる状態になるので、こうした通気が塞がる箇所が発生し難いのである。
日本の伝統的な木造技術というのは、如何に湿気を溜めないか、ということに腐心した技術だった。残念ながら今は、そうした伝統の知恵が活かされていない家づくりが目立つ。

家づくりをはじめるなら:高断熱デザイン住宅お任せnetを覗いてみよう!
にほんブログ村
↑クリックしてね