




































(十) 誰が袖 Tagasode
ニューヨークの公園で一度リス(栗鼠)を見かけたことがある。
リスだとは分かるが、しかしよく観察してもアメリカシマリスとニホンリスの違いが見出せなかった。
リスには、樹上性リス(滑空する種も含む)と地上に住むジリスの、異なる2タイプがある。シマリス類は、樹上生リスとジリスの中間的な存在であり、主に地上で暮らすが、木登りも巧みである。また、愛玩動物として飼育されている種も、環境適応力が高い事などを理由にシマリス属が多い。それゆえ近年、飼育環境から逃げ出したアメリカシマリスによる日本国内の生態系の乱れが懸念されている。
矛盾に満ちた時代のきしみが小動物の世界にも現れているようだ。
「 残念ながら、私にはニューヨーク市街の奥に蠢(うご)く底意地のようなものは、わからない。おそらくはアメリカの坩堝(るつぼ)の中にひそむ森のようなものが私の意識の奥底で掴めていないからだろう。私には古事記や日本書記や万葉集が示した日本人らしき意識の意味は分かっても、アメリカ合衆国という多民族がクロスした意識はかんじんのところが掴めない・・・・・ 」
幽・キホーテは、同じく太平洋戦争(日本では大東亜戦争)をおこしたアメリカと日本でありながら、その体験における決定的な差異というものを感じてきた。二国の本心もきっとそうであるはずだ。アメリカや日本がきっと沖縄を理解するには、この差異にまで深入りすることが要請されるにちがいない。比江島修治が久高島の闇に落ちた彗星を憂うということは、そういうことなのであった。



二人を乗せた早朝のバスは三条駅方面へと向かった。
万葉といえば、桜ではあるが、愛しきその最たるものは、冬のサクラである。
虎哉にはそう想われる。
「 桜木が最初に兆す花芽の、貧しくとも命弾けるその産声を聞くと、来る春を知り冬の過酷さを怨んだりはしない・・・・・ 」
散る花は怨みがましくさせる。
美しくなくとも愛しい花に巡り逢いたいと思う。
奈良坂を越えるにあたって雨田虎哉はそう願いたいのだ。
「 たぐひなき花をし枝に咲かすれば桜に並ぶ木ぞなかりける 」
と、西行は詠んで、素直に桜を筆頭にあげた。
百花繚乱あるなかに「なかりける」とは、桜もひどく惚れられたものだ。奈良に生まれた雨田虎哉も桜への傾倒は断然であった。80を過ぎた今もなお、佐保川の桜木が眼に焼き付いている。
「 だが・・・・・、未だ桜と無理心中とまではいかない・・・・・ 」
「 散る花を惜しむ心やとどまりて 又来む春の誰になるべき 」
と、さらに西行は詠むが、しかし虎哉の桜は、冬枯れて立つ葉のなき一樹が最も好ましく思われた。
一つ、二つ、三つとしだいに満ちる花芽つく趣にこそ、やがて豊かな満開に人が近づける夢がある。

「 西行は、咲き初めてから花が散り、ついに葉桜にいたって若葉で覆われるまで、ほとんどどんな姿の桜も詠んでいるのだが、そのなかで私がどんな歌の花に心を動かされるかというと、これは毎年決まっていた・・・・・ 」
それは花を想って花から離れられずにいるのに、花のほうは今年も容赦なく去っていくという消息を詠んだ歌こそが、やはり極上の西行なのだ。奈良に生まれたからそう思うのか。虎哉はいつも、そういう歌に名状しがたい感情を揺さぶられ、突き上げられ、そこにのみ行方知らずの消息をおぼえてきた。
「 私の、その行方なき消息は、決まって花芽なき冬の桜木から始まるのだ。毎年、一雨、また二雨が来て、あゝもう花冷えか、もう落花狼藉なのかと思っていると、なんだか急に落ち着けない気分になってくる・・・・・ 」
それは、寂しいというほどではなく、何か虎哉に「 欠けるもの 」が感じられて、とたんに所在がなくなるのである。
どうして貧しいのか。何が欠けたのか。そしてそういう欠けた気分になると、決まって西行の歌を思い出すのであった。西行は人の辿りつくあこがれをみごとに描いてくれた。奈良の山は、西行がみると仏の山となる。
「 梢うつ雨にしをれて散る花の 惜しき心を何にたとへむ 」
と、バスが一乗寺へと向かうと、あちこちの葉のない桜木が北風のなかで明るく悄然としていた。
静かに花芽だけを萌やそうとして懸命に凍える風の枝にしがみついている。その姿が次々に車窓の向こうを走るようになってくると、虎哉は、あゝ、今年もまた奈良の桜も、こゝから始まるのだなと思う。すると虎哉の眼には鮮やかに泛かんでくるものがあった。
「 あゝ、在所の山に佐保の桜がみえる。そしてあの、人形の姿が・・・・・ 」
それは、香織であるかさねの姿に似ているからだけではない。やはり何か欠けたものを感じる虎哉にとって、雨の日の自動車が、あのようにアスファルトに散った桜の花びらを轢きしめていくのが何んともいえぬ「哀切」であるように、遠い日を引き戻すそれは忘れ難き人形であった。そうして香織と同じ年齢の白い手に抱かれた人形であったことを覚え重ねて泛かべるほどに、悲しみが深く静かに噴き上げてきた。

「 話しても、かめしまへんやろか・・・・・ 」
そういう香織は、青白くある虎哉の頬が気になり、やはりバスの揺れは障るのか、思いなしか虎哉が急にやつれたようにみえる。だから静かに覗くように声をかけた。
無言のまゝ虎哉が振り向くと、口はしの笑窪をみせた顔がある。
屈託のない香織の顔を見せられると、さらに心残りの面影に弾みがついて、ふと香織の笑みに過ぎるかの一筋の翳かげをみ覚えた。そしてしだいにその翳は虎哉の裡にじんわりと沁みてくる。すると雨田家に嫁ぐ日の、今は亡き妻香代の花嫁姿がその翳のうしろに重なり合うように立っていた。
そのようにしてバスが百万遍の交差点にさしかかると、さらにその翳は色濃くなってくる。
百万遍から銀閣寺までは香代と一度だけ歩いた道なのだ。
二人して歩いた道は、虎哉の中にその記憶しかない。虎哉は香織の背後でかげろうその翳の揺らぎに、亡き香代が影となって還って来ていることを覚さとった。
「 何やな・・・・・だんだんに青うなりはッて、老先生、脚ィ痛いんやないか・・・・・ 」
やはりどうしても顔色が気がかりになる。そんな香織は、不安気に虎哉をみてそっと訊いてみた。
しかし虎哉はじっと妻香代の翳と寄り添っていた。
京の市井には、新婦が男児の人形を抱いて嫁入りするという慣習があった。それは嫁(か)しては男児を儲けて一家の繁栄をはかるという女の心得を訓ずるものである。家同士が定めた縁組により、お互いは一度も会ったことのない婚儀が当時の常であった。
虎哉の場合も例外ではない。香代は祖父秦野(はたの)正衛門が見込んだ婿を、素直に一途に信じて嫁にきた。婚儀の席で初めてみた白無垢の香代はまだ17歳、初々しくも婚礼の膝に固く市松人形を抱きしめていた。

「 そんな香代が雨田家に嫁いだことを実感したのは、ようやく嫡男光太郎を授かり、その産後の枕元に置かれた市松人形(いちまつさん)をみつめて嬉しそうに笑みたときであろう・・・・・ 」
しかし、それから香代が享うけた歳月はわずか五年でしかなかった。その香代は京都の知恩院の近くに生まれた。秦野家は式台の玄関、使者の間、内玄関、供待などの部屋がある武家屋敷の構えの家だった。
お手玉やおはじきが好きな少女は、行儀見習いの二人の女中さんから「 ことうさん 」と呼ばれ、ことうさんとは「 小嬢さん、末のお嬢さんのことで大阪では(こいさん) 」というが、そこで何の苦労も心配もなく育ったようだ。京都でも有名な美しい四姉妹であったらしい。そうした小譲(ことうさん)の婚礼がさすがである。
色振袖が錆朱(さびしゅ)の地に松竹梅模様、帯が黒に金銀の市松、黒留袖は「誰が袖大和百選」の中の沢瀉(おもだか)文様、黒振袖は土田麦僊(つちだばくせん)の扇面散しに光琳松の帯をつけた。婚礼調度はすべて京都の「初瀬川」で揃えたというのだから、いまでは考えられない「姫の豪勢」ぶりであった。虎哉がそんな香代の生い立ちを想えば、木の葉がそよぐように雅な京の暮らしが静かに始まっていくのである。
しごく短い結婚生活のため、香代の死は虎哉にとってどうしても夭折なのだ。
想えば想うほど若い面影に不憫さが倍増し、どうにも嫁ぐ前の京都での人生が長い香代の姿を追えば、香代から聞いた少女時代の彼女への興味ばかりが長くなる。

その理由は、おそらく虎哉が香代のことを日記にして長女君子へ綴り遺そうと考えたのが20世紀の最後の年末だというためだろう。
虎哉がそうしようとしたのは、20世紀を不満をもって終えようとしていたことが一つにはある。とくに日本の20世紀について、誰もが負を帳消しにする気を取り崩し、何にも正体の本質を議論しないで取り澄まそうとしていることに、虎哉はひどく疑問をもっていた。
「 我々こそ、真の(戦中戦後)にいたのではないか。もはや戦後は終わったのだと語られるが、しかし日本の敗戦の体質は負の赤児を抱いたまゝ一向に終わろうとしない。そうであっては、到底、今日の社会人に成り済ませない当事者の面々も多かろう・・・・・ 」
省みることもなく突かれ続ける除夜の鐘を聞きながら虎哉は、そんな怒りのようなものがこみあげていたのだ。
そのとき、桜が人の心を乱すものとは世の常のこと、いまさら言うべきこともないはずなのに、ちょっと待て、いま何かを感じたのでちょっと待て、と言いたくなるのは虎哉にとってじつに可笑しなことであった。


東山三条で乗り継いだバスの席に香織と虎哉の二人はいた。
「 三条駅からやしたら、近鉄の特急やと奈良まで40分たらずで行けることやし、老先生、一体どこに行かはるつもりなんやろか。ほんに、けったいやなぁ~・・・・・ 」
無口のまま何かに憑かれたような虎哉の気配に、香織はふと「 お父ちゃん・・・・・ 」と呼びそうになる自身がいることにハッとした。笛にこり、笛に呆(ほう)けた父増二郎の不可解な気随さが、いまこの老人の肩越しを這っているようであったからだ。
香織の頭の中では、でっぷり肥ったその増二郎の赤ら顔がくるりと一回転して、思いもよらぬほど大写しになっていた。しかし虎哉があの父と同じであるのなら、詮(せん)ないと思う。増二郎は呆れるほど頑固者だった。これは「 なるようにしかならへんのだ 」と、そう香織はわが心にそっといゝきかせることにした。
バスの車窓から祇園界隈をながめみることなど、香織には初めての感触である。
表の路線から花街の路地奥はみえないのだが、それでも香織には思い出深く刻まれた裏町の華やぎであった。そもそも祇園とは、インドのさる長者が釈迦のためにつくった寺「 祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)」からきている、と置屋の女将佳都子からそう教えられた。香織は虎哉の別荘に住み込むようになる二年前、二年間この界隈で暮らしている。その祇園四条から南の京都は香織には久しぶりにみる街並みであった。しかし四条から南はやゝ恐ろしい。
東山の終わりの裾野は南へと長くゆるやかに流れていた。
そうした八坂や祇園などは全く眼中にない虎哉は、半ば無意識で、メモ用紙に書きつけた「 ひなぶり 」という古びた筆文字を見つめながら、養母お琴が遺した言葉を温かく反芻(はんすう)したり、鞄から何やら海外の雑誌を引き出しては読んでいた。
香織は「 こんなン、ほかっとこ 」と思った。
東山七条の智積院(ちしゃくいん)を過ぎたあたりで虎哉は「 少し早目にきすぎたのではないか 」と腕時計をみた。つられて香織も携帯電話の液晶をみたのだが、まだ八時過ぎであった。
「 花は、哀しくて惜しむのではなく、惜しむことが哀しむことである。しかし何をたよりに惜しむべきか・・・・・ 」
と、そう反芻してつぶやくと虎哉は唐突に席を立った。
「 あれ・・・・・、次で、降りはるつもりなんやわ・・・・・! 」
香織が慌てゝそれに従って連れ立つと、祖父と孫娘にも映る二人は泉涌寺(せんにゅうじ)道でバスを降りた。
鳥辺野(とりべの)の南、泉涌寺への道はしずかで長いゆるやかな坂である。
虎哉は少し足を止め参道をながめながら遠い眼をした。
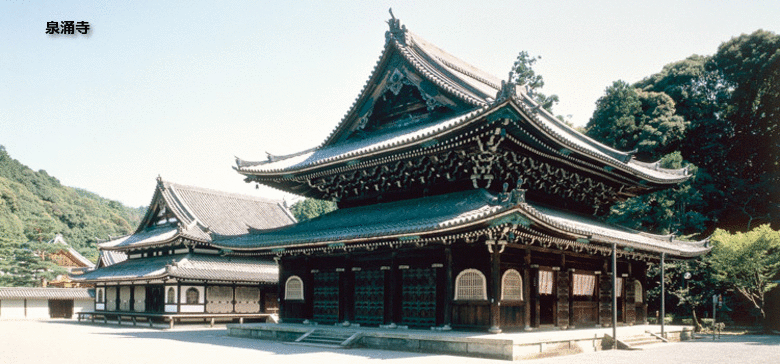
「 かさね・・・・・、300メートルほどこの坂を上ると総門がある。入ると左手が即成院(そくじょういん)というお寺さんだ。その本堂に二十五体の菩薩座像があるのだ・・・・・が 」
と、そこまでいゝかけると虎哉は、プツンと言葉の尻を切った。
坂をのぼりつめて総門、その先に大門、さらに奥の泉湧寺仏殿までの約1キロの間にある光景を、眼に積み重ねながら想い泛かべるだけで、すでに虎哉には遠く息切れる思いがした。自身で歩いたというより、幾度となく歩かされたこの坂道である。
いつもこの坂を想いながら見えるものは、何者かに毀(こわ)された後の荒寥(こうりょう)とした風景でしかなかった。あるいは瞞着(まんちゃく)されたような奇妙な脅(おび)えに身震いするほどの光景であった。そんな憧憬を曳き遺しているために、却(かえ)って泉涌寺に出向くことはどうにも気が重く、虎哉はこの界隈にしばらく足を遠ざけていた。
やはり幾度こゝに来ても虎哉は、ゆるやかなこの坂の、この世の一角に異様なものゝ出現をみせられて立ちすくむ思いがする。そうして今日もまたこゝには、どこからともなく匂ってくる暗い懐かしさを思い起こさせる特別の香気が沸き立つようであったのだ。
どうしても虎哉の心の裡に流れる体臭とその香気とが混ざり合うのである。
下りながら仏殿までの間を詰めねばならぬ不可思議さがこの寺にはある。手を引かれながら「 虎、足音さしたらあかん。音立てたらあかんえ~ 」という声を繰り返し聞かされた。
大門からその仏殿までは下り坂なのだ。そう言われると恐る恐る玉砂利を踏むことになる。ゆるやかな下り坂だが、幼い足は、とほうもなく長い時間に涙眼をして歩いた。
そんな虎哉が、この長いゆるやかな坂道を、母の手に引かれて初めて歩いたのは、大正という年号が昭和へと移り変わるころであった。こうした記憶に残された肌触りを現在まで具体的に噛砕いて考えたこともなかったが、やはり下り坂であることが不思議だ。
本殿までを下る寺院というものが珍しい。虎哉の記憶では他に例がない。なるほど記憶の影が歪むのは一つには坂の勾配にあるのかも知れない。今やその母影も眼にはおぼろげである。虎哉がまだ六、七歳のつたない記憶のまゝでしかない。だが、たゞそこから香り出るものは鼻孔の奥に籠るようにある。そうした母の匂いは82歳になろうとも確かで、それは母がいつも着物にに焚きしめていた追風用意(おいかぜようい)の香気なのだ。
「 人気のない山里にもかゝわらず明治生まれの母菊乃という人は焚きこめた香りを優雅にまとっては風に漂わせている女だった 」
香織がいま首もとに架けている更紗(さらさ)の匂い袋は、昨夜君子が手渡してくれたものだ。それはそもそも虎哉が君子の成人式の折に祖母菊乃の遺品として譲るために身にまとわせた「 誰袖(たがそで)」である。

「 やはり、九月がいゝ。今日はやめておこう。なぁ~・・・・・かさね・・・・・ 」
虎哉はそうポツリというと、香織が首にかける誰が袖をじっとみつめた。
西行の花は「 花みれば そのいはれとはなけれども 心のうちぞ苦しかりける 」と、いうものになっていったのだが、そもそも西行にとっての桜は、この歌の裡(うち)にある。桜を見るだけで「 べつだん理由いはれなどはっきりしているわけではないのに、なんだか心の中が苦しくなってくる 」と、そう詠んだ歌である。その「 いはれなき切実 」こそが、西行の花の奥にはある。
そうであるからまた虎哉にとっても「 惜しむ 」とは、この「 いはれなき切実 」を唐突に思いつくことである。虎哉はいま、それが亡き母の匂い袋の花に結びつく。さらに遠い日の月に結びつく。奈良で過ごした花鳥風月と体験した一切の切実とがこゝに作動するのだった。
そのなかで亡き光太郎と、亡き妻と、亡き母の三つの花こそは、あまりにも陽気で、あまりにも短命で、あまりにも唐突な、それこそが人知を見捨てる「 いはれなき切実 」なのだ。
しかしそう感じることは、何が「うつゝ」で何を「夢」との境界かを、消えて失うことを覚悟することでもあった。参道をみつめる虎哉は、香織に投げかける次の言葉を失くしていた。
「 えッ、やめはるのか。そしたら何や、それだけのために、老先生、こゝで降りはったんか 」
虎哉が何かをいゝかけたまゝ、プツリと途中で、妙な間を残し口をつぐむので、寒空に重い鞄を両腕にさげていたせいもあるが、あきれた香織は皮肉たっぷりにいった。
昨夜遅く書斎の窓を開けた虎哉は、さきほど想ったのと同じように、満州の荒野に咲いていた罌粟(けし)の赤い世界を思い出しては眼に訝しく、そう感じて窓を閉めた後、東京の自宅から持ってきていた聞香炉(もんこうろ)の入る木箱をそっと開けてみた。
白磁の筒型をしたその炉を取り出して机の上に置くと、背筋を伸ばし、あごを引き、体の力を軽く抜いて一呼吸整えた。そうして心を落ち着かせ終えると、一炷聞(いっちゅうもん)の作法で香をしずかに聞いた。まず鼻から深く吸い込み、顔をやゝ右にそらして息を吐く。その繰り返し七息の後、手にする聞香炉を心静かに見改めるように回してはみつめた。その聞香炉も亡き母菊乃が生前使用していた、室町期から雨田家に伝わる遺品であった。
すでにその菊乃とは鬼籍の人であるが、まだ虎哉の中では、過去になどなってはいない。
混沌として、滓(かす)のようなものが残されていた。香を焚かずともそこに母がいる。どうしようもなく、はかなくたって驚かない。はかないのは当たり前なのだ。西行もそういうふうに見定めていた。そこでは夢と浮世は境をなくし、花と雨とは境を越えている。この歌をぜひ憶えるとよい、と諭してくれたのが亡き菊乃なのであった。
「 世の中を・夢と見る見る・はかなくも・なほ驚かぬ・わが心かな 」
よろしいですか、という母の声が悉皆と耳奥に潜むごとくある。
「 細い口でピタリと撃ち終える、それは、それは、手厳しい声であった・・・・・ 」
そうしてまたその母は、ついでながら、さらに「西行学」を持ち出していえば、とくに「わが心かな」で結ぶ歌は、西行の最も西行らしい覚悟を映し出している歌なのであると継ぎ足してくれた。その母の眼の前に座る虎哉はいつも幼子ではなかった。
「 かさね・・・・・そうじゃない。今日、かさねを、尼あまさんにさせる気には、なれないのだ・・・・・ 」
しばらくぼんやりとしていた虎哉は、ハッとして我に返り、そう小声で香織に応え返した。
一瞬、我が母の強さにたじろいだ。その揺らぎが言葉を引き出した。
「 えッ、うちが尼、やて・・・・・! 」
いきなり辻褄の合わぬ薄情な話ではないか。
咄嗟にその声を呑みこんだ香織は、頭の中が透明になった。しばし唖然として固く立ちすくみつゝ香織は「 うち、頭ァ、剃るんや 」と思い強いられると、何やら黒髪の総毛が根元から硬直するようであった。


不意に意外な釘を頭からカツンと撃たれた香織は、焦点をどこにも合わせられない放心でもしそうな誰のものとも思えぬ眼を、丸くも細くもさせられずに、たゞツッ立ったまゝポカリと口をあけていた。それまで香織は「 老先生の脚ィ、痛うて歩けへんさかいに、うちが支えなあかんのやから 」と、一心にそう思っていた。
ここ二、三日、急に底冷えするような寒波が襲っていたのだ。
香織は、こんな急激な気候の変化はきっと虎哉の体に障るのだと、先日、出町柳の主治医のところに立ち寄って、虎哉の脚気(かっけ)には白米による精米されて不足したビタミンB1を補完するなど、温かいしゞみ汁などのなるべく精のつくものを食べさせて、できるだけ安静にして虎哉の気力を養えばいゝことを丁寧に聞いてきた。
また昨夜は寒い夜になりそうで、そうだからと虎哉の書斎に予備の炬燵(こたつ)まで納屋奥から引き出してきては、痺れや痛みが増さぬよう備えたりもしていた。さらに昨夜はいつもよい少し早目の午後九時には香炉を用意して、虎哉のまだ寝る前の寝室にそっと忍びこみ、虎哉が爽やかな寝ざめをみせるよう君子と二人計らって、百檀や丁字など焚かなくても香る香料を厳選したし、その香気が虎哉の患部を清め、寝室を浄化し邪気を払ってくれることゝ、憂鬱な気分を爽快にさせる作用があるのだからと、虎哉にそのことを意識させぬよう、そっとベッドの下に香炉を忍ばせたりもしたのだ。
「 来月は少しだけ連休もろて、祇園の花江姉さんとパ~ッと城崎きのさきにでも遠出したろ思て、約束してたんやないか。もうそれも、わややわ。なしてうち・・・・・尼やねん。そないなこと、前もっていうてもろたかて、うち承知でけへんことや。罰あたりなこと、何もしてへん・・・・・。毎日、しんどうても、ほんにお務めしとるつもりやし・・・・・ 」
もう、とりとめのない香織は、わなわなとふるえる手を、そう思ってはかろうじて握りしめた。
そのまゝ眼を伏せた香織は、こんな場合、やり場のない感情をどう表わせばいゝのかを、五郎や置屋の女将佳都子の顔を泛かべてはためらっていた。
「 老先生ッ、もう高齢や。80歳も過ぎたといえば、だいたいの男はんは、自分の限界がどんよりのしかかっている時期であるさかいに、いまさらきれいごとですませるものなんてないということも、あんた分かっとらなあかんえ。せやけど男はんの美学というものは、存外にどんな時期でもはずせないもんや。そこで美学と辻褄とがソリを競いあうもんなんや。するとなッ、最後ォにひっこんでもらうほうは辻褄のほうで、男はんいうたら美学ひっこめはらんもんなんや。香織にもそんな理不尽なとき、きっとある思う。せやけどな、短気だしたらあかん。老いた口ィは、そう思ても叩き返したらあかん。それかて養生や・・・・・ 」
以前、置屋の佳都子がそんな話を聞かしてくれたことがある。いま噛みしめてみると、なんとなく理解できそうにもあるが、やはり心の始末におぼつかない香織であった。
「 せやけど。尼寺で・・・・・成人式やなんて。やっぱ、うち嫌や 」
香織は君子から貰った胸の誰が袖をキュと握りしめた。そこにはサザンカの一枚もある。
ときとして虎哉の言葉づかいは地口や冗句に富んでいて、若い香織を翻弄させることがある。それが、ちよっとした自意識過剰であることは虎哉自身も分かっている。長女の君子にもずいぶん嫌な顔をされてきた。それは、どこか偽善的な意識であり、しかし自分を「 まともには見せたくない 」という、そんな矛盾もを交錯させる偽悪的でもあるのだからそうとうにひねくれているのだが、それでいてつねに影響力を計算しつゞけているような、どこか悲しい自意識なのである。そうした妙な自意識を牽引したと自身でも思われる泉涌寺という寺院は、虎哉の青春の「 傷のつくりかた 」を決定づけるほど衝撃的な世界であった。
自分でもそう思う虎哉がふと気づくと、ふいに不安を呷(あお)られた香織はしょんぼりとしている。虎哉はうつむく香織のその顔色を感じながらおもむろに笑みを泛かべて首を振った。
「 案外かさねも、阿呆やなぁ~・・・。実際だれが、かさねを尼にさせる。そんなことあるか。いや何、尼になろうとする女性の心情を推しはかることも大切だと思ってな。この寺は古くから、そういう女が通い合う道なのだ・・・・・ 」
虎哉はそう言いながら改めて腕時計をみた。
駒丸扇太郎と落ち会う約束の時間にはまだ少し間があった。泉涌寺の、この界隈はやはり秋がいゝ。こゝらはまだ京都の田舎といった淡い光が残っている。しかし、みな枯れたものゝ間にあって、この冬を越そうとしてしがみつくように残る常緑樹が黒ずんだ葉の色をさせて寒さに耐えて立っているのは、かえって生身の血が通うものゝ本性をみるようで、これが泉涌寺には好ましい本来の季節ではないかという気にもなる。虎哉は少し遠い眼をした。
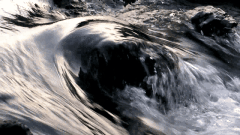


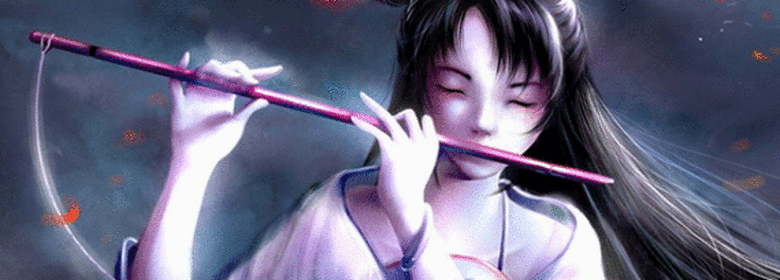











奈良・佐保川の桜










