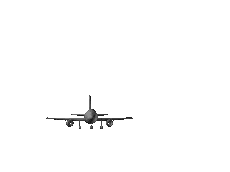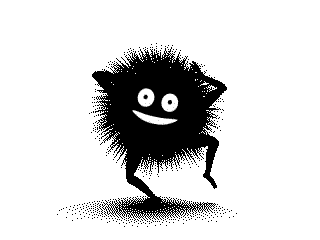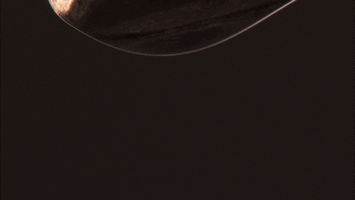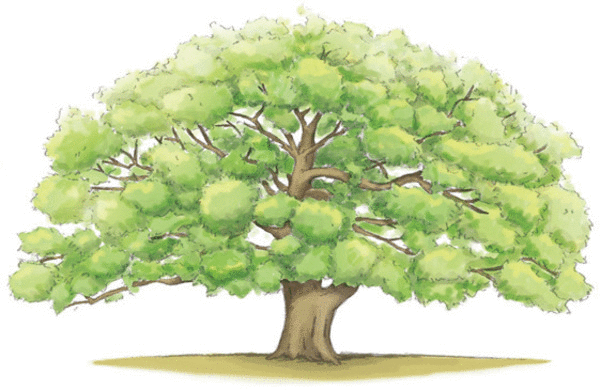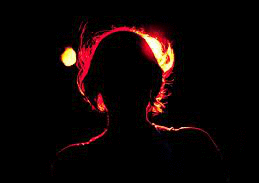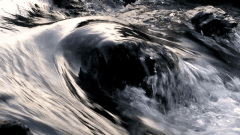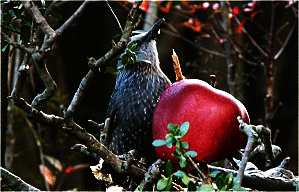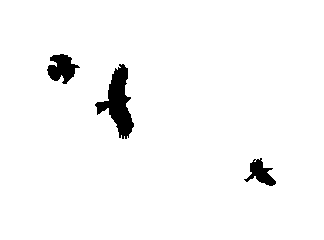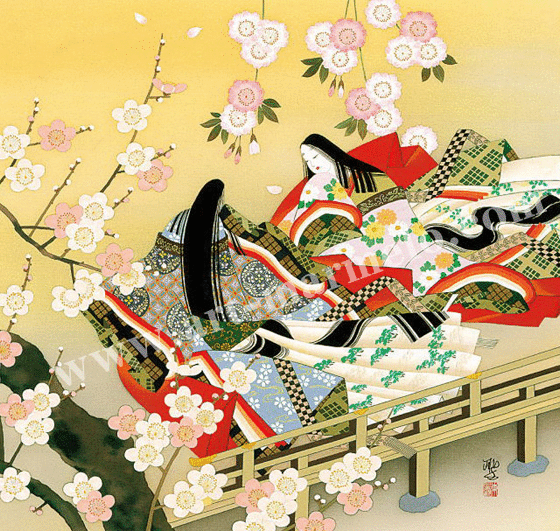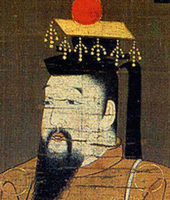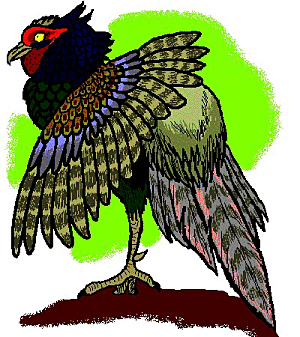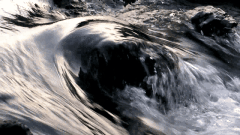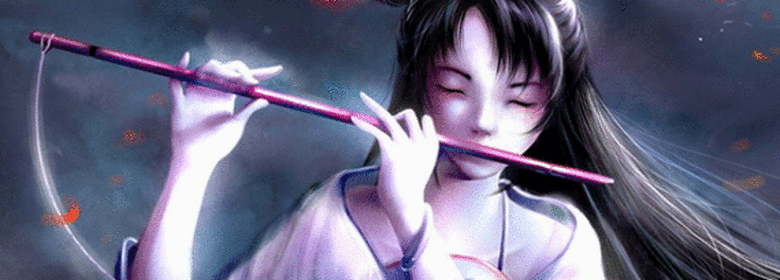(五) 弥勒の1√2 ② Mirokuno1√2
沖縄本島から宮古海峡を経て南西に約290km、宮古島は直角三角形のような形をした島である。
宮古島空港に着くと比江島修治は七色の日傘を開きながら漲水御嶽(ぴゃるみずうたき)と、ニコライ・A・ネフスキーの面影を泛かべた。そしてその眼にはもう一人の異国人を泛かべていた。すると白蛇にまかれて映る御嶽のそこに、滔々と豊かな水を奔らせる、とある疏水の流れが泛かんできた。そのとき修治は、雨田博士と駒丸扇太郎の会話を思い出していた。

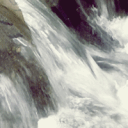

「 太古以来明治維新まで荒地のまま放置されていた原野がある!・・・・・ 」
想い浮かべたもう一人の異国人の名をファン・ドールンという。オランダ人土木技師である。1872年2月にファン・ドールンは来日し、お雇い外国人として契約を結んだ彼であるが、明治政府から求められていたのは全国各地の港湾・河川の整備であった。彼は日本初の科学的な水位観測を行なっている。そのドールンの姿を想い浮かべると、そこには幻の港湾「 野蒜築港(のびる築港)」が揺れるように重なっていた。これは日本初の近代港湾の建設であり、明治政府による東北開発の中心的な事業「仙台湾(石巻湾)に面する桃生郡の野蒜村(現・東松島市)」と位置づけられていたが、完成から3年後に台風で突堤が崩壊し、施設はそのまま放棄された。

明治維新によって江戸幕府は崩れ去り、世相は一変するのだが、同じく水源が乏しく荒涼とした原野が広がる安積地方も一変した。
それまで東北地方は永く後進性から脱しきれず開発が遅れ、戊辰戦争による後遺症がまださめやらぬ明治4年(1871年)新しい行政のもとに県が置かれ、安積地方は二本松県となり、直ちに福島県に変わることになった。
そしてり明治9年(1876年)福島・若松・磐前の三県が合併し、福島県が誕生した。
失業して生活に困窮する士族を救済する士族授産、食糧増産により富国強兵を国策とする明治政府は、全国より二千戸を移住させ、安積原野を開拓する計画を樹立、これが安積原野開墾事業である。

この開墾事業を成功させるため、日本海に流れる猪苗代湖の水を、奥羽山脈を貫き安積原野に導く猪苗代湖疏水事業が明治12年(1879年)に着工され、十六橋水門を手始めに、沼上隧道590mを含めた水路130kmは3年後の明治15年に完成した。
奥州街道の一宿場町であった郡山は「 安積三万石 」といわれ、用水不足に悩まされ、当地に豊かな水をもたらそうと苦心した人に、二本松領下長折の渡辺閑哉や、須賀川の小林久敬などがいた。
明治6年安場保和旧福島県令のもと、中條政恒は生活に困窮する二本松藩士の入植と、地元郡山の豪商らを説得し開墾事業に着手、数年にして100ha余の開墾ができた。この地を明治9年に訪れた内務卿大久保利通は、この開墾の成功と入植者による桑野村の誕生を見て、大いに心を動かしたのだ。当時の政府は失業した士族の相次ぐ反乱が起こり、士族授産と殖産興業の解決策にせまられていた。そのため全国からの士族を入植させ猪苗代湖からの導水を図る疏水事業が急がれていた。

「 大久保利通か・・・・・! 」
阿部家の伝承を白銀比に織り上げることに苦心する雨田虎哉には、万寿寺裏の笛蔵で駒丸扇太郎が語り聞かせた大久保利通像が最期まで眼の奥に焼き付いていたのだ。その大久保が暗殺されたのは明治11年5月14日のことであった。
「 大久保利通を水神として祀る大久保神社が、福島県郡山市にある・・・・・! 」
郡山といえば幕末は天領の地、大久保は安積疏水(あさかそすい)を完成させた立役者の一人である。

「 それがかの、紀尾井坂(きおいざか)の変だ。大久保が暗殺時に乗っていた馬車は、後に供養のため遺族が岡山県倉敷市の五流尊瀧院(ごりゅうそんりゅういん)に奉納して現存する。この修験道の寺院は本尊を十一面観音、天台修験系の一宗派である五流修験道の総本山で、そして南北朝時代に後醍醐天皇を奪還しようと試みた児島高徳(こじまたかのり)は当地の出身である。この一連は阿部家に連なっている! 」
扇太郎の口調を泛かべる博士は、眼に、桜の一樹に彫られた十文字の漢詩を泛かばせた。
「 天莫空勾践 時非無范蠡・・・・・ 」
後醍醐天皇は、先の元弘(げんこう)の変に敗れ隠岐(おき)へ遠流となる。
このとき児島高徳は、播磨・備前国境の船坂山において一族郎党二百余騎で佐々木導譽(ささきどうよ)ら率いる五百騎の天皇護送団を強襲し、後醍醐天皇の奪還を画策した。しかしこれは、天皇一行の移動ルート誤判によって失敗に終わる。そのため高徳は天皇一行を播磨・美作国境の杉坂まで追うものゝ、そのときすでに天皇一行は院庄(現在の岡山県津山市)付近へ達しており、完全な作戦ミスの前に、奪還の軍勢は雲散霧消して終えた。
その際に、高徳たゞ一人が、天皇の奪還を諦めず、夜になって院庄の天皇行在所・美作守護館の厳重な警備を潜り侵入する。やがて天皇宿舎付近へ迫るも、だがそれまでの警備とは段違いな警護の前に、高徳は天皇の奪還を断念する。このとき高徳は傍にあった桜の木へ小刀で『 天莫空勾践 時非無范蠡 』と、漢詩を彫り入れた。
「 天は春秋時代の越(えつ)王・勾践(こうせん)に対するように、決して帝をお見捨てにはなりません。きっと范蠡(はんれい)の如き忠臣が現れ、必ずや帝をお助けする事でしょう・・・・・ 」
と、いう漢詩を桜木に彫り入れる。こうして高徳は、この十字詩の意志と共に天皇を勇気付けた。するとちなみに朝になり、桜の木に彫られた漢詩を発見した兵士は、そこに何と書いてあるのかが解(げ)せなかった。そして外が騒々しいために、何事か仔細を聞いた後醍醐天皇はその桜の木彫りをみて、天皇のみ、この漢詩の意味が理解できた。

「 しかし、そう伝えられるが、その陰に阿部一族の一働きの影があった。桜木に彫られた、天勾践(こうせん)を空しうすること莫れ、時に范蠡(はんれい)の無きにしも非ず、の漢詩にある言葉通り、翌年に名和長高ら名和氏の導きにより天皇は隠岐を脱出、伯耆国船上山において挙兵した際には、高徳も養父とともに赴いて幕府軍と戦い戦功を挙げたとされるが、しかしその論功行賞の記録には高徳の名前が無い。だがそれで児島高徳の否定説とするのでは無い。こゝは阿部家伝の覚書に一つの裏付けがある。これを根拠とすると、范蠡(はんれい)とは阿部家第八代范衛門(はんえもん)、そうしてこの伝承の闇は晴れたことになる・・・・・! 」
虎哉博士は、そう闇を晴らした眼をまたそのまゝに、五流尊瀧院(ごりゅうそんりゅういん)へと向けた。
笛蔵の壁棚をのぞき七万種あるという蔵屋敷で、一連する大久保暗殺の一件に扇太郎の話が及んだとき、虎哉は魔窟にでも踏み込んだような恐れを感じた。そのときの扇太郎の口ぶりに泛かぶ五流尊瀧院の光景とは、虎哉の眼に、じつにリアルな血痕となった。
その眼にはまず、五流尊瀧院には頼仁親王(よりひとしんのう)の御庵室があり、庭内に「 この里にわれいくとせかすごしてむ乳木の煙朝夕にして 」と親王の歌碑がある。後鳥羽天皇の皇子は承久(じょうきゅう)の乱で備前国児島へと流された。そして院内会館には一太刀の血痕を刻み込んだ明治の古馬車が遺されていた。それは現在うるしも剥落し、経年の変化に依る損傷が著しい明治初期の馬車である。
「 血痕と島田一郎が振り上げた日本刀が当たった痕跡が130年弱経過した今日でも判っきり解る状態。大久保利通殺害時の際に犯人が使用し警視庁が証拠品として押収した日本刀。先端部分刃先が欠損しているのは、犯人の島田一郎が刀を振り上げた際に、大久保利通が乗っていた馬車に当り折損したのが原因。警視庁に依り証拠品として押収され保管されていたもの。刀に僅かな曇が見られる。関東大震災の際に警視庁本庁舎が被災炎上の際も無事。警視庁本庁舎特別資料室保存。一般非公開。特別公務用務者以外、部外者の警視庁本庁舎内部は一切立入不可 」
と、馬車の右扉付近に一太刀の血痕をこう記している。

「 その暗殺時の馬車、その骨格材がイブキなのですよ!。しかも馬は八瀬の駒・・・・・! 」
と、語りかけた扇太郎の眼は一段と輝きを増していた。
そして阿部家覚書にはイブキが使用されるに至るその経緯をつゞる。また覚書には郡山の大久保神社に関わる水神について記されていた。これらは幕末から明治初期の阿部家第二十三代清衛門と次代秋一郎の出生に関わるのであった。
「 そうか・・・・・!、あの五人の修験道がいた・・・・・ 」
漲水御嶽(ぴゃるみずうたき)へと向かう比江島修治はふと、京都・茶碗坂の古書院「冬霞」の主人を含む聖護院五流神道の修験者のいることを思い出した。それは音羽一郎(五玄)、笠羽二郎(五寿)、白羽三郎(五真)、鷲羽四郎(五学)、出羽五郎(五芳)の面々である。岡山県倉敷市の五流尊瀧院(ごりゅうそんりゅういん)が彼らの総本山であった。


修験道の寺院「五流尊瀧院」は天台修験系の一宗派である。
修験道の祖と言われる役小角(役行者)は、文武天皇3年(699年)朝廷より訴追を受け、熊野本宮に隠れていたが伊豆大島に配流された(続日本紀)。伝承によれば、この際、義学・義玄・義真・寿玄・芳玄ら5人の弟子達を中心に熊野本宮大社の御神体を捧持したとされる。そして彼ら5人は3年にわたり各地を放浪し、役小角が赦免となった大宝元年(701年)3月、神託を得て現在の熊野神社の地に紀州熊野本宮を遷座し、5人の高弟それぞれが尊瀧院、大法院、建徳院、報恩院、伝法院の五流の寺院を建造した。中でも尊瀧院が中心寺院となった。さらに時代は下り明治時代になると神仏分離令により、十二社権現は熊野神社となり五流尊瀧院と分離した。明治5年(1872年)修験道の廃止に伴い天台宗寺門派に属する。太平洋戦争終結後は、天台宗より独立し、修験道総本山となった。


「 さて・・・・・、この大久保暗殺の一件、阿部家伝にどう書き遺すか・・・・・! 」
雨田博士は、数多くの修験道が阿部家の門を法螺貝ほらがいの音で叩くのを覚えた。そして阿部家にて毎年、黄蘗(きはだ)の花を草木染めにして黄海松茶(きみるちゃ)の細縄をない最多角念珠(いらたかねんじゅ)にその荒縄を結いつける光景を泛かべた。
大久保利通は近代国家としての日本の基礎を築き版籍奉還や廃藩置県を断行する。しかしこれは明治維新の推進力となった士族勢力の意思に沿うものではなかった。彼らの多くは攘夷のために江戸幕府を倒したのだ。だが新政府は一転して諸外国との通商を国是とし、さらには士族の身分をも取り上げようとした。各地で士族の反乱が起こる。大久保はこれを鎮圧した。
この遺恨が大久保暗殺に至るトリガーとなる。
「 しかし京都の阿部一族はこの大久保を陰で加勢した・・・・・! 」
大久保利通と西郷隆盛とは、敵対勢力の首領となるが、この西南の役でも阿部一族は大久保に加担する。
その大久保は怜悧(れいり)と評されるが、第二十三代阿部清衛門は、その大久保らしくある怜悧さを、維新の本質を露光する悧発(りはつ)だと捉えた。大久保に、倒幕の齎(もたら)した維新、齎そうとする未来への証明を求めた。世の弛緩(しかん)に対し清衛門は炯眼(けいがん)で穎悟(えいご)であった。つまり、すでに日本の士族が軍隊の世界標準と比較して完全に時代遅れであり、外国の植民地になりたくなければ解体しなければならなかったことを十分承知していたのだ。

「 阿部清衛門は、その大久保を神荼鬱塁(しんとうつりつ)の水神にして祀る。それは阿部家の守り神でもある!・・・・・ 」
雨田博士はしかし、この大事件の多くを記し止めるにはすでに余命幾許もなく郡山大久保神社へと足を運ばす気力の余白はもう尽きかけていた。精根はもはや白々とあやかだが、その気力を振り絞る眼にはたゞ、明治10年代の明治政府において、大久保利通亡き後、国会開設運動が興隆するなかで、政府はいつ立憲体制に移行するかという疑問が持ち上がっていたのだが、どこの国の制度を参考にするかの問題は、虎哉に遺恨のごとく湧く戦禍の痛恨すら感じさせる大関心事だった。
「 天の理に、大久保暗殺を否定されゝば、かの大戦は否決されて消え、鎮火したのではないか! 」
1881年の政変、結果として自由民権運動や大隈の唱えるフランス流やイギリス流は否定された。そして施行された大日本帝国憲法は、君主大権を残すビスマルク憲法を模範とするものであった。天皇が君主であらせられることは建国以来の伝統ではある。
「 しかし、この君主大権を規範した憲法の制定以後、日本国はたゞ淡々と開国殖産政策を進め、対大戦をも帝軍国の威力で淡々と進軍をみせた・・・・・ 」
結果、戦禍の残虐を雨田虎哉は体験したのだ。そして反動の陰場にて、博士には暗殺される当日朝の大久保利通と阿部清衛門との、二人の面影が揺れ動くのであった。
「 5月14日午前7時、清衛門は、三年町裏にある大久保邸で二頭立て馬車の手配と点検を終えた後に、御者(ばしゃひき)の中村太郎を激励し、大久保に一言の挨拶を残して京都へと引き返した・・・・・ 」
その少し前の5月14日早朝、大久保は福島県令山吉盛典の帰県の挨拶を受けた。
二人は安積疏水の進捗について語り、そして話は二時間近くに及び、その山吉が辞去しようとしたときに大久保は三十年計画について述べている。これは明治元年から30年までを10年毎に3期に分け、最初の10年を創業の時期として戊辰戦争や士族反乱などの兵事に費やした時期、次の10年を内治整理・殖産興業の時期、最後の10年を後継者による守成の時期として、大久保自らは第2期まで力を注ぎたいと抱負を述べるものであった。
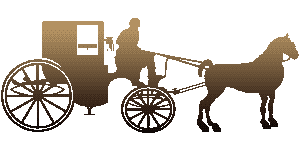
「 そして午前8時ごろに、大久保利通は、麹町区三年町裏霞ヶ関の自邸を出発。明治天皇に謁見するため、点検を終えた馬車で赤坂仮皇居へと向かった・・・・・ 」
博士の逝きそうな眼には、その大久保が紀尾井坂(きおいざか)へと差しかゝる三十年計画を抱えた怜悧な残像が痛切にある。そして博士が、かの大戦を仮に空白として一体何をもって埋め償うべきかと、逝く眼をしばし堪(こらえ)たとき、大久保の影はたゞ切実残念に遺された。
「 午前8時30分、紀尾井町清水谷(紀尾井坂付近。現在の参議院清水谷議員宿舎前)において、暗殺者6名が大久保の乗る馬車を襲撃した。日本刀で馬の足を切った後、馬車を引く御者の中村太郎は喉を突かれ刺殺、次いで乗車していた大久保を馬車から引きずり降ろした。大久保は暗殺者らに無礼者と一喝したが、瞬時に斬殺され、介錯として大久保の首を突き刺した兇刃(きょうじん)は地面にまで突き刺さっていた 」
このとき初代内務卿・大久保利通は全身に16箇所の傷を受ける。
その内の半数は頭部に集中していた。事件直後に駆けつけて遺体を確かめた前島密(まえじまひそか)の言葉を借りると「 肉飛び骨砕け、又頭蓋裂けて脳の猶微動する 」と悲鳴するごとく残虐な殺刃痕であった。

5月17日、青山墓地に設けられた祭典場で大久保の葬所式が行なわれ、ともに中村太郎および馬の遺骸も、大久保のすぐかたわらに埋葬された。この埋葬の一陰にいて阿部清衛門は涙眼のまゝ呆然とたゞ立ち尽くした。
中村は大坂の生まれだと本人は語るが、親のない名もない捨て子であったのを拾ったのは清衛門である。鳥羽伏見の戦闘、その折に東福寺境内の法堂前に赤児が一つ転がっていた。伝えでは赤児は、大久保に拾われて「 中村太郎 」の名を与えられたという。そう清衛門が願って申し出た通り、7歳となった阿部家の太郎は以後、中村姓を名乗らせた大久保によく仕え、二頭立ての馬車を引く際には御者を務めたのだ。
「 東福寺のイブキの下で太郎と命名した、その赤児を泛かべながら清衛門は泣いた・・・・・ 」
その古老の一樹が博士の最期の眼のなかにある。
そして眼は見開きのまゝ合掌した。雨田君子が眠らないその父虎哉の眼をそっと手で閉じたのは、しぐれ雪の降る午前5時であった。
「 日本人は勘違いすべきではなかった。いつまでも米国と結び合う日本の将来とは不安だ!。眼には、ペリー艦隊の旗艦ポーハタン号に掲げられていた星条旗が三度みたびはためく・・・・・! 」という阿部富造のいゝ遺した言葉を耳に篭らせ、香織の整えた羅国(らこく)の香りを聞きつゝ雨田虎哉は、遺言として白銀比の数式で、山端に奏でる旋律を一冊の現代風土記につゞり終えた後、雪闇に儚(はかな)くたゞ幽(かす)かな氷輪の下、西行のごとくしずかに永眠についた。













安積疏水