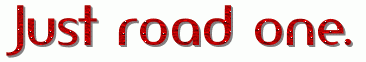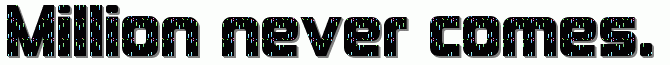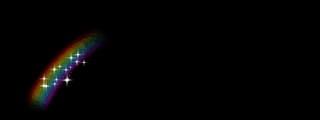
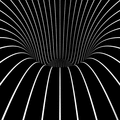



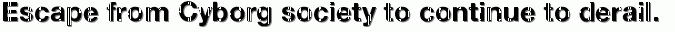





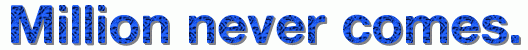




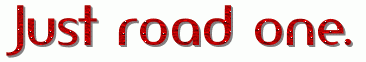
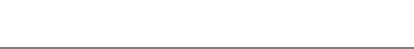










(一) 音羽坂 Otowazaka
東京のすきまから江戸や明治の顔が見え隠れする。
いにしえの穴。都内にはそんな覗き穴がいたるところにある。遭遇した人は埋設された知の社会の凹凸にしばし溶融されるのだ。
人はこの穴の底でブリコラージュされるとアタマとカラダが悩ましくも悶えはじめる。
この物語は、東京都内のそこかしこに、めずらしくも、白い悪魔と黒い天使とがほぼ平行して到達してから一週間後の、8月26日午前10時過ぎの、目白坂下の交差点角から始まる。白い悪魔と黒い天使は、都民に知られざる非常識な密言の論法で、世の常識と学の旧弊を打ち破る刷新の手段を指南してくれたのだ。聞き取れた声は3500万分の1という確率で耳に届いた雉子(きじ)の高鳴きであった。都心で日本の国鳥が非常識な声で鳴いたのだ。こうして世にいる悩ましきが「常識」にいちゃもんをつけてきた。
その悩ましい正体を求めて、比江島修治は東京メトロ江戸川橋駅へと向かっていた。
「 世界と日本のあいだに落ちているもの、それは方法なのだ・・・・・ 」
小日向台の自宅を出て7分後、修治は酷暑37℃の歩道を歩きながらセルバンテスの「方法」を持ち出して、その端緒を訥々と温めていた。なぜ、修治はセルバンテスを端緒にしようとするのだろうか。それはセルバンテスが人文と科学との両方の知の端緒に腰掛けたとびきりの哲人だったからだ。そしてこの男の結晶であるドン・キホーテが中世を喝破して世界を動かした一大傑作であるからだ。来日した彼を驚安の殿堂でペンギンと遊ばせている場合ではない。
「 定義したコマンドを、あとはリバース リーディングするだけだ・・・・・ 」
若きセルバンテスの脳髄を襲った監獄の雷鳴と割れ目を、修治はここ数年間じっくりと時間をかけて解き砕こうとしてきた。そして沖縄に向かおうとする今、セルバンテスの端緒を、自身の行動の端緒として試みる最初の旅立ちであった。ドン・キホーテを和訳するとき、十二段浄瑠璃のように進めていくという方法は、生体が和の情話としてシャッフルされるためか日本人としてじつに魅力的である。しかも複合的に未来を指南する彼のこの方法は、明確に21世紀後半の扉を開く可能性を秘めている。修治には密かなる確信があった。
「 セルバンテス的な再出発点ほどふさわしいものはない・・・・・。雉子はラテン語で「versicolor色変わりの」を意図をもつ 」
赤い衣に着替え還暦を過ぎた自身の行動規範を転換するにあたって、修治はこう結論付けていた。
スペインの作家ミゲル・デ・セルバンテスは「完了」から最も遠い「夜明け前の闇」に腰掛けた端緒の人である。「 ヨーロッパと自分のあいだに落ちているもの、それは方法にほかならない 」と中世の時間を享受して、それをラ・マンチャの男に託した人物だった。
「 しかし、僕は、従者サンチョ・パンサの視点から日本を見詰め直してみたい・・・・・。サンチョの立ち位置から・・・・・ 」
健全なロハスを希望すると、戦後日本が繰り返すヘビーローテーションを封鎖する必要がある。日本という国家が気になるから、議論の方法を端緒にリセットする必要がある。さきほど、妻沙樹子はそんな旦那の新しい旅立ちを冷静に見定めてくれた。
小日向と小石川は幾つかの深い谷間で結ばれて区街化されている。谷あれば坂ありで、この一帯は無数の小さな坂道がある。江戸や明治の顔が見え隠れするいにしえの覗き穴は、そうした坂道の端によく現れてくる。
考えるまでもなくこの覗き穴こそが、セルバンテスの端緒、その窓なのだ。
ここに中世の萌芽があり、江戸の鎖国、封建の崩壊、明治の維新、帝国の興国、戦闘と戦後、日本の進化がおしなべてある。
「 その穴に、まったく新たなフィジカルイメージを躍如させてみれば、それは、誰も見たことがない和洋服を着ることになるわ 」
60を過ぎて日本という方法を学び直したいという修治の後ろ姿を見送りながら沙樹子は憂いた瞳を輝かせた。
世の中の現象は、エネルギーがわかれば質量がわかるという図式によって成立する。こういう怪物のような装置を使って、今日までの素粒子物理学者たちは本気であらまほしき「ないものねだり」を創り出してきたのだ。この科学資本が、資本主義を基軸もろとも偏向させた。そこに遺産もあれば、しかし不の遺産も落とし撒かれた。結果、日本はヘビーローテーションを繰り返している。
東京とはこの「強請り」の精神に培われ拓かれてきた親不孝で失礼な容器なのである。
「 東京タワーは、まるで卒塔婆のようだね・・・・・! 」
と、以前に旦那がこう語りかけてきたが、死のプログラム化を告知され、東京スカイツリーに機能を譲渡してみると、やはりあの戦後のシンボルであった復興の赤色は進化の流血に思われてくる。しかも凋落の直後にテレビの話題を独占するようになると、もはや形骸となり荼毘された遺骨を拾わされるようで、野辺の送りに加わることだけはどうにも敬遠したくなる。進化は逆戻りしなくとも、沙樹子にはデボルーション(退化)する東京が感じられるのだ。そして旦那はあえて、この国家の条件をめぐって常識の正面を切りたいのだ。

お茶の水女子大の裏路地にある街灯には、白い蛾の影がひっそりと貼り着いていた。
黒くて太いケヤキの幹が枝先で突きあげた夜空には妙に青白い半月が泛かんでいる。
「 月の光もそうだけど、そもそも宇宙というもの、光とその光から生まれた物質でできている。そして光には質量がない 」
沙樹子は不在の帰宅を急ぎながらも、自身の午後からの歩行が真空のようで不思議だった。
誕生日だからと贈られた白い花束をながめ終えると、比江島沙樹子は音羽の自宅を出て、ふらふらと歩きはじめた。励起(れいき)したこういう気分は、その消息がやってきたところを思い出そうとすると、妻としてはいささか旦那の個人史的な事情を絡めたことになってしまう。人は紫外線のエネルギーを吸収して基底状態に戻るときに蛍光や燐光を発することがある。このとき沙樹子の身体はそうした蛍光体であったようだ。北京オリンピックの女子ソフトボールが金メダルで、星野ジャパンが韓国にもアメリカにも完敗し、なでしこジャパンが4位で、反町ジャパンは全敗したことを思い出してみると、これが現在の日本というもの、この「女は鼻息、男は溜息」であることが、女の沙樹子からしてざっくりと浮雲のようではないか。上野由岐子の、あのピッチングが心に残るほど、旦那方の武士道とやらが萎びれてみえる。男を鍛え直さないと、女の負担が増えるばかりだ。片輪だけが回り続けていた。何もかも気は混沌とするが、沙樹子は途中、林泉寺の縛られ地蔵をみたような淡い記憶がする。この日は、おそらく小日向台から茗荷谷に、さらに東へ春日通りをまたいで千駄木に出た。
おそらくという曖昧な記憶は、おそらく、この階段の先が私道だということを知らせる看板が何者かによって粉々に砕かれていたので、これは駅前ならではのご近所トラブルだと感じたことにある。しかしそれにしても都心で唯一青空のみえる地下鉄の駅が真ん前にあるとは思えない風情が漂う茗荷谷界隈の光景はぼんやりとだが見覚えていた。たゞ、その記憶の中にも明確な現実が一つあった。
下町臭さも残る茗荷谷駅前の路地には古い飲食店が並ぶ光景も見られるが、ここらは高級住宅街でもあり、それほど俗っぽさは感じられない。しかし非常に古い街なのでやけに寺が多かったりする。そんな道すがらだと思えるが、沙樹子のポケットには林泉寺の「しばられ地蔵」を縛る赤毛の紐縄が残されていた。どうやらそれは拾いモノの縄のようである。これだけは自身の存在が支持されてポケットに残された物証だった。
「 すでに願いが叶って解き捨てた紐か、それとも願掛けをしようとして落した不覚の縄なのか・・・・・ 」
だがいすれにしろ沙樹子はこの「しばられ地蔵」に逢いに来たのではなさそうだ。
自宅では実家の京都から送られてきた誕生日の白いササユリをみつめていた。しかしふと気づくと沙樹子は団子坂にいた。
意外なことに問題は「それから・・・・・」なのだ。
道々どうしたかを考えると、明治期には二間半といいますから5m弱の狭い坂道を下っていた。それは夢の中の出来事にも思えるが、しかし百合の甘い匂いが体に纏わりついてくる。これは自宅のユリか、あるいは漱石の百合か。昔はこの坂の下に団子屋があった。沙樹子は時々、匂いから湧き上がる記憶にひとり溺れることがある。この百合の香の深みに坂を下りきると、先は谷中へと続いていた。
「 僕には時々、欠如の実在がリアリティ・ダンスを躍るときがある 」
と、旦那の修治がいつも口にしたがるのだが、この言葉が沙樹子に何かを仕出かしたのか、そっと袖についた百合の名残り香を払うと、残りなく自己を放擲(ほうてき)したのは大助であった。夢は状態を人工的につくりだすことができる。おそらくこの状態を旦那が使う温度を借りていえば摂氏1京(けい)度、10の16乗度にあたるはずだ。
「 光速に近いスピードまで加速した陽子と陽子を衝突させて、ビッグバン直後に似た高エネルギー状態をつくりだし、そのとき出てくる粒子を次々に検出器にかけて精密に測定するとき、LHCは10のマイナス12乗秒後のエネルギーに相当する状態を人工的につくりだすことができる。しかしこれを物理の温度として変換するのではなく、精神的な体温として変換すると、そこに一つの莫大な夢ができる 」
旦那はきっとこんな言葉を付けたしてくるであろう。百合の香の、それはともかくとして漱石の大助についてだが、これは欧米の論理と日本とは合わない、日本を英語では語れない、日本の道は祖国愛をもつ、美意識こそが戦争を超える、といったことを、平坦にはしないが示唆させる夢ではないのか。漱石も大助も日本人であった。京都育ちの沙樹子は躰の芯が熱くなるのを感じた。
「 政府の国家についての説明は、誤解を招きやすい安易な説明ばかりに終始していて、何が国家の品格かがわからないだけでなく、何をもって国を愛する精神としているのかさえ説明できていない。とくに日本文化への説明は表面をすら撫でていない。もっと日本精神の惻隠の情とでもいうものを発揮したらどうかと思う。それが漱石の(それから)ではないか・・・・・ 」
沙樹子は東京の数ある覗き穴の一つから、こんな明治の夢の体温を掘り起こしたようだ。
こうして沙樹子は特異な発想力を発揮しはじめた。

石地蔵の頭を棒で叩いて雨乞いをする。
「 旦那の文明が劣化している。自己を放擲するとは、そうなるのか・・・・・! 」
この決然と出された劣化注意報に気づかされた沙樹子は、以降、地蔵を叩く願かけを五年間し続けてきた。旦那がついに干からびて壊れそうであるからだ。あるいは時が捲き戻され、時代が旦那を「エル・キホーテ el Quijote」化させているのだと思えた。
気づかされた、ということは、そう気づかしてくれのは団子坂なのだが、この坂の住人に森鳩甚八という男がいる。
新年そうそう軽い脳梗塞をしたため、男は歩行もままならないと聞かされていた。
その森鳩が秘書の宮川に肩をかかえられながら、突如、夕立の落雷のごとく玄関先に、久しく見せなかったあの猪首を現した。
森鳩甚八とは、明治以来の三福堂を森鳩一族の一員として牽引してきた実業家で、すぐれた苦労人あるいは読書人でもあり、また洋の東西をつぶさに見聞してきた文明人として80歳になるその森鳩が、いまこそ旦那の「文明劣化」を告発せざるをえないと言うのである。
「 ・・・というふうに断ずることは、なんとなく避けたいとも思っていたが、しかし、もはやそういう保留をしているわけにはいかなくなったようだ。三年も待ってみたが、比江島君から一向に音沙汰がない・・・・・ 」
いくつかの説明をした後、森鳩は三年前の喜寿祝いを引き出して、幹事役の旦那がその前日以来、森鳩邸に顔を出さないどころか連絡一本すらよこさないのだと、鼻頭の尖がりを赤らめていう。幹事役不在のまま、森鳩の喜寿祝いは放置されていた。
「 ほほほ、三年間も・・・ほほほ、それはそれは・・・・・ 」
この夕刻、あいにく沙樹子の旦那は不在なのであった。
それでも森鳩は上がり框に腰を据え、比江島修治が日本のウェブ社会をつくりだしたという視点から、ウェブの来し方もウェブの行方も昨日と明日のアメリカ文化をどう論ずるかということに符合するはずなのだから、それを論じれば今後の世界文明の問題も見えてくるのではないかという立場をとって、何とも大げさに御託をならべては、放置された喜寿祝いを旦那がどう意識しているのかを問題にした。
「 へ~ッ、旦那のミー文化が、今やそんな大問題になっていますか・・・・・ 」
そこで少々薄らとぼけた沙樹子は口休めにと、一端奥に下がり、さりげなく麦茶と音羽錦を森鳩の前に差し向けた。
「 さきほど旦那が作りましたの、我が家の小さな秋・・・・・ 」
比江島家ではいつも沙樹子が亭主役である。21世紀の文明がろくな提示をしていないと感じているのは森鳩もそうだが、旦那だって同じことだろう。特に価値観については同じはずだ。しかし森鳩と旦那とでは大きな違いが一つある。森鳩はウェブを文明だと考えているようだが、旦那の方は未だ文明でありえるのかと監察状態にあることだ。どちらかといえば文明視することを停止した。
その旦那が焚き出した小さな夏の秋、パクリと口に趣かせた森鳩を、音羽錦がどう介錯してくれたのかは分からないのだが、あの老紳士が馥郁(ふくいく)たる秋の香りを逃がすはずもなく、1時間ほど長居した森鳩は、喜寿祝いが保留されている件に念押して帰って行った。
沙樹子の旦那は普段、日本という国家を議論しはしない。国家という主題をあげつらわない。還暦を過ぎた旦那の関心はあくまで「日本という方法」にある。しかし世界史上の国家の相互関係についてならば、リタイヤを返上し大いに議論する。比江島修治とはそんな男であった。


八月も盆を過ぎると、雨乞いでもしたくなる残暑のなかに、次の季節が姿をみせてくる。
掘り出したサツマイモがその一つ。沙樹子の旦那はこの芋を、クチナシで黄金色に染め、蜜煮にする。するとやがてくる秋が、一足早く装いも鮮やかに粧旬となる。これを旦那は「音羽錦」と呼んで白磁の皿によそいでくれた。つまり使う素材を産地名ではなく我が調理場を引き出してくるのは旦那の遊び心、しかしこの素朴な粋を想像して、しっとりとした黄金色を口に運ぶと、残暑のそこに、すっきりとした秋の風味の驚きがあるのだ。サツマイモは、60℃程度の温度で長時間調理すると、でんぷんが糖質に変わり甘味を出す。
そんな旦那の手順は、まず下煮したイモに、硬くならないように糖度の薄い蜜、濃くした蜜と、二段階で甘さを含ませる。しかしそのイモの下煮がやはり要となる。たっぷりの湯と、イモが踊らない火加減を守り、煮崩れない加減状態をキープしつつ軟らかくする。旦那が見るのは時計より鍋の中、そして串を刺したときに、指に伝わる感覚で〆とする。旦那はこの串の材質と細さにも拘った。沙樹子は京都から節目正しい上賀茂産の竹を取り寄せる。毎年、こうして芯まで甘みを含ませて「なごみのひとときを、どうぞ」と差し向けてくれた。
「 だからといって私の旦那を、万能の天才などと思わないほうがいい。たんに名付けるなら説明がつかない多能の持ち主だ。でも、こんな肩書を見させられているだけでは、ひょっとしたらインチキなのかもしれないのかどうかも、分からないだろう。まして、今日のアート・パフォーンスの大半が旦那のような男の周辺から出てきたらしいということなど、決して世間には見えてはこないに違いない。これは、ま、妻だけが感じられる特異な才能なんてそういうものなのだから、この一風変わった旦那の解釈なんて焦らないほうがいいのだが、それでは旦那が渇水で干からびることになるだろうから、方法はともかくも石地蔵の由来に沿って、旦那がどういうことをしてきた男であったのか、ところどころに妻の感想を挟みながら石地蔵の頭を叩いてみたいのだ。これによって雨が降るかは、それは旦那次第だ・・・・・ 」
と、いうことだから旦那もやたら凄い女と出会い、二人は大学時代に、かなり濃密で危うい時を交わしあった。沙樹子は旦那に、つまりは望み通りのことをした。ようするに学生の若い旦那は、何としてでも背伸びしたかったわけである。その旦那は期待に応えて沙樹子を思う存分ぐにゃぐにゃにした。戦後のサバイバルを二人して謳歌した。雨乞いは、その旦那への恩返しのつもりでもあった。
その旦那とは、すでに二人の暮らしにひそむ「たくさんの私」のうちの何人かぶんの自己そのもの、沙樹子の自己群なのだ。
誰にも経験があることだが、美容室で洗髪して結ってもらったあと、肩筋や背中の肌のどこかに髪の毛が一本でもひっかかっていれば、どうにも落ち着かなくなるものだ。蚊がチクリと一刺ししただけでも、かゆくてたらない。ましてバッタやサソリがもぞもぞ背中を動いていれば、信じられないくらいに跳び上がる。皮膚はのべつまくなく異物と闘ってくれている戦場なのである。嫌いになった男に触られただけで、ぞっと鳥肌がたつ女性も少なくない。いやいや沙樹子の場合、そういうフィーリングのことだけではない。この旦那と二人して培った皮膚にはもっといろいろな機能がひそんでいる。枯れそうであるが、未だ可能性の余白が旦那には十分残されていた。
「 今の旦那は口とペンしか持てないが、日本だけを議論したいとは思わなかったのだ。それが旦那のラディカル・スタンスだ 」
そろそろと言挙げすることになるのであろうが、旦那の「日本という方法」は日本という国境には決して縛られないのである。きっと宇宙を下敷きにした国家日本の議論案内を試みることになろう。
国家とは何か、とくに日本という国家はどういうものなのかという問題は、一筋縄の議論では語り尽くせない。政治家が、今日の問題を日本という国家の問題としてちゃんと説明できるのかといえば、おそらくお手上げだろう。どうにも国家を主語とした議論は避けている。政治家は「是々非々」というが旦那には迷惑なことなのだ。国家を議論することには現在、多くの国民にひどい躊躇揺動がある。旦那は多くが躊らうこの問題にやや野蛮なほどにとりくんでいる。
「 歴史から切り離された国家はありえない・・・・・ 」
こんなことは沙樹子にも分かる。歴史観のままに戦前・前後をつなぐ見方を新たに確立しなければならないのだが、大問題は、それがまったくうまく繋がらないままになってきた。しかも、この二つのあいだには極端な断絶ができた。旦那はこの断線を科学的にどう復旧して、人文精神的にどう精査して連結させるかの、日本の方法に向かおうとした。



「 最近、ご主人が怠け者だと感じることはありませんか・・・・・ 」
と、五年前に、H医師を名乗る男からの電話口で、そう唐突に尋ねられた。
その2008年8月26日から8月31日にかけては、日本の紀伊半島から関東地方までの太平洋岸を中心に襲った豪雨災害の渦中にあった。都内でも積乱雲による激しい雷雨となっていたため、東京電力管内では約18,000戸が停電した。電話の呼び鈴を覚えたのは復旧後の夕刻であった。とりわけ八王子市で激しい雨が降り、京王高尾線の高尾~高尾山口間で土砂崩れがあり、高尾山口発高幡不動行き上り各駅停車が脱線した。その高幡不動とは通称である。
本尊を不動明王とする金剛寺(こんごうじ)は、日野市高幡にある真言宗智山派別格本山の寺院、寺号を高幡山明王院金剛寺とする。この寺は、平安時代初期に慈覚大師円仁が清和天皇の勅願により東関鎮護の霊場を高幡山山上に開いたのが始まりとされる。そして江戸時代、真言宗関東十一檀林の寺院として、多くの学僧を輩出した。以来「高幡のお不動さん」と呼ばれ人々の信仰を集めており、毎月28日の縁日には多くの参詣者で賑わうのであるが、天候が不順でなければ沙樹子も訪ねる予定であった。
この高幡には比江島家の小さな農園がある。8月の不動詣での帰りには毎年そこから新サツマイモを掘り起こした。
「 一見もないH医師から唐突にそう聞かれても、旦那の皮膚はそもそも皮膚呼吸をしているわけである。生物学や内科学では皮膚呼吸のことを「体表による外呼吸」と呼んでいる。つまり旦那は体全体で呼吸をしている生物なのだ。怠け物ではない。その旦那の体表である皮膚にはまた、汗腺や脂腺も満ちている。同じく沙樹子もまた汗の分泌身体であり、臭いや汚物の排泄身体なのだ。それらは人間の眼で見る限り紫外線や色素とも体臭とも、しょっちゅう仲たがい(トラブル)をおこしている。このせいで、シミにもアセモにもニキビにも悩まされることになる。香水をつけすぎることもある。何でもないようなホクロだって、れっきとした皮膚信号であり、18世紀の顔相学がしきりに主張したように、ホクロやシミは存在の暗部の情報なのである。旦那が怠け者に見えるとき、それは、つまりは皮膚はかぎりなく表層的であって、かぎりなく深層的なのだ。もっと言うのなら界面的なのだ。こんなに多機能で敏感な旦那の皮膚に怠け心が動いているはずがない 」
と、突き返してみたいのだが、しかしあらためて考えてみると、沙樹子はこのような旦那の体表をどこで、どんなふうに実感できているのだろうか。美容室の帰りに背中で感じる毛髪の異和感を感知しているだけで、体表的自己の発生にまでさかのぼれるだろうか。好きな男女が肌を合わしあっているだけで、誰もが体表に包まれた自分を感知できるのだろうか。
そもそも人類の歴史には、そのような体表をめぐる体感の痕跡をのこしてきた記録があるのだろうか。あるいは皮膚や体表が主人公になった物語があったのだろうか。少なくともこれまでのフロイト主義者たちはそのあたりの証拠をあげようとはしなかった。従ってH医師の質問とはまったくの愚問だとしか思えなかった。
「 日本国家と日本社会は異なっているのだ。僕も、国民も、これをごっちゃにしてはいけない。国家は社会そのものではない。社会を超越することもある。国民に財産の一部を拠出させる納税の義務を負わせ、他国の侵略に備えるために兵役の義務を負わせるとき、国家は社会の上に立つものだ。このように国家が権力としてのパワーを堅持するのは、軍事力・経済力・教育力を保持するためである。この権力には、必ずいくつものオーソリティと、国民の義務がつきまとう。一般的なネーション・ステートのとき、権力は軍事力・警察力・司法力に象徴され、この義務は納税の義務や兵役の義務に代表される。このことは国家があきらかに社会より超越したものだということをあらわしている。そもそも権力とはいくつかの国家装置によって支えられている。したがってこの国家の下に人が居るとき、その人とは国民ではなく、単なる人間として存在する。人間に国民という権力を与えては、国家の権力は堅持できないのだ。国民であることを所望する僕は、人間でいることを否定し、この国家を幻想のモノとして提起せねばならないのだ 」
これは旦那がセルバンテスの「方法」を持ち出して整理しようとしたであろう手記の断片である。現在の医療制度もこの国家装置とつながっている。多くの医師もH医師も、この装置内にいる人間である。この人間が旦那をうつ病と診立るのであるから、その診断は権力が下したうつ病となる。それは旦那の本望ではない。沙樹子は国民としての修治に寄り添おうとした。


「 そもそも敗戦に帰した日本人が、遊牧的な革新性や猟奇性および戦闘性を根底で疼かせてどうなるのか・・・・・ 」
沙樹子は何度か銀座の一角で中国人旅行者を撮る日本人記者のシャッター音を聞いた。求められてポーズに応える場面などはない。一方的なフォーカスである。あるいは和風パパラッチの盗撮なのだ。批判姿勢ならまだしも、これは儒教に象徴される中国的保守思想の歴史的な反感なのである。日本人はこうした感情もコントロールできなくなってきた。歴史的な国家論に振り回されている。
さてそこで沙樹子は、旦那を裸にして木に吊るし、両腕を枝にくくりつけた。さらに体の数箇所をを切り裂き、傷口から血をしたたらせた。まためぐりきた八月末の雨乞いの空に、そう旦那を描き起こして、沙樹子みずからが一口大きく深呼吸をした。
沙樹子は大空を借景して旦那の人柱を建てたのだ。
「 ここで、妻が動揺などしたらダメだ・・・・・ 」
メトロスの赤いハートをみて、そう覚悟を決めた沙樹子は、護国寺駅5番口を出ると、南の目白坂下の方へと歩いた。
出口から自宅まで約1キロの道だが、何とも長く感じる乾いた白い真昼の距離であった。
そして八幡坂(はちまんざか)の細い石段を上りながら沙樹子はまた「妻が動揺してどうする」と覚悟を固くした。先ほど新宿のJR総合病院の担当医浜田から旦那が「ここ数年、うつ病なのだ」と、そう打ち明けられたからだ。
うつ病という診断より、それを数年間、気づいてない沙樹子という妻がいることがショックだった。
思えば二ヶ月前に、夫の修治が普段通り勤めに出たのだが、毎日携帯すべきパソコンのハードケースごと書斎の机に忘れていた。それ以来、旦那の素行に疑問符をつけたくなる小さな不可思議が度々あった。そして修治の引き出しから一枚の診察券を発見した。
たしかめると、あのH医師の、しかも神経科ではないか。
普段なら帰宅してまず一番に風呂に入る旦那である。しかしここ一ヶ月ほどその定形が自由律詩のように崩れていた。風呂の前に、まず一杯の缶ビールを飲み、そのまま仮眠する。あるいは二階の書斎から窓の外をぼんやり見ていたりする。さらには風呂が夕食後になったりした。しかも入浴せず就寝することも度々あった。そこで担当の浜田医師と1時間話を詰めた。まさしくこれらが、うつ病の徴候である。
「 本人は、すでに病気のことは承知しているのだ。そうすると・・・・・ 」
翌朝、沙樹子は初仕事に雨乞いをした。これは今後、旦那をどう看取るかの初仕事なのだ。
高台の自宅から八幡坂を下る途中、階段脇に一体の古い石地蔵がある。
沙樹子は早朝、棒で叩くと雨を呼ぶと伝わるその石地蔵に、願をかけた。
雨は降りすぎれば厄介だが、干天(かんてん)なら慈雨と呼ばれ、恵みの雨と拝まれもする。照れば雨を、降れば陽光を、人間はこれを求め続けてきた。しかし天候には、降っても照っても農家は気がもめる。そこで人間は、科学的な雨乞いを発明した。人工降雨装置なるものがそれだ。雨を降らせたい地点に、ヨウ化銀の溶液を燃やして煙を上空に放つと、煙の粒子が雨粒をつくる理屈がそこに応用されている。そんな理屈が旦那の心のひび割れにも通じれば、石地蔵の頭など叩いて雨乞いの願かけなどせずに済むのだが、と科学よりは仏にすがることを決めた沙樹子は、石地蔵の頭を三回叩いてから合掌する。一回叩くとご利益ありと聞いていたが、余計な二回分は念のためだ。
「 無論、その真意を修治に気づかれてはならない。それが願かけの掟だから・・・・・ 」
と、その後も沙樹子は早朝の散歩とばかりに自宅を出て石地蔵の頭を叩き続けてきた。戦後の日本には、復興期よりこびりついた日本病がある。それは新憲法と結びついた資本主義下に漂白される脱水症と、瑞穂以来の農耕の知恵を忘れた痴呆症である。歴史をさかのぼって日本種の起源を思い出し、国家という頚木(くびき)から脱した新たな思想と社会性をもって未来に対応しなければならない。そもそも国を家とする国家郭図が21世紀にして封建的詭弁ではないか。家長に仮面した首相の選出、旦那はこのブロイラー化を拒もうとした。
世界文明はこれまで狩猟・牧畜・農耕・商業・貿易・航海・工業という7つの業態活動をエンジンにして拡大される。この列強国とまみれる日本は明治維新前、農耕のみがきわめて自給自足型で、たとえ閉鎖的になろうと退化がおころうとも、競争・交換・交雑の必要がなく育まれてきた。敗戦問題とは別にして、日本は近代になるとさっさと脱亜入欧をして豹変したが、農耕の民質を疎外した偏向意識こそが日本現代化の背景に噛み千切るように働いている。



「 お百度も過ぎたのに、雨は降らないわ。やはり私では、降らないのかしら・・・・・ 」
そう言いながら沙樹子はたゞ毎朝笑っている。
志があれば利刃のごとく百邪を払うという。百邪すべてが払えずとも数十邪が逃げていく。また、志は清泉のようなものである。自分という小川に泉がゆっくりと湧き出ていれば、そこへ向こうから濁水が入ってくることはない。清泉には緩まぬ湧出がある。清泉は悩まない。志をもつとは、この湧き水を絶やさないと決断することなのである。この故実に手習い、そういう志をもつには、では沙樹子はどうするかということで、近所にあった石地蔵がとんだトバッチリとなった。
「 あの地蔵、雨を降らさないと、叩かれ損だ・・・・・ 」
と、誰のために地蔵が叩かれ、何のために沙樹子が雨乞いをするのか、何も意に介さない修治がいた。
石地蔵を叩いて、雨が降ることはなかろうが、また沙樹子のせいでもなかろう。そんな話など引き出して明るく振舞おうとする沙樹子に、比江島修治は遣りようもない苛立ちも打ち消されるかのようで救われていた。
「 石川啄木もたしかあの地蔵には願をかけたという話が伝えられているわ 」
八幡坂とは、文京区音羽2丁目4番(坂上部は25番)と6番の間にある、階段の付いた坂道である。今宮神社の北、音羽2丁目4番と6番の間を西から東に上り、途中北に折れて、音羽2丁目25番と6番との間を上る。細いほそい階段の坂だ。
この坂の南側に、坂名の由来となった田中八幡宮があったが、その場所に現在は今宮神社が鎮座する。
つまり明治時代のはじめまで、現在の今宮神社の地に田中八幡宮があったので、八幡坂とよばれた。さらに坂上の高台一帯は「久世山」といわれ、かつて下総関宿藩主久世氏の屋敷があった所である。
盛岡中学校を卒業直前にして退学した啄木は、文学で身を立てるため、明治35年(1902)単身上京した。
そして、中学の先輩で金田一京助と同級の細越夏村の旧小日向台町にあった下宿を訪ねた。明治35年11月1日のことである。啄木はその翌日、近くの大館光(みつ)方に下宿先を移した。その啄木日記には「室は床の間つきの七畳。南と西に橡(えん)あり。眺望大に良し」とある。ここで与謝野鉄幹・晶子らに会い、文学に燃焼した日々を過ごしたが、しかし生活難と病苦のため翌年2月、帰郷せざるを得なかった。八幡坂の坂上近くに、その石川啄木の下宿跡がある。この時期の啄木をどう詮索しても雨乞いの理由は藪の中だ。だがその雨で、彼が一握の砂を湿らせてみたいと願望したのであれば、とするその空想だけでも沙樹子にはご利益があるようにも思われた。
音羽は、東京都文京区の北部に位置し、南北に細長く、最南端で神田川に接する。ここらは閑静な住宅街、音羽通りを挟む谷(音羽谷)の崖下と崖上に跨る街である。そして大手出版社であるKD社や音羽グループK社、また宇宙のごとく鳩山会館などが存在する。
1697年(元禄10年)に護国寺領となり町屋にしたが人が入らず、桂昌院の信任が厚かった奥女中の音羽という人物にこの門前町が与えられたため「音羽町」と名付けられた。
またここには、音羽の谷から小日向台地へ上る急坂である「ねずみ坂」がある。
この鼠坂の名の由来について「御府内備考」は「鼠坂は音羽五丁目より新屋敷へのぼる坂なり、至てほそき坂なれば鼠穴などといふ地名の類にてかくいふなるべし」とある。
森鴎外は「小日向から音羽に降りる鼠坂と云う坂がある。鼠でなくては上がり降りが出来ないと云う意味で附けた名ださうだ・・・人力車に乗って降りられないのは勿論、空車にして挽かせて降りることも出来ない。車を降りて徒歩で降りることさへ、雨上がりなんぞにはむづかしい・・・」と小説「鼠坂」でこの坂を描写している。また「水見坂」とも呼ばれていたという。この坂上からは、音羽谷を高速道路に沿って流れていた「弦巻川の水流」が眺められたからである。
以前、二人はこの「八幡坂」と「鼠坂」の二つある坂道を周遊してよく散歩したものだ。右回りに、左回りに、二つの坂を回ると約800メートルの散策道となる。日毎その順路を変えるのだが、そのために二つの坂は、交互に下り坂となり上り坂となった。
「 畳は自立したからこそ、日本のモノになった。座るだけでは畳じゃない、考える場所として畳は自立したのさ・・・・・ 」
日本ではスタティックな型から、動きや気配をともなうアクティブな間が生まれた。かって修治はこの坂道で、その理由を丹念に説明した。元来日本にはさざまな隙(すき)があって、その隙こそが次の調度の可能性をもたらしたことを強調した。こうして障子や屏風や壁代や簾といった「和の調べ」をもつ調度品が生まれたのだった。日本家屋の中で床の間は、いまでこそ生意気に座敷の大事を主張しているけれど、実際には、畳が板の間に重なり、廂に廻され、そのうえで座敷に敷かれたために、やむなく空いて生じた隙間スペースだったのである。それがみごとに自立していったのだ。
人生半ばにしてそれでも失望や痛痒を感じたり、人望から見放されてみなければ、この畳が自立した刺激を実感できないことだったのかもしれない。患いなくして刺激なし、うつ病もまた由ということになる。


心の病にかかる人間が増えてきた。特にサラリーマンが増えている。
大企業の社員が入る健康保険組合では、心の病の受診数が近年2割増えた。仕事のストレスが原因となる病気が大半を占める。今朝、そう新聞が報じていた。これは08年のリーマン・ショック後の景気低迷により、日本企業のリストラが進み、雇用不安を引き起こしたからだ。
「 心と体との対話を、常に心がけて下さい。あなたの場合、それも毎時間ごとに、不調のサインを見逃さないことが大切だ。無理をせず、養生して、しかし原則として薬を飲んで、たゞ回復を待つこと。おだやかにチェック&ビルド、そこに希望はありますよ・・・ 」
と、先日もまた繰り返し、主治医の浜田一平からそうチクリと釘を刺された。
「 これでは、仕事ができなくなる・・・・・ 」
うつ病は、働く人にとって非常に切実な症状だ。いわば仕事ができなくなる。最初のうちは「勘がにぶる」「アイデアが浮かばない」くらい。やがて物事の優先順位が分からなくなってきて、何が大切なのかピンと来なくなる。そして体の動きが遅くなる、口数が減る、会議で自分の意見が言えなくなる、というのも起きてくる。しかも物覚えが悪くなったり暗算が苦手になる。
比江島修治の場合も、実際に仕事の能率が落ちてきた。
そうして仕事の能率低下を覚えると、その自覚は周囲へと散乱する。「自分はもうダメだ」「まわりに申し訳ない」という自責念慮という考えが出てくるようになる。そうなると悪循環が始まって症状がどんどん進んでしまう。こうして症状が進むと何をすべきか全然分からなくなる。この症状が進むと何もないのに修治は泣いてしまうのだ。
何か悲しい出来事があったわけではない。そうだから気分転換でスカッと忘れることも出来ない。修治の症状には、そんな思い当たる節がない、自動的な不安や悲しみが継続した。
最初のうちは楽しいことが起きれば楽しいと思う感覚も残っていたが、何もしないと漠然とした嫌な気分がよみがえってくる。この先何も良いことがないのじゃないか、自分はダメなやつだ、何をしたってムダなのじゃないか、という考えも起きてくる。そこで医師浜田からは「精神運動抑制」だと診断された。そう聞けばたしかに、やる気が抑え込まれている。
「 昼間からは平気だから、自分はまだ大丈夫なんじゃないか、と思っているとこれが良くない。その変動こそがうつ病の特徴・・・・・ 」
と、浜田医師はいう。
この忠告も思い当たる自覚があった。最初のうちは朝の出社や登校がつらいというところから始まる。特に何か嫌なことがあるわけじゃなく、どうしても行く気が起こらないのだ。でも行かなきゃいけないことは分かってるので悶々としてしまう。すると布団から出るのさえ嫌で、さらに朝そのものが嫌になる。
そんな比江島修治は、だから朝だけは、かなり注意を集中させる必要があると感じた。
だがそうした朝だけに限定した意識が、すでに昼間のストレスを生じさせているのだと浜田医師は指摘する。うつ病は本人がその正確な不調に気づかない場合が多い。生真面目で実直な人間ほど、時間内に仕事を処理したがるものらしい。真面目人間は、疲れがたまって具合が悪くなるのを防ぐため、さらに細心の注意をはらうことになる。しかしそれでは二倍のストレスを抱え込む。たしかに修治は疲れているのに眠れず、毎晩酒をあおった。近年の修治はそんなうつ病を抱えて日本の情報化時代に対応しようと悩み続けてきた。
発症したのは、D広告代理業東京本社で働いていた5年前、担当する情報通信関連企業の発注量が急に増え、毎日5時間の残業が恒常化していた。酒はそうした人間には合法的なカンフル剤だ。だがその酒はしだいに量が増える。食欲は減退するが、飲酒欲は増進する。酒を切らした深夜、一度、キッチンで包丁を握って首にあてているのを、妻沙樹子が泣きながら止めた。残業した帰宅後も処理しきれない仕事のイライラが治まらず、不眠に悩まされていた。たしかにそれは異常なことなのだが、沙樹子もそれが、うつ病の徴候とは気づかない。互いに仕事上のストレスだと判断し、以後、家庭内トラブルを軽減することだけに努めていた。
旦那のうつ病には案外リーダビリティが起伏する。読み手である沙樹子の都合を持ち出すのも、うつ病なのである。これは沙樹子の持論なのだが、とするのなら、旦那のうつ病は、沙樹子の夫婦小説で、浜田医者のいう旦那の『うつ病』は知り合いになりたくない男の話なのだ。『仕事優先のうつ病』は名文なんかじゃなく、『旦那が治そうとする病』はただの妄想の産物で、『現代病』は傲慢の成果にすぎなくなる。したがって沙樹子が編集する旦那のうつ病は、妻という名うてのプロの旦那読みが、明治以来のベストセラーな男性を片っ端から俎上に上げた辛口談義なのだ。うつ病にもこういう旦那の読み方があることを、浜田医師に感じてほしいのである。
もしも日本人の美意識に投影された父的あるいは母的包括性のようなものがあるとするなら、そこには日本における「未明の父なるもの、母なるもの」の連続があるはずなのだ。
ドン・キホーテは聖書の次に世界的に出版されており、正真正銘のベストセラー小説で重版されてロングセラー小説でもある。この作品は、それまでの物語とは大きく異なる技法や視点が導入されていることから、世界初の近代小説ともいわれる。年老いてからも夢や希望、正義を胸に遍歴の旅を続ける姿が多くの人の感動をよんできた。
この連続にこそ未明の父なるものとするセルバンデスの連続性がある。そして本編の主人公の本名をアロンソ・キハーノという。このラ・マンチャ地方に生まれた男が、未明なる父と母の歴史に熱狂し、ドン・キホーテと変身して連続する。
日本はそもそもが常世(とこよ)の国で、翁(おきな)の国で、そしてマレビトの国としての「妣なる国」なのである。このように「母なる」と「父なる」が連用的につながっている。それがつながるままにセルバンテスは、比江島修治にとっての「母なる父」なのだった。こうした根本の問いを発しつつ旦那は羽田空港へと向かっていた。
うつ病から和製ドン・キホーテが産まれだそうとする。沙樹子は風が吹き上げたかのように愉快だった。