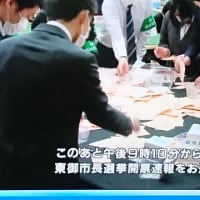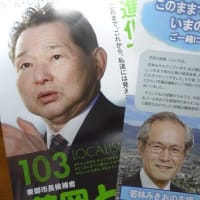温泉施設については現在年間利用券があります。これは年会費4万円を支払えば、市内のどの温泉施設も年間を通して利用できるというものです。これは温泉施設の利用促進を目指して導入され市民にとっても誠に便利な制度であり、現在1100名の方が利用しておられます。しかしこれが温泉施設の経営に影を落としていることは案外知られていません。
温泉施設がいずれも利用客を減らしている中、ゆうふるtanakaだけはこの3年間で1万4千人も利用客を増やしています。しかし収入増には結びつかず逆に4百万円減となっています。利用客が増えているのに収入は減るというおかしな現象がいま起きています。なぜでしょうか。
ゆうふるtanakaの年間入館者数は平成21年度で27万5000人で、入館料は9200万円となっています。利用者一人当たりの単価は334円です。ゆうふるtanakaを利用すると500円かかりますが、実際の単価はこれよりも166円も低くなっています。平成19年の単価は371円でしたから、ここ2年間で37円も下がってます。こうした状況の背景にあるのが年間利用券の存在です。
こうした年間利用券の問題は以前から指摘されていましたが、その利用実態はなかなか明らかにされてきてはいませんでした。そこで先日係の方にお願いして施設ごとの年間会員の数を教えていただきました。すなわち平成21年の年会員数は1474名(湯楽里館355名、ゆうふるtanaka431名、御牧乃湯257名、明神館122名、その他309名)で、この2年間で400名増となっています。
ゆうふるtanakaの場合を考えて見ましょう。431名の会員の年会費は、年会員と半年会員合わせて1800万円。入館料が9200万円ですからここから1800万円を差し引いた7400万円が一般利用者の入館料だと思われます。これを一般利用客の入館料500円で割ることで一般利用者数がわかります。14万7800名となります。
27万5000人のうち14万7800人が一般利用者で、のこり12万7000人が会員利用であったことがわかります。会員利用率は46.2%、すなわち一日の利用者の半分は年会員の常連さんです。平均の年間利用回数は295回にもなります。
こうしたヘビーユーザーが多いことがゆうふるtanakaの経営にどのような影響を与えているのでしょうか。仮に会員利用者数12万7000人に正規の利用料金500円をお支払いただくとすれば、6350万円の利用料金が入ってくることになります。実際の会費は1800万円ですから4560万円の逸失利益があったことになります。平成20年のゆうふるtanakaの営業損失は3650万円ですから十分黒字化は可能だったことになります。
むろん、年会費制度をやめればこれだけの利用は見込めないと思いますが、少なくとも年会費4万円という額は利用実態に見合っていないのではないでしょうか。平均利用回数295回に500円をかけると14万7500円になります。この利用料が4万円で済むのですから約10万円もの利益になります。これは市民公平の原則から逸脱していないでしょうか。ましてや温泉施設には市は毎年1億円前後の公金を支出しているのです。
また、年会員のお客さんはお風呂に入ることが目的ですから滞在時間もごくわずかで、食堂を利用したりお買い物をすることはほとんどないと思われます。もともと温泉施設の収入源は飲食の利用にあります。温泉部門が赤字でも飲食・宴会部門の黒字で利益をあげるという構図になっています。こうしたお客さんが増えることは温泉施設の経営をさらに圧迫することになります。
ちなみに御牧が原で営業をしている「ホタルの湯」には年間利用券制度はなく、回数券による利用を行っているそうです。年間利用券のあり方を考える時に来ているのではないでしょうか。
温泉施設がいずれも利用客を減らしている中、ゆうふるtanakaだけはこの3年間で1万4千人も利用客を増やしています。しかし収入増には結びつかず逆に4百万円減となっています。利用客が増えているのに収入は減るというおかしな現象がいま起きています。なぜでしょうか。
ゆうふるtanakaの年間入館者数は平成21年度で27万5000人で、入館料は9200万円となっています。利用者一人当たりの単価は334円です。ゆうふるtanakaを利用すると500円かかりますが、実際の単価はこれよりも166円も低くなっています。平成19年の単価は371円でしたから、ここ2年間で37円も下がってます。こうした状況の背景にあるのが年間利用券の存在です。
こうした年間利用券の問題は以前から指摘されていましたが、その利用実態はなかなか明らかにされてきてはいませんでした。そこで先日係の方にお願いして施設ごとの年間会員の数を教えていただきました。すなわち平成21年の年会員数は1474名(湯楽里館355名、ゆうふるtanaka431名、御牧乃湯257名、明神館122名、その他309名)で、この2年間で400名増となっています。
ゆうふるtanakaの場合を考えて見ましょう。431名の会員の年会費は、年会員と半年会員合わせて1800万円。入館料が9200万円ですからここから1800万円を差し引いた7400万円が一般利用者の入館料だと思われます。これを一般利用客の入館料500円で割ることで一般利用者数がわかります。14万7800名となります。
27万5000人のうち14万7800人が一般利用者で、のこり12万7000人が会員利用であったことがわかります。会員利用率は46.2%、すなわち一日の利用者の半分は年会員の常連さんです。平均の年間利用回数は295回にもなります。
こうしたヘビーユーザーが多いことがゆうふるtanakaの経営にどのような影響を与えているのでしょうか。仮に会員利用者数12万7000人に正規の利用料金500円をお支払いただくとすれば、6350万円の利用料金が入ってくることになります。実際の会費は1800万円ですから4560万円の逸失利益があったことになります。平成20年のゆうふるtanakaの営業損失は3650万円ですから十分黒字化は可能だったことになります。
むろん、年会費制度をやめればこれだけの利用は見込めないと思いますが、少なくとも年会費4万円という額は利用実態に見合っていないのではないでしょうか。平均利用回数295回に500円をかけると14万7500円になります。この利用料が4万円で済むのですから約10万円もの利益になります。これは市民公平の原則から逸脱していないでしょうか。ましてや温泉施設には市は毎年1億円前後の公金を支出しているのです。
また、年会員のお客さんはお風呂に入ることが目的ですから滞在時間もごくわずかで、食堂を利用したりお買い物をすることはほとんどないと思われます。もともと温泉施設の収入源は飲食の利用にあります。温泉部門が赤字でも飲食・宴会部門の黒字で利益をあげるという構図になっています。こうしたお客さんが増えることは温泉施設の経営をさらに圧迫することになります。
ちなみに御牧が原で営業をしている「ホタルの湯」には年間利用券制度はなく、回数券による利用を行っているそうです。年間利用券のあり方を考える時に来ているのではないでしょうか。