
本年最初のブログとなります。遅ればせながら、本年もよろしく御贔屓の程、お願い申し上げます。
あたくしの青春時代はフォーク全盛期でございまして、井上陽水、かぐや姫などが活躍していました。なかでも広島で15~20歳を過ごしたこともあり、吉田拓郎に傾倒していました。彼の歌のコピーを当時所属していた軽音楽同好会でもずいぶん演りました。彼の「ライブ73」というアルバムがあり、結構ハードなロックともいえるナンバーの中で「野の仏」という唯一アコースティックな曲があります。かぐや姫の南こうせつの釣りをする姿に、間近にあった野の仏がほほ笑むように感じるという状況をうたった歌です。作詞は岡本おさみなので、拓郎が感じたのか多少疑問ではありますが、この歌が好きでした。バックバンドにはハモンドオルガンで松任谷正隆が、そしてギターには高中正義が参加していました。拓郎も引退したし、ちんぺいさんも亡くなり、陽水も久しく見ていませんが、南こうせつは先年末の紅白にミニスカ姿のイルカと一緒にでていましたね。彼を見るたびにこの歌が脳裏に浮かびます。著作権の問題があるため、ここでは紹介できませんので、ユーチューブなどで視聴戴ければと思います。
で、今回のお題は「野のほとけ」でございます。
ここちはら台では宅地開発にあたり、遺跡発掘調査を行いそのあたりにあった野の仏はどのように処分されたのか、少し疑問に思っています。由緒正しい縄文・弥生・飛鳥時代の遺跡・遺物は多分それなりに処遇されて、例えば歴史博物館などに所蔵されていると想像されます。これは宿題でそのうちに調べてみましょう。
明治になり以前何度か紹介したように、神仏分離政策と決して政府主導でないにせよ多くの廃仏毀釈が行われ、神社やお寺に(当時は神仏一体でした)あった非常に多くの仏像は廃却されてしまいましたが、道筋などにおかれていた野の仏たちはそのまま置かれていたり、まとめて集められたりしたようです。いまでもちはら台を一歩出たところには例えば大宮神社の参道とか、草刈公民館に隣接する弁天様を祭る神社の傍らに、まとめて置かれています。
無論京都や鎌倉の寺院にある国宝級の仏師が彫った仏像ではありませんし、円空仏のように価値がべらぼうなものでもありません。またすべてが仏様ではないようです。
多分仏としては、地蔵菩薩(6体のものも含めて)と観音菩薩。それもこの辺りでは圧倒的に多い馬頭観音。そして不動明王などの明王像。仏像以外では村や在所の境界におかれる民間信仰の道祖神や庚申塚が挙げられます。
何が違うのかちょっと興味があり、書籍を中心に調べてみますと、まず仏像。
非常に身近な仏様としてあちこちにあるのが、地蔵菩薩と観音菩薩。
お地蔵様は他の菩薩(特に密教系で絢爛豪華な宝飾品に飾られた、ただし密教の胎蔵界曼荼羅では地蔵菩薩も有髪で表現されます)に比べると頭を丸め(円頂)錫杖と宝珠を左右に持った主に立像として表現されます。釈迦入滅後56億7千万年後に下生する未来仏、弥勒出現までの間、すなわち無仏の時代に衆生の済度を受け持つ菩薩でございます。
修行中(菩薩:ボディ・サッタはもともと修行中の存在ではありますが)に呼ばれたので円頂のままというのが、一般的な解釈です。もともとはバラモンの大地の神から派生したものと言われ、毘沙門天のブログでこの辺りはご紹介しました。
日本では奈良時代から信仰を集めていましたが、平安後期の末法思想の盛んだった時代に広まったといわれています。その中で六地蔵について。
もともとはインドの(仏教というわけでなく)輪廻思想に発していますが、人間は死ぬと地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の六道のいずれかに行き、それを繰り返すということで、その輪廻から脱するのが、涅槃であり悟りであるとされます。この六道それぞれにあって衆生を導くのが地蔵菩薩とされ、それぞれの道の地蔵を表したのが六道地蔵ということです。薬師如来や阿弥陀如来は7体であらわされますが、これは別のお話です。
この信仰は民間で盛んになり路傍や、墓地などに立つことになります。江戸時代にはさらに発展し現世利益としてとげぬき、延命、子育て、身代わりなどとそれぞれに効能がある尊体となっていきます。特に早世した幼児の守り本尊として水子供養や、賽の河原の地蔵(地蔵賛歌)となっても参ります。流行からすれば室町時代に西日本で一般化し、戦国から江戸時代に関東で多くなってまいります。特に冥界に行く死者を救うとして様々な形の六地蔵や丸彫り立像などが、路傍に立つようになります。

(椎名小学校近くの尊像)
次に観音様。こちらはいわゆる大乗仏教で般若経系(特に般若真経では主役ですな)、妙法蓮華経(法華経)で現れますが、現世利益の救済を施す菩薩です。観世音というのが中国語に最初に訳された表記ですが、般若真経を玄奘三蔵が訳したときにアヴァロキティの直訳に近い、観自在菩薩とあらわされました。が、これは一般的にはならなかったようですね。
南海補陀落山にお住いの観世音菩薩の中で、特に東日本で路傍に多いのが、馬頭観音でございます。この辺りは特に多い。観音さまの仏像は聖観音、千手観音、如意輪観音、准堤観音、十一面観音、さらに楊柳観音などと像や絵に描かれますが、唯一憤怒面を表すこともあるのが、馬頭観音です。頂上に馬頭をいただくところから馬頭観音と表されます。
いろいろな形がありますが、本来の形としては4面2臂像で正面は菩薩面左右2面が憤怒面、そして頂上の面の上に馬頭をいただく。正面も憤怒のものがありまありますし、どちらかといえば野の仏にはこちらが多いような気がします。もともとはヒンズー教のビシュヌ神が馬頭に変身して敵を打ち破ったという神話から来ているともいわれます。
草刈公民館奥の弁財天神社の村田川側に何体か集められていたり、大宮神社の参道にも何体か集められている。この観音様は馬に関わる生業(なりわい)に関わるというのは容易に想像できます。例えば中部地方(信州など)に多いのは街道沿いに馬による物品の輸送のためで、いわゆる馬借が多かったことが想像されます。いずれにせよ近世のものですが。農耕には西日本では牛、東日本では馬が多く使役されていたことは周知のことです。もともと東日本では武家が使う戦のための牧場(まきば)が多く、平安時代から東日本から東北にかけて朝廷や将軍に引き出物として重宝されており、軍馬以外は農耕馬として下げ渡されていたのは事実。
東日本は全体的に路傍に馬頭観音の石仏が多いとは言われます。対して西日本では馬小屋、牛小屋に「牛馬安全大日如来」のお札が見られるそうです。
農耕一般の守り神として、これはどちらかといえば仏教よりも民間信仰なのでしょうが、馬頭観音が信仰され、繁殖や豊穣のシンボルである二股大根が供されたことが多いようです。もともとは祖先や祖霊への供物ということなのでしょうか。
もう一つは馬の守り神という信仰です。馬が死ねば馬頭観音の碑を建て、二股塔婆をあげて供養するのですな。東北では厩を母屋と屋根を一緒にする風習もあり、馬は大事な家族なのでしょう。
話は飛びますが、西欧では特に牛については、使役に際し去勢をするのが一般的でしたが、日本では大切な家族として扱い、去勢する文化はなかったようです。実際に昔の絵巻物に出てくる貴族の乗り物である牛車では、暴れている姿が描かれています。結構やばい乗り物であり、生き物であったのかもしれません。日本で馬車の文化がなかったのも、去勢文化がなかったことも、徳川幕府の制度もございますが、それが遠因かもしれません。
さて、馬頭観音に戻り、もう一つは養蚕との関わりです。馬と蚕の関係は東北のイタコ祭文によるとの説もあります。長者夫妻が観音様に願ってできた美しい娘に、長者の飼っていた馬が懸想してしまい、怒った長者が馬を殺すとその皮が娘に巻き付き、天竺に飛び去り馬頭観音が現れた。そのあとに残った桑の葉に白い虫が現れて蚕になったというお話です。おしら様というのもこの系統です。もともとは中国の古書「捜神記」にある、蚕神馬明菩薩という物語からといわれています。
詳細はイタコの口寄せなどを調べると面白いと思いますが、死者の霊が返ってくるときの乗り物もしくは依り代が馬であるというのは、お盆の供え物や絵馬に残っている風習でもございますね。
この辺りに馬頭観音が多いのはさてどの辺りに起因しているのか。ちはら台をウォーキングしていると、北東部のちはら台と瀬又の境界辺りには、桑の木が多いことに気づきます。季節には桑の実が結構見られます。案外ちはら台造形以前は養蚕が盛んだったのかもと、これは根拠のない想像です。


(草刈公民館の弁財天神社傍らの馬頭観音)
仏様を離れて、次は道祖神についてです。これは里の結界を表し、村の境界に建てられた塞祭の神(さいのかみ)・道祖神で、地域を悪霊、悪疫が入ってくるのをを防ぐための神様です。信仰はかなり古くからですが、路傍の石像はほとんどが江戸時代のものと言われます。里の結界を示すと同時にそこから出る旅に際しての交通安全や、果ては妊娠、出産、幼児守護といった当時は容易に死に至る出来事に対する、安全祈願が込められていろことも多いようです。形としては男女2神が並んだものや、陽根、女性器などと多種多様です。

(椎名小学校入口の道祖伸)
最後が庚申塚。これも形は様々です。
そもそも庚申とは道教にある教えによります。人の体内にある三尸(さんし)と呼ばれる三匹の虫が、60日ごとに巡ってくる庚申(かのとさる)の夜に、人体を抜け出しその罪過を天帝に告げることにより、命を縮めるというのですな。それを防ぐために一晩中起きて言行を慎み健康長寿を祈念するという、いわば遊戯に等しいことが流行ってきたわけです。これに仏教的な要素が加わり、室町時代に庚申待ちをする講が結ばれ、供養塔を模した庚申塚が建てられるようになったとのことです。
夜っぴいて酒食をとることから、講内の連携も強くなり村の連帯につながるようになりました。似たような信仰に13夜月待ちなどもあります。13夜月はほぼ夜明け前に上がる月を飲食をしながら待ち、その姿が仏を見るようだとのまあ、現代のような娯楽の少ない時代の、娯楽の一つとしての信仰です。これも石碑が残っています。永吉の平野神社にある、昔は浜野ゴルフクラブにあったとされる、将門ゆかりの桔梗塚もこれだと、以前紹介しました。
(ちはら台近郊の神社たち)
さて庚申塚ですが、多種多様なものがあるのも特徴。ほぼ江戸時代に多様になったようですが、最も多いのが悪疫を調伏するという、青面金剛(しょうめんこんごう)で、日本固有神では猿田彦大神や山王大権現、仏教系では大日、薬師、阿弥陀の各如来に観音、地蔵の菩薩、不動明王など。さらに言わず聞かざる見ざるの三猿や、仁王、閻魔もあるようです。文字だけのものも多く、庚申・庚申塔というのが最も多く、上記の神仏の名前を彫ったものもあるようです。
というわけで、石像ゆえに年月を経て欠けたり、像がすり減ったりで判然としない石像も多々ございますが、ウォーキングの途中で見かけたら、手を合わせ古の庶民の願いに耳を傾けてみてはいかがでしょうか?
参考文献
図説 歴史散歩事典 井上 光貞監修 山川出版社
仏教と民俗 (仏教民俗学入門) 五来 重 角川選書


















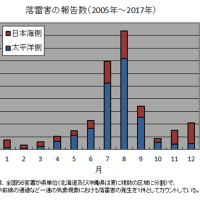




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます