直接ヤマトタケルを祀っている訳ではありませんが、熱田神宮も尊に関係の深い神社ではあります。三種の神器の一つ、草薙の剱であります。
元々は素戔嗚が倒したヤマタノオロチの尾から出てきた神剣であり、天照大神に献上され、天孫降臨に際して賜り地上に還ったものです。
ヤマトタケル東征の前に伊勢の倭姫より賜り、焼津の地方名の由来にもなった、火をつけられた野の草を薙いで防いだところから草薙と名付けられました。伊吹の神への対決を前にこの剣をミズヤ姫(尾張氏)の元に残していったために、神の祟りを受け亡くなったともいわれております。
その後熱田神宮に社を建てて祀られておりましたが、天智7年に僧、道行に盗まれ取り返されたうえで宮中に置かれましたが、天武帝の病気がこの剣の祟りと判り、再度熱田神宮に祀られることとなり、現在に至ります。
さて、尊の奥様即ち妃でございますが、仲哀天皇、犬上氏・建部氏の先祖となった子供たちを生んだとされる、崇神の皇女両道入姫、尾張氏の姫であるミズヤ姫に加え、吉備武彦の娘吉備穴戸武媛(きびのあなとのたけひめ)等等。
その中で東国でのヒロインはあずまの語源となった出来事の主役、穂積氏の忍山宿禰の娘弟橘姫(おとたちばなひめ)でございます。
東海道を東進し相模から上総に渡る際、走水の海の神が波を起こして、船が危うくなった際に、弟橘姫が己づから入水したために、凪いで一行は無事に上総に渡ることができたと古事記に。
この事件を東国平定後に足柄辺りで思い起こして、「吾妻はや(わがつまよ)」と三度嘆いたところから、東国をアヅマと呼ぶようになったと、お馴染みのお話でございます。
この事情に関わり千葉県内を主に弟橘姫にゆかりの地名、神社がございます。
以前市原市の自動車№は袖ヶ浦でありましたが、この地名は弟橘姫の袖が流れ着いたとの伝承によります。
神社としては千葉県木更津市にございます吾妻神社。社伝に寄れば流れ着いた袖を納める社を建立したのが創建。社名も吾妻はやの故事に由来するとのこと。
神奈川、群馬などに吾妻神社は何か所かございます。
更に上総二宮として、以前紹介しましたが、千葉県茂原市には、ヤマトタケルが弟橘姫の墓標として、橘の木を植えた由来の橘樹神社がございます。延喜式内社で、唯一正史に記された弟橘姫を祀る神社となります。
東征については、古事記と書紀では相応の食い違いもございますが、常陸、陸奥風土記にはほぼ天皇に近い扱いで、記述があり関東以北に伝説と神社が多いのも事実。
大和朝廷のかなり高いレベルの英雄が、アヅマと呼ばれる国々を平定していったことは、何となく史実であったのかと想像致します。
亡くなったのちに白い鳥になって舞い降りた神社とはまた異なる、ヤマトタケルを視るような気が致します。


















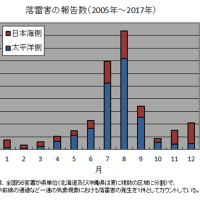




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます