草刈村大宮台の地に坐す「大宮神社」
橘の花薫る五月の初旬、大宮神社の神主、市川先生にお話を伺って参りました。とても丁寧に大宮神社の御由緒、ご祭神の大宮姫命のこと、この地の先史時代からの歴史などなど、とても膨大な情報量でありまして、1回のブログでは紹介しきれない。
今回は神社の御由緒などを中心にお伝えいたします。にしても楽しいあっというまの1時間少々でした。
我々の住むちはら台は、明治22年町村制施行による前は市原郡「草刈村」「番場村」「押沼村」の三村の一部でした。現在のちはら台西、南が草刈になります。
ちはら台団地開発に際し発掘された草刈遺跡群からは、東日本最大と言っても良いくらいの遺物が見つかりました。高台からは旧石器時代から、縄文時代の。更に弥生以降は4千にも及ぶ竪穴式住居跡、170基にも及ぶ古墳。大宮神社はこの草刈遺跡群のほぼ中央に位置し、また政治的にも中心の地に当たります。付近からの遺跡から鹿の骨で弥生後期頃と推定される太占(ふとまに)に使用された、卜骨が出土しており、祭祀の中心でもあったと推定されます。
神社の境内からは貝殻の破片がぽつぽつと顔を出しており、神社の高台のすぐ南側が縄文海進の頃は海であったことがわかります。この辺りの歴史、考古学のお話はまたいずれ。
さて、大宮神社の創建は確かなところは判っていませんが、少なくとも遺跡から発掘された奈良時代の土器に「草刈於寺杯」との墨書された盃が発見されたことより、およそ1300年前には、この地に大宮神社が鎮座していたことは、間違いないようです。その時代前後にこの地を治めていた菊麻国造にゆかりの神社であろうかとのこと。さてこの菊麻国造家、元々は久々麻と称し『先代旧事本紀』「国造本紀」には、成務天皇の時代、无邪志(むさし)国造の祖である兄多毛比命の子の大鹿国直を国造に定めたことにはじまるとされます。
系譜をたどれば天照大神にさかのぼりますが、兄多毛比命の兄弟とされる忍立毛比命は現千葉県内の上・下海上国造、千葉国造家の祖でもあります。千葉県にゆかりのある国造家の一つなのでしょう。
大宮神社という名前の神社は、日本全国に存在し、例えば同じ市原市の五井にある大宮神社がそうであるように、広大な境内に代表されるような神社を敬って「大宮」と氏子から呼ばれていたのが、それに神社をつけて社名にしたものなどが挙げられます。一般には祭神は一定している訳ではありませんが、草刈の大宮神社の祭神は社名と同じく大宮姫命であり、神社としては珍しくご祭神は一柱のみという特異な点が挙げられます。
例えば上記の五井大宮神社の祭神は、國常立命(くにとこたち)・天照大神・大己貴命(おおなむち:大国主の別名)の三柱で、千葉市若葉区大宮町の大宮神社は天鈿女命(あめのうずめ)・伊弉諾尊・伊弉冉尊、大山咋命、玉依姫等九柱などと比べても、大変珍しい神社でございます。本神社には8社の末社がありますが、それは後述。
ご祭神の大宮姫命については、市川先生も意味ありげに九州にあったとされる天智天皇とのゆかりの隼人(薩摩)王朝の大宮姫伝説からきているとのロマンチックなお話もされていました。菊麻国造家のゆかりのある、九州の人たちがいたのかもしれないとの空想もあるかと、心くすぐるお話であります。大宮姫伝説については天智天皇という大化の改新の立役者であり、現天皇家に繋がる重要な天皇ということもあり、なかなか伝説の域をでないところであります。ご興味のある方はネットでもいくつかのサイトがありますので調べてみてください。
もう一柱の大宮姫命は「オオミヤノメ」(延喜式神名帳では大宮売神とも表記)と称され、神祇官で祀られた天皇守護の八神のうちの一柱として、朝廷で重要視された神格で、古語拾遺に太玉命の子として、天岩戸から新殿に移った天照大神に侍女として仕えたとされます。宮殿の人格化とも、女官の神格化ともいわれ、「延喜式」の大殿祭(おおとのほがい)の祝詞においては、皇居に鎮座して親王や諸臣たちが過ちを犯すことなく心安らに仕えられるよう見守る神であるとされています。
本大宮神社の特殊な神事などを紹介致します。
まずは、これは菊間神社等にも共通致しますが、西向きに社殿が建てられているということです。通常神社というのは南もしくは東向きに建てられており、家庭での神棚もそう奨励されていますが、菊麻国造家にゆかりの神社の社殿は西向きです。理由は九州なのか、出雲なのかそちらに故地があるということなのでしょうか。
神事としては、秋の例大祭として10月31日に出雲に向かわれる神の御立ち。当日は氏子が入れ替わりで社殿におこもり直来をし、午後10時に太鼓を叩いて、神様を送り出すという行事です。そして11月30日には同様にお帰りの神事を行うということです。
旧暦の神無月に相当する日程で行われます。
現社殿は平成6年に境内の整備とともに改修され、本殿(昔の儘)を拝殿と本殿を併せて囲い込む形で、今日にいたっています。拝殿の奥の扉の向こう側には、以前のままの本殿が鎮座している訳です。
さて、これまで神社の御由緒やご祭神について記して参りましたが、少し周辺のお話を。
神社の高台を南に下ると、草刈公民館がございますが、その奥まったところに、これも西向きに弁財天神社が、一回り小ぶりな水神さんと並んでいます。その奥は沼になっていますが、これは江戸時代に周辺の水田の水利のために村田川の水をせき止めた「草刈の堰」建設にあたり、鎮守として創建されたものです。
また、給食センターの奥には川焼不動のお社が古墳の小高い上に鎮座しています。これは聖武天皇時代の国分寺建設にあたり、河原で焼いた瓦窯から村田川の水利を利用して運んだもののようです。京成線に並行している道路の瓦窯通りもこの故事に由来しているようです。
またちはら台の東に広がる押沼地区には製鉄つまりたたらの遺跡が発見されています。
最期に大宮神社の本殿左に並ぶ8社の末社について。
明治になって合祀令が発布され、付近の古墳に点在し、住民の氏神として祀られていた古社を取りまとめるようにとお達しがありました。そのために明治から大正にかけて8社が草刈大宮神社内に集められて、末社としてお祭りされることになりました。未だに各末社にはその氏子さんが大切にお祭りをされているとのことです。
ところで、神主の市川先生は雅楽の龍笛を能く演じられるとのことです。上総一宮の玉前神社にて、春のお花見の季節と、夏の満月の夜の海岸にて演奏をされるとのこと。昨年からコロナにより中止となりましたが、真夏の満月の雅楽演奏。なんと雅やかな風情でしょう。是非拝聴してみたいものです。
本殿

ご神木の楠木

弁財天神社



















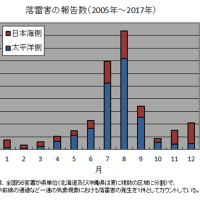




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます