大暑を過ぎお盆が過ぎると、そろそろ早稲の稲刈りが始まります。ちはら台の周りには黄金色の稲穂が広がります。ウォーキング途中で、少ないものの、懐かしい光景に出会います。
案山子でございます。明治時代に採用された唱歌にも歌われた、田んぼの風物詩ですね。
山田の中の 一本足の案山子 天気よいのに 蓑笠着けて
朝から晩まで ただ立ち通し 歩けないのか 山田の案山子
山田の中の 一本足の案山子 弓矢で威して 力んで居れど
山では烏が かあかと笑ふ 耳がないのか 山田の案山子
作詞は 武笠三 作曲 山田源一郎であります。明治後年のまだ日本の里山が田園で覆いつくされた時代の風景なのでしょう。
さらには、さだまさしさんの案山子。故郷を離れた弟に対して、気遣いながらも送り出した母親の寂しさに寄り添い、電話でもかけて来いとの、切なくも優しい歌です。こちらは私も中学を出て親元を離れた寮生活をしており、あとになって胸に響いた歌です。そして長男が就職で家を出た後の家内の寂しそうな表情が思い出されます。
さて、この案山子。語源は「かがす」から来ているとのこと。弥生時代に稲作が西から広がり、収穫に際して、夏の間は虫をせっせと食する益鳥スズメが、今度は稲を狙う害鳥になる。
まあすずめに限らないのですが、野生の動物や鳥は人間の存在を基本的に嫌うことから、人間の髪の毛などをこのヒト型の案山子に入れて、においを嗅がすことにより追い払うようになったとのことです。
この案山子君、実は古事記にも登場する、しかも神様としてです。祀られているのはなんと奈良の大神神社の末社としてといいますから、古い神様です。
登場する場面は大国主尊の国造り。少彦名が海の向こうからやってきましたが、誰もこの神様の名を知らなかったところに、ヒキガエルが「久延毘古なら、きっと知っているだろう」と言うので、久延毘古を呼び尋ねると「その神は神産巣日神(かみむすびのかみ)の子の少名毘古那神(すくなひこなのかみ)である」と答えた。この久延毘古命(くびひこのみこと)が、案山子くんです。
さらに古事記では山田の「そほど」のことと説明され、そほどというのは案山子の古名で、案山子の神格化とされます。田の神であり、農業神であり、山神の依り代とされます。
一方で田の中で一日中立って世の中を見ていることから、世のすべてを知る知恵の神ともいわれるようになります。蓑と笠はまろうどとして山から下りてくる象徴でもあるのですね。
ところでこの案山子という漢字ですが、日本に来朝した僧侶が用いたのが始まりのようで、案山は山の中でも平らな場所を指し、子は人や人形を意味するそうで、一般的になりました。
日本では案山子の主なる追っ払いの相手はスズメですが、西洋ではどうもカラスのようです。
英語では scarecrow すなわち烏(crow)を追う(scare)が語源となります。
子供のころに読んだ「オズの魔法使い」で、主役のカンザスから竜巻によりオズの国に飛ばされてきたドロシーの最初の付き人となるのが、脳みそがないと嘆く案山子くんです。
西の魔女の使い魔としてドロシー一行を襲うカラスを、その頭を捻り倒して危機を救う場面などは、カラス威し以上の役割で、喝采してしまいます。
その後冒険を経て、オズ大王から針がいっぱい飛び出たおがくずを詰めた脳みそを、頭の部分に入れてもらい、気球で去ったオズに代わり「エメラルドの都」の王を任せられることになります。
主題歌「虹の彼方に」で有名な映画では、カンザスに帰宅したドロシーの家に、農民として出迎えた優しい笑顔が、ほっこりさせていました。
写真はベイシア近くの田で仕事中の案山子君です。
さて、この辺りの稲田ですが、案山子はとても少ない。とある日ウォーキングの最中に、お仕事にいらしてた、潤井戸の稲作農家の方に唐突でしたが、お話を伺わせて戴きました。
この辺りでは確かに数軒の農家さんしか案山子を立てていませんが、この案山子の制作は結構な手間であるそうで、その割には効果が少ない。効果としてはキラキラ光るテープや、テグスを引くほうが格段に上だそうですが、それも結構な手間。
1割がスズメのためと割り切っているのが、その理由だそうです。虫を食べてくれるスズメに対するお礼と考えると、なるほどと。昔中国の文化大革命で、稲を食べるスズメを大規模に、それこそ国を挙げて退治したところ、虫による被害でしばらくは大不作に陥ったことがある。自然というのはよくできていて、バランスを崩すとこういうことになると、教えてくださいました。
一時盛んに喧伝された、合鴨農業についても、まだ一部では取り入れてはいるものの、合鴨君は雑食で田んぼのヤゴなどの虫を根こそぎ食べてしまい、それらの大型の昆虫の食料である小型の虫が増え、結局そのために農薬を追加するはめになるとのことで、それほど行きわたらなかったそうです。
人間が食べて美味しいもち米は、スズメ君も大好物のようで、少し頭が痛いけれど、収穫の時期をうるち米とずらすなどの方法で、しかし多少はスズメ君にも分け前は必要だと。優しい話を炎天下に伺いました。



















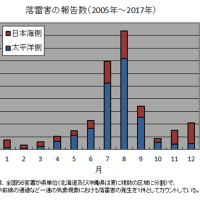




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます