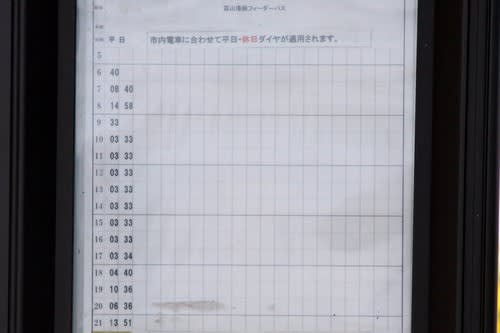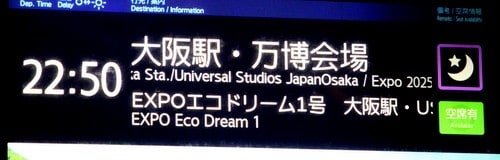2025年、エルガEV(LV828)デビュー。
待ち望んでいたJBUS製のEVバス「エルガEV」が、この春、続々と運行を開始しました。このエルガEVの登場は、ノンステップバスにおける、フルフラットという言葉の概念を変える大きな出来事になりました。これまでフルフラットというものは、通路に段差がないバスを意味していましたが、エルガEVは、客室全てのエリアで段差がありません。これは、モータを車軸に組み込んだインアクスルモーターを採用したことで実現したものです。言わば、EVバスだからこそ、フルエリア・フルフラットが可能になったと言えます。
しかし、段差をレスにしたことで、機器の配置やタイヤハウスの構造上、座席数が減ってしまうデメリットも生じました。フルフラットをとるか座席数をとるかは、判断がわかれるところです。各社のEVバスを見ると、フルエリアでのフルフラット、通路フルフラット、ひな壇、様々な形態があります。各メーカーはどのような選択をしたのでしょうか。
そこで、今回は、日本国内で運行している(していた)大型電動バスの後部レイアウトを比較してみることにしました。

まずは、いすゞ、エルガEV。
全てのエリアで段差のない、フルエリア・フルフラットを実現しました。モーターを足回りに組み込んだため、後輪のタイヤハウスが目立ちます。フルフラットにこだわったためか、タイヤハウス部に座席を設けず、更に最後部にEV機器を配置したため、座席数が少ないです。中ドアより後部の座席数は3列13席で、最後部は向かい合い座席です。今後、座席数を増加した仕様が登場するのか興味深いところです。

続いて、BYD、K8、2.0です。
足回りにモーターを付けたインホイールモーターを採用し、通路フルフラットを実現しました。座席に着席するためには、段差を上る必要があります。後部のエリアを広くとり、タイヤハウス部にも座席を設け、座席数は多いです。中ドアより後部の座席数は5列19席となりました。

K8、2、0には、いくつかのバリエーションがあります。
京浜急行バスでは向かい合い座席を採用することで、座席数を更に2席増加させました。他に奈良交通では後部を通路フルフラットではなく、ひな壇にしました。

次は、EVモーターズジャパン、F8シリーズ2です。
後部レイアウトは、ひな壇。他メーカーと比べて小さいサイズのタイヤを使っているためか、タイヤハウスはみられません。中ドアより後部の座席数は4列17席で、シートはハイバックタイプです。後部はアイポイントの高い座席が多いです。EVモーターズジャパンは、今後モデルチェンジを予定しています。どのような仕様になるのか注目されます。

アルファバス、e-City L10です。
後部レイアウトは、ひな壇。最後部にはEV機器を配置しており、中ドアより後部の座席数は4列16席です。アルファバスもモデルチェンジを予定しています。

(参考)スカニア、ボルグレンです。
EVではなく、ディーゼルエンジンの通路フルフラットです。一般的なノンステップバスは、最後部の床下にエンジンを配置し、プロペラシャフトで後輪の車軸に動力を伝えます。しかし、中央を通路にしたフルフラットバスでは、この方式が難しくなります。そこでエンジンを縦置きにし、プロペラシャフトを横にオフセットして動力を伝達しました。過去には国産車でも、この方式を採用した車種は存在しましたが、特殊な構造故に普及はしませんでした。エンジンの車両をフルフラットにするのは、制約が大きく難しいのがわかります。

いすゞ、エルガハイブリッドです。
ハイブリッド車で、起動時はモーターの力で発進します。最後部片側にはバッテリーを配置しました。後部床下にモーターとエンジンを搭載し、プロペラシャフトで後輪に動力を伝達します。ひな壇とプロペラシャフトを組み合わせた伝達方式のメリットは、タイヤハウス間の幅を広くすることが可能で、ラッシュ型仕様が作れることです。約1mの通路幅を確保できました。

日野、ブルーリボンシティハイブリッドです。
屋根上にバッテリーを配置したため、座席数は多くとれます。ラッシュ型仕様も存在します。

いすゞ、エルガをEV改造した、レトロフィットEVバスです。
ディーゼルエンジンを取り外して、EV改造しました。新車で導入するよりも安価にEV車を導入することが出来ます。

改造車ゆえに、バッテリー等のEV機器をどこに配置するのかが課題で、今回、国際興業に入ったタイプでは、車両の前部にEV機器を配置しました。そのため、ノンステップ部の段差のない座席が少なく4席となります。

トヨタ、SORAです。
水素を燃料とする燃料電池バスです。ベースとなった車両はブルーリボンシティハイブリッドです。実在はしませんが、タイヤハウスの形状を見る限りでは、通路幅を広くしたラッシュ型も作れそうです。

立山黒部貫光のトロリーバス8000形です。
日本最後のトロリーバス車両で、2024年に廃止になりました。ツーステップ車両で、床のトラップドア(点検口)からわかるように、モーターは車両中央に配置し、プロペラシャフトを介して後輪に動力を伝達しています。

関西電力の関電トンネル電気バスです。
日野ブルーリボンをEV改造しました。パンタグラフを装備し、折返し時間を活用して超急速充電を行います。座席を取り外してのEV機器取付はしていないので、改造車でも座席数が減らないのが特徴です。ただし、バッテリーの容量は大きくなく、長距離の運行には適さないため、継ぎ足し充電する運用が前提です。
今後、川崎鶴見臨港バスでは、パンタグラフ充電器による、超急速充電の実証実験が始まります。車両のスペックが公表されていないので、継ぎ足し充電を目的としているのか、単純に大電流による充電時間の短縮を目的としたものなのかはわかりませんが、都市部の新しい形として注目されます。

ここまで、様々なEVバスのレイアウトを見てみました。
レイアウトを決める上で、要点となるのは、モーターの配置場所と、バッテリー、インバータといったEV機器の配置場所です。
旧来からの、ひな壇を採用して、モーターを後部床下に配置、プロペラシャフトを介して、後輪に動力を伝えるか。

それとも、後輪そのものにモーターを配置するか。
EV車でフルフラットを実現するには、足回りにモーターを積んだ方が有利ということがわかりました。ただし、通路幅の広いラッシュ仕様にしたい場合は、旧来の方式の方が有利と言えます。

それから、EV機器をどこに配置するかも車内レイアウトに影響を与えます。特にEV改造車はバッテリー等の配置場所が課題となりました。
「EVバス元年」と言われた2023年から時が経過し、各都市、各事業者でEVバスの導入が進んでいます。全国レベルでは、まだまだですが、時間を重ね、今後もEVバスの台数が右肩上がりに増えていくことは間違いありません。これからEVバスの車内仕様が統一されていくのか、それとも多様化したまま、増加していくのか、日本のEVバスの発展が楽しみです。
-余談-
最近、某社のEVバスに乗車した際、立っていた60才代の男性が、バスの発進でよろける姿を目撃しました。よろけるとは書きましたが、転倒に近いよろけ方でした。もしかしたら、起動時に、手すりやつり革から手を放してしまったのかもしれません。無音から動き出したので起動に気が付かなかったのかもしれません。モーターは低回転からトルクがとれますし、回生ブレーキが強めに効く場合もあります。乗客もドライバーも、まだEVバスの挙動に慣れていないのが実情です。車内での転倒の危険性を考慮すると、多くの人が着席できるよう座席数は多い方が好ましいですし、同時に車内の段差は無い方が好ましいです。しかし、この二つは、現在の技術では両立するのが難しく、難題でもあります。