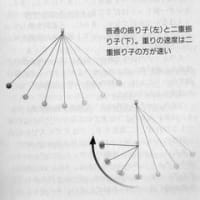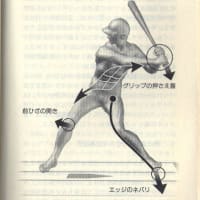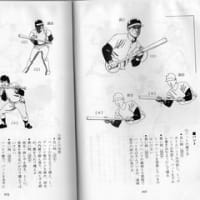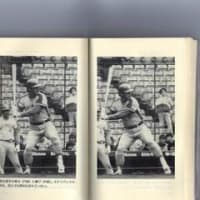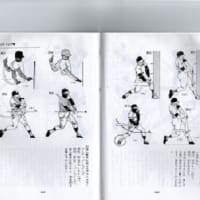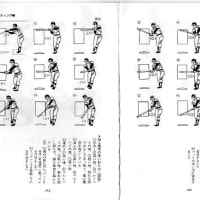始動を早くしましょう。早く始動して、「間」を設けるようにしましょう。
固まったようにじっとして、ポールが来るのを待っているより、早く始動して、その動きの中で「間」を設ける方が、タイミングが取り易いのです。
それにボールを呼び込めるし、ひきつけて打つ事が出来る様になります。
サンプルを選んでみました。
「どう動く」より「いつ動く」かを注目して見てください。
始動が早い例
中村選手
青木選手
高橋選手
谷選手
井口選手
片岡選手
この中でも井口選手が一番早いようです。
始動が遅い
大久保選手㊟
いずれもホームランばかりですが、始動が早い、遅いの例で取り上げているので、ホームランかどうかはこの場合関係ありません。
「どう動く」については、ある程度、見た目は、個人個人、オリジナルの部分があってもいいと思います。
脚を上げてもいいし、上げなくてもいいでしょう。
見た目は、大きな動きでもいいし、少し小さい動きでもいいと思います。
ただ、左ひざを右ひざにくっつけるようにするのは良くないです。
体幹のひねりが甘くなるからです。
左ひざは、ガニ股にしておいて、体幹をひねることにつられて、自然に、少し右ひざの方に寄って来るという感じでいいのです。
左脚を大きく上げるにしても、右にあまり寄せないようにしましょう。
バットを振る勢いをつけようと、左脚を右左、能動的に動かすことは良くないと思います。
「大きな筋肉を使う」と言う意識で動いていけばいいでしょう。
「大きな筋肉を使う」とは、体幹をひねっていくことです。
ひねり方は、こちらを参考にしてみてください。
体幹をひねれば、右サイドに軸がてきます。
脚、体幹、腕が連結して動くことが出来ると言う感じです。
右サイドに力がたまっているような感じです。
ちょっときついなという感じです。
早く始動しても、そのちょっときついなという、力がたまっている感じをキープすることで、待つ「間」が出来るのです。
それは、「身体を安定させる力」であり、「ボールを良く見るための力」「ボールをひきつける、呼び込めるための力」、「粘り」、「タメ」であり、かつ「バットを振る力」であります。
「始動を早くする」の「動」は、見た目は、個人個人、色々あっても、その「動」の目的は、体幹をひねっていく事とと理解していいと思います。
腰から下は、打ちに行って、左後ろへ、逆に、その上は、右後ろへと「割れ」ていきます。
背中の方から見て、「く」の字になるようにしましょう。
「く」の字の角は、右股関節に当たります。
それで、突っ込むことが防げます。
「間」をとって、タイミングの幅を設ける事が出来ます。
その「始動する」まえに、小さい筋肉等、動かせている人は多いです。
たとえば、グリップを上下させているとか、にぎにぎしているとか、手でバットを車のワイパーの様に動かしているとかあります。
体幹をひねっていくタイミングを、小さい筋肉の動きでとっているものだと推測します。
これは、個人個人のオリジナルの動きでいいと思います。
「いつ動く」かは、バスター打法でバットを引く時の、タイミングを目安にしてもいいでしょう。
あるいはそれより少し早くてもいいかもしれません。
「始動を早く」するには、最初は、タイミングが外れる事を怖がらないで、思いっきり早く動くことが大切です。
固まって、じっとしてボールが来るのを待っている人は、大体、怖がりのひとが多いようです。
最初の方は、失敗してもいいですから、「早く始動」しましょう。
タイミングは、一点勝負でとるのではなく、「幅」でとるのです。
ですからある意味、おおざっぱで良いのです。
以上、右打者の場合で書きました。
㊟大久保選手は、このVTRのときは、ホームランが出ましたが、明らかに始動は遅いと思います。しかし、その後、勉強したのかどうか解りませんが、解説者のときは、「始動を早く」しようと言っていました。それは自分への反省だったのかもしれません。
↓恐れ入りますがポチッとご協力お願いします。
 にほんブログ村
にほんブログ村
固まったようにじっとして、ポールが来るのを待っているより、早く始動して、その動きの中で「間」を設ける方が、タイミングが取り易いのです。
それにボールを呼び込めるし、ひきつけて打つ事が出来る様になります。
サンプルを選んでみました。
「どう動く」より「いつ動く」かを注目して見てください。
始動が早い例
中村選手
青木選手
高橋選手
谷選手
井口選手
片岡選手
この中でも井口選手が一番早いようです。
始動が遅い
大久保選手㊟
いずれもホームランばかりですが、始動が早い、遅いの例で取り上げているので、ホームランかどうかはこの場合関係ありません。
「どう動く」については、ある程度、見た目は、個人個人、オリジナルの部分があってもいいと思います。
脚を上げてもいいし、上げなくてもいいでしょう。
見た目は、大きな動きでもいいし、少し小さい動きでもいいと思います。
ただ、左ひざを右ひざにくっつけるようにするのは良くないです。
体幹のひねりが甘くなるからです。
左ひざは、ガニ股にしておいて、体幹をひねることにつられて、自然に、少し右ひざの方に寄って来るという感じでいいのです。
左脚を大きく上げるにしても、右にあまり寄せないようにしましょう。
バットを振る勢いをつけようと、左脚を右左、能動的に動かすことは良くないと思います。
「大きな筋肉を使う」と言う意識で動いていけばいいでしょう。
「大きな筋肉を使う」とは、体幹をひねっていくことです。
ひねり方は、こちらを参考にしてみてください。
体幹をひねれば、右サイドに軸がてきます。
脚、体幹、腕が連結して動くことが出来ると言う感じです。
右サイドに力がたまっているような感じです。
ちょっときついなという感じです。
早く始動しても、そのちょっときついなという、力がたまっている感じをキープすることで、待つ「間」が出来るのです。
それは、「身体を安定させる力」であり、「ボールを良く見るための力」「ボールをひきつける、呼び込めるための力」、「粘り」、「タメ」であり、かつ「バットを振る力」であります。
「始動を早くする」の「動」は、見た目は、個人個人、色々あっても、その「動」の目的は、体幹をひねっていく事とと理解していいと思います。
腰から下は、打ちに行って、左後ろへ、逆に、その上は、右後ろへと「割れ」ていきます。
背中の方から見て、「く」の字になるようにしましょう。
「く」の字の角は、右股関節に当たります。
それで、突っ込むことが防げます。
「間」をとって、タイミングの幅を設ける事が出来ます。
その「始動する」まえに、小さい筋肉等、動かせている人は多いです。
たとえば、グリップを上下させているとか、にぎにぎしているとか、手でバットを車のワイパーの様に動かしているとかあります。
体幹をひねっていくタイミングを、小さい筋肉の動きでとっているものだと推測します。
これは、個人個人のオリジナルの動きでいいと思います。
「いつ動く」かは、バスター打法でバットを引く時の、タイミングを目安にしてもいいでしょう。
あるいはそれより少し早くてもいいかもしれません。
「始動を早く」するには、最初は、タイミングが外れる事を怖がらないで、思いっきり早く動くことが大切です。
固まって、じっとしてボールが来るのを待っている人は、大体、怖がりのひとが多いようです。
最初の方は、失敗してもいいですから、「早く始動」しましょう。
タイミングは、一点勝負でとるのではなく、「幅」でとるのです。
ですからある意味、おおざっぱで良いのです。
以上、右打者の場合で書きました。
㊟大久保選手は、このVTRのときは、ホームランが出ましたが、明らかに始動は遅いと思います。しかし、その後、勉強したのかどうか解りませんが、解説者のときは、「始動を早く」しようと言っていました。それは自分への反省だったのかもしれません。
↓恐れ入りますがポチッとご協力お願いします。