
バンカラ。そういう言葉がある。古い昭和の雰囲気を感じる言葉だが、実際には明治時代に生まれた言葉らしい。
調べてみたところ、
バンカラとは、ハイカラ(西洋風の身なりや生活様式)をもじった語であり、明治期に、粗野や野蛮をハイカラに対するアンチテーゼとして創出された言葉だそうな。
バンカラという言葉を知っている方は、バンカラという言葉にどんなイメージを持つだろう?
私が「バンカラ」に対して持つイメージは、あまり流行ファッションなどに関心を示さず、やや汚れたり少し破れたりした学生服などを着る学生で、下駄履きで、細かいことをグタグタ言わず、なおかつ卑怯なことが嫌いで、男気のある男子学生・・・そんなイメージだ。
昭和の時代によくあった熱血学園漫画などによく出てきた番長などが、私の思うバンカラのイメージに当てはまっていた。
例えば、昭和の熱血漫画「夕焼け番長」「男一匹ガキ大将」などは、その典型だったと思う。
ネットで「バンカラ」について調べてみたところ、「バンカラ」にはやはり一定の定義はあったようだ。
それによると、バンカラは漢字で書くと「蛮殻」らしい。「蛮」は、「野蛮」の「蛮」と同じ字だね。
さらに、バンカラは、「言動などが荒々しかったり、あるいはそういう風にふるまう」人。
ウィキペディアによれば・・
「典型的な様式としては弊衣破帽がある。これは、着古し擦り切れた学生服(=弊衣)・マント・学帽(=破帽)・高下駄、腰に提げた手拭い、長髪(=散切り頭に対するアンチテーゼ)などを特徴とするスタイルで、第一高等学校を中心とした旧制高等学校の生徒が流行の発端である。」とのことだ。
さらに、こうも説明は続く。
「ハイカラのアンチテーゼとしてのバンカラは武士道にも通じ、「単に外見の容姿のみに留まらず、同時に内面の精神的なものも含めた行動様式全般」とも理解されていた。つまり外見に無頓着な体裁とそれを正当化するための動機が複合した文化であると言え、単に粗末・粗野なだけの恰好をバンカラと呼ぶわけではない。」
ともある。
その説明を読むと、私がバンカラに対して持ってた意味あいは、そんな間違ってはいなかったことが分かった。
ある意味、バンカラの特徴として汚れた学生服や、下駄履き、ポケットにしのばせた手拭い・・・などが共通してるのだとしたら、バンカラにもいわゆるファッションがあったことにはなる。
昔のヒット曲「我が良き友よ」の歌詞に描かれた登場人物は、「下駄を鳴らして」やってきて、「腰に手拭いぶらさげて」いたことを考えると、まさにバンカラファッション。
私は学生時代、バンカラというものに対しては、けっこう良いイメージを持っていた。むしろ、カッコよさみたいなものも感じていた。
たとえ服装が汚れていても、髪の毛がボサボサでも、そんなことは気にしない点。そのくせ、惚れた女性には一途ではあり、優しさもあるが、ナンパではなく、けっこう硬派で奥手な点。
そんなイメージもよかった。
ただ・・・ここで大事なのは、バンカラがかっこよく思えたのは、例えばその服装ゆえにだけではない。
私が思うに、なぜバンカラがかっこよく思えてかというと、私のイメージするバンカラには正義感や男気があったから。
前述の説明によれば、私がバンカラにイメージしていた正義感や男気は、「武士道」に由来するものだったようだ。
武士道に由来する正義感や男気が根底にあったからこそ、その「汚れた服装」も「下駄履き」も「腰の手拭い」もかっこよく思えたのだと思う。
だから単に「汚れた服装」を着ていたり下駄を履いているだけだったり、腰に手拭いをぶら下げていればカッコイイというものではないし、それでバンカラになれるというわけでもない。
正義感や男気がバンカラの根底にある以上、いじめなんてとんでもないのだ。陰湿で卑怯なことは、バンカラにとっては対極にあるものだ。
バンカラというのは、逆にその正義感や男気から、いじめられている子を助けたり、困っている人を助ける心意気を持っているから、カッコよく思えたのだ。
格好は薄汚れていても、その正義感や男気がかっこよかったのだ。
単に汚れた服を着て、粗野な言動をしてバンカラのつもりでいるとしたら、それはバンカラではなく、単に乱暴で汚れた学生さんでしかないのだ(笑)。
そういえば、昭和の青春ドラマ「俺は男だ!」の挿入歌に、「男なら気にしない」という歌があった。
その歌の歌詞には、誰かと誰かが恋仲になったって、手紙を出したのに返事がこなくたって、格好が悪かったって、男ならそんなことどうでもいいじゃないか、細かいことは気にしない・・・という内容のことが歌われていた。
これなども、多分に「バンカラ」というものを意識したものだったように思う。
「俺は男だ」の主人公「小林弘二」は、友情に熱く、正義感が強く、剣道の腕も上々だったから、そういう意味ではバンカラの資格は有していた。
ただ、小林弘二は、・・・汚い服を着ていたという印象は私はないし、下駄履きでもなきゃ、腰に手拭いもぶら下げてはいなかった。。
そういう意味では、明治のころに比べたら、バンカラ像は変化していってるのかもしれない。「俺は男だ」か放送されてから何十年もたつ平成の今なら、なおさら。
今は、昔よりも男子学生はおしゃれになり、昔ながらのバンカラを「カッコイイ」と捉えるのかどうかは分からない。
ただ言えるのは、根底に「武士道に通じる正義感、男気があり、卑怯なことは嫌い」というものがある人は、「ふり」ではなく、本当にそんな人がいれば、今でも慕われる気はする。
たとえその人が、汚い服を着てなくても、下駄履きじゃなくても、腰に手拭いをぶらさげていなくても。
そういう人は、スピリットはバンカラを受け継いでいるのだろうと思う。
ただ・・
バンカラ気質のルーツがもしも武士道にあるのだとしたら、本物のバンカラはきっと・・・プライドは高いだろうね。
なんてったって、武士はプライドが高かったから。プライドのために命をかけていたから。
とりあえず、平成の世を生きる皆さん、「バンカラ」を今の時代でどう思いますか?
















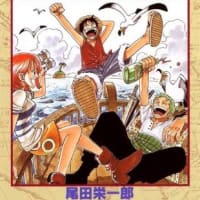
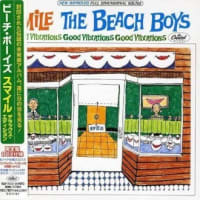









朴歯の音が聞こえてくるようです。
女房共々、元気いただきました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
バンカラの話題に共感して下さる方がいらっしゃって、嬉しいです。
バンカラという言葉も、最近はあまり聞かなくなり、寂しいかぎりですね。
「夕焼け番長」は残念ながら知りませんが、ぼくのバンカラは「硬派 銀次郎」でした。一見粗野に見えるが、筋が通った凛としたたたずまい。男が惚れる男でした。
武士道的精神があったから「さすがは日本人だ」と言われたのでしょうが、現在は…。歩きスマホしている連中の代表が政治をやっている感じです。
案外、調べてみると、思いがけない情報を得ることがあるもんですね。
硬派 銀次郎・・・確か本宮ひろし先生の作品でしたよね。
少し読んだことがあったと思います。
さわやか万太郎・・なんていう作品もありましたっけ。
昔「男一匹ガキ大将」という本宮作品に出てきた「戸川万吉」と「久保銀次」というキャラをもじったような作品群でした。
本来のバンカラには根底に武士道精神があったから、かっこよく見えたのでしょうね。
真の意味でのバンカラは、今はめったにいないんでしょうね。
格好だけでは真のバンカラにはなれないのですから・・。