小学校1年から高校3年までは、各学年別の学習月刊誌というものがあった。
小学校の時は「小学一年生」から始まって「小学六年生」まで。これは小学館が発行していた。
で、中学の頃は「中一時代」~「中三時代」(旺文社)と「中一コース」「中三コース」(学研)。
高校の頃は「高一時代」~「蛍雪時代」(旺文社)。学研にも「高一コース」~「高三コース」があったと思う。
今回は「コース」や「時代」ではなく、小学校の頃の小学館の学習月刊誌をとりあげてみたい。
毎号、付録がつく・・というのは、当時の月刊誌の売りだったが、それはこの小学館の月刊誌にも当てはまった。
で、一番楽しみだったのが「組み立て付録」だった。
学研の「科学」の付録(教材)はプラスチックや薬品などが登場したこともあったが、小学館の組み立て付録は「紙製」だった。
ちょっと難しいと、完全な形では組み立てられないことがあったが、それでも本誌の中に組み立て付録の入った分厚い付録ケースがはさまっていると、ワクワクしたものだ。
この紙製の組み立て付録に慣れてしまった時に、学研の「科学」に出会った時は随分新鮮に思えたもんだった。
「学研の科学」の付録(教材)はプラスチック製だったり、本物の薬品が付いていたりしたもんだから、本格的にも思えた。
一瞬、小学館の学年別学習月刊誌の「紙製の付録」が、ちゃっちく思えたくらいだった。
だが、どちらにも良さはあった。
学研の科学の教材の本格的な印象には圧倒されたりしたが、小学館の学年別学習月刊誌の「紙製の組み立て付録」にも楽しさがあり、その良さはそれぞれ別物だったと思う。
この組み立て付録は、作ってる最中が一番盛り上がるのだ。
組み立てて出来上がってしまうと、出来上がった直後は数回それで遊んだりするのだが、数回遊べば私の興味は急速に萎えてしまった。
やはり、組み立ててる最中が一番楽しい。
本誌に載ってる「組み立て付録の作り方」を読みながら組み立てるのだが、時にはどうもその説明通りに作りあげることができないこともあった。・・実は、私は・・・不器用なもんで(笑)。
ヘンな所に差し込んでしまったり、紙が破れてしまったり・・。
また、やっとこさ出来上がっても、完成品を見ると、意外に「しょぼ」かったり(笑)、脆かったり、ひしゃいでいたり。
完成品で遊んでみても、思ったほどの楽しさではなかったり。
まあ、だから、完成品は数回遊んで終わり・・みたいな状況だったのだろうと思う。
もっとも、こういうのを組み立てるのが異様に上手い奴もいて、そういう子が作った「完成品」はもっと見映えがよかったのだろう。。見映えがよく作り上げることができれば、もっと遊んだかもネ。
組み立て付録には色んなものがあった。
どんなのがあったかは、すぐには思い出せないけど、なぜか今も印象に残ってる組み立て付録が1つだけある。
それは低学年の頃だったと思う。
確か・・・「家」の組み立て付録だった。
組み立てながら、こんな家に住んでみたいな・・と思った。
どちらかというと、女の子向けの組み立て付録だったような気もするが。
家の中がよく見え、作りながら私は妄想の世界でこの家の住人になっていった、
しまいには、この家がどういう場所に建っていて、はるか向こうにはどんな景色があり・・・ということまでイメージしてしまっていた。
私のイメージでは、どこかの郊外にこの家は建っており、近くには森があり、はるか向こうには山々が見え。でも家だけはモダンで。組み立て付録の家は、けっこうモダンだったからね。
そんなイメージだった。
しまいには、このイメージだけが独り立ちし、夢の中にも出て来るようになり。
いつしか、この家と、この家をとりまく環境は、私の頭の中に、現実に一度見たことがあるような錯覚でインプットされていった。
まるで、幼い頃に一度行ったことがあるような風景になってしまった。
今も心の中に、この光景は残っているような気がしているし、どこかに旅すると、私はこういう光景を探しているのかもしれない。無意識のうちに。
なぜこの付録からそこまでイメージを膨らませたのかは分からない。
付録を作りながら、そこまでイメージを膨らませることができたのは、この付録が子供の空想力をおおいに刺激するのに役立ったということになる。
そういう意味では、「ためになった」。
思うに、こういう付録では、子供に想像の余地を与えるようなものがいいのだろう。いや、「作り方」ではなく、その完成品をとりまく仮想の空間のことだ。
何もかも送り手側が指定してしまったり、説明しすぎたりすると、想像の壁になってしまう。
子供の想像力を刺激するようなものがいいんだと思う。
時には、ちっぽけな付録が、その子のその後の発想において大きく役に立つことになるのかもしれないのだから。
今にして思えば、ああいう組み立て付録の企画を毎号考えるのは、出版する側にとってはけっこう大変だっただろうね。
最近、ワンテーママガジンってのが流行っている。
ある1つのテーマに絞ったマガジンで、付録も付いて来る。中には、毎号パーツが付いてきて、毎号買っていくうちにパーツが揃ってくるというパターンもある。
小学館の月刊学習誌の付録も、そういう付録をつけてもいいかもしれないね。
例えば、箱庭のパーツの組み立て付録が毎号ついてきて、揃えると色んなパーツが充実し、充実してきたパーツをどのように配置するかはユーザーの発想次第・・みたいな。
あ、でも毎回の付録をずっと保管していかねばならないのは、大変か・・。たいがいの場合、そういう付録は、いずれ処分されるのがオチだったからね。
そんなことを考えると、どこかに小学館の月刊学習誌の組み立て付録の博物館みたいな場所があって、年代別に展示されていると楽しいな・・などと思ったりもしている。当時の付録を今も保存してある家なんて、そうは無いだろうしネ。
それにしても・・予定では、大人になったら、あの付録のような家に住む筈だったんだがなあ(笑)。
今のような住居に住むなんて、想像もしてなかったなあ。
先日なんて、卑猥な英語で壁にスプレーで落書きされてしまったもん。私、そんなプンスカな環境に住んでます。
まったくもう!消すの、大変だったんだから!しかも、恥ずかしいし。
玄関の外に出て、道行く人がチラチラ見てる中、卑猥な文字の落書きをタワシでゴシゴシ消さねばならない悲哀、ワカルカナ~、ワカンネエダロウナ~。
どこのどいつか知らないが、他人の家に、あんな落書きすんなよ~。 タワシでこすると、壁には傷がつくんだぞ~。
タワシでこすると、壁には傷がつくんだぞ~。
もう、ぷんすか&ぷんすか! 

最新の画像[もっと見る]
-
 ゴン太のコネロク
3日前
ゴン太のコネロク
3日前
-
 ウェイス・ア・ボディー・ダウン by ジョン・ハーレイ
6日前
ウェイス・ア・ボディー・ダウン by ジョン・ハーレイ
6日前
-
 残酷な海水浴
1週間前
残酷な海水浴
1週間前
-
 またしても盛り上がる鬼滅の刃
2週間前
またしても盛り上がる鬼滅の刃
2週間前
-
 ミルキーの謎
3週間前
ミルキーの謎
3週間前
-
 新宿ダダ by 山川ユキ
4週間前
新宿ダダ by 山川ユキ
4週間前
-
 2025年夏、参院選を前にして思う。
1ヶ月前
2025年夏、参院選を前にして思う。
1ヶ月前
-
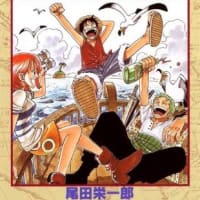 ジャパンアニメランド
1ヶ月前
ジャパンアニメランド
1ヶ月前
-
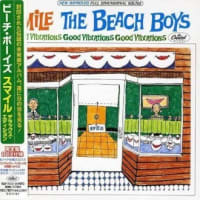 やはり書かずにはいられない、ブライアン・ウィルソンのこと。
2ヶ月前
やはり書かずにはいられない、ブライアン・ウィルソンのこと。
2ヶ月前
-
 冷夏の中を飛んだ、あの宇宙船
2ヶ月前
冷夏の中を飛んだ、あの宇宙船
2ヶ月前










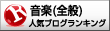






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます