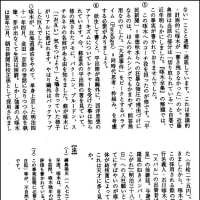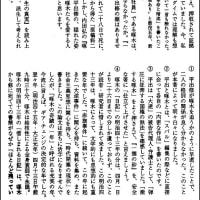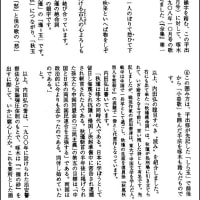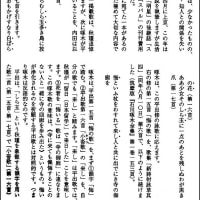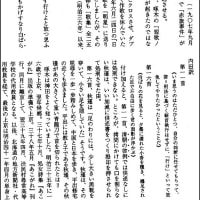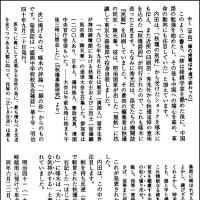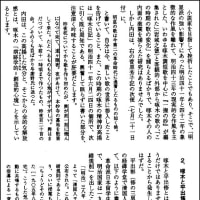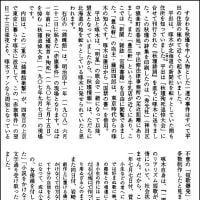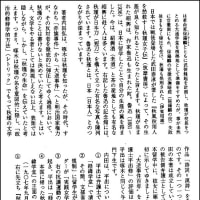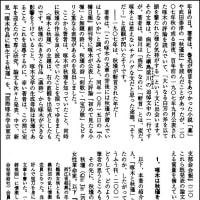先日(五月二十七日)、「文学と音楽の両面から雨情詩を浮き彫りにする試み」という見出しの『講演と演奏による野口雨情』を聞いた(場所・武蔵野公会堂パープルホール)。
野口存彌による講演「野口雨情・詩人としてどう生きたか」と、「武蔵野雨情会」による演奏《野口雨情詩曲集》(歌唱:佐藤文行(二期会会員)。ピアノ:要浩子)があり、〈第3部〉では「みんなで歌おう雨情さん『雨情名作童謡集』」で、私も参加者の一人として会場の人たちと熱唱、雨情の詩の心を堪能した。
ところで、以下は、私が抱いている雨情の「人と作品」についての、長年気にかかっていることどもの、疑問であり、備忘録である。
シャボン玉 とんだ
屋根までとんだ
屋根までとんで
こわれて消えた
2
シャボン玉 消えた
飛ばずに消えた
うまれてすぐに
こわれて消えた
風 風 吹くな
シャボン玉 とばそ
数多い雨悄の童謡の代表作の一つ、この「シャボン玉」(「しゃぼん玉」とも表記される)は、シャボン玉で子どもたちが遊んでいる様子が描かれているが、これは①雨情が青年期(精しくは最初の結婚の際)に生まれて生後八日で亡くなった長女を悼んだ作品であるという説。②雨情が再婚してから生まれた後の妻の次女(大正十年生まれ、同十三年九月没)が数え年四歳で亡くなって、それで雨情は人の命のはかなさをシャボン玉に託した、とする説がある。
先般刊行された『野口雨情 郷愁の詩とわが生涯の真実』(日本図書センター刊・人間の記録第一七二巻・二〇一〇年刊)巻末の「雨情年譜」(野口存彌)を見ると、雨情は最初の結婚を明治三十八年(一九〇五)に高塩ひろ、としていて、翌年、雅夫、明治四十年に右記早逝したみどり、大正二年に美晴子を設けている。しかし大正四年五月、ひろと離婚。三年後の大正七年秋、中里つると再婚。翌八年香穂子が誕生。以降、恒子、美穂子、九萬男、存彌、陽代、喜代子、恵代と、先妻との間に三人(男一人、女二人)、後妻との間に九人(男二人、女七人)の子に恵まれていて、大変な子福者である。だから、自分の子供の死がテーマともモチーフともなって「シャボン玉」が書かれた、という説は、夭逝した子があっても一応脇に置いた方が良いと思う。それに創作家(作詞者)は、常に具体例を作品に刻むと言い切ることはできない。雨情は吾が子を作品にすることは終生無かった。
以下は結論的になるが、右記した会で当日配布されたパンフレットに盛られた詩の一編、「人買船」が明治期に「社会主義詩人」として出発した野口雨情の、その後の童謡・民謡を通底するアルファでありオメガであると私は改めて認識した。
人買船に
買はれて行った
貧乏な村の
山ほととぎす
日和は
続け
港は
凪ぎろ
皆さん
さよなと
泣き 泣き
言ふた。
注目すべきは第三連である(傍線安宅)。
明治四十四年一月十八日。大逆事件の判決公判の日。二十六名の被告中二十四名に死刑宣告が下った。法廷から退場の順序は唯一人女性の管野須賀子が第一番目だった。その際、管野は編み笠を脱ぎ、皆の方をふり返ると、
「皆さん、
さようなら!」
と声を発した。これに呼応して被告たちもまた「万歳!」と和した。
一昨年は大逆事件百年の節目であり、本誌「群系」も特集を組んだが、シンポジュウムが数々行われ、出版物として朝日新開記者田中仲尚の大部な『大逆事件―死と生の群像』(岩波書店)ほかの出版が今も続いている状況にある。
右に掲げた雨情の「人買船」の第三連は、この管野の泰然とした姿・行動を「核」にしている。
(ちなみに、当時獄中の管野から横山勝太郎弁護士に送られた針文字の手紙か改めてこの度各紙に取り上げられたが、実物の写真は『管野須賀子全集3』(弘隆社・一九八四年刊)の扉写真において見ることができる)