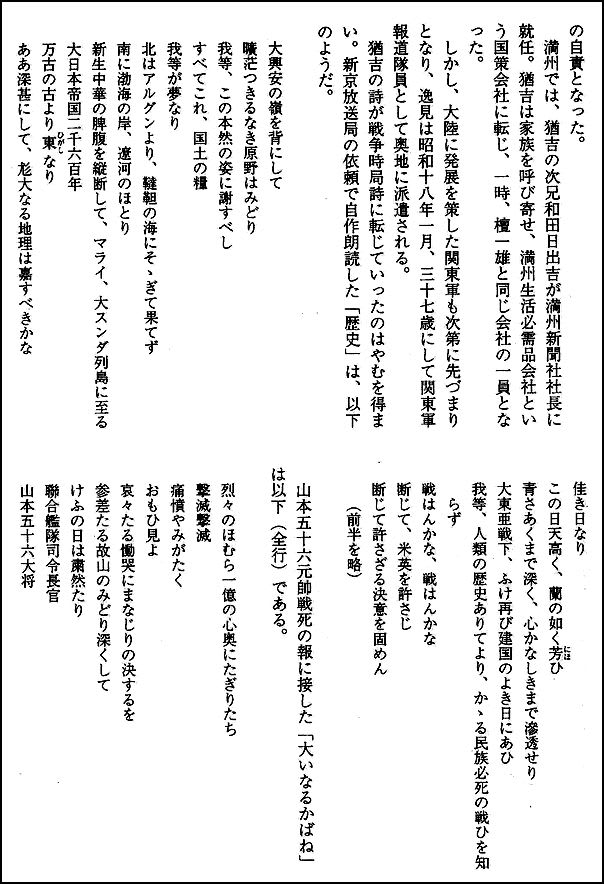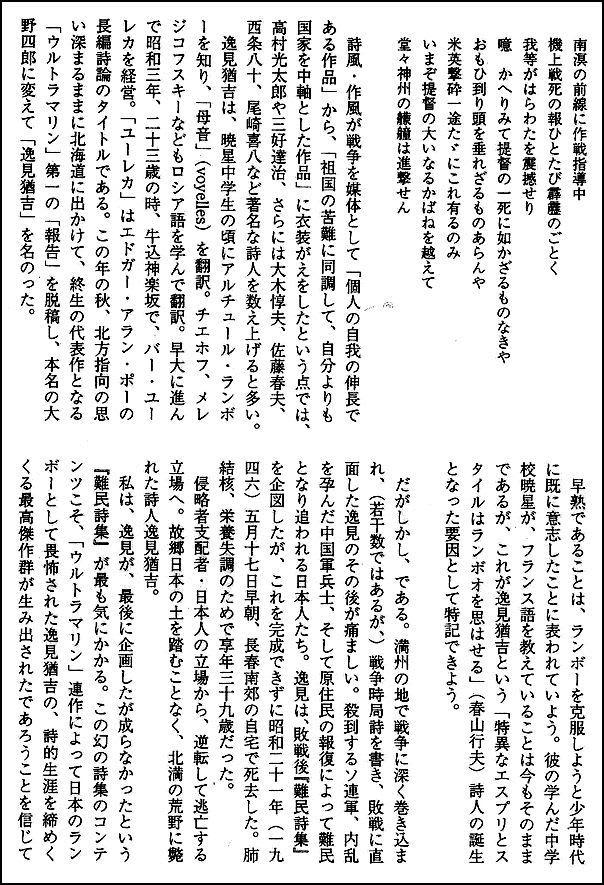東京創元社版『現代日本名詩集大成』第七巻(昭和35年11月刊)は、「草野心平・中原中也・八木重吉・岡崎清一郎・逸見猶吉・尾形亀之助・山之口貘」を収めている。
定評ある詩集を完本で収録したこの詩全集で、「逸見猶吉」というどこか奇異な感じの筆名のこの詩人の作品に触れた人がこれまでに多いと思われる。俗事にわたるが繰り返すと逸見の次兄の和田日出吉は「満洲新聞」社長に赴任した著名なジャーナリスト。その妻は女優の木暮実千代。弟大野五郎は画家として知られる。
以下、極私的に書くが、現在私か住む北区豊島五丁目団地はJR王子駅近くにある。「田端文士村記念館」にJRで二駅。文京区の「鴎外記念図書館」にはバスで行ける。また都営南北線で「三四郎池のある赤門」の「東大前」は四駅目。加えて『逸見猶吉ノート』(菊地康雄著・一九六七年・思潮社刊)によって逸見猶吉の墓所が、JR王子駅北口から石神井川沿いに少しのばったところの紅葉寺にあることを知った。
そこで、先日、北区立中央図書館からも行き易い石神井川に架かる紅葉橋のほとりに在る紅葉寺(これは通称で、正しくは真言宗豊山派、金剛寺)の墓苑に建つ大野家の墓を拝んできた。墓苑は、かなりに広く、そのほぼ中央の花崗岩の立派な墓石に「大野家之墓」と彫られている。裏面に「墓誌」が刻まれ、「大野旧住下野国都賀郡谷中村…」と見え、大正八年三月の建立とある(この谷中村は足尾銅山の廃液流出によって廃滅した)。
墓石の背後に新旧の卒塔婆が十本ほど立っていて、その一本に「大野裕史」の立てたものがあった。「裕史」は、猶吉の二男。右記菊地の著によると、裕史は昭和十七年生。三男雄示は同十九年生まれ(長男は夭折)。
先の『現代日本名詩集大成』に付してある猶吉の「小伝」に、
(略) 一九四六年五月十七日、蒙古風の吹き捲く長春郊外で北を見つめつつ仙れた。
とある。
遺族は妻静(猶吉より二歳年長)、次女真由子、長男隆一、次男裕史、三男雄示。
猶吉没の翌々月、在留邦人の帰国が始まり、胡蘆島から乗船というので遺族五人は南下。しかし錦州省北大営で疑似コレラが発生。静は死亡、真由子は小児麻痺ゆえに、母の五日後〈呼吸停止〉で世を去った。三人の男児は別々に引き取られたが長男隆一は早くに亡くなっている。また真由子は〈呼吸停止〉と見えるが、菊地の著に「〈安楽死〉デアッタ」とある。逃避行の際に足手まといになった子供を見捨てた、という痛ましいケースがここにもやはりあったのかと想像する。
以下に私か逸見猶吉の人と作品とに惹かれる所以を綴ってみる。
一つには、彼の小伝に、敗戦翌年「長春郊外で北を見つめつつ仆れた」とあることに拠る。私の叔母も、北満(現在、中国東北部と呼称)牡丹江に入植したが、敗戦と同時に夫はシベリアに連行され、幼い娘を抱きかかえての逃避行のさなか、母子は栄養失調と発疹チフスで死んだ。
逸見の死因は、肺結核と栄養失調。
木山捷平は満州帰りの作家。長春で逸見と交際があり、「皆んなで(死んだ)逸見をかついで近くの原っぱのニレの木の下に仮埋葬をした」と書いている。
私の叔母と娘とに遺骨は無い。野ざらしのままの「大量の死者」としての最期であったと聞くばかりだ。
平成十三年(一九九九)夏、私は師 尾崎秀樹に率いられて長春での「日中大衆文学研究シンポジュウム」に参加した。この旅は、シンポジュウムの後、北上してハルビンに向かい、途中、葉山嘉樹が、入植地から長女百枝とともに敗戦後の脱出行の途次落命した徳恵駅付近の埋葬地を尋ね、また七三一部隊の跡地にも足を運んだ。私は、もしも右記した叔母・姪の死の土地に(個人行動で)行けないか、と考えていたが、それは不可能なことだった。しかし長春(戦中には「新京」という呼称が日本の傀儡政府によってこの都市に付けられていた)からハルビンへの距離感を体得したことで、室生犀星が日・中・露の勢力が互いに牽制しつつある、この時期、昭和十二年春に、何故、駆り立てられたように「落魂した白系ロシアの女人」を求めて北に松花江を眺める遥かなこの地に急いだのか、その犀星のメンタリティーが良く判った(しかし、そのコンテンツは脇道になるのでここでは省く)。
右の「日中シンポジュウム」の中国側案内役は、呂元明さん。当時吉林省の、師範大学教授で、その後も度々来日。早稲田大学、法政大学、京都の国際日本文化研究センターなどとのパイプが太い。呂さんは少年時、七三一部隊の、真の姿を実見してもいる生き証人である。逸見猶吉、葉山嘉樹やはり満州で果てた前衛詩人野川隆を中国人研究者として一貫して追究している。私は帰国後、何年か後に偶然ながら、この人と中野区立中央図書館地下で開催されていた「中国書画展」会場で再会した。逸見の『難民詩集』追尋を呂さんも長年の宿題としている。先出の菊地康雄『逸見猶吉ノート』には、未定稿の「難民詩集」を託された人の足どりが書かれており、敗戦後の動乱の渦中に消えたとされる逸見の「幻の詩編」の存在は完全に消えていない。
ペンを逸見猶吉の墓前に戻すと、「大野家之墓」を訪ねたことで猶吉の二男裕史氏が健在であることが分かった。
右に、墓背後に立てられていた卒塔婆のことを書いたが、「平成二十三年四月二十三日」と記して立てられたものが二本あって、それは、最も新しい日付のもので、表に、
1、〈為翠蓮院吟詠妙智大姉七七日忌菩提也〉
と書かれ、裏をみると一本は「大野啓一」、一本は「鍛冶晶子」が立てたものの由。
裕史氏の名は、その三年前の卒塔婆で表に、
2、〈爰宝塔為華光童女祥月成三菩提也〉
とある一本の裏に見えた。すなわち、
〈南無遍照金剛 平成一九年八月二日 大野裕史〉
と。しかし「華光童女」とは、誰であろうか。
ちなみに、以下の3とする一本には、こう書いてあった。
3、〈爰大施餓鬼者為先祖代々一切精霊成三菩提也〉
と。その裏に、
〈南無遍照金剛 平成二十二年七月二十日 大野智子〉
とある。これを見ると、3の「大野智子」が1の「妙智大姉」ではあるまいか。そうならば「智子」は、自らが主となって立てた3の翌年に「大野啓一・鍛冶晶子」二人によって卒塔婆が立てられ供養されていることになる。
3に「先祖代々一切精霊」と記し、大野家累代の死者を供養した当主である人が「大野智子さん」であろうことは見易い。
ともかく、この日の「掃苔」によって、大野裕史が「逸見猶吉三男の裕史」と同定されたことで、私の心は和んだ。これ以上、ことさらに大野家一族の只今をほじくるのは行き過ぎといえる。
紅葉寺の墓苑は、石神井川の紅葉橋の橋たもとから右岸、深く岸下を流れる石神井川を見下ろす場所にあって、かなりに広い。このあたり石神井川の両岸は桜の名所だ。
この訪苑の日、墓苑のあちこちに丁度盛りのつつじが燃えるようだった。初夏を思わせる日の午後遅くに、墓苑を出て紅葉橋に佇つと両岸の桜の並木は青々と葉を茂らせており、眼下深くには、清冽な流れが音立てていた。私は右岸を下流に向かって歩き出した。途中に「音無さくら緑地」がある(石神井川は、このあたりでは音無川と呼ばれている)。石神井川の旧川を利用したもので、歩道から深く弓なりに入りこんでいる。かつての石神井川は蛇行し、このあたり下流での氾濫が多かった。今は紅葉橋の一つ下の松橋を過ぎると大きな暗渠に流れは吸い込まれ、飛鳥山の下を抜けて隅田川に注ぎ込む。その「大工事」が何年にもわたって継続している。JR王子駅の下を抜けたところまでは完成したが、その先の隅田川へと出て行く個所の工事が延々と停滞している。「音無さくら緑地」の一方の入り口が右記松橋のたもとなので、紅葉橋との間、丁度一橋間を川べりの道から外れてこの「緑地」の中を抜けてみた。旧川の流れの姿を見せて緑地がU字形に続く、奥まったところに昔からの天然河岸も一部残っており、湧水を利用した流れもある。
この日、私は「緑地」を抜けて、ふたたび川べりの道に戻り、下流の飛鳥山の方向に歩きだそうとした。
その時のことだ。川べりの低いセメント塀の上に長さニメートルを超す青大将が寝そべっているのを見た。太陽が西に傾き、夕景が訪れかかっていた。
この右岸の道を通る人は少ない。私は驚いて立ち止まり、長大な青大将をつくづくと見、丁度通り合わせた年輩の男性に、「青大将!」と教えたところ、「ああ、さくら緑地の主ですよ。今日は暖かだったから日なたぼっこに出て来たんでしょう」と、近所の入らしく別に驚きもしない。
私には、逸見猶吉の墓所のある紅葉寺の墓苑と接している「古くからの緑地」の、その主が、この青大将ならば、それは逸見猶吉の化身とも見えた。
石神井川は、右記した暗渠を抜けると隅田川と合流して東京湾に至る。さらに太平洋へと隅田川の流れが水面下深くに突出して進んでゆこう。私はこの堂々たる青大将が、隅田川からの見えない太い水流の化身となって世界に泳ぎ出し、拡がっていくとよい、と願って、この日の逸見猶吉の墓参を終えた。
詩誌「歴程」を介して高村光太郎は以下の如くに書いている。
「逸見猶吉の詩の魅力はその稀有な高層気圏的気凛にある。その詩に於ける思想も生活も言葉もすべて此の稀元素のやう
な気凛の噴煙を吐かしめる因数的存在としてのみ意味がある。彼の詩は字面のどこにもなくて、しかも字面に充実して人を捉
へる。その由来を究尽してゆくと何もないところに出てしまふくせに、究尽の手の脈には感電のやうなショックが止まない。詩の
不可思議をまざまざと示す彼の詩は、殆ど類を絶して、彼以後に彼の如き声をきかない。彼のやうな詩人は多作であり得るわ
けがないから、恐らく遺した詩は極めて少いであらう。ウラニウムのやうに小さくて、又そのやうに強力な放射能を持つてゐる
のだ。今座右に一篇の彼の詩もない。しかし曾てよんだ彼の詩のひびきはりんりんと耳朶をうつてやまない。思想も生活も言
葉も此の無形の実在に圧倒され、しう伏せられて遂に思ひ出せない。その詩人が死んだら、もう二度とその類の詩をきき得な
いという稀有な詩人が、こんどのどさくさの中の多くの死にまじつて死んだのである。」(「逸見猶吉の死」・昭和二十三年七月『歴程』逸見猶吉追悼号)。
光太郎自身は、昭和二十年四月十三日、米機の空襲で東京千駄木のアトリエが焼尽し、五月、岩手県花巻の宮沢賢治の生家に疎開、八月同家が炎上、十一月から同県稗貫郡大田村山口の小屋で独居自炊の生活をしていた。そして、詩集『典型』のコンテンツとなる「自己流論」の日々の中で伊藤信吉に出したハガキに「逸見君のことが気がかりです」と記した。逸見の死を知って宮崎稔に宛てたハガキには、「(略)実に大きな犠牲と思ひます。詩人としての逸見猶吉の埋合せになる詩人今日はまったく無し。凡庸な詩作者のみ多い時に本当の詩人を又一人失ひました。」と書いた。
私は考える。ランボーは詩を捨ててアフリカに去ったが、逸見猶吉の場合は、スタート時に、日本のランボーとして畏怖されたものの、一度は軍国詩になびき、敗戦によって自らの「詩人としての運命」を噛みしめ、きっと亡国の詩、断腸の詩を書いたはずなのだ。逸見の「難民詩集」は、彼の死によってその「文字言語」は見えないが、逸見猶吉の思念・メンタリティを受容する者がいるかぎり遍在していく、と。
逸見の知友のロシア文学者長谷川濬は、作家長谷川四郎の兄だが終戦後オーストラリアに移った白系露人作家バイコフの『偉大な王』の訳者(四郎との共訳)としても知られるが、猶吉の死の報に駆けつけている。
「逸見の宅に行くと関谷が撫然として出て来た。私は黙って八畳間にはいった。そこに私は逸見の死体を見た。髪をばさばさ
に伸ばし、骨と皮だけの顔はうす黒く、けわしい鼻が突起し、白い眼を半分開いたまま、じーと動かず、逸見は息絶えていた。
あの精悍な顔色は消え失せ、病苦に打ちのめされた痕を残したまま目をむいて横たわる逸見の死顔を見て、私は茫然と立っ
ていた。彼の細君と三人の男の子がうろうろと歩き廻っていた。私は手にしてた小枝を二本彼の首の処へ架けて坐し、合掌し
た。細君の話によると、朝早く彼女と軽い会話を交し、末の男の子がよちよち歩く姿を見てにやりと笑い、細君に向かって『こい
つが一番楽しそうだな』といった。彼女はうなずいて隣室へはいり、長女の世話をして再び病室へばいると、もう息絶えていた
そうである。あのうす笑いが最後で、逸見はあっけなく死んだらしい。」(「逸見猶吉の死」・昭和二十二年七月『日本未来派』第二号)。
天から届いたとしか思われない稀有の作品と引き換えに果てるのが詩人の生命体、として見れば、ランボー、ニイチェ (詩も書いた)、石川啄木、中原中也、そして逸見猶吉など早逝の詩人は、死を媒体としてそのクオリアを読者個体のミトコンドリアに届けていることを思わないわけにはいかない。
本稿の執筆について、前出菊地康雄著『逸見猶吉ノート』の恩恵を受けた。記して感謝する。
(註1)「人物研究」第20号所収・安宅夏夫「室生犀星・喰爾濱伝説」
(註2)同著の「続編」刊行が予告されているが、未刊である。
〈付記〉
本稿、稿了後、国立国会図書館にて次の二冊の参看を得た。
1、尾崎寿一郎著『逸見猶吉 ウルトラマリンの世界』
(二〇〇四年刊・発行・著者)
2、尾崎寿一郎『逸見猶吉 火檻1 篇』
(二〇〇六年 漉林書房刊)
1、2の著者尾崎寿一郎は、一九六〇年代から五十年を投じて、この二著を仕上げた。以下に最大の要所を挙げると、猶吉の「戦争協力詩」は、「書かされたというべきか、その苦渋に耐える無念が惨み出ている」という。これの実証が胸打たれるハイライトだ。在満の関東軍は、報道演習と称して在満日本人の文士・詩人を動員し、非常時局に対処せよと圧力を加えた。詩人逸見猶吉は同時に生活人大野四郎であり、妻と四人の子供を抱えていた。「協力詩」を求められて違背した場合、赤紙で引っぱられて前線に出されて抹殺されることになる。兄和田日出吉とその妻木暮実千代、弟で画家の大野五郎にも累を及ぼしかねない立場にあった。大杉栄・伊藤野枝を関東大震災直後に惨殺した元憲兵大尉甘糟が仕切るのが満州の新興日本の文化界なのであった。逸見猶吉の一本気、侠気、純粋、その底に流れるアナーキーな思想を見逃すドジな国策文化人甘糟ではない。
ここで、私はアフリカに渡ったアルチュール・ランボーが詩を断ったのとは逆に逸見は最期まで詩を棄てなかったことを思う。為に「戦争協力詩」を書く羽目に至ったことが無残である。もっぱら断筆のランボーが褒められるが、私は逸見猶吉こそ「真の詩人」と呼びたい。当時日本には、ぬくぬくとした生活をしつつ「戦争協賛詩」を書いた詩人は多くいる。
尾崎寿一郎は、鮎川信夫、高野喜久雄の「見当違いな猶吉詩批判」を批判する。また川村湊には次の二著『満州崩壊』(文春新書・一九九七)、同『文学から見る「満州」』(吉川弘文館・一九九八)があるが、総じて逸見猶吉の「人と作品」を読み抜いてはいない、と捉えている。
尾崎は、半世紀に及ぶ現地取材・生存者へのインタビューを重ねた。また「逸見猶吉の詩」を真に読めていない鑑賞文が出回っていることにも言い及ぶ。硬質・難解で鳴る猶吉詩の、初めての受容は、尾崎のこの二冊からだと言える。逸見猶吉研究の、見事に成熟したこの大部の書が、「〈核爆発〉が日常となった日本国における詩界・文化界」、に作裂し続けることを私は念願する。〈鎮魂と悲哭の書〉であることは無論だが、逸見猶吉が蘇生し、歩み出した、と言いたい稀有の書だ。
唐突なようだが、室生犀星の詩と、渡満後の逸見猶吉の詩とを並べる。犀星は昭和十二年四月十九日、満州旅行に出発。五月七日に帰京した。この間の詩的収穫に『哈爾浜詩集』(冬至書房・昭和三十二年刊)がある。
逸見猶吉は、昭和十三年十月、在満作家たちによる季刊文芸誌「満州浪漫」に参加。翌十四年一月、ハルビンに遊び、同誌第二輯に「地理二篇」(「海拉爾」「哈爾浜」)を発表。翌十五年三月刊に萩原朔太郎編纂『昭和詩紗』(冨山房百科文庫第九十九篇)に「哈爾浜」「海拉爾」が代表作として収録された。
先ず、犀星の『哈爾浜』に入っている「はるびんの歌」と「中央大街附近」(共に初出「中央公論」昭和十二年十二月)を見る。
はるびんの歌
きみははるびんなりしか
古き寶石のごとき艶をもてる
ハルビンの都なりしか。
とつくにの姿をたもちて
荒野の果にさまよへる
きみこそ古き都はるびんなりしか。
燐寸のレッテルのごとき
数々の館をならぶる
きみは我が忘れもはてぬはるびんなりしか。
はるびんよ
はるびんよ
我はけふ御身に逢はむとす。
中央大街附近
ここ過ぎて濁江見ゆるはいづくぞ、
中央大街の甃石に
波の秀のくる大河は何といふ江ぞも、
波の間に行く蒸気船、
鋭どき鴉の群はきのふもありしか、
濁れる波はこころを痛ましめ
遠き草原の岸べにつづきたり。
草原のあなたに
そ聯といへる國のあるものか。
次に逸見の「哈爾浜」「海拉爾」を引く。
哈爾浜
埠頭区ペカルナヤ
門牌不詳のあたり秋色深く
石だたみ荒くれてこぼるるは何の穂尖ぞ
さびたる風雨の柵につらなり
擾々たる世の妄像ら傷つきたれば
なにごとの語るすべなし
巨いなる土地に根生えて罪あらばあれ
万筋なほ慾情のはげしさを切に疾むなり
在るべき故は知らず
我は一切の場所を捉ふるのみ
かくてまた我が砕く酒杯は砕かれんとするや
かかる日を哀憐の額もたげて訴ふる
優しさ著るしきいたましき
少女名は
風芝とよべり
死の黄なるむざんの光なみ打ちて
麺麹つくる人の影なけれどもペカルナヤ
ひとしきり西寄りの風たち騒ぐなり
海拉爾
凄まじき風の日なり
この日絶え間なく震捲せるは何ぞ
いんいんたる蝕の日なれば
野生の韮を噛むごとき
ひとりなる汗の怒りをかんぜり
げに我が降りたてる駅のけはしき
悲しき一筋の知られざる膂力の證か
啖ふに物なきがごと歩廊を蹴るなり
流れてやまぬ血のなかに泛びづるは
大興安のみぞおちに一瞬目を閉づる時過ぎるもの
歴史なり
火襤褸なり
永遠熄みがたき汗の意志なり
風の日 樺飛び 祈りあぐる
おゝ砂塵たちけぶる果に馬を駆れば
色寒き里木旅館は傾けり
結論的なことを書くと、両者の詩が、いずれも文語調であることは、萩原朔太郎の後期の詩からの通底である。
朔太郎晩年の詩集『氷島』(昭和九年刊)は、これは中期の作「郷土望景詩」(ほぼ大正十四年作。同年刊の詩集『純情詩集』に「愛憐詩篇」[少年時代の作]と併せて刊行された)と同じ文語調の作品で占められる。朔太郎は口語自由詩の完成者であったが、「古き日本語の文章語」に本卦帰りした。三好達治は「郷土望景詩」を「朔太郎の最高頂点を示す」としながら同じく文語調の『氷島』を「声韻のかすれ乱れた頽廃期以後のもの」とする。これが当たっているかはここでは問わない。
ここでは犀星と猶吉が、文語体に移動した所以を見たい。犀星の『哈爾浜詩集』は、犀星のスーベニール(旅人の詩)。その哈爾浜行きは、亡命落魄の白系ロシアの美女たちとの積極的な接触であった「事実」は、犀星以外の誰にも知られなかったが、この旅の間の満足した昂揚感と、これと背中合わせに生じた夢醒めた旅人としての悲哀の思いは、これは文語体でしか表現できないものであった。
犀星の文語体の詩は、大正十一年十二月刊の『忘春詩集』において、にわかに集中して書かれた。生後一年で長男豹太郎が早逝した悲痛感は口語調で表現できなかったのだ。この喪失感は、朔太郎の、「青春喪失の念」を表現した先述の「郷土望景詩」と連動している。朔太郎と犀星との通奏低音は、いざとなると古き日本語の文章語に本卦帰りをすることで共振する。
逸見猶吉の場合は、その詩魂は早大時代にアルチュール・ランボーの詩によって目覚め、先述の通り昭和四年、二十三歳の時、伊藤信吉編纂『学校詩集』(十二月刊)に「ウルトラマリン(第一 「報告」、第二「兇牙利的」、第三「死ト現象」)を寄稿して詩界を驚倒させた。翌昭和五年『詩と詩論』(第五号)で吉田一穂は、「最も新らしい尖鋭的な表現、強靫な意思の新らしい戦慄美、彼は晴天に歯を剥く雪原の狼であり、石と鉄の機構に擲弾して嘲う肉体であり、ウルトラマリンの虚無の眼と否定の舌、氷の歯をもったテロリストである」と絶讃した。
伊藤信吉も、「総じて作風は暗く険しく、自虐の牙をもってなにものかに噛みつく精神の激しさが、同時代の詩人たちを戦慄的な共感に誘った。この特色はその後の多くの作品に脈絡し、渡満後の作品に「凄まじき風の日なり/この日絶え間なく震撼せるは何ぞ/いんいんたる蝕の日なれば/野生の韮を噛むごとき/ひとりなる汗の怒りをかんぜり」(『無題』)などの表現がある」と猶吉の「前衛」としての詩が特段に傑出している所以を述べている。この評に見合うべく、同じく早逝した中原中也、伊東静雄、立原道造などとともに逸見猶吉の、やはり数少ないけれども秀でている作品について、多方面から更なる批評を請いたいと、考える。
右に引用した二編にも見られる朔太郎晩年の文語詩篇との照応・交響は、朔太郎詩が日本の最高の詩だと言われる以上、その「脈絡」「系譜」において猶吉の詩を勘考・感受したいと思う。出発時の「前衛詩」が、境遇の変化によって、かくも変貌する所以は何か。そしてその作品の詩的真実はいかなるものなのかを。個体としての猶吉の詩の変貌は、一人猶吉だけが時代によって受けた挫傷によって発したものではないと考える。朔太郎の文語詩編の褒貶が相半ばしている一半は先述したが、猶吉の文語詩編への言及は未だ管見には入らない。
それはともかく、猶吉の詩風が満州に来てから、外見は室生犀星の『哈爾浜詩集』とも同調する文語詩に変わってしまう。
なぜなのか。コンテンツを濃い詠嘆の文語の器に盛っているために、ちょっと見には犀星の作と見分けがつかない。しかし、犀星の二編は、前者「はるびんの歌」ならば、「はるびんよ/はるびんよ」と語りかけて「積恋の人の元に急ぐ風情」だし、後者「中央大街附近」は松花江の彼方はるかの、「ソ連」の方を眺めての、共に旅行者のスーベニール(記念品)でしかない。
しかし、猶吉の「哈爾浜」と「海拉爾」の二編は、悲傷、心を破っている。
1.石だたみ荒くれてこぼるるは何の穂尖ぞ
(「哈爾浜」)
2.この日絶え間なく震憾せるは何ぞ
(「海拉爾」)
1,2に見る問いかけの口調は、発表の時系列を調べると犀星が『哈爾浜詩集』収録の詩編を初出時に掲載した「中央公論」(先述)を逸見が目にしていたからの表現かとも思われるが、そうでなくとも猶吉の「斃れ伏した狼が石に齧りついている」といった索漠とした悲傷の思い、心を破られたその姿から、猶吉の作品が単なるスーベニールではないことを汲み取りたい。外見の一致が各個体の内面と必ず一致するはずはない。
詩は無論、生まの体験によってのみ成るわけではない。だが、全人生・全体験から抽出され、惨み出る詩人の体液でないわけはない。そうでなければ詩は「言語の遊戯」であって、読む人を打たない。
戦後、日本の現代詩の世界から思想性が消えてしまったと言われる。「相対的安定・米ソ対立の消失」という政治・国際問題で制動された。しかしこれは見かけのことだ。心眼をもって取り込み、生み出す巨視的・根源的な思想性が日本の詩界に蘇える日が来るか、来ないか。
辻井喬は『伝統の創造力』(岩波新書・二〇〇一年刊)で、野村喜和夫・城戸朱理編『討議戦後詩-詩のルネッサンスへ』(思潮社・一九九七年刊)を取り上げ、「来るべき「詩のルネッサンス」がハイデガー的な「決断」か、ベンヤミン的な「中断」に近いものかという問題提起は、読者に向けられた二人の礼儀正しい修辞ではあっても、それ以上のものではない。というのは、詩の衰弱、詩の滅亡について深く検討されることのないこの総括は、はじめから詩の救済を目的としたものではなかったのだから」と「物足りない」としている。
辻井の著は、「日本の文化が衰弱していると感じられるのはなぜか」という根元的な難問に答える著で、今日現在見られる日本の詩歌・小説の歩みを思想性に着目して検証したもの。ことごとく肯綮にあたる炎の文辞に満ちている。今日、画期の詩人が仰望されよう。
現在、日本には直面する戦争はない。しかし、戦争によって詩人・作家がどのように生きたか、生かされたかの具体例の一つとして、逸見猶吉の「人と作品」はある。鋼鉄の如き詩魂が苦く辛く変容しつつ奏でた、全四十編に充たない『逸見猶吉詩集』を「原子炉爆発の連鎖による地球消失」も視野に現れた時代にさしかかった今日現在、切実さの度合いを深めて読みたいと私は考える。
その変遷は、総括してみると単純である。しかし、それを「単純だ」とは誰も言えない。リトマス試験紙の反応と同じで、詩人も状況の変化によって見事なまでに変わってしまうのだ。
戦時において、詩人の運命は、いかに転変していくものなのか。その実験材料の一つが以下に見られよう。
逸見猶吉は、「ウルトラマリン」の総題のもとに、「報告」「兇牙利的」「死ト現象」の三編が激烈な戦慄感に貫かれたランボーを思わせる詩風で、一挙に前衛詩人の頂点に立った感があった。以下、代表作「報告」を引くが、この連作は昭和四年、伊藤信吉編纂『学校詩集』に発表された。詩誌「学校」は、その頃前橋市に住んでいた草野心平を中心に伊藤信吉、横地正次郎が協力して刊行。前橋は萩原朔太郎、萩原恭次郎につながる地だ。「学校」グループは全体に「詩の前衛」であり、ダダ的で、アナーキスチックな色調を特色とした。
草野心平の回想では、昭和四年に逸見は早大政経学部の学生で前橋に草野を訪ねており、草野、高村光太郎、高田博厚、岡本潤、岩瀬政雄と赤城山に登ってもいる。
報 告
ソノ時オレハ歩イテヰタ ソノ時
外套ハ枝二吊ラレテアツタカ 白樺ノヂツニ白イ
ソレダケガケハシイ 冬ノマン中デ 野ツ原デ
ソレガ如何シタ ソレデ如何シタトオレハ吠エタ
《血ヲナガス北方 ココイラ グングン密度ノ深クナル
北方 ドコカラモ離レテ 荒涼タル ウルトラマリ
ンノ底ノ方へ――》
暗クナリ暗クナツテ 黒イ頭巾カラ舌ヲダシテ
ヤタラ 羽搏イテヰル不明ノ顔々 ソレハ
目二見エナイ狂気カラ転落スル 鴉ト時間ト
アトハサガレンノ青褪メタ肋骨ト ソノ時オレハ
ヒドク凶ヤナ笑ヒデアツタラウ ソシテ 泥炭デアルカ
馬デアルカ 地面二掘ツクリ返サレルモノハ 君モシル
ワヅカ二一点ノ黒イモノダ
風ニハ沿海州ノ錆ビ蝕サル気配ガツヨク浸ミコンデ 野
ツ原ノ涯 ハ監獄ダ
歪ンダ屋根ノ下ハ重ク 鉄柵ノ海ニホトンド何モ見エナイ
絡ンデル薪ノヤウナ手ト サラニソノ下ノ顔卜
大キナ苦痛ノ割レ目デアツタ 苦痛ニヤラレ
ヤガテハ霙トナル冷タイ風二晒サレテ
アラユル地点カラムザンナ標的ニサレタオレダ
アノ兇暴ナ羽搏キ ソレガ最後ノ幻覚デアツタラウカ
弾創ハ スデニ弾創トシテ生キテユクノカ
オレノ肉体ヲ塗沫スル ソレガ悪徳ノ展望デアツタカ
アア 夢ノイツサイノ後退スル中ニ トホク烽火ノアガル
嬰児ノ天ニアガル
タダヨフ無限ノ反抗ノ中ニ
ソノ時オレハ歩イテヰタ
ソノ時オレハ歯ヲ剥キダシテヰタ
愛情ニカカルコトナク 瀰漫スル怖ロシイ痴呆ノ底二
オレノヤリキレナイイツサイノ中ニ オレハ見夕
悪シキ感傷トレイタン無頼ノ生活ヲ
顎ヲシヤクルヒトリノ囚人 ソノオレヲ視ル嗤ヒヲ
スペテ痩セタ肉体ノ影二潜ンデルモノ
ツネニサビシイ悪ノ起源ニホカナラヌソレラヲ
《ドコカラモ離レテ荒涼タル北方ノ顔々ウルトラマリン
ノスルドイ目付
ウルトラマリンノ底ノ方ヘ――》
イカナル真理モ 風物モ ソノ他ナニガ近寄ルモノゾ
今トナツテ オレハ墜チユク海ノ動静ヲ知ルノダ
時代は、徐々に軍閥政治に傾き、満州事変以後、十五年戦争の時期、国内で窒息する芸術青年たちは大陸の地、満州に向かう者も多かった。草野心平は昭和十五年に国民政府宣伝部顧問として南京に行き、そこで現地召集を受け、敗戦時には南京集中に収監された。逸見は昭和十二年一月、日蘇通信社新京(現・長春)駐在員となって、二月に単身赴任した。
その出発前に、長女多聞子が、小石川区雑司ヶ谷の東大付属医院分室で死亡。続いて次女真由子が生まれたが、小児麻庫に罹る。この長女と次女のことが、逸見の生涯の自責となった。
満州では、猶吉の次兄和田日出吉が満州新聞社社長に就任。猶吉は家族を呼び寄せ、満州生活必需品会社という国策会社に転じ、一時、檀一雄と同じ会社の一員となった。
しかし、大陸に発展を策した関東軍も次第に先づまりとなり、逸見は昭和十八年一月、三十七歳にして関東軍報道隊員として奥地に派遣される。
猶吉の詩が戦争時局詩に転じていったのはやむを得まい。新京放送局の依頼で自作朗読した「歴史」は、以下のようだ。
大興安の嶺を背にして
曠茫つきるなき原野はみどり
我等、この本然の姿に謝すべし
すべてこれ、国土の糧
我等が夢なり
北はアルグンより、韃靼の海にそゝぎて果てず
南に渤海の岸、遼河のほとり
新生中華の脾腹を縦断して、マライ、大スンダ列島に至る
大日本帝国二千六百年
万古の古より東なり
ああ深甚にして、尨大なる地理は嘉すべきかな
佳き日なり
この日天高く、蘭の如く芳ひ
青さあくまで深く、心かなしきまで滲透せり
大東亜戦下、ふけ再び建国のよき日にあひ
我等、人類の歴史ありてより、かゝる民族必死の戦ひを知
らず
戦はんかな、戦はんかな
断じて、米英を許さじ
断じて許さざる決意を固めん
(前半を略)
山本五十六元帥戦死の報に接した「大いなるかばね」は以下(全行)である。
烈々のほむら一億の心奥にたぎりたち
撃滅撃滅
痛憤やみがたく
おもひ見よ
哀々たる慟哭にまなじりの決するを
参差たる故山のみどり深くして
けふの日は粛然たり
聯合艦隊司令長官
山本五十六大将
南溟の前線に作戦指導中
機上戦死の報ひとたび霹靂のごとく
我等がはらわたを震撼せり
噫 かへりみて提督の一死に如かざるものなきや
おもひ到り頭を垂れざるものあらんや
米英撃砕一途たゞにこれ有るのみ
いまぞ提督の大いなるかばねを越えて
堂々神州の艨艟は進撃せん
詩風・作風が戦争を媒体として「個人の自我の伸長である作品」から、「祖国の苦難に同調して、自分よりも国家を中軸とした作品」に衣装がえをしたという点では、高村光太郎や三好達治、さらには大木惇夫、佐藤春夫、西条八十、尾崎喜八など著名な詩人を数え上げると多い。
逸見猶吉は、暁星中学生の頃にアルチュール・ランボーを知り、「母音」(voyelles)を翻訳。チエホフ、メレジコフスキーなどもロシア語を学んで翻訳。早大に進んで昭和三年、二十三歳の時、牛込神楽坂で、バー・ユーレカを経営。「ユーレカ」はエドガー・アランーポーの長編詩論のタイトルである。この年の秋、北方指向の思い深まるままに北海道に出かけて、終生の代表作となる「ウルトラマリン」第一の「報告」を脱稿し、本名の大野四郎に変えて「逸見猶吉」を名のった。
早熟であることは、ランボーを克服しようと少年時代に既に意志したことに表われていよう。彼の学んだ中学校暁星が、フランス語を教えていることは今もそのままであるが、これが逸見猶吉という「特異なエスプリとスタイルはランボオを思はせる」(春山行夫)詩人の誕生となった要因として特記できよう。
だがしかし、である。満州の地で戦争に深く巻き込まれ、(若干数ではあるが、)戦争時局詩を書き、敗戦に直面した逸見のその後が痛ましい。殺到するソ連軍、内乱を孕んだ中国軍兵士、そして原住民の報復によって難民となり追われる日本人たち。逸見は、敗戦後『難民詩集』を企図したが、これを完成できずに昭和二十一年(一九四六)五月十七日早朝、長春南郊の自宅で死去した。肺結核、栄養失調のためで享年三十九歳だった。
侵略者支配者・日本人の立場から、逆転して逃亡する立場へ。故郷日本の土を踏むことなく、北満の荒野に斃れた詩人逸見猶吉。
私は、逸見が、最後に企画したが成らなかったという『難民詩集』が最も気にかかる。この幻の詩集のコンテンツこそ、「ウルトラマリン」連作によって日本のランボーとして畏怖された逸見猶吉の、詩的生涯を締めくくる最高傑作群が生み出されたであろうことを信じているからだ。
図式しておくと、若年にして激越な詩を書いて〈日本のランボー〉と指呼されたものの、戦争によって国粋詩を書き、そして「侵略者」から一転「難民」として短い生涯を果ててしまう。敗戦後に書かれ、流亡の後、ドサクサの間に湮滅してしまったと伝わる「難民詩編」の束こそ、疾風怒濤の戦難に遭遇した最も尖鋭な詩人が、魂をつかみ出して綴った極北の詩群であったろうと私は想像している。
逸見猶吉 明治四〇(1907)・九・九~昭和二一(1946)・五・一七。詩人。本名大野四郎。栃木県生。早稲田大政経学部卒。暁星中学時代から文学に親しみ、同人誌「蒼い沼」「二人」「VAK」などを創刊、伊藤信吉編『学校詩集』(昭4)に載せた連作『ウルトラマリン』で、新しい尖鋭的な表現が詩壇で注目された。草野心平・高橋新吉・中原中也らと創刊した「歴程」を主な舞台に詩を発表、昭和十二年日蘇通信社新京駐在員となり、満州文芸協会委員として活躍したが、肺結核、栄養失調の為当地で死去。菊地康雄編『定本逸見猶吉詩集』(昭41)がある。(稲井牧子) (明治書院・『日本現代文学大事典』)
檀一雄は、『青春放浪』(筑摩書房・一九五六年刊)において、満州の首都新京(現・長春)で逸見猶吉と邂逅した当時のことを描いている。
檀は、東大時代、西部新宿線中井駅の傍のワゴンという喫茶店でウイスキーを飲んだが、この店のマダムは萩原朔太郎の先夫人稲子、と聞いていた。ここで文芸評論家古谷綱武と会い、古谷の推挽で文壇に進出する糸口をつかむことになる。
この檀が、文学よりも好む「馬賊」にあこがれて満州に渡った。その地での放浪生活は数奇をきわめるが、この時期に、大学同期の友人で一足先に大陸の映画界に進出した坪井与(戦後、東映に入り幹部)に逸見を引き合わせられる。
逸見は、昭和十二年(一九三七・満州では康徳四年)一月、「日蘇通信」新京駐在員となり、二月、単身赴任した。同十四年六月、満州生活必需品会社に転じる。檀と逸見は、同十六年に同じ会社の同僚として勤めることとなった。その初対面のシーンを檀の『青春放浪』から引く。
それでも、私と坪井とビールを一、二本飲んで待っていと、
「ヤー」
と片手を挙げながら、奇ッ怪な騎士がやってきた。頭にトルコ人の達磨帽をかぶっている。身体にボウボウの毛バ立った シューバをまとっている。が、その達磨帽もジューバも、くたびれつくした羊羹色だ。たとえば、帝政ロシアの敗残兵が、満州で金に困り果ててソイツを売り、それを買い受けた満人がまた転々と着古したのを、やっと場末の屑物市から拾い出してきたようなアンバイだ。
雄大であった。蒼古の奇趣があった。
当の男は、浅黒く、沈痛なオモモチだ。唯今、中世の遍歴の騎士が、鎧カブトを身にまとって立ち現れたように見えた。
「こちらは檀一雄。こちらは逸見猶吉さん」
逸見の風貌は、早大時代からの文学仲間で、戦後に「肉体派文学」を宣言して一家を成した田村泰次郎のペンでも、その一半が鮮やかに描出されている。
「中野会」の会場で、私はひとりの色飽くまで浅黒く、精悍無類な風貌の、まわりから際だって毅然たる態度の男を見た。それが逸見猶吉だった。私たちはすぐに友だちになった。それまでに、私は「詩と詩論」などで、逸見の凄まじいばかりの荒涼凄絶な心象風景をうたいあげた、いくつかの詩を読んで、すっかり魅せられていた。現実に見る逸見と、詩から受ける逸見の印象とは、ぴったりとみごとに合致していた。作者と、その作品とが、これほどみごとに合致している場合は、まったく、稀なことにちがいない。
逸見は神楽坂で「ユレカ」という酒場をやっていたが、まもなく、それをやめて、東中野の駅に近い家の二階に下宿して、付近の萩原朔太郎の別れた夫人がやっていた喫茶店にかよったりしていた。うす暗い部屋には、古びた机のほかには、なにもなく、机の上に古びた鉄片が一枚、灰皿がわりにおいてあった。
「旅順の砲弾の破片だ」
最後に満州で客死する運命となる、彼の礦野への憧れは、すでにその頃から育まれていた。
(『わが文壇青春記』新潮社・昭和38)
右に続けて、昭和十一年の記述には、以下のようにある。
またある夜は、草野心平や逸見猶吉たちと、銀座裏の酒場で泥酔した。草野は蒼白な顔をした身体を垂直に床に立て、両腕を木製の模型人形のようにひろげたり、斜めにしたりして、「おれは、時計だ」とわめいて、いつまでもその運動をやめなかった。逸見がその草野に、黙って灰皿を投げつけた。帰りに円タクに乗り、和田倉門の堀端をとおりかかると、突如、闇から「とまれ!」という鋭い声とともに、キラリと銃剣が窓ガラスのそとで閃いた。車内で正体もなく、酔いつぶれている私たちを、兵士はじいっとにらんでいたが、しばらくすると、「行け」といった。
中央線が、ふたたび、東京駅まで走りはじめたのは、(二・二六)事件の日から何日目だったろうか。その最初の電車に、私は河野サクラ(元鹿地亘夫人)と一っしょに乗りこんでいた。河野サクラは、それまで、新橋の橋際にあった小さなスタンド酒場に勤めていたが、私は武田麟太郎につれられて、そこへ行き、彼女と知りあった。その身体つきには、どこか成長を途中でとめたようなところがあったが、少年のように清潔な感じの女であった。性質も、ほがらかで、よくロシアの民謡を口ずさんでいた。 (前掲書より)
金沢出身の詩人で室生犀星門下の棚木一良も新京時代の逸見の日常を記す。
私か新京の一条アパートに移ったのは昭和十二年の三月上旬で、もう彼は住んでおられ、草野心平からハガキで留守宅の状況を報告したものが来ていたのをみてオヤッと思って、会ったのが初まりで、大野四郎のペンネームが逸見猶吉と知ったわけでした。(中略)和田日出吉が兄貴で、あの人さわがせをした『人絹』についての弁護などをきかされた。一条アパートの生活も帰りが遅かったのは毎晩飲み歩いたのでしょう。
この棚木一良は、敗戦後引揚げて郷里の金沢で公務員として過ごしたが、戦後再建された「石川詩人会」の顧問的立場で、浜口国雄他、左翼的立場の詩人と伍して石川県の詩界に重きを成した。ちなみに和田日出吉はジャーナリスト、妻は女優木暮実千代。
先出、田村は、満州における「酒中生活」の逸見の様子を、こうも描いている。
私は十三年も満州を旅して、逸見に逢つたが、十四年も新京で逸見と逢ひ、いつしよに一夜を、ロシア女たちの家ですごした。彼は酔つて、階上階下とロシア女を追ひまわし、家じゆう長いこと騒然とさせながら、やがて静かになつた。
逸見は、馬賊に入婿希望の檀に、白系ロシア美人を勧めるが、檀はロシア語がチンプンカンプン。「帝国大学の威信未だ地に墜ちざる為に、当の大学は落第(注・実際は卒業した)し、今や、ロシア美人の好配偶の獲得の資格審査に於て、落第を宣せられた模様」という泣き言。
やがて檀はハルビンに移り、逸見とは別れ、それぞれの道を行く。檀は昭和十六年の十月帰国。太平洋戦争開始の十二月に高橋律子と見合いののち婚約。再び渡満。翌春帰国、律子と結婚。律子は檀の出世作となる『リツ子・その愛』『同・その死』のモデルである。檀は同十九年夏、陸軍報道班員として中国に渡り翌春帰国。リツ子は腸結核となり、九州福岡伊崎浦の実家で病臥。
ともかく、無頼・異能の作家檀一雄の出発時に邂逅した逸見猶吉だが、戦局が急変していく中で、その詩風も大きく移っていった。