
一年以上も楽しみにしてきた今シーズンメトの大目玉、極私的ですが、先日もドレスデン・アーメンで盛り上がって前夜祭的にわくわく感も募っていたパルジファル。
後から思えば、これは絶対的に素晴らしい音楽作品だし、それぞれ単独で出てきてもうれしい優秀な音楽家たちが揃いに揃ったのだから、当然といえば当然だったのでしょうけれど、今回のパルジファルは、これは近年のメトでもずば抜けて素晴らしいものを聴かせて貰った、今後「あれは凄かったね」と語り草になっていいレベルじゃなかったか、と思います。
以下、日本でもHD映画上演がある演目ですので、先入観を持ちたくない方はスキップしてください。またつらつら書きのこの記事、見に行くか見に行かないかの判断としては参考にはならない、というところ、どうぞご承知おきくださいませ。
Daniele Gatti ダニエレ・ガッティ 指揮
クンドリ: Katarina Dalayman カタリーナ・ダライマン
パルジファル: Jonas Kaufmann ヨナス・カウフマン
アンフォルタス: Peter Mattei ペーター・マッテイ
クリングゾル: Evgeny Nikitin エフゲニ・ニキチン
グルネマンツ: René Pape ルネ・パーぺ
ティトゥレル: Rúni Brattaberg ルーニ・ブラッタベルグ
声: Maria Zifchak マリア・ジフチャック
小姓: Jennifer Forni, Lauren McNeese, Andrew Stenson, Mario Chang
騎士: Mark Schowalter, Ryan Speedo Green
花の乙女たち: Kiera Duffy, Lei Xu, Irene Roberts, Haeran Hong, Katherine Whyte, Heather Johnson
François Girard フランソワ・ジラール 演出
[追記 3/19] あれからつらつら、たまに思い出して考えたりすると、ジラールの演出の一番の良い点は、「痛み」の共通点を「血」で象徴させて上手く描きだしていたこと、かも知れません。(白鳥、アンフォルタス、過去から今に至るまでの苦悩の血の川からの流れが陰濁にたまる地下のクリングゾルの館、ミサが「痛み」の血を皆で共有する、それぞれの信者が他者の痛みを自分の痛みのように感じるべき、ということを象徴化したようなリチュアルだったこと、等)
今回の聖杯・聖槍の儀式、イエスの苦難の「痛み」の意味を持たせると同時に、異性との性的交わりをシンボル化していた(槍は男性、杯は女性だった)のも、今回の解釈での救済とは、異性との交流が、「愛のないセックス=罪深い快楽」という次元に囚われになっている図式をやっと超えられた、ということだったのかも。愛を通じた男女の次世代を再生する尊い行為という意味を取り戻した、ということだったのかもしれません。
好き・嫌い、この作品の舞台化として同意するか・同意しないかにかかわらず、なかなか意味深い演出でございました。
兎に角ソリストたちが文句なしに素晴らしい。
パーぺのグルネマンツ、これだけ大げさになることなく、しっとりとした深みを感じさせてくれる人物像を歌いきるとは、これだけ権威や押さえ殺した悲しみや慈愛を表現してもらえるとは、凄い!です。シンプルなシャツとズボンに裸足で、特に大げさな演技もないのに落ち着いた父親的権威や愛情のようなものが微妙な仕方で滲み出てくるのは舞台表現者としても素晴らしいと思います。
出だしの紗がかかった奥の舞台上で同じ服装をした集団の中でも、なぜか、あ、あそこにいる、とすぐにパーぺは後姿だけで分かってしまったりすると、あぁわたしのメト鑑賞の年月=この人がいた、のだものなぁ、と自分でも可笑しかったですけれど。パーぺはメト育ちで毎年出てくるのが当然かと思ってましたが、来シーズンはメトの出演なしなのですよね、しかし世界中で引っ張りだこなんだから仕方ありません。さ来シーズン以降戻ってきてくれることを期待いたします。これだけ素晴らしいものを聴かせて貰ったのだから、一シーズンの不在くらい我慢できそうです。

マッテイのアンフォルタスはこれ以上なにを望めるか、というレベル。こんなにも苦しみがこちらの心が痛くなるまでしくしく伝わってくるアンフォルタス、豊かな歌唱表現はもとより、うなり声や微妙なため息や息継ぎの具合などでもその苦悩を表現していて、もう鳥肌が立つほどのパフォーマンス、凄いです。わたしはマッテイの甘い歌声には非常に弱いものですから、ついその魅力にうっとり心を奪われてしまい、意識していないとアンフォルタスとして鑑賞する視点をうっかり忘れてしまうのが難といっちゃあ難なのかもしれませんけれど。
昨日のラジオの幕間インタビューでは、今回のアンフォルタスは梅毒に罹っているので足に力が入らない、という設定だと監督に言われた、と言っていましたけれど、支え役の二人に全く遠慮せずに全力を掛けているように見える迫真の演技も凄かったのでした。

カウフマンは先シーズンの生煮えだったファウストとは歌唱も演技も大違いで、ほんとこんどは前回のような大勘違い演出家に当たらなくて、妙なことにならずに良かったことです。1月のリーダーアーベントでもいよいよ磨きがかかったような自然な柔らかな歌い上げを堪能させて貰いましたけれど、今や少々無理したような感じがする箇所は全くない、なんとも美しくもニュアンス・音色も多様な歌唱、いよいよ乗りに乗ってる時期なのだな、という印象です。
「だって知らなかったんだもん」から「なにこれ?」を経て「分かった」の道筋がしっかり伝わってくるのはさすがです。
特に2幕のアンフォルタスの苦しみを自らはっと悟って恐ろしくなってから、断固として駄目だ、や、今までぼんやり聞いて・見ても理解していなかったことの意味が見えてくる、クンドリにも同情を見せる、ところまでの経緯はお見事でした。あっち行け、ではあっても、Du weißt wo du mich wiederfinden kannst のニュアンスには、鬼でさえ心が溶けて涙を浮かべることでしょう。

ダライマンは初日のラジオの出だしでは喉の衰えも少々感じましたし、この日も少々高音が突出したかな、というところもありましたけれど、魔性の女的・母親的・娘的な強さやはかなさ、多様な女性の面を持つクンドリとして、温かみがあるダライマンの歌唱はなるほど、彼女で良かったのだな、でした。

二キチンは血を被ったり飲んだり、まぁ凄い登場の仕方ですけれど、初日のラジオの印象よりしっかりとした歌唱だったし、その声に若々しい風味がほのかにあるのと、今回の演出のせいで、クリングゾルの悲哀というか、男を捨てるという犠牲を払ってもその結果は不毛だった、という悲劇、クリングゾルも悲しい人なのだなと共感を持てるようだったのが非常によかった。
ガッティ・メトオケは出だしがちょっとばらついて、あのメロディの深遠な美しさを最初っから感じさせてくれなかったのは残念でしたけれど、気になったのはそこだけ。ガッティは、テンポコントロールも山や谷のつけかたもかなり大胆で、「わたしはこう思うのでこういうつくりにします」というのが聞こえてくるのが非常に刺激的というか。少なくともこの作品への愛情とか思いが熱く伝わってくるような感じがして、聴き手側も熱く盛り上がってきます。わたしは非常によいと思いました。パルジファルはモチーフが顔を覗かせる仕方も洗練されているし、リブレットもオケも意味深で、聞けば聞くほどなぞを生むような魅力がありますし、トリスタンやローエングリンやマイスタからの引用もあるんじゃないかという気がして、背後世界が無限に広がるような面白さがありますけれど、それぞれのモチーフを非常に大切に扱うガッティだと、その面白さが倍増するような。音楽が雄弁な作品は、こういう人が振ってくれると一層刺激的と感じます。しかし最初の幕間でガッティが暗譜で振っているのに気づいたときには、さすがにその気合の入れようの凄さに驚愕しました。

演出に関してはそれぞれのソリストが自由に表現できる余裕をたっぷり持たせてあるし、よくやった、そして背景の空のグラフィックス、人々の配置を含めて、どの瞬間を撮っても絵として非常に美しかったな、という印象です。ブーイングも結構飛んでましたけれど、兎にも角にも音楽と歌手が中心のシンプルな演出で、要所要所で音楽的にグワッと感動したい肝の箇所でそれを邪魔をするような性質のものでなかったことは、わたしは逆にブラボーを送りたいと思います。これがガッティじゃなくて控えめ大人しめの指揮者だとまた違う印象だったかもしれませんけれど。
パルジファルの演出というと割とワーグナー自身の指示通り正確にやっているんだろう旧バイロイト版、旧メト版で「他人の物語」として知っているような気になっていたのが、つい半年前に見たヘアハイム版、あの当時コメント欄でもお喋りしてましたけれど、あれにはわたしはかなり刺激を受けました。それまでさほど共感を持たなかったパルジファルくん、あの演出は、わたしにとっては、慣れ親しんだ世界の新たな意味に気付いたりするその成長過程を共に、うんその気持ち分かる、そしてまた真剣に考えながら一緒に辿っていけるようなものだった。人間の原罪はもとより、ドイツ人もそうか分かりませんけど日本人として自分が抱えている戦後いつまでも消えない第二の原罪、そこからいつか救済されるということはあるのか、なんてことにも波及して考えさせられる演出だったのでした。そういえばアモルファスにしろパルジファルにしろクンドリにしろそれぞれの第二の原罪を抱えているのかもしれないですね。「知らなかった」とか「当人が死ねば終わり」で済まされない、「これは物語じゃなくて、観客にとってもバイロイトにとっても自分たちが未だに抱える問題なのだ」としてパルジファルを語ってくれたヘアハイム版、あれはまだ一回さらっと見ただけですけれど、今回のメト版を見たら、あれももう一度見たいなぁ、と思ったのでした。ジラールの演出は「このお話」の現代における演出としてはなかなか良くできていた、でしたが、あそこまで自分のことのように感じる・考えさせられるような刺激はなかったです。
ワーグナーは子供の頃は恐らくキリスト教の教育を受けていたけれども、古今東西の神話や宗教、神秘主義に傾倒したり、「神は死んだ、俺らは強い意志で超人になるのだ」なんて言うお友達がいたり、ということもあるせいか、パルジファルでは既存のひとつの宗教に納まりきれない、かなり独自の宗教観を提示しているように見えます。ジラールはそういうことを踏まえ、意図的に特定の宗教味を消してジェネリックにしたんだと思いますけれど、わたしの目には北米系プロテスタントだか新興宗教臭があったり、またニューエイジ的な感じもしたりして、個人的には違和感があって好みではなかったですけれど、好き嫌いは別としても、よくここまでやった、という印象。
わたしSFは好きだったり、宇宙にはロマンを感じるけれど、宇宙のイメージに精神的に大いなるものはあまり感じない体質で、そういえば惑星だってユロフスキ&LPO版でこんな面白い面もあるのか、ということに気づくまでは「わくせえ、だせえ」(すいませんオヤジギャグです)なんて思ってたりしたんでした。
なので「こいつがあの預言のおばかさんかも!」という場面で、うわっと巨大な星が出てきたときなんかはつい「2001年宇宙の旅?それとも未知との遭遇かい!」と心の中でプッと吹いちゃったり、儀式のハンドサインなんかも、うへぇこれは随分トレッキーだかトレッキアンに受けそうだわ、などとニヤついたりもしてましたが。
あと3幕で、話ばかりでなかなか救いがやってこないので、信徒たちのやる気がなくなって、この宗教セクトのリーダー格であるグルネマンツからも心が離れている、という状況の表現の一環で、あたかも「あ、あれは救済のしるしでは」というように一斉に信徒たちが何かに注目して「なーんだ、また違った」とがっかりするような演技がありましたか、あれも少々ノストラダムスとかOXの予言とかが外れてがっかりしてるような感じで、オカルト臭さがあったかなぁ。ヘアハイムの演出は、個人的には、ああいうのを本来的意味で現代人にピンと来る演出と言うのだ、と思いましたけれど、最近も12月21日に世界が終わる、なんて話が大流行していたし、現代社会ではジラールのこういうスター・トレック調・ニューエイジ調が宗教観としてしっくりくるという人が多くいるのかもなぁ、と納得はできるような気はします。

しかしまぁ、上着や靴を脱いで白いシャツになって求道する、とか、ハンドサインなどの宗教上のしきたり等もその意味が分かりやすい上に一貫性があって、よく練ってあることは確かです。クリングゾルの服装も、あれはもともとは他の騎士たちと同じ白いシャツにスーツだったのが長い間血の川に浸って赤いシャツになってしまったのだ、ということだったんでしょうかね。なかなか考えてあります。
血と言えば、当初話しとして血が舞台を流れる設定だと聞いたときは、十字軍とか人間の歴史上でが宗教や正義の名の元に無駄に流してきた血を表現しているのかと思ってましたけれど、ジラールの血の意味はそういうことじゃないイエスから始まる「犠牲」やアンフォルタスに代表される「痛み・苦しみ」の意味なんでしょうかね。
そして苦悩の血の小川がパカッっと裂けた地下にあるような感じのクリングゾルの館、プロダクション写真が出てきた時には、血に染まった白いドレスやベッドなどは気持ち悪いなぁ、そしてどうしてもああいう絵だと生理とか流産とかを連想してしまって、あれはセックスはするけど不毛の女クンドリということなのかしらん、だけど生々しくてちょっと嫌だな、と思っていました。
実際は危惧したよりも生理的不快感はなかったです。ただ血の池に突っ立っているフラワーメイデンたち、後ろを向いてるのかと思ったら、日本のホラー映画で井戸から出てくる子と同じようにあれは長い黒髪を前に垂らしてたんで、一斉に首を上げてばしっと髪を後ろに投げて、あれは正面を向いていたんだと分かった時は、ギャ(怖)だったし、また一斉にサワッと水音をさせて血の中に跪いたりするのは、気色良いとは言えないです。確かあの貞子というのも特殊能力のせいで井戸に閉じ込められて永遠に大人の女性になれないまま不思議な次元の世界に存在し続けているのではなかったか、そこら辺の哀しみは、この幻の次元だけに存在し、クリングゾルの城崩壊と共にはかなく滅びていく美しいフラワーメイデンと共通するのだ、ということだったのでしょうかね。そういうことならジラールのまなざしにも、パルジファル並みに人の痛みや哀しみへの深い同情があったかもしれません。

ジラールの演出はかなりよくできてるけど、個人的に手放しでは好みとは言えないな、というのは、ニューエイジ調もありますが、それよりも二点目として大きいのは、なんとなく底辺に「性」の要素がかなり強く感じられるせいだったかも。
そんな見方をした人がいるか分かりませんが、最初の聖杯の儀式でアモルファスが聖杯に指を入れるやり方を見てて、わたしはパッと「破瓜」?というコンセプトが頭に浮かんでしまい、それで指についた血を、額に十字を切るのと同じような仕方で騎士団に授けるような儀式が、かなり気色悪く感じました。あんなのやだ、気持ち悪い、という印象があるのは、あの儀式に感じ入ることなく違和感を覚えて躊躇するパルジファルに共感を持ちやすくなるので、演出効果の狙い通りなのでしょうけど。同じ儀式の場面、確かヘアハイムは使徒のそしてカソリック教会の根底にある自己偽善・欺瞞を描いていて、強烈なショック効果がありましたけれど、ヘアハイムのが思考を刺激する意味的なショックだったのに対して、ジラールのは生理的に気持ち悪いというショックだったような。
聖杯に指を入れる儀式は、3幕で今度は徳を得たパルジファルが指でなく聖槍を使ってその儀式をするので分かるのですけれど、イエスの血を受けた杯にふたたびその血を流させた槍を浸すことで「イエスの犠牲の場を再現する」という意味があるのでしょうかね。カソリックの「(パンは私の肉、ワインは私の血)このようにしてわたしを覚えていなさい」と毎回(伝統的には聖金曜以外の)ミサでまざまざと使徒がイエスのことを思い起すしきたりと同じことなんだと察しましたが。まぁ16世紀日本でも話しとしてミサの段取りを聞いた人々が「キリシタンは嬰児の肉を食らって血をすする」と気味悪がったらしいですけれど、わたしがこのジラールが描いた儀式が気持ち悪いと感じたのも、それと同じなのかな、あちこちに性的なほのめかしを感じたのは気のせいなのかな、ちょっと分かりかねます。

ただ先の2幕の不毛な女の哀しみもそうだったですけれど、不毛の荒野で救済の奇跡を求める人々、1幕では男女は水や血の流れる小川を境に隔たれていて、やっと3幕でパルジファルが戻ってきてアンフォルタスが救われると、その隔たりが無くなって男女が交じり合うのですけれど、あれにはやはり性的というかフェミニズム的な意味があるんじゃないか、女性と交流するのが邪悪なことでなくなったと言っているのかもとは感じました。貞節にこだわって女性をサークルに入れなかったのが、パルジファルの魔の城の粛清によってそういう妙な呪いが解けた、「アノニマスな別性」の有象無象の群集じゃなくて、それぞれ違う行動を始めた女性たちはやっと個人として生きることができるようになった、男性はセックスも含めて女性とちゃんと向き合って共に前に歩けるようになった、とかいう解釈だったのか・・・ あれがパルジファルがもたらした救いのひとつとして男女混合・平等社会があったのだ、と言っているのだとしたら、へぇそんなもんなの、とわたしはそこには格別共感を覚えるということはありませんけど。
しかしまさかあの救いはパルジファルは梅毒菌を駆除してくれてめでたしめでたしだったのです、というような単純なことじゃあないことを望みます。どちらにしても個人的にはパルジファルは確かに色々解釈のしようがあるなぁ、こういうのもありなのかもなぁ、でした。
それにしてもテンペストでデビューしつつも、なかなかいい公演に当たらないのですっかり忘れていたメトの「出まち」システム、興奮さめやらないこの日の公演後は、そうだ、もうひと目見れるんだった!と思い出しましたよ。現地ではMadokakipさまやMadokakipさまのところでお知り合いになった方、そしてもう一人お着物でいらした方にもお会いできて、楽しかったのでした。ジラールはおしゃれなおじさんですぐにタバコを咥えたのがおもしろい。一見怖い二キチンはかなりナイスな青年なのだわ。しかしカウフマン、パーぺ、マッティがほぼ同時に現れると、まぁ非常にホットな3人の音楽家たちがこんな人口密度高い感じでひとかたまりでそこにいるという図、はやはり凄い。どうにもぼーっとしてしまいました。
★★★★★










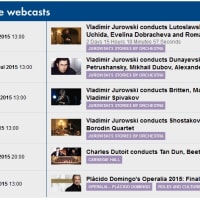

![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7e/75/86269acbcad34761132575feb03d125f.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/79/07/0c1611b6ea026eed0a0b094175423d2c.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/03/7b/050b793778320ffdd0ee65e474b84a24.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0b/1f/86664af8b7c7633697df5b104d2e7724.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/66/e2/b84c41a2579268d55f363286f23b1002.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/18/08/c4d0391455c0920b0ec523a41cd3d726.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/52/23/d9c577dfb8141fea8bd128d6023cd6cd.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/36/7b199e47cf9aaa3c0353f6d09f978e83.jpg)
Pape 様、Kaufmann、Nikitinそれぞれ自分のロールを研究しそれを表現していて素晴らしいと思いましたが、やはり一番耳をひかれたのはMatteiのAmfortas。 元々美しい声の人ですが、苦しい息遣いなど含めてなりきり表現に、ぞくぞくしました。 私の場合はマイクで拾っているものなので全て聞けたということもあるでしょうが、METの会場にいらしても、それが伝わったのですね。 昨年のシーズン発表で彼がAmfortasに配役されていると知った時は、あれっと思いましたが、ここまでドンピシャときたのには驚きでした。
ところでKaufmannは表現の手段として、かなりsotto voceを使っていたように思いますが、会場ではどのようにきこえていたのかしら?
>演出に関しては
>兎にも角にも音楽と歌手が中心のシンプルな演出
これって、とても大切だと思います。 でも、Mattei=Amfortasはかなり無理な態勢で歌っていたとききましたが、どうだったのでしょうか?
今回私は音だけが頼り、かつドイツ語が全くわからないのに対訳を見ずに鑑賞していたので、舞台上のシンボル(?)や、演出とリブレットとのかい離(があったとしても)は、気にせずにすみました。 これも、素直に感動できた理由かもしれません。 昨年のバイロイトの Herheim版や、二期会のGuth版は全くの読み替えで、それなりに考えさせられる所はあったのですが、この2つのプロダクションは、もともとあったキリスト教的要素をブラックに表現するか、全く削除していたように思います。 実は、知り合いのオペラ好きイタリア系アメリカ人女性が、METで鑑賞した感想を6ページくらいのレポにしてを送ってきてくれたのですが、彼女はこの点を含めて今回の演出が全く納得いかず憤慨していて、歌手はこんなにすばらしかったのにとありました。 私も最近、演出に憤慨したことがあったので、彼女の気持ちもわからないわけではありません。 ただし、ちょっと外野的に俯瞰してみると、読み替えや新しい演出を受け入れられるかどうかのポイントは、所詮観客の主観に左右されてしまう。 一方、最近の何でも説明したがる演出家は、多分ティーネージャーまで含めたオペラ初心者を意識して、無理やり分かりやすいストーリー展開にしているような気配もあるので、ハリウッド的になるのも当然の帰結かもしれません。 今回の作品は、このブロックバスター的な部分は、貞子ちっくなフラワーメーデンだけかしら? 私の個人的な感覚としては、その作品の骨幹となる部分が残っているかどうかが大切。 その意味では、もともと複雑で解釈のしかたが何通りもなりえる、ある意味オープンなWagner作品って、料理のしがいがあるのかもしれません。
そういえば、一時期METでは、Good FridayにParsifalを上演していましたよね? シーズンに一回ぽっきりの公演もあったかと。 一度、Good FridayにBouleyで豪華ランチを食べた後、トライベッカからタクシーをとばして、METでParsifalを鑑賞したことがあります。 初めてのParsifalだったのですが、季節がらもあって、なんとなくRedemptionとかに思いを馳せたものでした。
> 一番耳をひかれたのはMatteiのAmfortas
> 苦しい息遣いなど含めてなりきり表現
> 私の場合はマイクで拾っているものなので全て聞けた
Kew Gardensさま、ほんと素晴らしかったです。この4人、そしてガッティ!、ほんと今までも程度の差はあれ優秀と思ってましたけど、今までの何倍も凄いと思えるような素晴らしいパフォーマンスだったです。
そうか、マッティの唸りや苦しい息遣いの表現、ハウス内でもびしびし聞こえてくるくらいですから、ラジオで聴くともっと凄かったかもしれませんね。BBCはうふふ、偉いぞ、まだ聴けるのですね、わたしも「あの感動を再び」で聴いてみようと思います。
カウフマンは普段のモードがメゾピアノ~メゾフォルテ弱ぐらいだったかな、非常に自然な無理しない感じが、色んなことの意味を学んでいく最初は素朴な青年として、わたしはしっくりきて、そしてまたその対比として、パルジファルが、あっそうなのか!と思うところとか感情が盛り上がるところでのフォルテが非常に生きてくるので、わたしは凄くいい解釈だと思いました。そしてほんと微妙なソットヴォーチェの表現、自分の名前を知る場面とか、クンドリにYou know where to find meなんていうところとか、3幕の神妙な感じなどは特にわたしはかなりジンときました。仰るとおり、自分のロールを研究しそれを自分らしく表現していたなぁ、とわたしは思いました。
ただメトはかなり歌手フレンドリーな音響なのですが、舞台は真ん中から後ろの響きが悪いので、2幕の地の池では早く前の方に来てよ、とは思いましたが。
>> 演出に関して
> 知り合いのオペラ好きイタリア系アメリカ人女性が、METで鑑賞した感想を6ページくらいのレポにしてを送ってきてくれた
> 舞台上のシンボル(?)や、演出とリブレットとのかい離(があったとしても)
> 素直に感動できた
パルジファルはとにかく色んな要素があって結論づけも簡単に行かないし、さらっと感想文は書けないなぁ、です。わたし自身、今週末のユロフスキがあるので後が詰まってるという状況じゃなかったら、もうもっともっと言いたいことが沢山あるものですから、延々感想文をひきのばしてたことだと思います。
演出に関しては、なるほどこの人はあらすじだけで演出してるおばかではないな、自分の中で独自に消化して出してきたんだな、というのが感じられるのと、無理やり「俺の読みはこうだ」と、歌手たちが納得できないような妙な演技の動きや舞台上で独自のドラマを展開、とかいうことで音楽のニュアンスを邪魔するようなことがなかったせいで、ドラマの要所要所のツボが味わえた、の二点で、わたしは悪くないと思いました。わたし自身は演出や美術に苦笑いする点があっても、ある意味それは頭の端に置いといて、「セミステージング」的に音楽家たちが繰り広げるドラマを堪能できるものであったのがとても良かったです。
ただわたしはワーグナーは好きですけれどワグネリアンではないので、確かに「先生の指示と違う」と憤慨する方々がいらっしゃるのも分かります。一番違和感があったのは3幕でなんとクンドリが聖杯を掲げて儀式に参加するところかな、あれはジラールの今回の演出の世界では、杯は女性で槍は男性でなければならない理由があったからだ、とわたしは理解してましたけど。あと緑や生きた自然が全くなかったのだわ。
> 読み替えや新しい演出を受け入れられるかどうかのポイントは、所詮観客の主観に左右されてしまう
仰るとおり。読み替えものは同じものを見ても観客によっては全く違う理解がありえますし、また監督が意図していたことと実際に見えるものが違うということもありますよね。いつもながらわたし自身は勝手に「自分にはこう見えた」のをしゃあしゃあと書いちゃいましたけど。メトの最近の演出にはもう疲れていて、今回は事前に談話等を読んだりしていないので、これからになりますけれど、ジラールが実際どういう意図でやっていたかを知るのは楽しみです。
> ティーネージャーまで含めたオペラ初心者を意識して、無理やり分かりやすいストーリー展開にしているような気配もあるので、ハリウッド的になるのも当然の帰結
> ブロックバスター的な部分は、貞子ちっくなフラワーメーデンだけかしら?
このイメージ、たしかなんかの映画で見たなぁという演出、増えましたね。世界・世代共通言語的なハリウッド風記号としては、リングの貞子と(あらそういえばあれもリングだわ、奇遇というかオヤジギャク風というか・・・)、もうひとつは背後の壮大スペクタクルSF風な惑星の映像だったかしら。ワグネリアンかつトレッキアン、なんていう人にはツボに入る演出かもしれません。
> Mattei=Amfortasはかなり無理な態勢で歌っていたとききました
Madokakipさまが、以前の公演ではマッテイは自分の手で足を掴まされていた、と仰っていて、そんな胸を縮めるようなことは歌唱に影響しないのか、とわたしも聞いてびっくりしました。この日は二人のお付きの肩を台にして腕にかなり力を入れていたりと腹筋にいつもと違うリキが掛かっていたかもしれませんが、恐らく体勢の無理度は抑えられていたのかもしれませんね。それでも全力でお父さんの墓に這って行くとか凄い熱演でした。
> 唯一不満があるとしたら、オケの音がまだなっているのに拍手がわきあがる
ほんと酷いですよね。メトだけじゃなく、わたしは心中ではこっそり「わざわざお金と時間をかけて音楽作品を聴こうという目的で来てる筈の観客なのになんと失敬な」とあきれることはほんとしょっちゅう。これはもう慣れるしかないのだ、と自分に言い聞かせていますが、ほんといちいちがっくりきます。チャイコフスキとかベートーヴェンとかうわっと盛り上がって爆発的に終わるような作品ならともかく、それまで普通に注意を払って聴いていたら少なくともふっとため息がでてから拍手というのがノーマルな人間として自然なような気がする作品でもあれをやる人々は、ほんと音楽的に文盲という以上に、どこか配線の具合がおかしいのではないかと思います。
そして恒例の携帯ですけど、今回も何度かあって、酷かったのが、ちょうどグルネマンツとパルジファルの最初の会話の部分、簡単な、名前は?、分かんない・・・などの会話ですけれど、「考えたことはなかったけど自分は一体どういう人間なんだろう」というある意味哲学的問いがパルジファルの中で生まれる微妙な箇所(ここのカウフマンの微妙にはっとして考えているように読み取れるような演技の表情、非常に良かったです)、あそこのかなり繊細な「間」のところで、ピコピコ携帯を鳴らしたりとか、もうほんといい加減にして欲しいもんです。
> 一時期METでは、Good FridayにParsifalを上演していました
> 一度、Good FridayにBouleyで豪華ランチを食べた後、トライベッカからタクシーをとばして、METでParsifalを鑑賞したこと
> 季節がらもあって、なんとなくRedemptionとかに思いを馳せた
それはそれはあらゆる次元で素晴らしく印象に残る聖金曜だったのでありましょう!
パルジファルは四旬節に合わせるというのが恒例なのですかね。わたし自身はお肉も音楽も好きなので聖金曜でなくとも四旬節中の金曜には両方ともちょっと控えるべきかな、なんて弱気になってしまいますが、確かにタイムリーというか、罪、贖罪、犠牲、禁欲、奇跡等々、色々考えさせられますね。ジラールのようにジェネリックな超自然・神秘主義アプローチでもいいのですが、ワーグナー独自で本来的でない要素が種々含まれているとはいえ、やはり他者の痛みに対する深い同情・愛の力による癒しというところは、キリスト教的要素抜きではその深い背後の意味は十分に語れないところもあるかと思います。
歌手で驚いたのは、私もマッティ。「美しく」そして心に迫ってくるようにアンフォルタスの痛みを、あれほど歌い出すとは想像していませんでした。パーペのグルネマンツは、録音や演奏会を通して知っていましたので、期待通りの充実したもの。やっと聴けたカウフマンは、抑えた歌唱と演技が、あの役ではとても効果的に働いていて、その美しい容姿と相まって、実に見事なタイトルロールでしたね。
舞台は陰陽勾玉巴のように男女が配置され、「性」が演出上での大きな要素になっていると思いました。NYに出かける前に、galahadさんから、今回のメトの「パルシファル」は「荒地」のような舞台らしいと言われていたのですが、「荒地」とはもちろん、T.S.エリオットの書いた20世紀を代表する詩のこと。彼は、この詩で第一次世界大戦後の荒廃した状況から抜け出す道を、聖杯の伝説などの枠組みを使いながら探ったわけで、そしてその聖杯の物語が、キリスト教以前の豊穣祭祀とも密接な関係があり、セクシュアルな意味合いを強く帯びていたはずなどと、頭のなかで、ずっと思いめぐらしながら、舞台を眺めていました。一幕の終わり、拍手をしようとした隣に座っていた大学生のウチのドラを制し、この舞台作品における拍手のこと、この劇場と作品との関係などを、したり顔に講釈したのでした。
> 第一次世界大戦後の荒廃した状況から抜け出す道を、聖杯の伝説などの枠組みを使いながら探った
うわぁ、そうか! 名古屋のおやじさま、さすが凄い!です。
そうだ、そうですね、ほんとだ、「荒地」なのだわ。
思わず百年ぶりにざっと読みかえしてしまいましたよ(無料でキンドルにダウンロード、ふふ、便利な世の中です)。
ほんと、三幕の舞台設定、乾ききった地に水がない世界はWhat the Thunder Saidそっくりですね。そして娼婦の館や堕胎、水・川のイメージや、時空を超えてギリシャ神話やヒンズー教、仏教的対話、そしてフィシャー・キング的な暗示もありますものね、なるほどジラールがこの作品とエリオットの世界と重ねた心は理解できます。そうかぁ、ちょっとまたもう一度考え込んでしまいます(というパターンがパルジファルの場合、派生して永遠に続くような、ふふ)
> 一幕の終わり、拍手をしようとした隣に座っていた大学生のウチのドラを制し
> この劇場と作品との関係など
いいエピソードですねぇ、確かにそうですよね。メトで他の人が一幕後に拍手したからってつられて拍手することはないんです。経緯を知った上で、拍手するのがふさわしいか、しないのがふさわしいかは自分で考えましょう、なのでした。
そういえば話は飛んで、バイロイトじゃなくてメトとのこの作品の関係も面白いものなのですね。つい先日知りました。ワーグナー家はバイロイト外での上演は禁止してたのに、メトは著作協定圏外だったので、悪い言い方をすると「くすねて」1903年に初演したとか。その公演に参加した音楽家たちはバイロイトはもちろん欧州のハウスでもしばらく干されてた、なんて話があったようですね。20世紀初頭のNYの音楽シーンはなかなか面白い逸話が溢れています。
> ガッティのスローテンポに少々辛い思い
うふふ、そのお気持ちも分かります。思いをじっくり込めるところはほんとに笑っちゃうほどじっくりやってましたよね。でもガッティの場合、あの大胆にも思えるテンポ・強弱コントロールなども、たとえ自分の思っていたのと違っていても、なぜそうするのかというのがなるほど、と納得できるものがあるように思えるというか、ガッティはこう考えているのでないかな、と色々想像できたので、とても面白かったです。
皆様の雄弁なパルジファル評を伺って感心しています。特にKinox様は深く読み取っていらっしゃるようなので、何も新しいことを言えるわけがありません。
兎に角メトの公演と、フィラでHDを見てそのあとDVDをいただいて、大変に感激いたしました。特に期待を大きく上回って驚かせたのはアンフォルタスのペーター・マッテイでした。これはみんな批評家たちも同じことを言っていますよね。声の美しさもさりながら、 今まで見たこともないほど全面的に信じられるアンフォルタスでした。彼の体が大きく背が高いので、外見的にも彼の肉体的精神的な苦しみが 倍加されているように見えました。手で動かない脚や腿をつかんで立たせているのを見て、私はあっと思いました。これはそんな経験のある人にしかできないのじゃないかしらと思って。
このたびの上演は全く清潔で見終わった後さわやかな感動がありましたが、それだけでなく、深く考えざるを得ませんでした。
ジラール氏が「これは単なるオペラじゃなくてミッションである」というようなことを言っていましたが、たしかにこのキャスト全体が深い使命感を持って舞台にのぞんだのではないか、という印象を持ちました。
初めに全員がスーツの上着を脱いで白シャツ姿になり、靴を脱ぎ、時計など生活合理化の器具は全部捨てて円座についた後、グルネマンツの指揮下に祈るのも、祭壇があるわけではなし、何一つ宗教的な道具も装飾品も建物も窓もないひび割れた土地で一斉に肩を丸め頭を下げ、又頭を上げて、中東的な感じで祈っているのが非常に印象的でした。
真っ白で簡単なシャツが、パルジファルという主人公の無知だけれども清潔無邪気な状態を象徴しているようでした。
人間は、生きて経験や知識を積み重ねるにつれて汚れてぼろぼろになっていきます。三幕でモンセルバートの騎士たちがぼろぼろになっていたのも,パルジファルがよれよれになって疲れ果ててやっとアンフォルタスのいる場所をさがしあてたのも、そんな人間の一生の進路を示しているようです。
そのなかでパルジファルの彷徨による汚れは本質的な汚れではないことが、彼が死にものぐるいで守った聖槍によって象徴されています。
もう皆さんがいろんな立派なことを指摘していらっしゃるのに全く同感なので, 繰り返しはやめて思ったことをすこしだけ。
批評家たちの多くが第二幕の背景の岩の割れ目は アンフォルタスの傷口だと解釈しているようですね。たしかにクリンゾルはその傷口の中で、そこにいる女たちを全部支配して,アンフォルタスの苦しみが永遠に続くように血を補充し続けていたのでしょう。
あの花の乙女たちは普通の演出と全く違った乙女たちでしたが、それはそれで厳しさと正しさがありました。長い黒髪をたらして鋭い槍を目の前にたてている所は整然として美しくさえありました。私は中世の比叡山などの僧兵という、とんでもないことを考えました。女の僧兵が白い衣で長槍を持って整然と構えている。ジラールさんはワグナーの仏教に対する興味と勉強のことを言っていましたが、まさか彼は女の僧兵など考えはしなかったでしょう、第一仏教にもそんなものは存在しなかったのですから。
けれども全員に長い黒髪を垂らさせたのは実に傑作だと思いました。Kinox様もあの髪がさっと翻される見事さを指摘していらっしゃいましたが、私はあの動作に驚きました。たしかに東洋人が二人ほど歌い、バレーにも日本人か中国人がいたと思いますが、みんな東洋人に見えませんでしたか?髪の毛を統一しただけであんな効果が生まれたのだとびっくりしました。あの様式化された、角立った動きは従来の花の乙女たちと全然違いますが、私はかえって気に入りました。
乙女たちがパステルカラーの衣裳でべたべたパルシファルにくっつく演出は鼻につきます。バイロイトの看護婦姿の女たちもうるさいものです。
彼女たちがパルシファルのシャツをはぎ取ってしまったのは気に入りませんでしたが, 彼はクンドリイの出場でそっとシャツをつけたので安心しました。
カタリナ・ダライマンのクンドリイは母性的すぎましたが、納得はいきました。明らかに年寄り過ぎ、美人でもない彼女が魅惑に満ちた美女の誘惑に成功しそうにはとても見えないので、彼女を従来よりももっと母性的にすることに決めたのかも知れません。これは、ダライマン女史自身の決断かも知れません。彼女もよく歌いました。
私にとても興味があったのは十二月にミラノでローエングリンをすごく上手に演じたカウフマンが、今度はその父親のパルシファルを演じたことです。 グート氏はローエングリンを父親のパルジファルによく似た、純真な、世間知らずな人間に仕立て上げました。パルジファルの方はもうワグナー自身の指示で純粋無垢な愚か者で始まるのが通例となっていますが、ラスカラのローエングリンは愚か者ではないけれど純粋無垢で環境に適応できない人間として演出されてそれは大変成功したようです。
だからカウフマンはパルジファルを息子にちょっと似た人物に仕立て上げることも出来たのに、全く違った方法で演じました。動作を最小にとどめ、ばかな猿芝居は全くさけて、ただ不思議に思いながら周囲の人物を観察する若い男です。そうして第一幕では白鳥を眺めて少し動かされたようですが、『同情による知識』を得た様子は全く見せず、 ただ最後に,深まって広くなって血のながれる溝をじっとのぞきこんでいるだけでした。
彼が自然な、しかもうまみのある表情を見せるのがHDでよく見えて清潔なパルジファルが信じられました。『ニューヨーカー』の一人の批評家が「カウフマンが主役をがっかりするほど不明瞭に演じた」(disappointingly indistinct account of the title role)
と書いたので、何をこのバカ、何も分かっちゃいないんだと思いました。
パペのグルネマンツ,素敵でした。特に慈愛深い、奥深いグルネマンツを、大好きなパペが演じてくれて私は大満足。4人の主演以外の歌手たち、クリンゾルのYevgeny Nikitin、ティトゥレルのRuni Brattaberg,従者たち、みんな満足しました。合唱もあの150人からの合唱団をDonald Palumbo氏はよく統一して,全曲にとてもよい雰囲気を流しました。
指揮のダニエレ・ガッティ氏はテンポで少し批判されていましたが、たしかに彼は他の指揮者が変化をつける所を同じテンポでゆっくり演奏していたようですね。それから序奏と聖金曜日の音楽は、私はいつも魂を洗われるような思いをするのを期待しているのですが、それが起こりませんでした。かえって他の部分で美しいと感じることが多かったのです。これは全く個人の主観です。
もうひとつ難を言えば、始めから終わりまで少し暗すぎました。背景のプロジェクションはまことに劇的で、Kinox さまがおっしゃったように、どの一コマをとっても絵になりましたが、私は凡人だから聖金曜日はやはりもう少し青空が見えて緑も見えて欲しかったのです。
けれども、歌唱演技演出すべて、私もこの『パルジファル』は「語り草」に残る公演だと思います。
マッテイは、何やらせても毎回毎回素晴らしい歌手、とは思いつつも、事前にはマッテイとワーグナーってちょっと合うかどうか分からなかったのですが、全くの杞憂、ほんと、歌唱表現も演技も素晴らしかったですよね。わたしが見に行った日はHD放送日だったので、ちょっと演技が変わったのかもしれません。そうですか、手で足をつかんで立ったりなども以前の公演ではあったのですね・・・
パーぺもいつもながらさすが、ほんとここまで歌唱だけでなく解釈も素晴らしい歌手陣で聴けるとは幸せなことです。
> ジラール氏が「これは単なるオペラじゃなくてミッションである」
はぁ、これは感じいるものがあります。やはりそういう姿勢・気迫は舞台から伝わってきて、演出内容に同意するしないはともかく、よく自分なりに練ったな、自分なりに最大限のものを出してくれたんだな、という演出でした。
ジラール氏の力量もそこにはあるかもしれませんけれど、今回、この素晴らしい作品を自分たちができる限りの最高の形で聴かせようというミッションを持つ音楽家たちのシナジー、素晴らしかったです。
> 人間は、生きて経験や知識を積み重ねるにつれて汚れてぼろぼろになっていきます
> 三幕でモンセルバートの騎士たちがぼろぼろになっていたのも,
> パルジファ ルがよれよれになって疲れ果ててやっとアンフォルタスのいる場所をさがしあてたのも、
> そんな人間の一生の進路を示しているようです。
> そのなかでパルジファルの彷徨による汚れは本質的な汚れではないことが、彼が死にものぐるいで守った聖槍によって象徴
非常に含蓄のある慧眼なご指摘ですよ。わたしはこのご指摘自体にじんと感動してます。それを咀嚼してまたパルジファル思索しようと思います。
> カウフマン
> 自然な、しかもうまみのある表情を見せる
> 動作を最小にとどめ、ばかな猿芝居は全くさけて、ただ不思議に思いながら周囲の人物を観察する若い男
わたしも今回の人物描写、非常によかったと思います。そうなんですよね、一幕では「へぇ」と素朴に、だけどしっかり一つ一つのことを観察している少年。その心には、勝手にこうだと決め付けるような偏見・先入観はありませんし、そして自分だけがいいことしようとか自分だけが救われればいいや、というような欲もないんです。今回のカウフマンのパルジファルの成長段階の歌唱および演技の表現、わたしはあれは素晴らしいと思いました。
> 指揮のダニエレ・ガッティ氏はテンポで少し批判
ガッティがわたしは良かった、と思った点は、一つ一つのライトモチーフを非常に丁寧に扱っていて、そしてそれを通じてガッティが語るストーリーが伝わってくることでした。
たとえば一幕の終わり、パルジファルがてくてく歩きながら、あぁグルネマンツはあんな事を言っていたなぁ、とかアモルファスは苦しそうだったなぁ、とかあの儀式はなんだったんだろう、なんてことをぼんやり思い返している、という様子が、まるで目に見えるように音楽で語らせてました。
この人はわたしは多くは聴いたことはないですけれど、大抵、あぁこういうことを伝えようという意図がちゃんとあってやっているのだな、以前は気がつかなかったけれど、そうか作曲家はそう思ってこのメロディをここに持ってきた、とガッティは言っているのだな、というのが聴こえてくるのが良いです。わたしが大胆、と言ったのは、「大抵過去の巨匠はここでこうやってたはず」通りでなく、しかもたまにわたし自身もちょっと違うかな、な部分があったとしても、ガッティはわたしはこうだと思うのでこうやる、という頑固な、しかしその音楽のつくりを通じで非常に雄弁なところがあって、あれは聴いてて面白いです。
> 『ニューヨーカー』の一人の批評家
> 何をこのバカ、何も分かっちゃいないんだと思いました
あはは、お気持ちわかります。先日のユロフスキの評のいくつかは、わたしも全くそれと同じ反応をしてましたから。まぁ音楽的に文盲、かつ作品自体の理解がないにも、そしてロバの耳にもほどがある、と、ぷんぷん憤慨するやらあんまりあきれて大笑いするやら、でございました。
> みんな東洋人に見えませんでしたか?髪の毛を統一しただけであんな効果が生まれたのだとびっくり
ほんとにそうでしたね。そして「比叡山などの女の僧兵が白い衣で長槍を持って整然と構えている」というのはわたしも分かるような気がします。どこか筋が通ったいさぎのよさがありましたよね。
映画オーディション組みのキーラ・ダフィーもflower maidenの一人としてデビューだったのでした。注記し忘れてました・・・
「3幕でパルジファルが戻ってきてアンフォルタスが救われると、その隔たりが無くなって男女が交じり合う」
「女性と交流するのが邪悪なことでなくなったと言っている」
「貞節にこだわって女性をサークルに入れな かったのが、パルジファルの魔の城の粛清によってそういう妙な呪いが解けた」、
「アノニマスな別性」の有象無象の群集じゃなくて、それぞれ違う行動を始めた 女性たちはやっと個人として生きることができるようになった、男性はセックスも含めて女性とちゃんと向き合って共に前に歩けるようになった」
こういう解析には全く同感。三幕でまずクンドリイが救済されて溝を越えて男性領土(男性はどちらにでも行けたのですけれど)に入っていて、最後の場面で女性がみんなこちら側に来て男性もあちらへ行って男女の組が出来ているのを見て、ほんとにそういう解釈なのだなあと感動しました。これでこのパルジファルの演出はほんとに現代的だとはっきりわかりました。
それとは別に、
この間言い忘れた変なこと、非常に我田引水的な事をちょっと。
私は、何もかも日本にくっつける日本主義的人間だ、などと誤解される怖れはあるのですけれど、Kew Gardens さまも「貞子ちっくなフラワーメーデン」なんておっしゃってたので、遠慮なく申し上げます。
あの騎士たち、グルネマンツの二人の従者、アンフォルタスの従者たち,それからある時点での騎士団全部の姿勢は、ジラール氏、ひょっとすると日本の時代劇の映画から取ったのじゃないかしら、とつまらない事を考えたのです。
一番始めに見た時から、「あら、欧州の中世の騎士たちがあんなひざまづき方をしたかしら」と思って見てると、どうも日本の武士が戦争中に主君の所へ帰って来て報告などする時、片脚は膝まづいて手を地上につき、片脚はたててその上に肘を角張らせて手を置くという姿勢、それをパルジファルの騎士たちがみんなやっているので奇異の感に打たれたのです。私はこの間もシェークスピアの歴史劇を見たし、時代物の演劇や映画の場面からそういう姿勢を思い出そうと思って一生懸命考えたのですけれど、あんな姿勢を欧米の演劇からは思い出せません。その姿勢はアンフォルタスがひざまづいている時にちょうど肩を貸すのに都合のいい姿勢です。そうして左右反対の手をついて、二人の騎士は対照的な姿勢を取っています。
Kinoxさまが「パルジファルでは既存のひとつの宗教に納まりきれない、かなり独自の宗教観を提示しているように」
「ジラールはそういうことを踏まえ、意図的に特定の宗教味を消してジェネリックにしたんだ...わたしの目には北米系プロテスタントだか新興宗教臭があったり、またニューエイジ的な感じもしたりして、個人的には違和感があって」
とおっしゃいましたが、
全くその通りだと思うのですが、ジラール氏はその過程で東洋的な感じのするフラワーメーデンを入れてみたり,クンドリイの運命は仏教の輪廻転生だなどと言ったりして、なるべくこのオペラが全面的に北欧州原産的になるのをさけているのかしらという感じがします。それでこういう姿勢も取り入れたのかなあと思いました。
「特定の宗教味を消してジェネリックにした」というのは全くContemporary的New Age的な意図で、若い人たちも理解出来るでしょう。
とは言っても、ワグナーの音楽脚色が全くキリスト教的なので第三幕はキリスト教シンボリズムから逃れ得ていませんが。
Kiera Duffy が出ていたのですか?さすがのKinox様,よくご存知ですね。Pierrot Lunaireをいつか歌ったのは知っていますが。
そして先日友達から聞いたのですが、なんだか「最終幕の最後の最後に立ち上がって一歩二歩歩みよる女性とパルジファルが見詰め合っている、あれはローエングリンのお母さんになる人じゃないか」なんていう解釈をしている人もあるそうです。わたしはそんなところは全く気づきませんでした。
またKiera Duffy、わたしは映画で見ていただけですが、CSTMさまは生で聴いてらっしゃるんですね、素晴らしい。
> クンドリイの運命は仏教の輪廻転生
> ワグナーの音楽脚色が全くキリスト教的なので第三幕はキリスト教シンボリズムから逃れ得ていません
CSTMさま、これは全く同意します。
本文中でちらっとニーチェに触れましたが、ワーグナーは、少々キリスト教としては異端な神秘主義的エックハルトや仏教・インド哲学的ショーペンハウエルに影響を受けているんだったと思います。ショーペンハウエルは仏教的な「罪と輪廻」のコンセプトとか語ってますけれど、クンドリが罪のせいで“成仏することなく”と言ったらいいのか、千何年も同じ状態で生かされている、というのはもろにショーペンハウエル的世界でしょう。
しかしワーグナーは、本文中にわたしは「ワーグナーは子供の頃は恐らくキリスト教の教育を受けていたけれども、古今東西の神話や宗教、神秘主義に傾倒」と書きましたけれど、世間や専門家がどう定義しているのか詳しくは分かりませんけれど、ワーグナーの宗教観は、直接的に自ら仏教に道を求めたとか学んだ人のもの、というより、あくまでもキリスト教から出発した人が、ショーペンハウエル等の第三者を通じた仏教的世界観・倫理観に多少の影響を受けたにとどまる、という印象が、勝手かもしれませんがわたしにはあります。乱暴な言い方をすると「神の力なんて必要ない、自分が強い意志をもって輪廻までも超越する」ニーチェが少なくともこの終幕に腹を立てた位には、わたしもワーグナーがここで描いたのはキリスト教な枠組みが色濃い「救い・許し」だった、と思います。
> 東洋的な感じのするフラワーメーデンを入れてみたり,
> 騎士団全部の姿勢は、ジラール氏、ひょっとすると日本の時代劇の映画から取ったのじゃないかしら
> 片脚は膝まづいて手を地上につき、片脚はたててその上に肘を角張らせて手を置くという姿勢、
> それをパルジファルの騎士たちがみんなやっている
あぁ騎士たちの所作、さすがのご指摘ですよ!、今回の演出には日本的なものの影響は絶対的にあちこちにあるでしょう。
ちょっと関係なく、またSF映画に飛んじゃいますが、スターウォーズなんかもあれはアーサー王物語的といえるかもしれませんけど、もろにサムライの話ですよね。ジェダイなんかも禅修業みたいだし、「フォース」なんかも武士の気合に似たところがあるんじゃないかと。
アメリカ人の友人に狂信的でないですけれど「自分はトレッキーと呼ばれてもおかしくないかも」という人がいて、彼の持論だとスタートレックのスポック、そしてヴァルカン式挨拶のハンドサインが有名なヴァルカン人、あれも「知的で精神性の高い日本人を模しているのだ」そうです、ふふ。なんでもヴァルカン星人は独自の哲学・宗教に基づいて自ら感情を律したり、座禅のようなことをして精神を鍛えたりするとか。
今や日本的なものは高い宗教性や禁欲的精神を示唆するのに一般的にも一番分かりやすい記号なのかもしれません。
それと、この演出がニューエイジ的だと言ったのは、わたしの貧相な理解ではニューエイジっていうのは、既存のキリスト教の宗教の枠組みに対抗するような形で、仏教やアメリカン・インディアンの風習とか禅の精神とかヒンズー教とか多種の宗教から影響を受けていて、身体的なものから、自然、宇宙的なもの、あるいは「何かを集中してやる」行為、など、ありとあらゆるものに霊性を見出すような思想なんじゃないかと。またこの演出にはニューエイジがよく唱える「われわれはひとつなのだ」のコミュニティ性とか、(キリスト教の「父」性権威に対して)女は凄い!とか、そして「水瓶座の時代」のオカルトチックなコンセプトとかが見られ、あまりに符号するところが多くて、もしかしてひょっとしてジラール自身はキリスト教はもとより既存の宗教の色のついていないものをやろうとしていたのかもしれないけれど、ここまでもろニューエイジ的傾向が見られると、やっぱりわたしはニューエイジのラベルを貼ってしまいたくなります。そしてニューエイジが影響を受けている宗教の原産国はアジアや世界各国だったにしても、わたしにとって、ニューエイジ的世界観というのはどうしても北アメリカ、特に西海岸的イメージが濃いです。
この演出で描かれた宗教観が「現代の多くの観客にピンとくる」のだ、と言われれば、それはそうなのかもしれないな、ですけれど、同じように仏教にも遠からぬ影響を受けたことは間違いないだろうという共通点はあるにしろ、今回の演出のニューエイジ的な思想が、ワーグナーのパルジファルの宗教観と合致しているのかどうか、はわたしも、うーん、それはどうかな、と思います。