When words leave off music begins.
BGM on "♪YouTube":
Dedicated to "goo blog"(7-2)






 :「花久の里」は駐車場が少ない記憶があって久しく行っていなかったのですが、いつの間にか奥に広く駐車場が出来ていたんですね。これなら休日でも停められるんじゃないでしょうか。それでも、イベント時はちょっと厳しい台数かな?こんどバラの時季に行ってみよう。
:「花久の里」は駐車場が少ない記憶があって久しく行っていなかったのですが、いつの間にか奥に広く駐車場が出来ていたんですね。これなら休日でも停められるんじゃないでしょうか。それでも、イベント時はちょっと厳しい台数かな?こんどバラの時季に行ってみよう。
 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ













 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ



御 由 緒
当神社の創建は、藤原秀郷公が天慶の乱に際して、日夜素盞嗚命に戦勝を祈願し、これが成就したことにより、天慶三年(九四〇)四月、京都の八坂神社(祇園社)から勧請して創祀した。
当初は宇北山(現中久喜)にまつられたが、小山城築城に際し、城の鎮守と仰がれ、平治年間(一一五九~六〇)に当地へ遷座された。以来、小山六十六郷(小山市全域に野木町、国分寺町、下石橋、結城市小田林地区を含む)の総鎮守と仰がれる。
徳川家康公は、慶長五年(一六〇〇)七月、当神社境内で小山評定(軍議)を開き、参籠して関が原の戦勝を祈願した。祈願成就した事により、五十一石余の社領を寄進した。のち家康公の崇拝神社なる故をもって、家光公の命により、日光東照宮造営職人の奉製になる朱神輿(アカミコシ)が、当神社に奉納された。
昭和初期には、本殿、神輿殿、直会殿、大鳥居、手水舎、社務所などが竣工、同五十七年三月には、須賀神社会館が竣工して、年中の諸行事や結婚式場として、利用されている。
平成二年四月に創建一〇五〇年大祭を斎行し、これを記念して神門廻廊造営事業に着手し、同八年五月に竣工した。その後引き続き、社殿、末社、神輿殿、手水舎等の屋根銅板葺替工事、並びに、境内森林に檜苗木一千本を植栽し、境内施設整備をした。
参詣者は、小山六十六郷は勿論、県内外から広く暑い崇敬をうけている。
境内には、小山の伝説で有名な「七ツ石」(夜泣き石)や藤原秀郷公碑、小山朝政公碑、小山義政公碑、天狗党に参画した昌木晴雄翁碑、筆塚などがあり、神域の須賀の森には、杉、檜、欅、椿、銀杏等が生い茂り、多くの野鳥が棲息している。





 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ













 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ

























 :今回は「深谷ねぎまつり」のサテライト会場にもなっている『アリオ深谷』に車を停めて、無料のシャトルバスを使ってみました。
:今回は「深谷ねぎまつり」のサテライト会場にもなっている『アリオ深谷』に車を停めて、無料のシャトルバスを使ってみました。
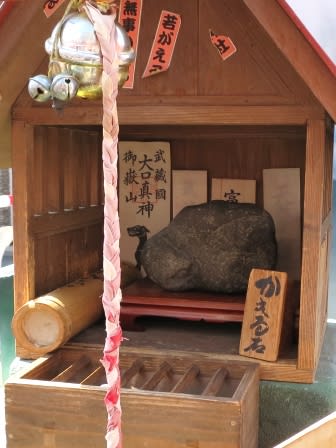
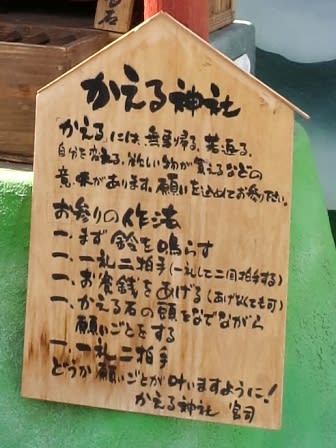
 :ここです
:ここです








 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ



古代の武蔵と上野(こうずけ)の国府を結ぶ官道であった上野信濃越後本道は、鎌倉時代には鎌倉街道となり、信越地方と鎌倉を結ぶ重要な交通路になった。日蓮が佐渡に流された時この道を通って行ったという当地に残る伝説も、この道の重要性を伝えたものであろう。当社の鎮座する小前田は、その道筋に当たり、中世には交通の要地とされていた。この小前田という地名は、南飯塚(当社の旧社地)に当社が祀られた時、その前面の平野を御前田原と呼んだことに始まるといわれ、中世には武蔵七党猪俣党の小前田野三郎信国の居館があった。
当社は、小前田の西部の、街道から少し入った「庚(かのえ)塚」と呼ばれる所に、民家に囲まれて鎮座している。境内には、所々に杉や欅が茂りこんもりとした杜を形作っているが、太平洋戦争以前は今とは比較にならないほど杉の古木が多く、昼なお暗いほどであった。こうした境内のたたずまいからは、当社が創建以来、現在地にあると言ってもだれも疑う者はないに違いない。
(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)

 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ