時効というのはよく
犯罪者が逮捕を免れる条件として
一般に知られていることです
確かに犯罪者が犯罪を犯しても時効が成立していれば 逮捕されることはありません
例えば人を殺して 逃走行為の結果
時効が成立すれば基本的に警察は逮捕はできないはず
しかし 時効の利益の放棄ということを知らない方は多いかもしれません
時効の利益の放棄というのは
犯罪者が時効が成立していても
時効が認められない場合で
この場合は犯罪が証明されれば再び逮捕されてしまいます
時効の利益の放棄とはどんな意味なんでしょうか
判例は時効は
犯罪者が逃走行為によって逮捕を免れるという利益を行使する者なので
その利益を享受しようとしないものまで保護するわけではいかないという立場をとっております
時効が成立したからといって犯罪者が犯罪者でなくなるわけではありません
逮捕されないという特権を
手に入れたにすぎません
犯罪がバレてマスコミから批判されたからといって それに
抗弁権はありません
裁判所は時効が利益
その利益は逮捕されないという利益を獲得したに止まります
犯罪者であることが
否定されるわけではないのです
時効の利益の放棄はそれを踏まえた上で
その利益さえ
活かそうとしないと認められたような場合
時効の利益の放棄が成立し
時効が成立していても再び逮捕要件を満たしてしまうことになります
では具体的にどのようなことをすれば時効の利益の放棄に 該当するのでしょうか
1 加害者である犯罪者が 被害者を非難するような行動を取った場合
マスコミなどの
手段を用いて 被害者に対する 批判などを行う
2 犯罪者が被害者のそば近くで仕事または生活を共有する状態にある
その生活の過程の中で 被害者に再び犯罪に該当するような 行為をした場合
これらのような場合時効の利益の放棄と言って
時効が 最終的には成立しません
この記事のコメントの欄の中に
記事の内容を疑問視するコメントがつきました
まずコメントの内容を私なりに理解しますと
1 時効の利益の放棄は民法の概念
刑法にそのような概念はないとのご指摘です
2 刑事訴訟法は強行法規なので
曖昧な理由で 変更が行われるとは考えにくい
そのような反論
反論はそのように理解した上で
お答えいたします
1 時効の利益の放棄という考え方は刑法の規定の中でもあります
ただし私が大学時代に読んだ教科書の中に書いてあったことや
判例の見解であることから
どの判例ですかという指摘はできません
しかし 刑法の教科書の中に時効の利益の放棄ということが説明されていることに間違いはありません
2 強行規定である 刑法という法律の性格から
変更の基準があいまいだとしておりますが
刑法は犯罪について規定する法律ですから
時効は刑事訴訟に帰属する問題になります
従って 時効が成立するケースが
いつも 広すぎる こちらの方が刑法の趣旨から入っておかしいと思います
時効の中断という言葉を検索キーなどで調べても
多くの場合民事事件あるいは民法の問題として取り扱われています
パソコンなどは一般的に多く使われてるほうが優先ですから
しかし刑法の中に時効の中断という理論はしっかり教科書に説明されています
パソコンに載っていないから間違っているというのは
時効の利益の放棄も教科書に
なっていたことなので間違いございません
一般に判例に 基づいて物を言うというのは
弁護士などのような実務家はそうかもしれませんが
刑法には理論と条文という二つの側面があります
理論として論じられていてそれを間違えてすることができないのです
自分は 刑法 の専門家ではないので
時効の利益の放棄ということを自分で語るのは不可能です
教科書に載っていたことをそのまま理解して伝えてるだけです










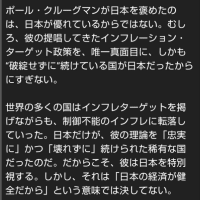





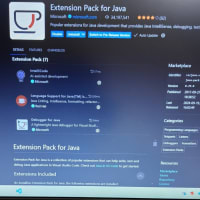

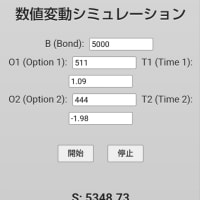

犯罪者は、刑事事件で、強行法規の刑事上訴訟法が適用されます。
公訴時効は、一定年度経過で、検察官が公訴提起できず、提起すると裁判所が公訴棄却を言い渡します。
強行法規ですので、誰もかってに変更できません。
筆者の言われる、被害者の批判するというような、曖昧なことで、公訴時効が変わるということは考えられません。
筆者の言われることの根拠があれば、教えて下さい。
Yahoo で検索したところ、刑法の時効の利益の放棄はありません。
刑法の条文上で、時効の利益の放棄の条文はありません。
刑法は罰則規定ですので、構成要件に該当する犯罪者を規定するものです。
手続き面は、刑事訴訟法が規定しますので、時効の利益の放棄のことを規定するなら、刑事訴訟法に規定するはずです。
勘違いでしょう?
自論を正しいと言っておられるなら、時効の利益の放棄の規定する条文が何条に書いてあるか、できたら判例も示してください。