さて、日本が協力する大前提として、まずこの「デオ・グラシアス」に、ほんとうに日本の資金を管理して、農業の事業を実施していく能力があるかを確かめる必要がある。ずさんな資金の使い方になったり、購入した資材などが盗まれたりするような、弱い管理体制では困るのである。大使館の館員が何度も現地を訪れて、こういう点は十分調査をした。手間暇かかるけれど、この手順は欠かせない。そして、この協同組合が、きちんとした運営管理をしていることを確認した。
そうして、いよいよ、どういう構想で協力を図っていけるか、を話し合うのである。資金額には限度があるから、協力分野を絞る必要がある。「デオ・グラシアス」側は、キャッサバ芋を粉砕する機械がほしい、それでアチェケという、そぼろ状のパスタ製品を作りたい、と言ってきた。キャッサバ芋商品化事業を希望するというのだ。
芋の粉砕、ですか、と私はあまり乗り気がしない。たしかにキャッサバ芋は、この地域の主食だから、どこの村でも粉砕機をほしがっている。粉砕機を提供すれば、村人たちはもちろん喜んで活用するだろう。しかし私としては、日本だからこそ出来ること、日本らしい協力を行いたいのだ。
私は村に出かけたときに、沢山の湿地帯があることを観察していた。村の土地の長たちが提供してくれた土地には、湿地帯が多かった。キャッサバやトウモロコシなどの、普通の農作物の耕作には不利な土地だから、誰も手を付けずに残っていたのだ。しかし、湿地帯にこそ適している作物がある。稲作だ。
それに、米はこれから将来性のある作物である。キャッサバ芋よりも手軽に料理ができることもあり、都市を中心に、米の需要が急増している。したがって、稲作に成功すれば、これは確実な需要があるであろう。
バグボ大統領も、稲作を奨励している。人々はだんだん米食に移行しつつある。それなのに、農村は米を作っていない。タイや中国からの米を輸入が急増している。食べることができないカカオやコーヒーを作って輸出し、食べるための米を輸入している。こんな不経済なことがあるか。米を自給しよう。これが独立記念日での大統領のメッセージだった。
何より、稲作協力といえば、もちろん米が主食の日本人には馴染みがある。国際協力機構(JICA)は、昨年のTICAD以来、「アフリカ稲作振興のための共同体(Coalition for African Rice Development:CARD)」という協力枠組みを進めている。「CARD」では、サブサハラ・アフリカの米生産を、向こう10年間で倍増(1400万トンから2800万トンへ)する、という目標を掲げている。稲作振興は、日本の協力の優先分野なのだ。
偶々、コートジボワールには「アフリカ稲センター」(英語:WARDA、仏語:ADRAO)という国際研究機関が存在している。この機関では、稲作とくにネリカ米の普及に努めている。この国の国内紛争から逃れるため、2005年以降、本部をベナンのコトヌ近郊に移したけれど、コートジボワールに残る施設では、留守を守ってまだ何人かの稲作研究者が活動している。私はそこを訪ね、そこのディアタ博士と知り合うことが出来た。ついで、ベナンのコトヌ近郊にある本部も訪ねて、稲作の技術的な話を聞いた。
いろいろ研究して、コートジボワールの低湿地帯の農村に、稲作は有望であるという結論を得た。そして多くの人々が、コートジボワールの農村で、稲作普及を試みるという計画に、前向きに取り組むことを約束してくれた。
村々の長たちが提供してくれた土地。近代的農業を手掛けたいとの意欲に満ちた地元の若者・婦人たち。取りまとめの協同組合「デオ・グラシアス」。「アフリカ稲センター」の稲作専門家。日本政府の稲作振興への意欲と資金。このように、協力案件の絵を描くための、絵の具が揃った。
(続く)
そうして、いよいよ、どういう構想で協力を図っていけるか、を話し合うのである。資金額には限度があるから、協力分野を絞る必要がある。「デオ・グラシアス」側は、キャッサバ芋を粉砕する機械がほしい、それでアチェケという、そぼろ状のパスタ製品を作りたい、と言ってきた。キャッサバ芋商品化事業を希望するというのだ。
芋の粉砕、ですか、と私はあまり乗り気がしない。たしかにキャッサバ芋は、この地域の主食だから、どこの村でも粉砕機をほしがっている。粉砕機を提供すれば、村人たちはもちろん喜んで活用するだろう。しかし私としては、日本だからこそ出来ること、日本らしい協力を行いたいのだ。
私は村に出かけたときに、沢山の湿地帯があることを観察していた。村の土地の長たちが提供してくれた土地には、湿地帯が多かった。キャッサバやトウモロコシなどの、普通の農作物の耕作には不利な土地だから、誰も手を付けずに残っていたのだ。しかし、湿地帯にこそ適している作物がある。稲作だ。
それに、米はこれから将来性のある作物である。キャッサバ芋よりも手軽に料理ができることもあり、都市を中心に、米の需要が急増している。したがって、稲作に成功すれば、これは確実な需要があるであろう。
バグボ大統領も、稲作を奨励している。人々はだんだん米食に移行しつつある。それなのに、農村は米を作っていない。タイや中国からの米を輸入が急増している。食べることができないカカオやコーヒーを作って輸出し、食べるための米を輸入している。こんな不経済なことがあるか。米を自給しよう。これが独立記念日での大統領のメッセージだった。
何より、稲作協力といえば、もちろん米が主食の日本人には馴染みがある。国際協力機構(JICA)は、昨年のTICAD以来、「アフリカ稲作振興のための共同体(Coalition for African Rice Development:CARD)」という協力枠組みを進めている。「CARD」では、サブサハラ・アフリカの米生産を、向こう10年間で倍増(1400万トンから2800万トンへ)する、という目標を掲げている。稲作振興は、日本の協力の優先分野なのだ。
偶々、コートジボワールには「アフリカ稲センター」(英語:WARDA、仏語:ADRAO)という国際研究機関が存在している。この機関では、稲作とくにネリカ米の普及に努めている。この国の国内紛争から逃れるため、2005年以降、本部をベナンのコトヌ近郊に移したけれど、コートジボワールに残る施設では、留守を守ってまだ何人かの稲作研究者が活動している。私はそこを訪ね、そこのディアタ博士と知り合うことが出来た。ついで、ベナンのコトヌ近郊にある本部も訪ねて、稲作の技術的な話を聞いた。
いろいろ研究して、コートジボワールの低湿地帯の農村に、稲作は有望であるという結論を得た。そして多くの人々が、コートジボワールの農村で、稲作普及を試みるという計画に、前向きに取り組むことを約束してくれた。
村々の長たちが提供してくれた土地。近代的農業を手掛けたいとの意欲に満ちた地元の若者・婦人たち。取りまとめの協同組合「デオ・グラシアス」。「アフリカ稲センター」の稲作専門家。日本政府の稲作振興への意欲と資金。このように、協力案件の絵を描くための、絵の具が揃った。
(続く)



















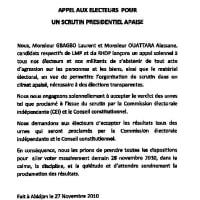
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます