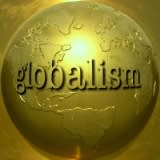グローバリズム(英: globalism)とは、地球上を一つの共同体とみなし、世界の一体化(グローバリゼーション)を進める思想である[1][2]。現代では、多国籍企業が国境を越えて地球規模で経済活動を展開する行為や、自由貿易および市場主義経済を全地球上に拡大させる思想などを表す。訳して地球主義とも言われる。
「グローバリズム」という語は1991年以後に使われるようになったが、歴史的には何度も見られた傾向である。19世紀から1945年までの欧米列強による帝国主義・植民地主義もグローバリズムの一種であるが、3国以上の列強の勢力圏で閉じた経済活動を行うブロック経済であった。英語では、イギリス世界(グロブブリテン)を中心とした世界構築という意味合いが含まれる。
1970年代に国際決済が一気にオンライン・グローバル化。
1991年にソビエト連邦が崩壊した後は、アメリカ合衆国の圧倒的な軍事力を背景とした世界の画一化や新自由主義を指す事が多い。これは、しばしば各国独自の伝統・慣習と衝突するため、反米主義者などからしばしば、「グローバリズムはアメリカ帝国主義およびアメリカニゼーション」である」として批判される。
近年では国際会議の折などに反グローバリズムのデモが行われることがある。
グローバリズムは、多国籍企業による市場の寡占もしくは独占固定化に至る可能性が高い。例として、参入に巨額の資金が必要な半導体製造等の業種は、リスクが高く新規参入が困難であることから、多国籍企業による市場寡占・独占固定化の可能性が高くなる。参入が困難な業種ほど寡占・独占固定化が進むと予測される。
グローバリズムによる相互依存が高まると、原油を初めとする資源価格高騰によって、持てる者である資源国がますます富み、無資源国が高値で資源購入を余儀なくされる状況が深刻化する。一部の多国籍企業による国際市場の寡占・独占固定化が強まると、資金・資本に乏しい国家からの企業の参入は極端に不利となる。
国内産業が多国籍企業に支配された低開発国は、先進国から国際援助を受けても資金が国内産業に回らずそのまま国外に流出し、低開発国からなかなか離陸できない。無資源国で有力な産業が少なく、国外市場参入もできない国は世界を一つの市場として共有するメリットは無いため、グローバリズムの市場共有を放棄する可能性も生ずる。
逆に、ソフトウェア産業等のようにわずかの資金で参入でき、1人の人間のアイデアが大きく生かされる業種は、多くの雇用がアウトソーシングの形で先進国から開発途上国に流れており、世界的な産業規模の拡大が続いている。
ロシア、中国やインドの急速な台頭による多極化や、経済面での地域統合の動き(南米の南の銀行、ヨーロッパのユーロ通貨など)により、今後グローバル化の動きは相対的に後退し、世界のブロック経済化が進んでいく可能性もある[誰?]。
(wikipedia)