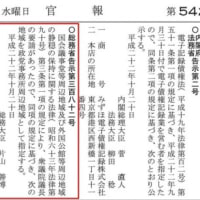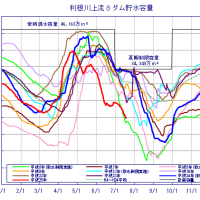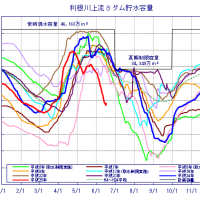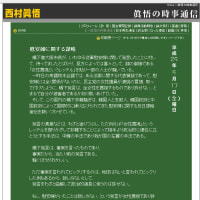これは分かりやすい。
社団法人日本土壌肥料学会:土壌・農作物等への原発事故影響WG:放射性セシウムに関する一般の方むけのQ&Aによる解説(要点を摘記)
カリウムを多く施肥するという手法は、北欧でも実施された。人間が安定ホウ素剤を服用するのとちょっと似た理屈。
スウェーデンの今:チェルノブイリ事故後にスウェーデンが取った汚染対策(その2)

社団法人日本土壌肥料学会:土壌・農作物等への原発事故影響WG:放射性セシウムに関する一般の方むけのQ&Aによる解説(要点を摘記)
土に降ったセシウム137の70%が、粘土鉱物に強く保持されるという研究結果も報告されています。白米への移行は0.002~0.1であるとすると、上下の比は50倍にもなる。これは、土壌の性質によるらしいが、作ってみなければ分かるまい。作付け可かどうか微妙な地域では、米を作って、収穫して結果を測定してみるしかないのでは。それで出荷できない場合は補償するしかない。値が下がる場合も風評被害として利益の差額を補償するしかあるまい。
半分の濃度に減る時間(滞留半減時間)は水田作土で9~24年、畑作土で8~26年
土のカリウムの濃度が高いほど、セシウム137が作物へ吸収される量が少なくなるという研究事例があります。
土から白米への移行係数(白米1 kg当たりの放射能濃度/土壌1 kg当たりの放射能濃度の比)は0.00021~0.012と報告されています。(中略)原子力災害対策本部では、「移行の指標」として0.1という値を用いています。この値は、かなり安全側に配慮した指標
イネが吸収するセシウム137全量の12~20%が玄米に移動します。また、ぬかで白米より高い濃度にあることが知られており、このためセシウム137の濃度は、白米のほうが玄米に比べ30~50%程度低い
カリウムを多く施肥するという手法は、北欧でも実施された。人間が安定ホウ素剤を服用するのとちょっと似た理屈。
スウェーデンの今:チェルノブイリ事故後にスウェーデンが取った汚染対策(その2)