福島県の「大内宿」といえば、
旅行好きの人であれば、そこそこの知名度じゃないかと思う。
岐阜の「白川郷」ほどではないが、
今でも、それなりの規模のかやぶき屋根の昔の街並みを
保存している集落として、
ちょっとした観光地となっている。
先般はテレビでも、
ネギ一本をさじの代わりに使ってそばをかきこむ
ネギそば(お店によっては「高遠そば」とか、
「祝言そば」とか、いろいろな言い方をする)などとともに
紹介されており、
休みともなれば、
ひろいとは言えない集落に、観光客が押し寄せ、
春から秋の連休ともなれば
都内と変わらないような人口密集地になる。
おいらも、この休みを利用していってまいりました。
観光に。
大内宿がどんなところかは、
福島観光協会のサイトでも見てもらうとして、
宿場町全体でまとまった数の茅葺屋根の家屋が保存されており、
集落の一番奥の高台から見た景色はなかなかのものです。
件の、「ネギそば」も大変おいしい。
会津はそばの産地としても有名で、そばそのものがとても甘くて
いい味がする。そば通の人に言わせれば
今はそばの端境期で、そばの香りなんか全然しないということだが
そんなことはない。そりゃ、季節のものに比べれば
味が落ちるのはやむを得ないかもしれないが、
独特の歯ごたえや甘みは、はっきりそれとわかるおいしさでした。
また、ネギも、根元から一本丸ごとがじがじかじるわけだが、
採りたてのせいか、想像されるような臭みや辛み、えぐみはなく、
そばと合わせると甘さが引き立ち、
適度な辛さと香りで、とっても味わい深い。
ネギ一本丸ごと、というと
最初は、うげっと思うが、食ってみるとそんなことはない。
お店に入って、そばを食べながら店の中を見渡すと
昔のままの調度品などがあり、興味深い。
家の周辺にはツバメが多く、完全に雀を駆逐した感じがある。
たぶん、ツバメといえば茅につく虫などを食べてくれるのだろうから、
追い出したりするようなことはしないのだろう。
ツバメの方も人に慣れているようで、
人がいても気にする風でもない。
それはまあ、それとして。。。
川越などでもそうだが、
「街並保存」というと、どうしても
昔からある建物を保存することが重視され、
建物を建物として、
つまり、人間がそこで暮らし、そこで生きる必然性までは
保存できないことがしばしばである。
それはやむを得ない面があるのだが、
それにしても、それがここまで極端なケースも珍しいだろう。
あらかじめ断っておきたいが
ここでおいらが何か批判めいたことを書いていても、
決してそれは地域で生活している人々のことを
非難したり、何かしらの対案を提案したいわけではない。
あくまでも、ただの一観光客の感想である。
そう、一観光客としての感想を言うなら、
この街の風景を見ながら、
正直な話、ある種のグロテスクさとでもいうべきものを
感じざるを得なかったのである。
整然と並んでいる茅葺屋根の建物は、
いずれもいくつかの例外を別としてほぼすべて軒先を商店として
その内側では観光客用の食堂を経営している。
その空間からは、茅葺屋根やこの古い建物の中で生活している人々の
生活感は全く感じることができない。
建物は、古い時代の遺品として見世物としてそこに立っているだけで、
その建物自体が持つ合理性や歴史性といったものとは
無縁な存在となってしまっている。
きれいに手入れされ掃除が行き届いた建物の軒先には
整然と販売用の土産物が並べられ、
建物の一部では、今では民宿としても活用され、
物好きな観光客に、レトロな雰囲気の一泊を体験させることになる。
しかし、そこでの食事や宿泊からは
昔の人々がこの広いとは言えない集落の中で
いったいどのような日々を送り
どのようにしてこの建物を活用し、
どのようにしてこの建物を維持していたのかを
想像することは、やや困難であろう。
相沢韶男さんという方が作成した書物で
『大内の写真記録 瞬間の遺産一』
と、写真集がある。地元の土産物屋で一部1,000円で販売している
小さな写真集である。
この写真集と現在の(観光客だらけの時期の)この集落を
見比べるなら、その差は歴然である。
この写真集は、昭和44年ごろのものが中心である。
茅葺屋根の家屋は、豪雪地帯の盆地で生きる人々の生活を守り、支えていた。
人々は、この茅葺屋根により、冬の雪や夏の暑さから守られていたのであろう。
写真からうかがわれる生活感といったものは
現在の集落からは全く感じることができない。
集落の、建物は残された。しかし、この集落の生活は完全に変わってしまったのであり、
当然、建物の存在意義も変わってしまった。
建物を相変わらず生活の手段である。しかしそれは
観光客を呼び集めるため、見世物として残された茅葺である。
こうした街並みを保存する、というのは
実際、難しい問題である。
日本は近代化を推し進める中で、
当然生活の利便を追求してきた。
昔の古臭い生活というのはその中で、
順次排除されていったのだが、特に、
豪雪地域などで、雪に苦しめられる人々にとって、
雪の苦労を少しでも楽にしてくれる近代の利便を希求する思いは、
雪の苦労がない地域で生活している者にはちょっと想像できないものが
あったのではないかと思う。
(田中角栄および角栄的なものがなぜあれほど力を持てたのか、
こうしたことを抜きに考えることはできないと思う。)
当然、街並みを保存することと、近代的な生活を
どのようにして両立させるのかが問題になる。
勿論、コストが許すなら
部分部分を改良してゆけば済む話である。
実際、そうやっている地域も少なくない。
会津の、大内宿から会津若松へと向かう道路沿いの町の多く、
大内宿からやや北上した博士山のふもとの集落、
こうしたところでも、古い民家が立ち並び
現役として利用されているものを目にする。
そうしたものの多くが、昔風のつくりの建物の上に、
金属でできた茅葺屋根の型を取った屋根をいただいているのだ。
この金属板でできた茅葺屋根の滑稽さは言葉では表現しようがない。
なんとも、見るも無残な姿である。
しかし、この外観上の滑稽さの中には
そこでの生活を守っていこうとする人々の知恵や工夫が
織り込まれている。観光客の無責任な感想よりは、はるかに
重要で実質のあるものだ。いったい、守るべきは
茅葺の屋根なんだろうか、そこでの生活なのだろうか。
と、いっても、
そういう二者択一の問題設定も、やはり適切とは言えない。
大内宿の茅葺屋根は
確かにそこで生きる人々の生活と収入を
守っているのだ。
そもそもを言えば、
例えば富士山や白神山地の世界遺産登録などにも共通していることだが、
昔の街並みや古くからの自然環境を保護するため、
ユネスコなどに登録し観光立地を進める、
というのは、やや矛盾した課題である。
街並でも、自然でもそうだが、
それと意識して人間が手を入れなければ
守ることはできない。(「手つかずの自然」など、
太平洋の離島など一部を除けば、日本にはない。)
ブナ林など、一部の好事家が
いくら「素晴らしい」といったところで、
大規模開発にさらされてしまえば
ひとたまりもない。
だから、街並みなり植生なりを守ろうとしたら、
人々がそれを意識して守らなければならないのだが、
そのためには、
それを守らなければならない積極的な意味を作り出さなければならない。
単に、街並が美しいから、とか、歴史的に価値のある建造物だから、では、
実は、十分な理由にはならない。なぜなら、
そのような価値を見出したとしても、
それを守り続けるには、応分のコストがかかるからである。
だから、そこで何を守ろうとしているのかにかかわらず、
最終的にはそれを守ろうとすれば、それ自体の中に
何らかの形で金銭的価値を見出すしかない。しかし、
そもそもそれ自体の中には金銭的価値がないから
破壊されているものを守るため、そこに金銭的価値を
見出そうというのだから、矛盾した営為といわざるを得ない。
となると結局、守りたいものすべてを守ることはできない。
金銭的メリットと、それ以外の価値との間で折り合いをつけなければならない。
どこで折り合いがつくのか。
例えば観光資源というような形で、
当の守るべきものを貨幣化しようとする場合のことを考えよう。
貨幣化ということはつまり、この場合、典型的には
観光地化を進めることに他ならないが、
そのためには、結局、何らかの「守るべき」価値を
放棄することが、多くの場合、必要になる。
どのような価値が放棄されるべきかは、
結局のところ、関係者間の対立と妥協とを通じて
決定されることにならざるを得ない。
この、守るべき価値が何であるのか、おおざっぱな合意がある場合でも
実際に行動しようとなれば、
常に合意があるわけではなく、
なるべく多くのものを残したい、という人と
なるべく多くの資源を貨幣化したい、という人の間で
綱引きが行われ、その中で、緩やかに、
あいまいな形で決まってゆくことだろう。
こうした綱引きについて言えば、
現代社会においては例えば白神山地のように
実生活からある程度距離を置くことが可能な自然環境にかかわる問題より
大内宿のような、現にそこで人々が生活している場のほうが
めんどくさい問題に発展することもあるかもしれない。
何しろ、現にそこで人間が生活しているのである。
そこで生活している人々からすれば、
まずは自分たち自身の生活そのものを合理化・近代化したいと
望む人が少なくないだろう(誰がそれを非難できる?)。
そして、そういう人々にとっては、そのための
観光地化なのである。茅葺屋根を守るための、ではない。
この場合、
街並みを保存しようという目標は同じでも、
保存することを目的とし、そのため、その一部を観光地化することを
選択する人と、
街並みを観光地化することによって生活を物質的に向上させよう
という意欲を持っている人と、
完全に呉越同舟となってしまう。
なるべく、自分たちの生活を
近代化しながら、観光資源を再生産しようとすれば、
結果として残るのは、茅葺屋根という物理的な外観上の存在だけで
そこでの生活は、すべて観光地化に対応したものになってしまうだろう。
まあ、こんなことは、外部の人がとやかく言って始まるものではないし、
とやかく言うべきでもないのだろう。
「街並を保存しよう」ということなら、
まだ外部の者にも言いようがあるが、
「昔のまま、昔ながらの生活を続けてください」などと、
いえようはずもない。
そういう意味では、大内宿が、現状のような形で保存されていることについては、
素直に関係者各位の努力に感謝するべきなのであろう。
ただしかし、感謝しているだけでも始まらない。
何も大内宿のことだけではない。
これから日本で、あるいは世界各国各地域で
人々の暮らしや歴史的遺物、自然環境を保存しようという動きは
ますます活発化することだろう。
しかし、そこには、すでに近代化を済ませ、
自分たちは、普段は近代的な生活を享受し、
そして時間とカネがあるときには
近代的な移動手段を用いて、
こうした遺産を観光に行ける特権を有している人々が
地域に現に生きている人々の暮らしを無視し、
自分たちだけの都合に合わせ、時には
開発を進め、時には遺産の保存を訴える、
こうしたことを続けることであろう。
そして、遺産に指定された側でも、
自分たちの生活を近代化し
合理化することを求めて、それに呼応することも少なくないだろう。
そうした動きを止めようというのは、おろかである。
しかしながら、場合によっては、
それでもなお、そこで、昔ながらの生活を続けることを
選択する人あるいは、選択せざるを得ない人たちも
いるかもしれない。
何を、どのような価値を保存するべきなのか、
そして、そのような価値について合意ができたとして、
どうすれば、それが保存できるのか、
どのように保存するべきなのか、
大内宿のありさまをぼけっと眺めているだけでも、
そうしたことを考える上での
一助になるのではないか、と思うのである。
あ、そうだ、思い出した。
富士山が世界遺産に登録されたんだってね。
おめでとうございます。
旅行好きの人であれば、そこそこの知名度じゃないかと思う。
岐阜の「白川郷」ほどではないが、
今でも、それなりの規模のかやぶき屋根の昔の街並みを
保存している集落として、
ちょっとした観光地となっている。
先般はテレビでも、
ネギ一本をさじの代わりに使ってそばをかきこむ
ネギそば(お店によっては「高遠そば」とか、
「祝言そば」とか、いろいろな言い方をする)などとともに
紹介されており、
休みともなれば、
ひろいとは言えない集落に、観光客が押し寄せ、
春から秋の連休ともなれば
都内と変わらないような人口密集地になる。
おいらも、この休みを利用していってまいりました。
観光に。
大内宿がどんなところかは、
福島観光協会のサイトでも見てもらうとして、
宿場町全体でまとまった数の茅葺屋根の家屋が保存されており、
集落の一番奥の高台から見た景色はなかなかのものです。
件の、「ネギそば」も大変おいしい。
会津はそばの産地としても有名で、そばそのものがとても甘くて
いい味がする。そば通の人に言わせれば
今はそばの端境期で、そばの香りなんか全然しないということだが
そんなことはない。そりゃ、季節のものに比べれば
味が落ちるのはやむを得ないかもしれないが、
独特の歯ごたえや甘みは、はっきりそれとわかるおいしさでした。
また、ネギも、根元から一本丸ごとがじがじかじるわけだが、
採りたてのせいか、想像されるような臭みや辛み、えぐみはなく、
そばと合わせると甘さが引き立ち、
適度な辛さと香りで、とっても味わい深い。
ネギ一本丸ごと、というと
最初は、うげっと思うが、食ってみるとそんなことはない。
お店に入って、そばを食べながら店の中を見渡すと
昔のままの調度品などがあり、興味深い。
家の周辺にはツバメが多く、完全に雀を駆逐した感じがある。
たぶん、ツバメといえば茅につく虫などを食べてくれるのだろうから、
追い出したりするようなことはしないのだろう。
ツバメの方も人に慣れているようで、
人がいても気にする風でもない。
それはまあ、それとして。。。
川越などでもそうだが、
「街並保存」というと、どうしても
昔からある建物を保存することが重視され、
建物を建物として、
つまり、人間がそこで暮らし、そこで生きる必然性までは
保存できないことがしばしばである。
それはやむを得ない面があるのだが、
それにしても、それがここまで極端なケースも珍しいだろう。
あらかじめ断っておきたいが
ここでおいらが何か批判めいたことを書いていても、
決してそれは地域で生活している人々のことを
非難したり、何かしらの対案を提案したいわけではない。
あくまでも、ただの一観光客の感想である。
そう、一観光客としての感想を言うなら、
この街の風景を見ながら、
正直な話、ある種のグロテスクさとでもいうべきものを
感じざるを得なかったのである。
整然と並んでいる茅葺屋根の建物は、
いずれもいくつかの例外を別としてほぼすべて軒先を商店として
その内側では観光客用の食堂を経営している。
その空間からは、茅葺屋根やこの古い建物の中で生活している人々の
生活感は全く感じることができない。
建物は、古い時代の遺品として見世物としてそこに立っているだけで、
その建物自体が持つ合理性や歴史性といったものとは
無縁な存在となってしまっている。
きれいに手入れされ掃除が行き届いた建物の軒先には
整然と販売用の土産物が並べられ、
建物の一部では、今では民宿としても活用され、
物好きな観光客に、レトロな雰囲気の一泊を体験させることになる。
しかし、そこでの食事や宿泊からは
昔の人々がこの広いとは言えない集落の中で
いったいどのような日々を送り
どのようにしてこの建物を活用し、
どのようにしてこの建物を維持していたのかを
想像することは、やや困難であろう。
相沢韶男さんという方が作成した書物で
『大内の写真記録 瞬間の遺産一』
と、写真集がある。地元の土産物屋で一部1,000円で販売している
小さな写真集である。
この写真集と現在の(観光客だらけの時期の)この集落を
見比べるなら、その差は歴然である。
この写真集は、昭和44年ごろのものが中心である。
茅葺屋根の家屋は、豪雪地帯の盆地で生きる人々の生活を守り、支えていた。
人々は、この茅葺屋根により、冬の雪や夏の暑さから守られていたのであろう。
写真からうかがわれる生活感といったものは
現在の集落からは全く感じることができない。
集落の、建物は残された。しかし、この集落の生活は完全に変わってしまったのであり、
当然、建物の存在意義も変わってしまった。
建物を相変わらず生活の手段である。しかしそれは
観光客を呼び集めるため、見世物として残された茅葺である。
こうした街並みを保存する、というのは
実際、難しい問題である。
日本は近代化を推し進める中で、
当然生活の利便を追求してきた。
昔の古臭い生活というのはその中で、
順次排除されていったのだが、特に、
豪雪地域などで、雪に苦しめられる人々にとって、
雪の苦労を少しでも楽にしてくれる近代の利便を希求する思いは、
雪の苦労がない地域で生活している者にはちょっと想像できないものが
あったのではないかと思う。
(田中角栄および角栄的なものがなぜあれほど力を持てたのか、
こうしたことを抜きに考えることはできないと思う。)
当然、街並みを保存することと、近代的な生活を
どのようにして両立させるのかが問題になる。
勿論、コストが許すなら
部分部分を改良してゆけば済む話である。
実際、そうやっている地域も少なくない。
会津の、大内宿から会津若松へと向かう道路沿いの町の多く、
大内宿からやや北上した博士山のふもとの集落、
こうしたところでも、古い民家が立ち並び
現役として利用されているものを目にする。
そうしたものの多くが、昔風のつくりの建物の上に、
金属でできた茅葺屋根の型を取った屋根をいただいているのだ。
この金属板でできた茅葺屋根の滑稽さは言葉では表現しようがない。
なんとも、見るも無残な姿である。
しかし、この外観上の滑稽さの中には
そこでの生活を守っていこうとする人々の知恵や工夫が
織り込まれている。観光客の無責任な感想よりは、はるかに
重要で実質のあるものだ。いったい、守るべきは
茅葺の屋根なんだろうか、そこでの生活なのだろうか。
と、いっても、
そういう二者択一の問題設定も、やはり適切とは言えない。
大内宿の茅葺屋根は
確かにそこで生きる人々の生活と収入を
守っているのだ。
そもそもを言えば、
例えば富士山や白神山地の世界遺産登録などにも共通していることだが、
昔の街並みや古くからの自然環境を保護するため、
ユネスコなどに登録し観光立地を進める、
というのは、やや矛盾した課題である。
街並でも、自然でもそうだが、
それと意識して人間が手を入れなければ
守ることはできない。(「手つかずの自然」など、
太平洋の離島など一部を除けば、日本にはない。)
ブナ林など、一部の好事家が
いくら「素晴らしい」といったところで、
大規模開発にさらされてしまえば
ひとたまりもない。
だから、街並みなり植生なりを守ろうとしたら、
人々がそれを意識して守らなければならないのだが、
そのためには、
それを守らなければならない積極的な意味を作り出さなければならない。
単に、街並が美しいから、とか、歴史的に価値のある建造物だから、では、
実は、十分な理由にはならない。なぜなら、
そのような価値を見出したとしても、
それを守り続けるには、応分のコストがかかるからである。
だから、そこで何を守ろうとしているのかにかかわらず、
最終的にはそれを守ろうとすれば、それ自体の中に
何らかの形で金銭的価値を見出すしかない。しかし、
そもそもそれ自体の中には金銭的価値がないから
破壊されているものを守るため、そこに金銭的価値を
見出そうというのだから、矛盾した営為といわざるを得ない。
となると結局、守りたいものすべてを守ることはできない。
金銭的メリットと、それ以外の価値との間で折り合いをつけなければならない。
どこで折り合いがつくのか。
例えば観光資源というような形で、
当の守るべきものを貨幣化しようとする場合のことを考えよう。
貨幣化ということはつまり、この場合、典型的には
観光地化を進めることに他ならないが、
そのためには、結局、何らかの「守るべき」価値を
放棄することが、多くの場合、必要になる。
どのような価値が放棄されるべきかは、
結局のところ、関係者間の対立と妥協とを通じて
決定されることにならざるを得ない。
この、守るべき価値が何であるのか、おおざっぱな合意がある場合でも
実際に行動しようとなれば、
常に合意があるわけではなく、
なるべく多くのものを残したい、という人と
なるべく多くの資源を貨幣化したい、という人の間で
綱引きが行われ、その中で、緩やかに、
あいまいな形で決まってゆくことだろう。
こうした綱引きについて言えば、
現代社会においては例えば白神山地のように
実生活からある程度距離を置くことが可能な自然環境にかかわる問題より
大内宿のような、現にそこで人々が生活している場のほうが
めんどくさい問題に発展することもあるかもしれない。
何しろ、現にそこで人間が生活しているのである。
そこで生活している人々からすれば、
まずは自分たち自身の生活そのものを合理化・近代化したいと
望む人が少なくないだろう(誰がそれを非難できる?)。
そして、そういう人々にとっては、そのための
観光地化なのである。茅葺屋根を守るための、ではない。
この場合、
街並みを保存しようという目標は同じでも、
保存することを目的とし、そのため、その一部を観光地化することを
選択する人と、
街並みを観光地化することによって生活を物質的に向上させよう
という意欲を持っている人と、
完全に呉越同舟となってしまう。
なるべく、自分たちの生活を
近代化しながら、観光資源を再生産しようとすれば、
結果として残るのは、茅葺屋根という物理的な外観上の存在だけで
そこでの生活は、すべて観光地化に対応したものになってしまうだろう。
まあ、こんなことは、外部の人がとやかく言って始まるものではないし、
とやかく言うべきでもないのだろう。
「街並を保存しよう」ということなら、
まだ外部の者にも言いようがあるが、
「昔のまま、昔ながらの生活を続けてください」などと、
いえようはずもない。
そういう意味では、大内宿が、現状のような形で保存されていることについては、
素直に関係者各位の努力に感謝するべきなのであろう。
ただしかし、感謝しているだけでも始まらない。
何も大内宿のことだけではない。
これから日本で、あるいは世界各国各地域で
人々の暮らしや歴史的遺物、自然環境を保存しようという動きは
ますます活発化することだろう。
しかし、そこには、すでに近代化を済ませ、
自分たちは、普段は近代的な生活を享受し、
そして時間とカネがあるときには
近代的な移動手段を用いて、
こうした遺産を観光に行ける特権を有している人々が
地域に現に生きている人々の暮らしを無視し、
自分たちだけの都合に合わせ、時には
開発を進め、時には遺産の保存を訴える、
こうしたことを続けることであろう。
そして、遺産に指定された側でも、
自分たちの生活を近代化し
合理化することを求めて、それに呼応することも少なくないだろう。
そうした動きを止めようというのは、おろかである。
しかしながら、場合によっては、
それでもなお、そこで、昔ながらの生活を続けることを
選択する人あるいは、選択せざるを得ない人たちも
いるかもしれない。
何を、どのような価値を保存するべきなのか、
そして、そのような価値について合意ができたとして、
どうすれば、それが保存できるのか、
どのように保存するべきなのか、
大内宿のありさまをぼけっと眺めているだけでも、
そうしたことを考える上での
一助になるのではないか、と思うのである。
あ、そうだ、思い出した。
富士山が世界遺産に登録されたんだってね。
おめでとうございます。










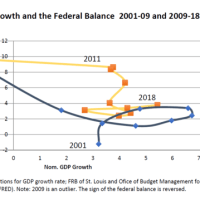
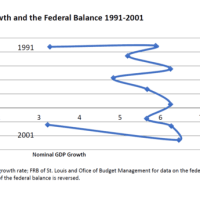
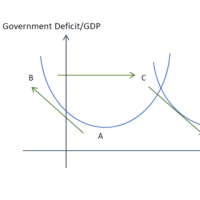
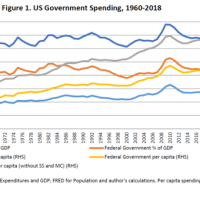
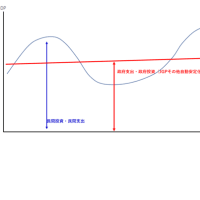
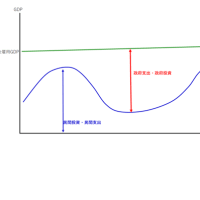
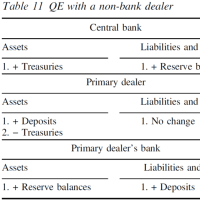
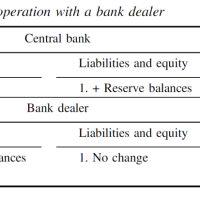
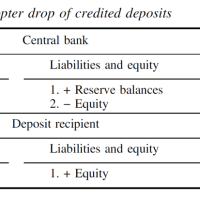
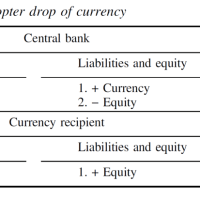
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます