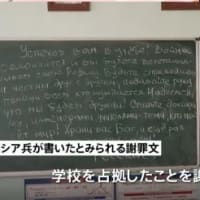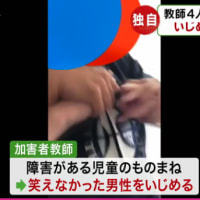・【FT】なぜ中東の炎は鎮火できないのか <前>
(フィナンシャル・タイムズ 2006年7月27日初出) デビッド・ガードナー
レバノンでの戦いには、絶望的なデジャビュ的感覚がつきまとっている。目の前で繰り広げられている戦いは、ある種の再放送ではないのかと。もうずっと昔から延々ひたすら続いてきた遺恨試合の、再々々々々々…マッチなのではないかと。その要素は確かに強い。しかしだからといって、今の状況がいかに異常なほど危うい状態にあるか、これまでと違ってどれだけ危険か、見過ごしてはならない。
レバノンとイスラエルの対立は、今回の侵攻がなくても十分すぎるほどひどい状況だった。最悪だったのはイスラエルによる1982年の全面侵攻。このときはレバノンからパレスチナ解放機構(PLO)を追放することが目的だった。この侵攻を機に、西ベイルートは2ヵ月にわたり占拠され、約1万9000 人が殺害された(このほかにベイルート郊外のパレスチナ難民キャンプ、サブラとシャティラでは多くのパレスチナ難民が虐殺された)。この侵攻によって最大の打撃を受けたのは実はPLOではなく、イスラエルの評判だった。そして1982年のこの侵攻がきっかけとなって、イスラエルの仇敵「ヒズボラ」誕生の土壌が作られたのだ。
今回の侵攻にあたって、イスラエル軍参謀総長のダン・ハルツ中将は「レバノンの時計を20年前に逆戻りさせてみせる」と挑発的に豪語した。中将本人が意図した以上に、この発言はイスラエルの本音をさらけだしたのではないか。
レバノンはこれまでに何度も、外国勢力の代理戦争に利用されてきた。シリアしかり、イスラエルしかり、サウジアラビア、リビア、イラン、ヨルダン、アメリカしかりだ。こうした諸外国がこれまで、レバノンの土地と宗派対立を利用して代理戦争を展開してきたのだ。しかしこれまでの戦いでは、戦火はレバノン領内にとどまっていた。
今回は違う。中東の地政学的な文脈や状況が変わってしまったからだ。とりわけイラクのせいで、中東に地殻変動が起きてしまったからだ。今の紛争当事者たちは、世界最大のガソリンスタンドにいながら、マッチ遊びをしているようなものだ。
イスラエルのレバノン攻撃が今後どうなるのか。1982年侵攻と同じくらい危険できまぐれなものになる危険がある──というだけでは済まされない。
イスラエル軍が2000年にレバノンを撤退するまでの間、ヒズボラはイスラエル精鋭部隊に激しく抵抗したわけだが、今回はそれにも増して激しく抵抗している。だからこそ、イスラエルの攻撃が激化している──というだけでも済まされない。
今回の衝突がこれまでと違うのは、レバノンでとどろく砲声のひとつひとつが全て、中東地域全体に響き、ひいては世界中に響き渡るからだ。目を凝らしてよく見てみると分かる。この戦いをレバノン領内のみに封じ込めるなど、できるわけがない。イスラエルがヒズボラを完全に崩壊させるまで、あるいはロケット砲がこれ以上届かないところへ追撃するまで、戦いはレバノンの外には絶対に拡大しない──などという展望は、妄想にすぎないのだ。
最近まではイラクについても、似たような妄想があった。米国はイラク事業を成功させて、ラディカルで新しい「自由」のアジェンダ(テロに強硬姿勢で臨み、テロの原因にも強硬に取り組むという政策方針)を中東地域で追求する──はずだった。
しかし今やイラクは国家として破綻してしまった。イスラム教シーア派とスンニ派の宗派対立で連日100人前後が殺される、闘鶏場のようなところになってしまった。そして、オサマ・ビンラディンが唱える全体主義的聖戦思想にとって、攻撃対象のやたらと多い、かっこうの最前線となってしまったのだ。
・【FT】なぜ中東の炎は鎮火できないのか <中>
新たに権力を握ったイラクのシーア派がいなければ、米国の「自由プロジェクト」はとっくの昔に完全崩壊していただろう。しかしイラクのシーア派は、シーア派の多く住むレバノンがイスラエルによって破壊されつつあることと、そのイスラエルの行動を米国が容認していることに、激怒している。イラクのシーア派過激派指導者モクタダ・サドル師が率いる民兵組織マフディー軍は、ヒズボラをモデルに組織されたもので、米軍が2004年にイラク・ナジャフで大掃討作戦を展開したときには、ヒズボラはマフディー軍と共に米軍と戦っている。それだけにマフディー軍は、レバノンの現状を前に、再び決起したくてウズウズしているのだ。
レバノンでの戦いがエスカレートするシナリオとしてはほかにも、もっとわかりやすいものがある。ヒズボラがこれまでの脅しを実行に移し、長距離ミサイルをイスラエル中心部に撃ち込めば、たちまち戦いは拡大する。戦況がまたたくまに拡大している今の状況からすると、これは避けられない展開のように見える。そして、そんなことになればイスラエルは怒り狂うに決まっているのだ。
イスラエルの連立政権は権力基盤が弱く、イスラエル軍司令部の顔色をうかがわざるを得ない状態にある。そしてイスラエル軍は(ヒズボラに兵士を拉致され)プライドを傷つけられているだけでなく、中東地域における抑止力の弱体化を深く懸念している。そんな状況だけにイスラエル軍にとって、ヒズボラを庇護し支援しているシリアやイランに仕返ししてやろうという誘惑は、とても強いもののはずだ。
ハマスやヒズボラが挑発的に仕掛ける国境紛争が、なぜこうして一気に地域戦争の瀬戸際まで悪化してしまったのか、検証しておくべきだ。重要な原因のひとつは、ブッシュ政権にある。ブッシュ政権は恐ろしいことに、外交的に全く役立たずで、かつ、より良い未来を切り開くためには(イスラエルが)ひたすら砲撃するのが一番だと信じている。このまさに致命的な組み合わせが、今のレバノン情勢を形作った大きな要因のひとつなのだ。
中東における最大の不安定要因──つまりイスラエルとパレスチナの関係──が長くほったらかしにされて腐りかけていたのは何も、イラク統治の大失態に米国がエネルギーをかけすぎたからではない。「パレスチナ国家」をどうするこうするというレトリックはともかくとして、イスラエルはヨルダン川西岸の占領地域や東エルサレムのアラブ人地区の土地を、少しずつ少しずつ、自分たちのものにしてきた。そしてジョージ・W・ブッシュ米国大統領は、これを容認してきたのだ。
中東で展開しているのは、現代で最重要なドラマのひとつだ。しかしアラブ諸国、ムスリム諸国において、米国は信頼を完全に失墜させている。宗教国家イランよりも、民主主義国アメリカの方が危険な国だという結果が、イスラム圏で行われた複数の世論調査から出ている。米調査会社ギャラップによるムスリム動向調査でも、こうした結果が出た。調査の結果、「米国は危険な国」」と答えた回答者のほとんどが敵視しているのは、西側の価値観そのものではなく、米国の政策なのだと明らかになった。ムスリムが米国を敵対視するようになったのは、ブッシュ政権下でおきた三つの出来事が原因だという。
ひとつ目は、2002年4月の出来事。アラブ世界は愕然として衛星テレビを見つめていたのだ。ブッシュ外交のとりはからいによって、イスラエルが西岸地区に再侵攻できるようになり、そしてまだまだ脆弱なパレスチナの政府機関を次々とずたずたにするのを、アラブ世界は暗然と見つめていた(ちなみに、 2006年1月パレスチナ総選挙におけるハマス勝利の下地が、このときに作られたわけだ)。
・【FT】なぜ中東の炎は鎮火できないのか <後>
ふたつ目は2004年4月の出来事。2年前よりさらに大勢のムスリムたちが、テレビを愕然と見つめていた。テレビ画面は二元同時中継で分割されていることもあった。画面の半分には、ファルージャを破壊する米軍が映し出され、もう半分には、ガザ南部ラファを破壊するイスラエル軍が映されていた。イラク・アブグレイブ刑務所における米軍虐待スキャンダルが暴露されたのは、この直後。そしてブッシュ大統領は4月16日、西岸地区の不法入植地にイスラエルがとどまることを認める書簡を、(現在は意識不明状態の)アリエル・シャロンに送ったのだった。アラブ諸国は米国のこの書簡を、「第二のバルフォア宣言」と受け止めた(訳注:「バルフォア宣言」とは1917年に英外相がユダヤ人有力者に対して、パレスチナにおけるユダヤ人国家建設を約束した書簡)。
三つ目の出来事は、現在進行中だ。ブッシュ米大統領とコンドリーザ・ライス米国務長官は、イスラエルの戦争目的実現を「外交」と勘違いしている。中東でかろうじて残っていたかもしれない米国に対する好意的な評価など、砲撃で焼け焦げたベイルート南部やレバノン南部の焦土の下に埋まっている。
今のこの現状について、慎重に考えるべき側面がひとつある。米国および米国と協力関係にあるスンニ派諸国はイラク戦争後、イラン主導でシーア派過激主義が勢力を拡大することに危機感を募らせていた。そしてイスラエルは、この情勢を正確に認識したというわけだ。
イスラエルがレバノン攻撃を開始した当初、エジプトやサウジアラビア、ヨルダンといったスンニ派諸国の政府の間では、一見するとヒズボラが攻撃されている事態を、ひそかに喜ぶ雰囲気さえあった。最初のうちは。サウジアラビア当局者は「正当な抵抗」と「無責任な冒険主義」を混乱してはいけないと戒めていた。サウジ王国の国教ワッハーブ派の聖職者たちは「偶像崇拝的シーア」に同情してはいけないと、信徒たちに説教していた。しかしイスラエルが何のためらいもなくレバノン人の生命や生活を破壊してまわるに至り、事態は完全に一変した。
アラブ諸国の指導者たちは、湾岸やレバント(東地中海沿岸)地域で、イランの影響力が拡大することを恐れてはいるが、実際はそれにも増して、自分たちの国民の反応を恐れているようだ。
米政府ときわめて親しいサウジアラビアのアブドラ国王は2002年、アラブ連盟の首脳会議をまとめ上げ、1967年の第三次中東戦争(六日間戦争)の全占領地返還と引き換えにイスラエルを国家承認するという中東和平案を提案した人物だ。しかし、そのアブドラ国王でさえもがレバノン攻撃を受けて、「永遠に続く忍耐などない」とイスラエルに警告しているのだ。アブドラ国王は言明した。危険がこれほどはっきりとあからさまになり、危険がこれほど高まったことはないと。「イスラエルの傲慢のせいで中東和平が破綻するならば、戦争のほかに選択肢はない」と。
(フィナンシャル・タイムズ 2006年7月27日初出) デビッド・ガードナー
レバノンでの戦いには、絶望的なデジャビュ的感覚がつきまとっている。目の前で繰り広げられている戦いは、ある種の再放送ではないのかと。もうずっと昔から延々ひたすら続いてきた遺恨試合の、再々々々々々…マッチなのではないかと。その要素は確かに強い。しかしだからといって、今の状況がいかに異常なほど危うい状態にあるか、これまでと違ってどれだけ危険か、見過ごしてはならない。
レバノンとイスラエルの対立は、今回の侵攻がなくても十分すぎるほどひどい状況だった。最悪だったのはイスラエルによる1982年の全面侵攻。このときはレバノンからパレスチナ解放機構(PLO)を追放することが目的だった。この侵攻を機に、西ベイルートは2ヵ月にわたり占拠され、約1万9000 人が殺害された(このほかにベイルート郊外のパレスチナ難民キャンプ、サブラとシャティラでは多くのパレスチナ難民が虐殺された)。この侵攻によって最大の打撃を受けたのは実はPLOではなく、イスラエルの評判だった。そして1982年のこの侵攻がきっかけとなって、イスラエルの仇敵「ヒズボラ」誕生の土壌が作られたのだ。
今回の侵攻にあたって、イスラエル軍参謀総長のダン・ハルツ中将は「レバノンの時計を20年前に逆戻りさせてみせる」と挑発的に豪語した。中将本人が意図した以上に、この発言はイスラエルの本音をさらけだしたのではないか。
レバノンはこれまでに何度も、外国勢力の代理戦争に利用されてきた。シリアしかり、イスラエルしかり、サウジアラビア、リビア、イラン、ヨルダン、アメリカしかりだ。こうした諸外国がこれまで、レバノンの土地と宗派対立を利用して代理戦争を展開してきたのだ。しかしこれまでの戦いでは、戦火はレバノン領内にとどまっていた。
今回は違う。中東の地政学的な文脈や状況が変わってしまったからだ。とりわけイラクのせいで、中東に地殻変動が起きてしまったからだ。今の紛争当事者たちは、世界最大のガソリンスタンドにいながら、マッチ遊びをしているようなものだ。
イスラエルのレバノン攻撃が今後どうなるのか。1982年侵攻と同じくらい危険できまぐれなものになる危険がある──というだけでは済まされない。
イスラエル軍が2000年にレバノンを撤退するまでの間、ヒズボラはイスラエル精鋭部隊に激しく抵抗したわけだが、今回はそれにも増して激しく抵抗している。だからこそ、イスラエルの攻撃が激化している──というだけでも済まされない。
今回の衝突がこれまでと違うのは、レバノンでとどろく砲声のひとつひとつが全て、中東地域全体に響き、ひいては世界中に響き渡るからだ。目を凝らしてよく見てみると分かる。この戦いをレバノン領内のみに封じ込めるなど、できるわけがない。イスラエルがヒズボラを完全に崩壊させるまで、あるいはロケット砲がこれ以上届かないところへ追撃するまで、戦いはレバノンの外には絶対に拡大しない──などという展望は、妄想にすぎないのだ。
最近まではイラクについても、似たような妄想があった。米国はイラク事業を成功させて、ラディカルで新しい「自由」のアジェンダ(テロに強硬姿勢で臨み、テロの原因にも強硬に取り組むという政策方針)を中東地域で追求する──はずだった。
しかし今やイラクは国家として破綻してしまった。イスラム教シーア派とスンニ派の宗派対立で連日100人前後が殺される、闘鶏場のようなところになってしまった。そして、オサマ・ビンラディンが唱える全体主義的聖戦思想にとって、攻撃対象のやたらと多い、かっこうの最前線となってしまったのだ。
・【FT】なぜ中東の炎は鎮火できないのか <中>
新たに権力を握ったイラクのシーア派がいなければ、米国の「自由プロジェクト」はとっくの昔に完全崩壊していただろう。しかしイラクのシーア派は、シーア派の多く住むレバノンがイスラエルによって破壊されつつあることと、そのイスラエルの行動を米国が容認していることに、激怒している。イラクのシーア派過激派指導者モクタダ・サドル師が率いる民兵組織マフディー軍は、ヒズボラをモデルに組織されたもので、米軍が2004年にイラク・ナジャフで大掃討作戦を展開したときには、ヒズボラはマフディー軍と共に米軍と戦っている。それだけにマフディー軍は、レバノンの現状を前に、再び決起したくてウズウズしているのだ。
レバノンでの戦いがエスカレートするシナリオとしてはほかにも、もっとわかりやすいものがある。ヒズボラがこれまでの脅しを実行に移し、長距離ミサイルをイスラエル中心部に撃ち込めば、たちまち戦いは拡大する。戦況がまたたくまに拡大している今の状況からすると、これは避けられない展開のように見える。そして、そんなことになればイスラエルは怒り狂うに決まっているのだ。
イスラエルの連立政権は権力基盤が弱く、イスラエル軍司令部の顔色をうかがわざるを得ない状態にある。そしてイスラエル軍は(ヒズボラに兵士を拉致され)プライドを傷つけられているだけでなく、中東地域における抑止力の弱体化を深く懸念している。そんな状況だけにイスラエル軍にとって、ヒズボラを庇護し支援しているシリアやイランに仕返ししてやろうという誘惑は、とても強いもののはずだ。
ハマスやヒズボラが挑発的に仕掛ける国境紛争が、なぜこうして一気に地域戦争の瀬戸際まで悪化してしまったのか、検証しておくべきだ。重要な原因のひとつは、ブッシュ政権にある。ブッシュ政権は恐ろしいことに、外交的に全く役立たずで、かつ、より良い未来を切り開くためには(イスラエルが)ひたすら砲撃するのが一番だと信じている。このまさに致命的な組み合わせが、今のレバノン情勢を形作った大きな要因のひとつなのだ。
中東における最大の不安定要因──つまりイスラエルとパレスチナの関係──が長くほったらかしにされて腐りかけていたのは何も、イラク統治の大失態に米国がエネルギーをかけすぎたからではない。「パレスチナ国家」をどうするこうするというレトリックはともかくとして、イスラエルはヨルダン川西岸の占領地域や東エルサレムのアラブ人地区の土地を、少しずつ少しずつ、自分たちのものにしてきた。そしてジョージ・W・ブッシュ米国大統領は、これを容認してきたのだ。
中東で展開しているのは、現代で最重要なドラマのひとつだ。しかしアラブ諸国、ムスリム諸国において、米国は信頼を完全に失墜させている。宗教国家イランよりも、民主主義国アメリカの方が危険な国だという結果が、イスラム圏で行われた複数の世論調査から出ている。米調査会社ギャラップによるムスリム動向調査でも、こうした結果が出た。調査の結果、「米国は危険な国」」と答えた回答者のほとんどが敵視しているのは、西側の価値観そのものではなく、米国の政策なのだと明らかになった。ムスリムが米国を敵対視するようになったのは、ブッシュ政権下でおきた三つの出来事が原因だという。
ひとつ目は、2002年4月の出来事。アラブ世界は愕然として衛星テレビを見つめていたのだ。ブッシュ外交のとりはからいによって、イスラエルが西岸地区に再侵攻できるようになり、そしてまだまだ脆弱なパレスチナの政府機関を次々とずたずたにするのを、アラブ世界は暗然と見つめていた(ちなみに、 2006年1月パレスチナ総選挙におけるハマス勝利の下地が、このときに作られたわけだ)。
・【FT】なぜ中東の炎は鎮火できないのか <後>
ふたつ目は2004年4月の出来事。2年前よりさらに大勢のムスリムたちが、テレビを愕然と見つめていた。テレビ画面は二元同時中継で分割されていることもあった。画面の半分には、ファルージャを破壊する米軍が映し出され、もう半分には、ガザ南部ラファを破壊するイスラエル軍が映されていた。イラク・アブグレイブ刑務所における米軍虐待スキャンダルが暴露されたのは、この直後。そしてブッシュ大統領は4月16日、西岸地区の不法入植地にイスラエルがとどまることを認める書簡を、(現在は意識不明状態の)アリエル・シャロンに送ったのだった。アラブ諸国は米国のこの書簡を、「第二のバルフォア宣言」と受け止めた(訳注:「バルフォア宣言」とは1917年に英外相がユダヤ人有力者に対して、パレスチナにおけるユダヤ人国家建設を約束した書簡)。
三つ目の出来事は、現在進行中だ。ブッシュ米大統領とコンドリーザ・ライス米国務長官は、イスラエルの戦争目的実現を「外交」と勘違いしている。中東でかろうじて残っていたかもしれない米国に対する好意的な評価など、砲撃で焼け焦げたベイルート南部やレバノン南部の焦土の下に埋まっている。
今のこの現状について、慎重に考えるべき側面がひとつある。米国および米国と協力関係にあるスンニ派諸国はイラク戦争後、イラン主導でシーア派過激主義が勢力を拡大することに危機感を募らせていた。そしてイスラエルは、この情勢を正確に認識したというわけだ。
イスラエルがレバノン攻撃を開始した当初、エジプトやサウジアラビア、ヨルダンといったスンニ派諸国の政府の間では、一見するとヒズボラが攻撃されている事態を、ひそかに喜ぶ雰囲気さえあった。最初のうちは。サウジアラビア当局者は「正当な抵抗」と「無責任な冒険主義」を混乱してはいけないと戒めていた。サウジ王国の国教ワッハーブ派の聖職者たちは「偶像崇拝的シーア」に同情してはいけないと、信徒たちに説教していた。しかしイスラエルが何のためらいもなくレバノン人の生命や生活を破壊してまわるに至り、事態は完全に一変した。
アラブ諸国の指導者たちは、湾岸やレバント(東地中海沿岸)地域で、イランの影響力が拡大することを恐れてはいるが、実際はそれにも増して、自分たちの国民の反応を恐れているようだ。
米政府ときわめて親しいサウジアラビアのアブドラ国王は2002年、アラブ連盟の首脳会議をまとめ上げ、1967年の第三次中東戦争(六日間戦争)の全占領地返還と引き換えにイスラエルを国家承認するという中東和平案を提案した人物だ。しかし、そのアブドラ国王でさえもがレバノン攻撃を受けて、「永遠に続く忍耐などない」とイスラエルに警告しているのだ。アブドラ国王は言明した。危険がこれほどはっきりとあからさまになり、危険がこれほど高まったことはないと。「イスラエルの傲慢のせいで中東和平が破綻するならば、戦争のほかに選択肢はない」と。