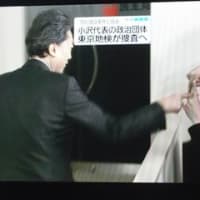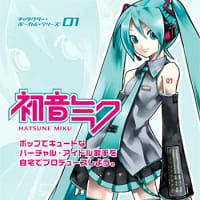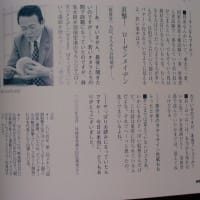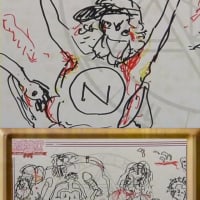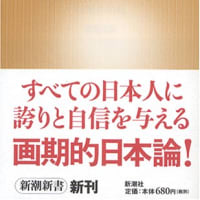私は「ダ・カーポ」をよく読む。
お手軽な情報誌という趣のこの雑誌だが、左派系言論人の連載や寄稿が多いことが特徴。
斎藤貴男氏のコラムも隔週で掲載されている。
その中で稲泉連なる人物の書評が掲載されていた。
私は書評を読むのが好きなのだが、稲泉氏の書評を読んでなんだこりゃと思った。
加藤淑子さんの『ハルビンの詩がきこえる』という作品の書評だったのだけれど、
後半に以下のようなことが書かれていた。
しかし、現在からみれば、満州国は中国侵略のための傀儡国家であり、そこで過ごしたことについて(娘の加藤登紀子があとがきで少し触れているが)、なにか一言あってしかるべきだと思った。
なんと傲慢な書評だろう。
「満州国が中国侵略のための傀儡国家」という歴史認識については敢えて問わない。
私が傲慢だと思ったのは自分の歴史認識、政治主義を加藤淑子さんに押し附けようとしている点だ。
『ハルビンの詩がきこえる』が歴史問題をテーマとした内容であれば、
自己の歴史認識と照らし合わせ、それについての批評も当然ありうる。
が、本作は純粋に満洲での思い出を綴った内容である。
満洲国についての歴史的な意味附けを問う必要は無い。
例えば、稲泉連氏がチベットを旅した紀行文を書いたとしよう。
その内容は純粋にチベットの文化や気候、人々に接して感じた文であるとする。
そして私がその本の書評を書いたとして、
「かつて、チベットは独立国家であった。ところが、中国によって侵略され国は消滅し、多くのチベット人が虐殺された。現在でも弾圧は続いており、そこで過ごしたことについて、なにか一言あってしかるべきだと思った。」
などという一文を書いたとしたらどうだろうか。
氏は自分のしたことを忘れて「それは、別の問題じゃないか」と思うのではなかろうか。
稲泉連の哀しさはどのような本も政治主義抜きに読むことが出来ないということである。
お手軽な情報誌という趣のこの雑誌だが、左派系言論人の連載や寄稿が多いことが特徴。
斎藤貴男氏のコラムも隔週で掲載されている。
その中で稲泉連なる人物の書評が掲載されていた。
私は書評を読むのが好きなのだが、稲泉氏の書評を読んでなんだこりゃと思った。
加藤淑子さんの『ハルビンの詩がきこえる』という作品の書評だったのだけれど、
後半に以下のようなことが書かれていた。
しかし、現在からみれば、満州国は中国侵略のための傀儡国家であり、そこで過ごしたことについて(娘の加藤登紀子があとがきで少し触れているが)、なにか一言あってしかるべきだと思った。
なんと傲慢な書評だろう。
「満州国が中国侵略のための傀儡国家」という歴史認識については敢えて問わない。
私が傲慢だと思ったのは自分の歴史認識、政治主義を加藤淑子さんに押し附けようとしている点だ。
『ハルビンの詩がきこえる』が歴史問題をテーマとした内容であれば、
自己の歴史認識と照らし合わせ、それについての批評も当然ありうる。
が、本作は純粋に満洲での思い出を綴った内容である。
満洲国についての歴史的な意味附けを問う必要は無い。
例えば、稲泉連氏がチベットを旅した紀行文を書いたとしよう。
その内容は純粋にチベットの文化や気候、人々に接して感じた文であるとする。
そして私がその本の書評を書いたとして、
「かつて、チベットは独立国家であった。ところが、中国によって侵略され国は消滅し、多くのチベット人が虐殺された。現在でも弾圧は続いており、そこで過ごしたことについて、なにか一言あってしかるべきだと思った。」
などという一文を書いたとしたらどうだろうか。
氏は自分のしたことを忘れて「それは、別の問題じゃないか」と思うのではなかろうか。
稲泉連の哀しさはどのような本も政治主義抜きに読むことが出来ないということである。