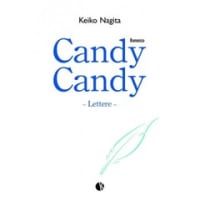キャンディキャンディFinalStoryファンフィクション:水仙の咲く頃
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
第3章
恋に落ちたマクベス
恋に落ちたマクベス
1924年10月27日 ポニーの家にて
親愛なるO.B.
公演旅行への出発前に、この手紙があなたに届くことを願いながら送ります。わたしの出発は11月6日です。あなたはどうやってそんなにいつも旅をしていることに耐えているのかしら? わたしはまだ荷造りも始めていないのにもう家を離れたくないわ。たぶん、あなたもアルバートさんも、いつも忙しく旅をしているのが一番合っているのね。わたしにはとても無理。
アルバートさんと言えば、ちょうどお便りが届いたところです。サンクスギビングには戻ってくるのですって。素敵でしょ? 5ヶ月も出張でいなかったので、会ったらハグをして、どれだけ寂しかったか伝えたくて仕方ありません。今回はもっと長くこちらにいてくれて、一緒に過ごせたらと願っているの。
いずれにせよ、12月まで待たなければならないわね。今は、ポニーの家では冬の準備に大忙しです。今週は、わたしがポニー先生の果樹園からリンゴと洋ナシとアプリコットを収穫してきたので、みんなで冬のための砂糖漬けを作っているところです。レイン先生はお菓子作りになるとたいていイライラしてくるのだけど、ポニー先生は楽しんでいます。二人ともあなたに愛を送っています。
どうぞ、お母様に、わたしはいつでもお母様のことを心に留めていますと伝えてください。お母様は今シーズンは公演旅行に行かれるのかしら? この前アーチーと話をした時、お母様が映画に出るという噂があると聞いたのだけど、それは本当なの?
まとまりがなくなってきたわね。クリスマス前に送るお手紙はこれが最後になります。公演旅行の間、体にはじゅうぶん気をつけてください。それから、ポニー先生のためにあなたがしてくれていることに感謝しています。
かしこ
キャンディ
追伸1
子供たちからはキャンディもパイも取り上げませんからご安心を。わたしのような魔法使いは、いつでも欲しい時に自分でケーキを焼けますの。でも、あなたみたいに人を変な名前で呼び続ける不届き者には、味見をさせてあげません。
追伸2
O.B.はおばかさんの略です。わたしの名前はキャンディスだって何回言えばいいのかしら?

グランド・セントラル駅の途絶えることのない騒音も、今は思考の雑音の方が大きいテリュースには気にならなかった。列車の個室にすでに落ち着き、旅行の日程をもう100回近くも確認して万全に備えていた。そしてもう一度その一分の隙もないブルックスブラザースの背広の上着の袖をあげて腕時計を見た。テリュースにはこの旅の始まりが不安だった。
不安をやわらげようとして、テリュースはグレーのピンストライプの上着とハンブルグ帽を脱ぎ、ドアの近くのフックに掛けてからまた座席に戻った。そうする間に列車が動き出した。テリュースは目を閉じて、この旅の間、すべてのことが期待通りになることをただただ願った。そして反射的な動作で、キャンディから一番最近届いた手紙を入れてあるベストのポケットを触った。
その手紙の一言一言に、テリュースは複雑な感情を経験していた。アルバートさんのことを話している段落を彼の思考が受け入れるまでに、その手紙を何回か読み返さなければならなかった。この数か月間に、キャンディは幾度かの機会にアルバートさんについて言及していた。最初の頃の手紙でキャンディは、二人が学生の頃から知っていた《あのアルバートさん》が、実は彼女の養父だった話をしてくれた。その真実はテリュースにとって衝撃的で、その考えに馴染むまでにはしばらく時間が必要だった。
事実を把握し始めると、キャンディが手紙の中で何度もアルバートさんの名に触れることにも理屈が付いた――しばらくの間は。しかし、止むことのないアルバートさんの話題に、テリュースの忍耐にも次第に限界が来ていた。実際問題として、キャンディとアルバートさんは法的な絆で結ばれているという屹然とした事実があるにも関わらず、晴らすことのできない不安がそこにはあった。
アルバートさんがそれほど年をとっていないことや、キャンディと血がつながっているわけではないという考えが、テリュースの守りを外させなかった。26歳の女性が、アルバートさんのような37歳くらいの独身男性を好きになるのは不思議なことだろうか? テリュースはそれが不可能ではないのを知っていた。実際に、10歳以上も若い女性と結婚する男性は少なくないのだ。
おそらく、キャンディがアルバートさんのことをそれほどの親愛の情を表して手紙に書き続けなければ、このようなことは考えもしなかっただろう。テリュースは、アルバートさんが記憶喪失で苦しんでいた間、キャンディと同居していたことを忘れていなかった。その時は、キャンディもアルバートさんも互いに法的なつながりのある関係であることを知らなかったのだ。その頃に、少なくともアルバートさんの側に、何らかの感情が芽生えた可能性だってある。その上アルバートさんはキャンディが自分と別れた後に彼女のそばにいた。キャンディとその大物実業家の絆がさらに強まったのがその時期であったのは確実だ。この最後の考えは、10年経った今でもテリュースの心を蝕んだ。
しかしながら、この長い年月の間キャンディとアルバートさんの関係が明らかな変化をせずに過ぎていることは、テリュースを勇気づけるありがたい事実だった。それでも……そうであったとしても……もしアルバートさんが忍耐強く、キャンディが大人になり過去を忘れるのを待っているのだとしたらどうだろう? テリュースは、すべての望みが消え失せているとしても、一人の男が一人の女性を何年も愛し続けられることを経験から知っていた。
その時ドアを優しくノックする音がテリュースの考えを中断した。
「どうぞ」 テリュースが言うと50代前半の男性が個室に入ってきた。
「紅茶でございます、グレアム様。角砂糖お一つと、レモンでございますね?」 個室のテーブルに紅茶を置きながらその男性は聞いた。
「それでいいよ、ヘイワード」 テリュースは窓に目をやりながらぼんやりと答えた。
「他になにかございましたでしょうか?」 ヘイワードが訊ねた。
「今は特にないが、ボストンに着く20分前になったらドアをノックしてくれ」
「かしこまりました」 軽くうなずくと、ヘイワードは扉を閉めて出て行った。
10年以上もショービジネスの世界に身を置いてきた結果、テリュースは公演旅行の間に快適に過ごせるだけの権利に浴していた。その一つが個室での旅あり、また一つがアシスタントの手助けであった。テリュースは、実務をこなしてもらうために4年前からマーティン・ヘイワードを雇っていて、その働きぶりには満足していた。イギリス生まれのヘイワードは彼の個人的なアシスタントとして、ホテルの予約、荷物の管理、テリュースが他の団員たちと食事に出かけたくない日の食事の注文、その他必要な手配を取り仕切ってくれていた。テリュースはヘイワードの思慮深く控えめなところが気に入っていた。
ヘイワードが出ていくと、テリュースはさっきと同じ問題についての考えにふけった。
思考は遠くキャンディのいるインディアナへと飛んだ。明日キャンディは名簿の最初の後援者を訪ねるために、インディアナポリス行きの列車に乗るはずだとテリュースは日程を計算した。キャンディに会いたいという願望は日増しに切実になっていた。キャンディは今の年齢でどのようになっているだろうか……と再び自分に問いかけてみた。
テリュースは今でも思い出の中のキャンディの明るい笑顔や、手におえない天然のカールの髪のイメージを大切にしていた。――かつて愛して止まなかった大きな緑の瞳の輝きはいまでもそこにあるだろうか……? 過去数か月の文通の中で、テリュースは何度か写真を送ってほしいと頼もうかと考えたが結局できなかった。キャンディは個人的な事柄については決して手紙に書かなかったし、二人の共通の過去の話題にも触れず、軽い話題に終始していた。そのような状況で写真をリクエストするのはそぐわないと思い諦めたのだ。テリュースはただ、間もなく状況が良い方向に変化すればいいがと願った。

テリュースの列車がボストンに向かう一方で、キャンディは荷造りにとりかかっていた。20日間以上もの旅になるので、何を持って行くのかについて十分に検討する必要があった。頭の中で、まだ詰めなくてはいけない荷物について思考をめぐらせていた。ポニーの家の改修計画、新しい教室や診療所など改修が済んだ部分の写真、後援者に宛てたポニー先生とレイン先生からの手紙、一年を通して撮影された子どもたちの写真、翌年の予算の写し、その他後援者に見せるための諸々の書類などがキャンディの荷物リストの最優先だった。それからポニー先生が作った刺繍や砂糖漬けなどの後援者への贈り物も詰める必要があった。
それだけのものを持ち運ぶので、自分自身の荷物に関しては必要最小限にならざるを得なかったが、キャンディはだてに1920年からこの旅をしているのではなかった。交互に着替えられる洋服をいくつか選び、今回はアニーのサンクスギビングのパーティーを考慮に入れなければならない。
シカゴが旅の最後の訪問先になる。アードレー家とコーンウェル家とブライトン家は最大の後援者だったので、年に一度のご挨拶から外すわけにはいかなかった。ポニーの家のために、キャンディはビジネスと家族の行事を一緒にこなす方法を編み出していた。サンクスギビングのパーティーに出席してアニーを喜ばせ、アルバートさんに会って、それから子どもたちのための寄付を受け取る――これを一度の訪問で済ませてしまうのだ。
ディナーパーティーのことを考えながら、キャンディはクローゼットを開いた。できる限り荷物を軽くしたいという思いはあったが、パーティーに着るものは持って行かなければならない。そのような日に軽装で出かけてアニーを落胆させたくはなかった。キャンディは前月にアニーがキャンディのために買ってきた3着のガウンを見た。その中で最も注意を惹いたのは、足首をかすめるようなアシンメトリーの裾の薄い生地の赤いカクテルドレスだった。赤はいつでもキャンディの一番好きな色だ。直観的にその赤いドレスを取り出そうとしたにも関わらず、キャンディの目がもう一つのガウンをとらえた。
「これは何? スリップなの? それともナイトガウン?」 アニーがそれを最初に見せた時にキャンディは聞いた。
「違うわよ! カクテルドレスよ! わからない?」 むっとした様子でアニーが答えた。
「でもアニー、わたしの下着より裾が短いじゃない!」 キャンディはショックを受けて声高に言った。
「これが来年の流行なのよ、キャンディ」 アニーは辛抱強く説明した。「裾はどんどん短くなっているのよ。誰もが膝下3センチくらいの短いスカートを履くようになるわ。それってスキャンダルじゃないこと?」
「本気で言ってるの?」
「もちろんよ! わたしがいつでもパリからの最新情報に詳しいことは知っているわね」 アニーは得意そうに言った。そういう意味では、アーチーとアニーはおしゃれ好きの夫婦として完璧な組み合わせだった。
キャンディは、シンプルなラインに裁断されたその奇妙なドレスをもう一度見た。丸首に縫い付け飾りがほどこされ、アールデコ調の装飾がついた、袖なしの、体にぴったりした細身のドレスだった。そしてそのドレスは特徴的な裾の長さだけでなく、他の部分でも風変りだった。明るいグレーの絹のような生地の上に、数えきれないほどの銀とグレーと薄緑色のクリスタルのビーズがたれ下がっていたのだ。
「面白い! ドレスと一緒にビーズも動くわ!」 もう一度よく見てからキャンディはクスクスと笑った。
「じゃあ気にいったのね?」 アニーは、キャンディが自分の好みに合う何かを見た時に、いつもその目に光る輝きを見つけて嬉しくなって問いかけた。
「着心地がよさそうよ。ロングスカートの裾につまずいて転ばなくて済むもの。それからこのシンプルさが粋だわ。5歳の男の子みたいに足を見せるのに慣れなければならないとしても、問題にはならないわね」
「このドレスはキャンディのためにあるようなものだって思っていたの」 アニーは喜んでそう言うと、一瞬の沈黙の後にためらいながら付け加えた。「エルロイ大おばさまがいらっしゃるところでは着ないようにするのよ。裾の長さのことではやきもきしているから」
アニーの最後の一言に、キャンディは笑いをこらえきれなかった。
「とっても控えめな表現だわ」 笑いが収まるとキャンディは最後にそう付け加えた。
「違うわよ! カクテルドレスよ! わからない?」 むっとした様子でアニーが答えた。
「でもアニー、わたしの下着より裾が短いじゃない!」 キャンディはショックを受けて声高に言った。
「これが来年の流行なのよ、キャンディ」 アニーは辛抱強く説明した。「裾はどんどん短くなっているのよ。誰もが膝下3センチくらいの短いスカートを履くようになるわ。それってスキャンダルじゃないこと?」
「本気で言ってるの?」
「もちろんよ! わたしがいつでもパリからの最新情報に詳しいことは知っているわね」 アニーは得意そうに言った。そういう意味では、アーチーとアニーはおしゃれ好きの夫婦として完璧な組み合わせだった。
キャンディは、シンプルなラインに裁断されたその奇妙なドレスをもう一度見た。丸首に縫い付け飾りがほどこされ、アールデコ調の装飾がついた、袖なしの、体にぴったりした細身のドレスだった。そしてそのドレスは特徴的な裾の長さだけでなく、他の部分でも風変りだった。明るいグレーの絹のような生地の上に、数えきれないほどの銀とグレーと薄緑色のクリスタルのビーズがたれ下がっていたのだ。
「面白い! ドレスと一緒にビーズも動くわ!」 もう一度よく見てからキャンディはクスクスと笑った。
「じゃあ気にいったのね?」 アニーは、キャンディが自分の好みに合う何かを見た時に、いつもその目に光る輝きを見つけて嬉しくなって問いかけた。
「着心地がよさそうよ。ロングスカートの裾につまずいて転ばなくて済むもの。それからこのシンプルさが粋だわ。5歳の男の子みたいに足を見せるのに慣れなければならないとしても、問題にはならないわね」
「このドレスはキャンディのためにあるようなものだって思っていたの」 アニーは喜んでそう言うと、一瞬の沈黙の後にためらいながら付け加えた。「エルロイ大おばさまがいらっしゃるところでは着ないようにするのよ。裾の長さのことではやきもきしているから」
アニーの最後の一言に、キャンディは笑いをこらえきれなかった。
「とっても控えめな表現だわ」 笑いが収まるとキャンディは最後にそう付け加えた。
キャンディは回想から覚めるとそのドレスをもう一度見た。するといたずらっ子のような笑顔が表情に現れた。もしレイン先生がその顔を見たら、キャンディが何かいたずらを企んでいることがすぐに分かっただろう。
「ねぇ、エルロイ大おばさま」 キャンディは鏡の中の自分に向かって意地悪く話しかけた。「サンクスギビングの日に、じっくり鑑賞できるものはいかが?」
この新たな悪ふざけのことを考えながら、キャンディはそのドレスと、ドレスに合わせてアニーが買ってきたシルバーグレーの甘美な肩掛けを荷物に詰めた。

小山の多い景色が、列車が間もなく目的地に着くことを示していた。11月13日の朝だった。キャンディが旅に出てからもう1週間が経過していて、今はとにかく次の目的地のホテルにたどり着き、シャワーを浴びたかった。
その年のキャンディの予定はぎっしり詰まっていた。最初はポニー先生の幼少時代からの友人のジョーンズ夫妻を訪ねるためにインディアナポリスへと向かった。ジョーンズ夫妻は本屋のチェーンを経営していて、ギディングスさん(夫妻はポニー先生をこう呼んでいた)が孤児院を始めた時からの後援者だった。いつものように夫妻はキャンディを温かく迎え入れ、寛大な寄付をしてくれた。次の訪問先はシンシナティだった。そこでキャンディは聖ヨセフ・ド・ボローの修道女たちを訪ね、レイン先生からの手紙を監督者に届けた。それから何年も前にシカゴの病院でキャンディが担当した年配の銀行家にも会った。以来その男性はポニーの家の忠実な後援者で、今年はこれまで以上の寄付をしてくれた。
キャンディの次の目的地はピッツバーグだった。この街で、キャンディはこれまで面識のなかった人物と会う約束をしていた。その人物はアルバートさんからカーネギー家とのつながりを通して紹介された。今は亡き鋼鉄王、アンドリュー・カーネギーはアルバートさんの祖父と同じようにスコットランドからの移民だった。カーネギー氏とアルバートさんの祖父のアードレー氏は、彼らがまだ成功を収める前にアメリカへの旅の途中で出会い、二人の友情はアードレー氏が亡くなるまで続いた。カーネギー氏は5年前に亡くなったが、未亡人となったルイーズ・カーネギー夫人は慈善活動に精力的に参加していたのだ。キャンディは、その未亡人の心が動いて、ポニーの家に寛大な寄付をしてくれることを期待していた。すべてが予定通りに進めば、キャンディはその日の午後早くにカーネギー夫人と昼食を共にしているはずだ。
田舎の景色が少しずつ都市の郊外の景色へと変わっていった。空はどんよりしていて、雨が降りそうな気配だった。キャンディは右手にはめていた手袋を外し、気温を確かめるために窓に触れた。気温は7度くらいだと確認すると、キャンディはカーネギー夫人に会う前に温かいお風呂に入る必要があると考えた。良い印象を与えるために、午後までにしゃんとしておきたかったのだ。
列車が人口密度の多い地域へと入ると、キャンディは街を分断している2本の川の印象に驚いた。中央の3角形の土地に、他の都市部から何本もの橋が架かっていた。列車はその橋の一つの上を走り、間もなくペンシルバニア駅に到着する。
列車から降りた時、時刻は9時30分だった。キャンディは、まるでその朝ピッツバーグ中の人がそこに集まっているかのような人混みを通り抜けるのに苦労した。キャンディの荷物を運んでいるポーターは、この混雑について何のコメントもしなかったので、この混乱はここでは平常のことなのだと理解した。
間もなくタクシーに乗ると、キャンディはルネッサンス・ピッツバーグ・ホテルへと向かった。ポニーの家はアルバートさんとアーチーの寄付だけに頼るべきでないとキャンディが決めた時、アルバートさんは一つの妥協案を示した。キャンディの決断を尊重する代わりに、寄付金集めのための旅費はアルバートさんが出すことを受け入れるというものだ。そのことに関してこの大実業家は断固としていたので、キャンディに選択肢はなかった。そのためキャンディは旅を通して高級ホテルで甘やかされることとなった。たいていの場合、後援者やその人たちが住む街に詳しいポニー先生が宿泊先を提案し、ジョルジュが数か月前から予約をすることになっていた。しかし、ルネッサンス・ピッツバーグ・ホテルの大きなロビーを見た時キャンディは、こんな豪華な宿泊先を選ぶとは、今度ばかりはポニー先生もやり過ぎだと思った。
どうやって建築されたのかと不思議に思わずにいられない大きなガラスのドームからは朝日が差し込んでいた。ドームの下では堂々たる大理石の階段が、この場所は贅沢とは何かを知っている者のために建てられたのだと主張していた。悪いことに、ホテルのコンシェルジュがアードレーという名前にふさわしいと思われる仰々しい礼儀作法でキャンディを迎えたが、これはいつものことだった。
キャンディは内心ため息をついた。アードレー家の一員であればそのような状況は避けられないことは、もうずっと前からわかってはいた。ポニーの家でどれだけ慎み深い生活を送っていようが、街に来れば社会的に重要な女性として扱われるのだ。そのような考えにはいつも居心地の悪さを感じたが、心の平静のためにはそれを受け入れて生きていくしかないのだ。
部屋に一人になりあたりを見回すと、キャンディの目はきれいなフルーツの盛り合わせのバスケットにぶつかった。バスケットの上に置かれたカーネギー夫人からのカードを読んでキャンディは嬉しくなった。夫人の思いやりに喜びアプリコットを掴んでおいしそうにかじりつくと、すっぱくて甘い味が口を潤した。それからキャンディは部屋の点検を始めた。
ベッドの近くには2つの大きな窓があった。薄いカーテンが開いていたのでキャンディは窓ガラスを通して街を見下ろした。何台かの車がちょうどホテルの前に止まり、大勢の人が入り口を埋め尽くしているようだった。
「まぁ! 忙しい街ね! シカゴでも人がいっぱいだと思っていたのに!」 キャンディは窓を離れて浴室に向かいながら無頓着に言った。

11時30分にはキャンディは大理石の階段をロビーへと降りていた。上質なキャバリーツイルで仕立てられたふじ色のドレスを着ていた。そのなめらかで格好の良い首には黒い絹のスカーフが巻かれ、同色のコートとクロッシェ帽子が外見をこぎれいにまとめていた。受付に鍵を預けると、約束の場所へとタクシーで向かった。
キャンディがホテルを出てすぐに、眼鏡をかけ、仕立ての良いビジネススーツに身を包んだ中年の男性が受付に近づいてきた。
「今の方はアードレー嬢ですか?」 眼鏡の男性が聞いた。
「左様でございます」 従業員が形式的に答えた。
「お部屋は何号室ですか?」 男性が5ドル札紙幣をそっと手渡しながら再び聞くと、その受付は急にはきはきと話し始めた。
「178号室でございますが、午後遅くまでは戻られないご予定です」
「完璧だ。ありがとう」
他には何も言わずに後ろを向くと、その男性は自分の部屋へと大理石の階段を上って行った。

*引用の範囲を超えた当サイトのコンテンツの無断転載はお断りいたします