
【Tokyo-k】雨は降り続いている。瀬戸内の海を眺めて来た者には、雨の日本海はことのほか暗い。仙崎の街を離れ、仙崎湾を東へ回り込むと、山陰本線の長門三隅駅が現れて、香月泰男(1911-1974)が生まれた三隅町(現・長門市三隅)に入ったと知れる。湯免温泉という小さな温泉郷があって、香月泰男美術館はその一角にある。東京で絵を学び、戦争に駆り出され、シベリアに抑留された香月が、「ここが<私の>地球だ」と生きた地である。

この画家の作品に本格的に触れたのは、没後30年展が東京で開催された2004年のことである。それほどに縁遠かった画家だが、痩せこけた死者の顔で埋まるシベリア抑留の記憶を描いた作品群に、それはもう、言い様もない衝撃を受けたのだった。以来、もっとこの画家を知りたいと、代表作のシベリアシリーズ観たさに山口市の県立美術館に出かけたこともある。今回は郷里に建てられた香月個人のための美術館に立ち寄ったのである。

美術館は、彼の作品から想像していたように暗くも重々しくもなく、白い瀟洒なデザインに雨に濡れる桜が寄り添って、静かである。壁面には抑留者の顔が浮かぶが、彼らさえ、今や安住の地に収まっているかのようである。シベリアシリーズは県に寄贈され山口市で展示されているため、代表作が欠けている物足りなさはあるけれど、戦争とは無縁の作品を通じて画家の人となりを知るには、こちらの美術館がふさわしいかもしれない。

興味深かったのは復元されたアトリエである。制作の合間の気分転換だったのだろうか、画家はブリキの人物像など、様々な造形を楽しんで作っている。大きなものは中庭にも展示されていて、戦争の理不尽と悲惨を全身に強いられた人間が、やがて色彩を思い出し、軽やかな感覚を取り戻して蘇って行く過程が窺えるような展示である。どれほどの辛酸を舐めたのか、戦後生まれの私に分かりようがないけれど、晩年の穏やかさは分かる。
 (横山操「茜」1963年)
(横山操「茜」1963年)
同じようにシベリア抑留を体験した同世代の画家に横山操(1920-1973)がいる。香月が三隅、横山が越後・蒲原平野と、共に日本海の風土の中で育った二人は、医科の家生まれという共通項もある。さらに父母の温もりの乏しい人生を生きたということも奇妙に似ている。画法が油と日本画と異なる道へ進んだ二人だが、敗戦とともにソ連軍の捕虜となり、香月はアチンスクに2年間、横山はカラガンダで5年間の収容所生活を送る。
 (香月泰男「北へ西へ」1959年)
(香月泰男「北へ西へ」1959年)
創作者はその魂が作品に現れるものだから、これだけ類似の多い二人を、人間研究といった観点から比較したい誘惑に駆られる。復員後、死相漂うシベリアシリーズに没入した後、香月はその土色で深い内省的世界を描くようになる。横山は戦後の日本に体当たりし、画布に黒を叩き付け続ける。香月が雪の朝の静寂に向かう一方で、横山の吹雪の夜は明ける兆しがない。帰る地があった香月と、郷里を棄てさせられた横山の違いだろうか。
 (香月泰男「愛情」1971年)
(香月泰男「愛情」1971年)
香月が母校の小学校に依頼されて制作した壁画は、穏やかな生の歓びに満ちている。だが横山が描く蒲原のハザ木は、枝に触れたら手が刺し通されそうである。この画家の胸の内には、いつも怒りがあったのだろうか。彼がアトリエを置いた街で、私もいま暮らしている。共に蒲原で生まれた者が、同じ街で死んで行くのだろう。幸い私は怒っていない。香月の「<私の>地球」という不思議な絵を見上げ、いろんなことを考えた。(2015.4.1)
 (香月泰男「<私の>地球」1968年)
(香月泰男「<私の>地球」1968年)
 (香月泰男「母子)1969年)
(香月泰男「母子)1969年)
 (香月泰男「雪の朝」1974年)
(香月泰男「雪の朝」1974年)

この画家の作品に本格的に触れたのは、没後30年展が東京で開催された2004年のことである。それほどに縁遠かった画家だが、痩せこけた死者の顔で埋まるシベリア抑留の記憶を描いた作品群に、それはもう、言い様もない衝撃を受けたのだった。以来、もっとこの画家を知りたいと、代表作のシベリアシリーズ観たさに山口市の県立美術館に出かけたこともある。今回は郷里に建てられた香月個人のための美術館に立ち寄ったのである。

美術館は、彼の作品から想像していたように暗くも重々しくもなく、白い瀟洒なデザインに雨に濡れる桜が寄り添って、静かである。壁面には抑留者の顔が浮かぶが、彼らさえ、今や安住の地に収まっているかのようである。シベリアシリーズは県に寄贈され山口市で展示されているため、代表作が欠けている物足りなさはあるけれど、戦争とは無縁の作品を通じて画家の人となりを知るには、こちらの美術館がふさわしいかもしれない。

興味深かったのは復元されたアトリエである。制作の合間の気分転換だったのだろうか、画家はブリキの人物像など、様々な造形を楽しんで作っている。大きなものは中庭にも展示されていて、戦争の理不尽と悲惨を全身に強いられた人間が、やがて色彩を思い出し、軽やかな感覚を取り戻して蘇って行く過程が窺えるような展示である。どれほどの辛酸を舐めたのか、戦後生まれの私に分かりようがないけれど、晩年の穏やかさは分かる。
 (横山操「茜」1963年)
(横山操「茜」1963年)同じようにシベリア抑留を体験した同世代の画家に横山操(1920-1973)がいる。香月が三隅、横山が越後・蒲原平野と、共に日本海の風土の中で育った二人は、医科の家生まれという共通項もある。さらに父母の温もりの乏しい人生を生きたということも奇妙に似ている。画法が油と日本画と異なる道へ進んだ二人だが、敗戦とともにソ連軍の捕虜となり、香月はアチンスクに2年間、横山はカラガンダで5年間の収容所生活を送る。
 (香月泰男「北へ西へ」1959年)
(香月泰男「北へ西へ」1959年)創作者はその魂が作品に現れるものだから、これだけ類似の多い二人を、人間研究といった観点から比較したい誘惑に駆られる。復員後、死相漂うシベリアシリーズに没入した後、香月はその土色で深い内省的世界を描くようになる。横山は戦後の日本に体当たりし、画布に黒を叩き付け続ける。香月が雪の朝の静寂に向かう一方で、横山の吹雪の夜は明ける兆しがない。帰る地があった香月と、郷里を棄てさせられた横山の違いだろうか。
 (香月泰男「愛情」1971年)
(香月泰男「愛情」1971年) 香月が母校の小学校に依頼されて制作した壁画は、穏やかな生の歓びに満ちている。だが横山が描く蒲原のハザ木は、枝に触れたら手が刺し通されそうである。この画家の胸の内には、いつも怒りがあったのだろうか。彼がアトリエを置いた街で、私もいま暮らしている。共に蒲原で生まれた者が、同じ街で死んで行くのだろう。幸い私は怒っていない。香月の「<私の>地球」という不思議な絵を見上げ、いろんなことを考えた。(2015.4.1)
 (香月泰男「<私の>地球」1968年)
(香月泰男「<私の>地球」1968年) (香月泰男「母子)1969年)
(香月泰男「母子)1969年) (香月泰男「雪の朝」1974年)
(香月泰男「雪の朝」1974年)









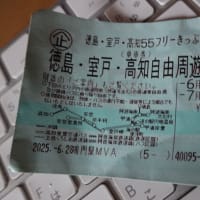



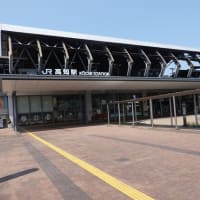










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます