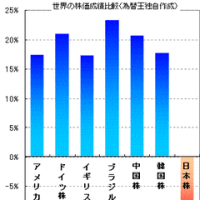竹内氏と知り合いの老齢の学者が、本書を読んで「この本は書かれるべきではなかったのです」と憤慨していたと、人から伝え聞いた。その人の甲高い口調を思い出して、すこし笑ってしまった。それだけ信奉者を怒らせるのだから、一読の価値はありそうだと思って読んでみた。戦後の言論界における丸山の位置と言説戦略が、戦前の帝大粛正講演会あたりから始めて、豊富な周辺的資料を駆使して活写されている。評者のように、理系畑で、丸山に興味のなかった人間にも、丸山がなぜ偉いと思われていたのかが、よく分かった。
丸山が言論界で注目を集めたのは、日本敗戦の翌年の1946年に発表した「超国家主義の論理と心理」だったらしい。この論文では、戦前の日本を西欧の国家主義とはことなる超国家主義として、法的権力と倫理、公と私の別が曖昧で、責任を持った主体としての個が未確立なまま、超国家主義に陥ったものとして位置づけているとの事だ。晩年には、執拗な持続低音としての日本的土着的なものをいったらしい。西欧の社会論理を基準に、そこからの逸脱、偏差として問題となる日本的なるものを執拗に追求している。社会設計主義への認識論的反省と伝統の役割の認識が欠如し、社会主義の可能性を信じ続けていたらしいので、進歩的文化人の元祖みたいな存在だったのだろう。
本書では、丸山が言論界におけるポジションをいかに確保してきたかが、ブルデューの文化資本の考えを援用して分析されている。丸山は東大の法学部教授で、文学部的な歴史研究を行っている。法学部(国家の行政機構や経済などの権力とのつながり)と文学部(文化資産の本丸)のおいしいところに絡んでいる。また、アカデミーに属しながら、ジャーナリズムでも雑誌を選んで、ときたまに影響力のある論文を出す。批判は高みにあるかのように黙殺する。敵対する在野の研究者とのいやらしいやりとも紹介されている。丸山の絶妙のポジショニングぶりが、豊富な周辺的資料を用いて、竹内氏らしく客観的、かつ信奉者から見たら意地悪に描き出されている。
丸山のたこつぼ型、ささら型、執拗な持続低音などの比喩は、ややアバウトな標語にすぎない印象をうける。西欧の社会論理を基準に、そこからの逸脱、偏差として日本を捉えようとするアプローチも、純日本的なのを言うのと同じく、ローカルな論理でしかない。梅棹の文明の生態史観や宗教疫学はアナロジーとしてより発展性があるし(宗教疫学についてはスペルベルの文化疫学など)、特定の地域の社会論理を基準にするのではない、より普遍的な社会科学の方向にあると思う。
本書には、次のようなエピソードが紹介されている。「丸山は師南原繁によって、今の国粋主義系の日本精神論を超克するような「科学的な」日本の伝統思想の研究を要請された。日本思想の論文であっても、注の半分が外国の学者の論文であるように、という無茶な言い方もされていたが、このいい方で、南原の言う「科学的」が、西欧の学問や分析理論をもとにした日本思想論であることがわかる。」(p.94)
ここで言う科学は、西欧の学問程度の意味で、仮説検証としての科学とは何の関係もない。実際、丸山は論文のまくらにヘーゲルを使ったりしていたようだ。国家の品格の著者で数学者の藤原氏が言うように、いくら精緻に概念体系が組み立てられていても、その説が人間社会に適合するか否かはわからない。哲学として思考の世界だけにとどまっていれば良いが、社会に適用されるなら、それは、ある種の社会神学として機能する。マヤの神官達が独自の宇宙論に基づいて社会に宣託を下すようなものだ。社会神学としての社会主義などは、精緻で雄大な学問体系だったが、それが現実の社会に適用されたとき何が生じたのか。我々は、数千万人の犠牲者とともに、その答えを知っている。社会科学の多くの領域では、まだ学説の輸入と言説の巧みさ程度で、学問的権威を維持できるようだ。その学問的権威とともにその教説が、実施にうつされると、社会神学として、社会に害をなすこともある。法と文、アカデミズムとジャーナリズムの間で影響力を駆使した丸山型の知識人の時代が過ぎた今日でも、社会神学の司祭達の時代はまだ過ぎていない
丸山が言論界で注目を集めたのは、日本敗戦の翌年の1946年に発表した「超国家主義の論理と心理」だったらしい。この論文では、戦前の日本を西欧の国家主義とはことなる超国家主義として、法的権力と倫理、公と私の別が曖昧で、責任を持った主体としての個が未確立なまま、超国家主義に陥ったものとして位置づけているとの事だ。晩年には、執拗な持続低音としての日本的土着的なものをいったらしい。西欧の社会論理を基準に、そこからの逸脱、偏差として問題となる日本的なるものを執拗に追求している。社会設計主義への認識論的反省と伝統の役割の認識が欠如し、社会主義の可能性を信じ続けていたらしいので、進歩的文化人の元祖みたいな存在だったのだろう。
本書では、丸山が言論界におけるポジションをいかに確保してきたかが、ブルデューの文化資本の考えを援用して分析されている。丸山は東大の法学部教授で、文学部的な歴史研究を行っている。法学部(国家の行政機構や経済などの権力とのつながり)と文学部(文化資産の本丸)のおいしいところに絡んでいる。また、アカデミーに属しながら、ジャーナリズムでも雑誌を選んで、ときたまに影響力のある論文を出す。批判は高みにあるかのように黙殺する。敵対する在野の研究者とのいやらしいやりとも紹介されている。丸山の絶妙のポジショニングぶりが、豊富な周辺的資料を用いて、竹内氏らしく客観的、かつ信奉者から見たら意地悪に描き出されている。
丸山のたこつぼ型、ささら型、執拗な持続低音などの比喩は、ややアバウトな標語にすぎない印象をうける。西欧の社会論理を基準に、そこからの逸脱、偏差として日本を捉えようとするアプローチも、純日本的なのを言うのと同じく、ローカルな論理でしかない。梅棹の文明の生態史観や宗教疫学はアナロジーとしてより発展性があるし(宗教疫学についてはスペルベルの文化疫学など)、特定の地域の社会論理を基準にするのではない、より普遍的な社会科学の方向にあると思う。
本書には、次のようなエピソードが紹介されている。「丸山は師南原繁によって、今の国粋主義系の日本精神論を超克するような「科学的な」日本の伝統思想の研究を要請された。日本思想の論文であっても、注の半分が外国の学者の論文であるように、という無茶な言い方もされていたが、このいい方で、南原の言う「科学的」が、西欧の学問や分析理論をもとにした日本思想論であることがわかる。」(p.94)
ここで言う科学は、西欧の学問程度の意味で、仮説検証としての科学とは何の関係もない。実際、丸山は論文のまくらにヘーゲルを使ったりしていたようだ。国家の品格の著者で数学者の藤原氏が言うように、いくら精緻に概念体系が組み立てられていても、その説が人間社会に適合するか否かはわからない。哲学として思考の世界だけにとどまっていれば良いが、社会に適用されるなら、それは、ある種の社会神学として機能する。マヤの神官達が独自の宇宙論に基づいて社会に宣託を下すようなものだ。社会神学としての社会主義などは、精緻で雄大な学問体系だったが、それが現実の社会に適用されたとき何が生じたのか。我々は、数千万人の犠牲者とともに、その答えを知っている。社会科学の多くの領域では、まだ学説の輸入と言説の巧みさ程度で、学問的権威を維持できるようだ。その学問的権威とともにその教説が、実施にうつされると、社会神学として、社会に害をなすこともある。法と文、アカデミズムとジャーナリズムの間で影響力を駆使した丸山型の知識人の時代が過ぎた今日でも、社会神学の司祭達の時代はまだ過ぎていない