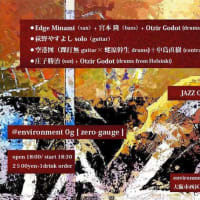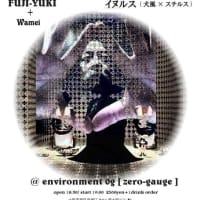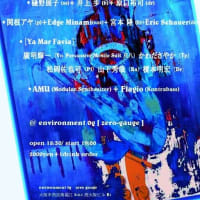音楽ファンとは困ったもので、好みでない音楽が耳に入るとそれは人一倍、苦痛となる。実際、私は知人の運転する車で日本のダンスホールレゲエを30分ほど聞かされた時、真剣に頭痛がしたし、スポーツクラブでボディバンプに参加した時もインストラクターがかけた大音量の「アイオブザタイガー」に我慢できず、すぐスタジオを出てしまった。音楽ファンは‘聞き流す’という事ができない。実に困ったものである。
ディスコが消滅し、クラブが定着するのは90年代初頭であったと思うが、いずれにしてもその密閉された空間で、DJという他人が選曲する音楽を聴かされる事にさほど苦痛を感じなかったのは何故か。もっともディスコ時代によく行ったのはソウル/ファンク系か、今思えばクラブのハシリだったニューウェーブ系のPALMSだけであり、間違ってもユーロビートなんかのハコには‘音楽以外の目的の時’しか行かなかったが。
クラブがより‘音楽’をメインとした場として成立したのは、やはりリミックスという‘創造’と一体であったからだろう。そこではダサいビージーズ等のベースパターンだけを生かしながらキックで2ビートを強調し、細切れになったボイスやシンセのメロが、ミニマルのように再生される事で、原曲が見事にカッコ良く変容されるマジックを体験できたし、ビバップにファンクベースをかぶせる事でダンスミュージック化したジャズの本来は楽曲の決定要素であったホーンによるテーマが単なる音響装飾音として分散されるような感覚も発見できた。それらの例が示すのは原曲を構成する諸要素を解体、交換する事で新たな音楽/ダンスの快楽を即興的に生み出す面白さであろう。
かつてディスコでは曲によってフロアに出るか、引っ込むかという明確な選択を余儀なくされていた。Pファンクやザップで飛び出して、アースやクール&ギャングでは「あーあ」と引き下がるという具合に。原曲がそのままプレイされるという事は音に拘らない客はともかく、我々、偏屈な‘音楽ファン’は曲毎に反応を変えざるを得ないという分断があったのだ。しかし、クラブではそれがなくなった。
クラブでは曲の連続感、その非境界性が実現され、あるセンスの元に統一された音楽空間があった。この新種の快楽はダンス自体の‘型’も溶解させ、それが単なる‘体の揺れ’に至る自由性の獲得として開放されたと思っている。ディスコに残存した‘曲=歌’としての要素が‘曲=リズム’に変容する事で、音楽と身体の開放性が増したようにも感じられた。
しかし。
それでも、私がクラブミュージックに対するある種、中庸的な感覚を払拭できなかったのは、リミックスによる原曲の再生と共に原型のパワーも同時に溶解するその‘レベル化’の感触故であったか。思えばディスコに於けるPファンクやザップに対する狂喜とクール&ギャング対するブーイングは両方共に‘極端’であるという事で実は一致していた。思い入れや嫌悪感という相反する感情移入の‘濃さ’が双方に存在していたのに対し、クラブでの音楽処理がいかにも、‘適度’なカッコ良さやスタイリッシュに満ち、無難であるという感覚から逃れる事はできなかったと思う。JBをリミックスしてもJBを超える事は絶対できないというジレンマとそれを了解事項とした遊戯感覚より‘創造性’こそを好むという‘音楽ファン’特有の旧体質はやはり、原曲こそへ向かうという性から逃れられないという事か。
デトロイトシーンの異端児、ムーディマンの『black mahogani』(04)、『black mahoganiⅡ』(04)はどろっとしたブラックミュージックの力が漲っており、JBをリミックスしながらJBを超える如きサウンドの攻撃性を有していた。私にとっては衝撃的なサウンドであり、オリジネイターの‘創造性’への狂喜と同等の感動を得た作品であった。そのムーディマンの2nd『Mahogany Brown』(98)が再発された。長く廃盤だったもので私は未聴。故に‘デト系再発にしては安い!’というタワーレコードの店頭に見つけたコピーに誘われるまでもなく、即、買いである。一曲目の「radio」ではブラック専門チャンネルから様々な名曲の断片が飛び出し、ムーディマンによる先達への畏敬の念に満ちた音楽世界が幕を開ける。全編に渡る高揚感はもはや、オリジナル/サンプリングという枠を超えるブラックミュージック通史の中心に到達する濃厚なハイサウンド。やはり感動。そして脱帽。
アルバムラスト「black sunday」での10分以上に及ぶボイスとシャウトとスクリーミンの応酬に、恐怖感と表裏一体となるようなブラックミュージックのグルーブの神髄を視る。ここで聴けるのはジェームスジェマーソンのベースプレイの神業のような運動と同等の労力がDJ/サンプリングアーティストにも求められ、その必要性を通過した後にクリエイトされる音楽の充実度の発見である。‘レベル化’に収まらない感情移入を表現したからこそ素晴らしい。もっとも、このような屁理屈を必要とする‘音楽ファン’とはやはり、 困ったものであると言えるかもしれないが。
2009.3.30