「ブラックアウト/オールクリア」が面白かったため入手しました。
Amazonで新品購入。

本書はオックスフォード大学史学部シリーズの始まりとなっている標題作はじめ、ヒューゴー賞・ネピュラ賞を受賞した短編を集めた作品集です。
原書は“The Best of Connie wiliis:Award-Winning Stories”(全10編)として一冊で出されているものが2分冊となり本書と「混沌ホテル」としなっています。
(「混沌ホテル」の方を前に入手していたのですが、史学部シリーズ流れでこちらから読みました)
分冊にあたり原書とは構成を変え本書「空襲警報」はシリアスなもの5編「混沌ホテル」はコメディタッチのもの5編収録となっています。
「空襲警報」は「見張り」のタイトル(高林慧子訳)でウィリスの第一短編集「わが愛しき娘たちよ」に収載されていたものを改題し、大森望氏の新訳となっています。
「オールクリア」=空襲警報解除の対語として「空襲警報」としたようです。
各編末にアシモフばりの自作へのコメント入り、巻末にウィリスのSF大会でのスピーチも収載されておりこちらも楽しめます。
内容紹介(裏表紙記載)
オックスフォード大学史学部の大学院生は、時間遡行技術を使って研究する時代に赴き、各々観察実習を行っていた。第二次大戦の大空襲下のセントポール大聖堂で、火災監視をすることになったぼくは……史学部シリーズ開幕篇の表題作を、新訳で収録。短篇集初収録作「ナイルに死す」、終末SFの傑作「最後のウィネベーゴ」ほか、ウィリスのシリアス系短篇から、ヒューゴー賞/ネビュラ賞受賞作のみ全5篇を収録した傑作選。
読後の感想としては、なにせ「ベスト・オブ・コニー・ウィリス」ですからかなりのものを期待していたのですが...。
「それほどでなはいかなぁ…」と感じました。
私が合わないのか…ウィリスが長編向けの作家なのか...。
「SF」短編集としての出来はアシモフの「変化の風」の方が上と感じました。
各編紹介と感想
○クリアリー家からの手紙 A Lettrer from the Clearys 1982年7月
1983年ネピュラ賞-ショート・ストーリー
ロッキー山脈の山間部の田舎町に住む少女は郵便局で見つけたクリアリー家からの手紙を持ち帰り家族の前で読み始めるが….。
「混沌ホテル」収載の著者の序文によるとウォード・ムーアの「ロト」に触発されて書いたとのこと。(終末テーマ)
冒頭ののどかな描写から一転しての緊迫した感じがよく出ているのですが...着想・展開とも型にはまりすぎているような気がしました….。
「SF」ならではの仕掛けも感じられずでどうも作品に入っていけませんでした。
訳者あとがきでは「信頼できない語り手」によるストーリーをよく味わう作品のようですが…。
○空襲警報 Fire Watch 1982年2月
1983年ヒューゴー賞・ネピュラ賞・SFクロニカル賞
オックスフォード大学史学部の学生バーソロミューは時間遡行した実習で第二次大戦下のセント・ポール大聖堂で空襲監視をすることになるが….。
本作が史学部シリーズ第一作なのですが設定は「ドゥームズデイ・ブック」の後となっています。
「ドゥームズデイ・ブック」の主人公ギヴリンが本作の主人公バーソロミューのルームメイトとして登場おり、すでに中世への時間遡行済な設定です。
シリーズを貫くテーマ的なものがすでに出ているですが、なんだか骨組みだけ見させられているような気になってしましました。
「ブラックアウト/オールクリア」の感想でも書きましたが、作中バーソロミューをセント・ポール大聖堂で探し求める場面が出てくるのでその場面での対比が楽しめます。
猫が絶滅しているということは「犬は勘定に入れません」の方で詳しく語られますがその辺もこの第一作から触れられているので設定済だったというようなこともわかります。
ただちょっと本作の描写、全体的に薄めなので期待して読んだ割には...というところはありました。
○マーブル・アーチの風 The Winds of Marble Arch 1999年10月,11月
2000年ヒューゴー賞
20年ぶりに夫婦でロンドンの大会(SF大会?)に訪れ、地下鉄に乗った主人公は正体不明の風に出会い...。
ウィリス54歳の作品ということでしのびよる「老い」と去りゆく「若さ」を郷愁でつつんで描いています。
「ブラックアウト/オールクリア」でも多く出てくるロンドンの地下鉄が出てきています、ウィリスのコメントによるとロンドンで一番のお気に入りはセント・ポール大聖堂で2番目は地下鉄のネットワーク全体とのこと。
独特の雰因気は楽しめましたが、ほぼ「SFではない」のでSFとして評価するとどうかなぁと思う作品ですね。
○ナイルに死すDeath on the Nille 1993年3月
1994年ヒューゴー賞・SFクロニカル賞-ショート・ストーリー
エジプト行きの飛行機に乗りナイルへ向かうツアーの一行は…。
これもSFではなくホラーという感じの作品。
初期の筒井康隆(60年代?)の短編にありそうな話だなーという感想でした。
ありきたりなツアーが徐々に異世界に引きずりこまれていく感じと、女性の描き方ウィリスならではと感心しました。。
「死後の世界」という意味では後の「航路」につながってくるのかもしれません。
○最後のウィネベーゴ The Last of the Winnebagos 1988年7月
1989年ヒューゴー賞・ネピュラ賞・SFクロニカル賞・アシモフ誌読者賞
犬が絶滅し世界がゆっくり下り坂に向かっているらしい近未来、ウィネベーゴを取材するカメラマン=記者は….。
訳者あとがきで「ウィリスの中短編の中でも小説としての出来栄えではたぶんこれがベストであろう」と書かれています。
確かに「?」な設定で年代も時折遡ったりして描かれるストーリーはなんとも巧みです。
「ラストどうなってしまうのかなぁ」と思いましたがすべての伏線を回収して見事に解決する手腕には舌を巻きました。
全体的に去りゆく者への郷愁漂い雰因気は感じたのですが…。
本書全体に言えることですがSFならではの「とんでもない」状況やら道具立てのない話が多かった気がします。
だからといって小説的にどうなのかというと私的にはそれほど入り込めませんでした。
ウィリスが長編向きなのか私との相性の問題なのかは???です。
作品的には「最後のウィネベーゴ」が一番楽しめましたが、「ウィネベーゴ」自体がいかにもアメリカなものなのが象徴的であくまで「アメリカン」な郷愁なのでそこが戸惑うところではありました。
〈付録〉
〇二〇〇六年世界SF大会ゲスト・オブ・オナー・スピーチ
〇グランド・マスター賞受賞スピーチ予備原稿
〇グランド・マスター賞受賞スピーチ
ウィリスはスピーチの名手でもあるそうです。
少女時代からどのような作品を読んできたのか等わかり楽しめました。
特に「ハインライン」に感謝していましたがアメリカ人にとって「ハインライン」それもジュブナイル作品は大きな影響があったんでしょうね。
↓SF的仕掛けがどうした!という方もその他の方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
Amazonで新品購入。

本書はオックスフォード大学史学部シリーズの始まりとなっている標題作はじめ、ヒューゴー賞・ネピュラ賞を受賞した短編を集めた作品集です。
原書は“The Best of Connie wiliis:Award-Winning Stories”(全10編)として一冊で出されているものが2分冊となり本書と「混沌ホテル」としなっています。
(「混沌ホテル」の方を前に入手していたのですが、史学部シリーズ流れでこちらから読みました)
分冊にあたり原書とは構成を変え本書「空襲警報」はシリアスなもの5編「混沌ホテル」はコメディタッチのもの5編収録となっています。
「空襲警報」は「見張り」のタイトル(高林慧子訳)でウィリスの第一短編集「わが愛しき娘たちよ」に収載されていたものを改題し、大森望氏の新訳となっています。
「オールクリア」=空襲警報解除の対語として「空襲警報」としたようです。
各編末にアシモフばりの自作へのコメント入り、巻末にウィリスのSF大会でのスピーチも収載されておりこちらも楽しめます。
内容紹介(裏表紙記載)
オックスフォード大学史学部の大学院生は、時間遡行技術を使って研究する時代に赴き、各々観察実習を行っていた。第二次大戦の大空襲下のセントポール大聖堂で、火災監視をすることになったぼくは……史学部シリーズ開幕篇の表題作を、新訳で収録。短篇集初収録作「ナイルに死す」、終末SFの傑作「最後のウィネベーゴ」ほか、ウィリスのシリアス系短篇から、ヒューゴー賞/ネビュラ賞受賞作のみ全5篇を収録した傑作選。
読後の感想としては、なにせ「ベスト・オブ・コニー・ウィリス」ですからかなりのものを期待していたのですが...。
「それほどでなはいかなぁ…」と感じました。
私が合わないのか…ウィリスが長編向けの作家なのか...。
「SF」短編集としての出来はアシモフの「変化の風」の方が上と感じました。
各編紹介と感想
○クリアリー家からの手紙 A Lettrer from the Clearys 1982年7月
1983年ネピュラ賞-ショート・ストーリー
ロッキー山脈の山間部の田舎町に住む少女は郵便局で見つけたクリアリー家からの手紙を持ち帰り家族の前で読み始めるが….。
「混沌ホテル」収載の著者の序文によるとウォード・ムーアの「ロト」に触発されて書いたとのこと。(終末テーマ)
冒頭ののどかな描写から一転しての緊迫した感じがよく出ているのですが...着想・展開とも型にはまりすぎているような気がしました….。
「SF」ならではの仕掛けも感じられずでどうも作品に入っていけませんでした。
訳者あとがきでは「信頼できない語り手」によるストーリーをよく味わう作品のようですが…。
○空襲警報 Fire Watch 1982年2月
1983年ヒューゴー賞・ネピュラ賞・SFクロニカル賞
オックスフォード大学史学部の学生バーソロミューは時間遡行した実習で第二次大戦下のセント・ポール大聖堂で空襲監視をすることになるが….。
本作が史学部シリーズ第一作なのですが設定は「ドゥームズデイ・ブック」の後となっています。
「ドゥームズデイ・ブック」の主人公ギヴリンが本作の主人公バーソロミューのルームメイトとして登場おり、すでに中世への時間遡行済な設定です。
シリーズを貫くテーマ的なものがすでに出ているですが、なんだか骨組みだけ見させられているような気になってしましました。
「ブラックアウト/オールクリア」の感想でも書きましたが、作中バーソロミューをセント・ポール大聖堂で探し求める場面が出てくるのでその場面での対比が楽しめます。
猫が絶滅しているということは「犬は勘定に入れません」の方で詳しく語られますがその辺もこの第一作から触れられているので設定済だったというようなこともわかります。
ただちょっと本作の描写、全体的に薄めなので期待して読んだ割には...というところはありました。
○マーブル・アーチの風 The Winds of Marble Arch 1999年10月,11月
2000年ヒューゴー賞
20年ぶりに夫婦でロンドンの大会(SF大会?)に訪れ、地下鉄に乗った主人公は正体不明の風に出会い...。
ウィリス54歳の作品ということでしのびよる「老い」と去りゆく「若さ」を郷愁でつつんで描いています。
「ブラックアウト/オールクリア」でも多く出てくるロンドンの地下鉄が出てきています、ウィリスのコメントによるとロンドンで一番のお気に入りはセント・ポール大聖堂で2番目は地下鉄のネットワーク全体とのこと。
独特の雰因気は楽しめましたが、ほぼ「SFではない」のでSFとして評価するとどうかなぁと思う作品ですね。
○ナイルに死すDeath on the Nille 1993年3月
1994年ヒューゴー賞・SFクロニカル賞-ショート・ストーリー
エジプト行きの飛行機に乗りナイルへ向かうツアーの一行は…。
これもSFではなくホラーという感じの作品。
初期の筒井康隆(60年代?)の短編にありそうな話だなーという感想でした。
ありきたりなツアーが徐々に異世界に引きずりこまれていく感じと、女性の描き方ウィリスならではと感心しました。。
「死後の世界」という意味では後の「航路」につながってくるのかもしれません。
○最後のウィネベーゴ The Last of the Winnebagos 1988年7月
1989年ヒューゴー賞・ネピュラ賞・SFクロニカル賞・アシモフ誌読者賞
犬が絶滅し世界がゆっくり下り坂に向かっているらしい近未来、ウィネベーゴを取材するカメラマン=記者は….。
訳者あとがきで「ウィリスの中短編の中でも小説としての出来栄えではたぶんこれがベストであろう」と書かれています。
確かに「?」な設定で年代も時折遡ったりして描かれるストーリーはなんとも巧みです。
「ラストどうなってしまうのかなぁ」と思いましたがすべての伏線を回収して見事に解決する手腕には舌を巻きました。
全体的に去りゆく者への郷愁漂い雰因気は感じたのですが…。
本書全体に言えることですがSFならではの「とんでもない」状況やら道具立てのない話が多かった気がします。
だからといって小説的にどうなのかというと私的にはそれほど入り込めませんでした。
ウィリスが長編向きなのか私との相性の問題なのかは???です。
作品的には「最後のウィネベーゴ」が一番楽しめましたが、「ウィネベーゴ」自体がいかにもアメリカなものなのが象徴的であくまで「アメリカン」な郷愁なのでそこが戸惑うところではありました。
〈付録〉
〇二〇〇六年世界SF大会ゲスト・オブ・オナー・スピーチ
〇グランド・マスター賞受賞スピーチ予備原稿
〇グランド・マスター賞受賞スピーチ
ウィリスはスピーチの名手でもあるそうです。
少女時代からどのような作品を読んできたのか等わかり楽しめました。
特に「ハインライン」に感謝していましたがアメリカ人にとって「ハインライン」それもジュブナイル作品は大きな影響があったんでしょうね。
↓SF的仕掛けがどうした!という方もその他の方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










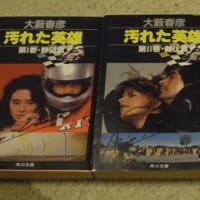
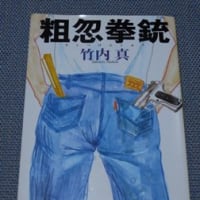
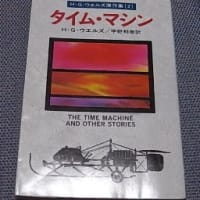
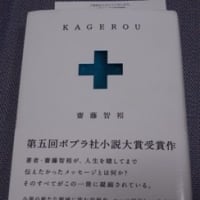
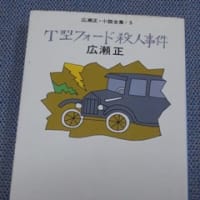
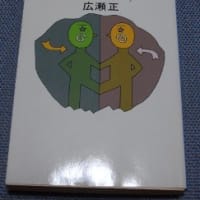


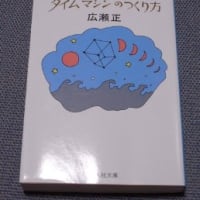
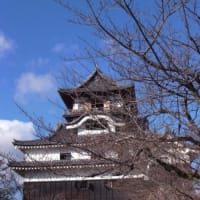
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます