「ヴォル・ゲーム」に続きSFです。
今年に入って「2010年宇宙の旅」から「ヴォル・ゲーム」まで比較的エンターテインメント寄りのSFを読んでいたのでボチボチ重め(と思われる)作品を読もうと本書を手に取りました。
本書の作者のロジャー・ゼラズニイはディレイニーらと並びアメリカのニュー・ウェーブSFの代表的作家ということになっているようです。
ゼラズニイ作品は小学校高学年の時に「わが名はコンラッド」の文庫本を図書館で何回か借り結局読まないで終わったのが記憶に残っています…。
ということで結局未読だった作家ですので今回が初ゼラズニイです。
知りませんでしたが「わが名はコンラッド」はギリシャ神話に題材を取り、本書はインド神話というように神話を題材とした作品が得意な作家のようです。
なお本書含めゼラズニイ作品現在すべて絶版の模様。
ということでブックオフで昨年購入
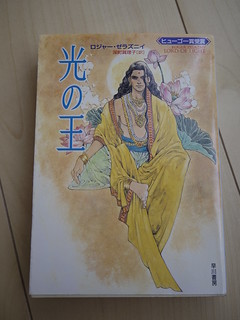
本書は‘12年ローカス誌SFオールタイムベスト23位、’06SFマガジンベスト38位にランクインしておりターゲット作品だったので購入していました。
1967年発刊1968年のヒューゴー賞を受賞しています。
内容紹介(裏表紙記載)
遙かな未来、人類は地球から遠く離れた惑星にインド神話さながらの世界を築いていた。地上の民衆は無知なまま原始的生活を送り、<天上都市>の不死となった<第一世代植民者>は科学技術を独占し、神として民衆を支配している。だが、シッダルタ、仏陀、サムなどの名で知られる男が、圧制下にある民衆を解放すべく、敢然として神々に戦いをいどんだ…たぐいまれな想像力で、SFと神話世界をみごとに融合した未来叙事詩。
俗っぽいシッダルダが出てくる点では光瀬龍の「百億の昼と千億の夜」に似ていますが、まぁゼラズニイがマネをしたというわけではないでしょう。(百億の…の方が発表少し前)
なお「百億の昼と千億の夜」の方が話のスケールは大きいですが本書の方が丁寧にインド神話をなぞって破綻のないストーリーを展開している分緻密です。
本作のネット評価を見ると「読みやすい」とか「おもしろい」という評価だったのでそのつもりで読み始めたのですが….。
私的には第1章は全然説明もなく話が展開していき「???…」でした。
第2章は説明もなくいきなり「過去?」という話になるので、さらに「?????」となりましたが第2章の終わり辺りでなんとなく筋立てが見えてぐんと読みやすくなりました。
時系列的には最終章の直前が第1章という感じで、各章1つのエピソードに独立しています。
最初は面喰いましたが、なかなか効果的な構成です。
どういう展開で第1章の話につながっていくのか、わかるようでわからないようになっていて面白かったです。
特にヤマがいつどうやってサムと仲間になるのかの興味をうまくつないでいます。
仏教やらヒンドゥー神話と遠い星のSF的お話との融合もうまいもんだなぁと思いました。
私はあまりその辺詳しくなく手塚治虫の「ブッダ」で描かれたシッダルダやらのお話しか知りませんがその程度の知識でも「なるほどねー」と感心しました。
ちょっと調べたところ、例えば主要登場人物「ヤマ」は「閻魔」なんですね。
(中国で道教とくっついて閻魔大王になっていったようです。)
意外とヒンドゥー教の神々は日本にまで影響を及ぼしているんですね。
というように話しの流れはかなり凝ったつくりですが、根本的にはシッダルダ=サムの「民主主義」的な社会を志向する行動が、専制的な体制に対して最終的に勝利を収めるという単純な話でもあります。
第2章からシッダルダがいろいろと革命を仕込んでいるのですが「勝利」へのキーマンは圧倒的な技術開発力と戦力をもつヤマ。
ヤマの裏切り理由はシッダルダの力というよりも基本的にふられた恨み….。
とこの辺も意外と単純です。
この辺が「読みやすい」とされるところですかねぇ。
そうはいっても背景にある「転生することが可能な人間の命って何?」とか、インド神話と登場人物のキャラ付など深く考えるといろいろ思う所が出てくる作品でもありそうです。
あとあまり触れられていませんでしたが神々が転生するための人間の体って「もともとその体の持ち主の命はどうなっているんだろうか?」と気になったりしました。
取られちゃった人は可哀そうですよね…。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
今年に入って「2010年宇宙の旅」から「ヴォル・ゲーム」まで比較的エンターテインメント寄りのSFを読んでいたのでボチボチ重め(と思われる)作品を読もうと本書を手に取りました。
本書の作者のロジャー・ゼラズニイはディレイニーらと並びアメリカのニュー・ウェーブSFの代表的作家ということになっているようです。
ゼラズニイ作品は小学校高学年の時に「わが名はコンラッド」の文庫本を図書館で何回か借り結局読まないで終わったのが記憶に残っています…。
ということで結局未読だった作家ですので今回が初ゼラズニイです。
知りませんでしたが「わが名はコンラッド」はギリシャ神話に題材を取り、本書はインド神話というように神話を題材とした作品が得意な作家のようです。
なお本書含めゼラズニイ作品現在すべて絶版の模様。
ということでブックオフで昨年購入
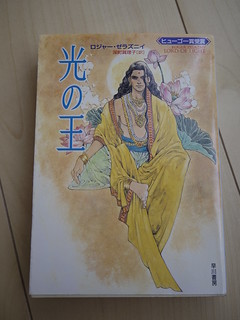
本書は‘12年ローカス誌SFオールタイムベスト23位、’06SFマガジンベスト38位にランクインしておりターゲット作品だったので購入していました。
1967年発刊1968年のヒューゴー賞を受賞しています。
内容紹介(裏表紙記載)
遙かな未来、人類は地球から遠く離れた惑星にインド神話さながらの世界を築いていた。地上の民衆は無知なまま原始的生活を送り、<天上都市>の不死となった<第一世代植民者>は科学技術を独占し、神として民衆を支配している。だが、シッダルタ、仏陀、サムなどの名で知られる男が、圧制下にある民衆を解放すべく、敢然として神々に戦いをいどんだ…たぐいまれな想像力で、SFと神話世界をみごとに融合した未来叙事詩。
俗っぽいシッダルダが出てくる点では光瀬龍の「百億の昼と千億の夜」に似ていますが、まぁゼラズニイがマネをしたというわけではないでしょう。(百億の…の方が発表少し前)
なお「百億の昼と千億の夜」の方が話のスケールは大きいですが本書の方が丁寧にインド神話をなぞって破綻のないストーリーを展開している分緻密です。
本作のネット評価を見ると「読みやすい」とか「おもしろい」という評価だったのでそのつもりで読み始めたのですが….。
私的には第1章は全然説明もなく話が展開していき「???…」でした。
第2章は説明もなくいきなり「過去?」という話になるので、さらに「?????」となりましたが第2章の終わり辺りでなんとなく筋立てが見えてぐんと読みやすくなりました。
時系列的には最終章の直前が第1章という感じで、各章1つのエピソードに独立しています。
最初は面喰いましたが、なかなか効果的な構成です。
どういう展開で第1章の話につながっていくのか、わかるようでわからないようになっていて面白かったです。
特にヤマがいつどうやってサムと仲間になるのかの興味をうまくつないでいます。
仏教やらヒンドゥー神話と遠い星のSF的お話との融合もうまいもんだなぁと思いました。
私はあまりその辺詳しくなく手塚治虫の「ブッダ」で描かれたシッダルダやらのお話しか知りませんがその程度の知識でも「なるほどねー」と感心しました。
ちょっと調べたところ、例えば主要登場人物「ヤマ」は「閻魔」なんですね。
(中国で道教とくっついて閻魔大王になっていったようです。)
意外とヒンドゥー教の神々は日本にまで影響を及ぼしているんですね。
というように話しの流れはかなり凝ったつくりですが、根本的にはシッダルダ=サムの「民主主義」的な社会を志向する行動が、専制的な体制に対して最終的に勝利を収めるという単純な話でもあります。
第2章からシッダルダがいろいろと革命を仕込んでいるのですが「勝利」へのキーマンは圧倒的な技術開発力と戦力をもつヤマ。
ヤマの裏切り理由はシッダルダの力というよりも基本的にふられた恨み….。
とこの辺も意外と単純です。
この辺が「読みやすい」とされるところですかねぇ。
そうはいっても背景にある「転生することが可能な人間の命って何?」とか、インド神話と登場人物のキャラ付など深く考えるといろいろ思う所が出てくる作品でもありそうです。
あとあまり触れられていませんでしたが神々が転生するための人間の体って「もともとその体の持ち主の命はどうなっているんだろうか?」と気になったりしました。
取られちゃった人は可哀そうですよね…。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










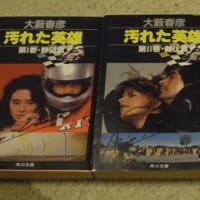
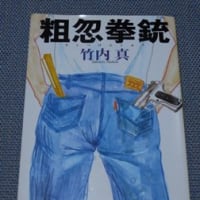
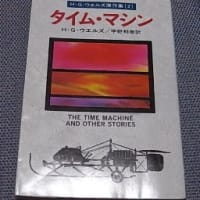
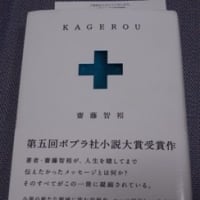
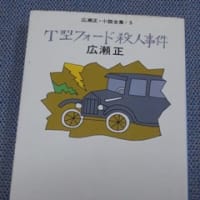
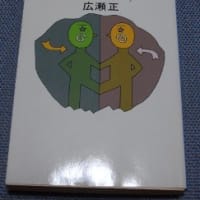


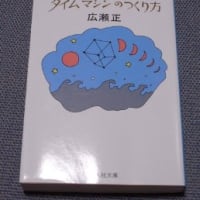
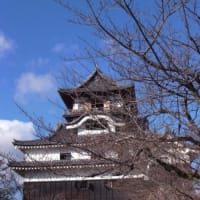
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます