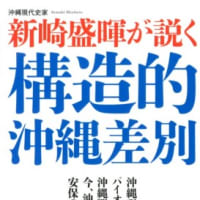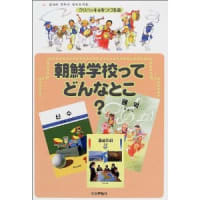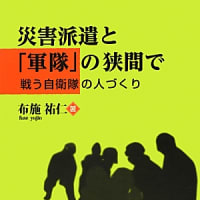今回の福島原発事故によって、原発周辺地域は高濃度の放射能汚染に見舞われ、もはや長期にわたって生活圏として機能しえないとされている。周辺で栽培された野菜などの農産物に関しても出荷停止措置が取られ、農家は苦境に陥っている。そんな中、3月24日には福島県須賀川市の農家の男性が自殺するという痛ましい事件も起きた。これは遺族が言うように、「原発に殺された」のである。原発は地域に住む人々が代々積み上げてきたものを一瞬にして破壊したのであった。
このように、原発という存在は生活領域としての「地域」と根本的に対立する。それにもかかわらず、1966年に日本発の原発(日本原電東海1号機)が稼動して以来、2010年末時点で54基もの原発が日本全国に建設されてきたのである(世界第三位)。なぜこれほど多くの原発が建設されることになったのか、そしてそれによって人々の生活はどのように変容していったのか、「地域」の視点から見ていきたい。
まず、原発の立地政策を考える上で、日本の原子力政策全体について簡単に触れておきたい。日本において原発は90年代半ばまで「直線的成長」を遂げてきた。世界的にはスリーマイル島事故やチェルノブイリ事故といった大規模な原発事故を契機に停滞状況に陥り、総基数はほぼ横ばいで推移している状況とは対照的である。社会情勢の変化によっても浮沈を経験しなかったのは、「国家安全保障のための原子力」という公理(吉岡斉)を大前提とした国策であったからであった(当ブログ「原子力の「平和利用」を見直す―福島原発事故から日本の原子力政策を問う―」参照)。そして所轄官庁(経済産業省)の主導権の下に電力会社、政治家、地方自治体有力者を加えた四者による談合で政策が決定されてきた。つまり、地方自治体有力者が直接のパイプとなって各地域での立地政策が進められてきた。
では、原発が立地されるのはどのような地域なのだろうか。64年に原子力委員会が決定した「原子炉立地審査指針」においては(1)原子炉の周囲は原子炉からある距離の範囲が非居住区域であること、(2)原子炉からある距離の範囲であって、非居住区域の外側の地帯は低人口地帯であること、(3)原子炉敷地は人口周密地帯からある程度距離が離れていること、などを挙げられている。しかしながら、この指針の具体的な基準は示されることはなく、立地調査が進められていった。その結果、「いくつかの例外を除いてはいずれも外洋に面した臨海部であり、過疎地域がねらいうちされているのである」(山川充夫「原発立地推進と地域政策の展開」(二))。自治体からしてみれば、原発に伴う様々な経済効果を期待して積極的な誘致運動を展開していくことになる。
日本の原発立地過程においては全ての許認可権が政府に集中し、自治体の役割については原子力関係法規には一行も書かれておらず、一切権限が付与されていない。しかし暗黙のルールとして都道府県知事の同意が必要とされる。加えて土地買収と漁業権放棄の同意を得なければならない。この三点の条件をクリアしたとき、原発建設計画はほとんど実現したことになるのである。ただし、上記のような経済的理由で自治体は原発立地に賛成することが多い。そのため原発立地過程において主要な問題となるのは土地買収と漁業権放棄の同意となる。
後二者の条件をクリアする上で、主導権を取るのは自治体自身であった。まず県知事を頂点とした地元政官界、商工業団体、農漁業団体の有力者たちの階層的ネットワークの上層部(自治体幹部、県議、市町村議など)との同盟関係を電力会社が事前に構築し、地権者・漁業権者への説得工作が展開される。同時に委託業者による用地買収工作が進められる。そうした水面下の根回し工作が十分に行われた上で、原発立地計画の正式発表がなされる。そして、用地買収問題の最終的解決と漁業補償問題については上記ネットワークによる利益誘導が行われるのである。
今回事故が起きた福島原発の立地に際しては、当時の県開発公社が両条件の実現を積極的に推し進めた。自治体は住民に対して原発とは明言せず、「大工場」を誘致するとして現地調査を行った後、予定地のに突然計画を告げた。そのうち毛萱は総会で全員反対の意思を示したが、隣の波倉が一人当たり一、二千万円の補償金をつかまされ、容認に回ってしまったため毛萱は孤立してしまった。毛萱内に条件(容認)派が生まれる中で代議士、県議、町議の強制収用などの威嚇を含んだ執拗な戸別訪問によって、ついに反対勢力もつぶされてしまったのである。ある酪農家は土地買収と引き換えに家族が東京電力で雇用されるという条件を飲んだという。賛成派住民には企業や自治体への就職が優遇されるが、反対派に対してはその道は閉ざされてしまうなどという形で利益誘導が行われる(鎌田慧『日本の原発危険地帯』参照)。
このように、日本における原発立地過程は極めて非民主主義的である。電力会社と自治体が一体となって誘致運動を進め、住民にはほとんど情報が与えられない中で原発賛成を強いられる。住民の同意を得るためにはカネや恫喝といったあらゆる手段を行使するのであった。これこそが社会情勢の変容にも関わらず、日本に54基もの原発が「安定的」に造られてきた背景であり、まさに迷惑施設を押し付けてきたのである。そして今回、押し付けられた原発によって福島の人々の生活領域は徹底的に破壊された。押し付けてきた者達の責任は相当に重い。徹底した責任追及と相応の処罰が求められよう。
このように、原発という存在は生活領域としての「地域」と根本的に対立する。それにもかかわらず、1966年に日本発の原発(日本原電東海1号機)が稼動して以来、2010年末時点で54基もの原発が日本全国に建設されてきたのである(世界第三位)。なぜこれほど多くの原発が建設されることになったのか、そしてそれによって人々の生活はどのように変容していったのか、「地域」の視点から見ていきたい。
まず、原発の立地政策を考える上で、日本の原子力政策全体について簡単に触れておきたい。日本において原発は90年代半ばまで「直線的成長」を遂げてきた。世界的にはスリーマイル島事故やチェルノブイリ事故といった大規模な原発事故を契機に停滞状況に陥り、総基数はほぼ横ばいで推移している状況とは対照的である。社会情勢の変化によっても浮沈を経験しなかったのは、「国家安全保障のための原子力」という公理(吉岡斉)を大前提とした国策であったからであった(当ブログ「原子力の「平和利用」を見直す―福島原発事故から日本の原子力政策を問う―」参照)。そして所轄官庁(経済産業省)の主導権の下に電力会社、政治家、地方自治体有力者を加えた四者による談合で政策が決定されてきた。つまり、地方自治体有力者が直接のパイプとなって各地域での立地政策が進められてきた。
では、原発が立地されるのはどのような地域なのだろうか。64年に原子力委員会が決定した「原子炉立地審査指針」においては(1)原子炉の周囲は原子炉からある距離の範囲が非居住区域であること、(2)原子炉からある距離の範囲であって、非居住区域の外側の地帯は低人口地帯であること、(3)原子炉敷地は人口周密地帯からある程度距離が離れていること、などを挙げられている。しかしながら、この指針の具体的な基準は示されることはなく、立地調査が進められていった。その結果、「いくつかの例外を除いてはいずれも外洋に面した臨海部であり、過疎地域がねらいうちされているのである」(山川充夫「原発立地推進と地域政策の展開」(二))。自治体からしてみれば、原発に伴う様々な経済効果を期待して積極的な誘致運動を展開していくことになる。
日本の原発立地過程においては全ての許認可権が政府に集中し、自治体の役割については原子力関係法規には一行も書かれておらず、一切権限が付与されていない。しかし暗黙のルールとして都道府県知事の同意が必要とされる。加えて土地買収と漁業権放棄の同意を得なければならない。この三点の条件をクリアしたとき、原発建設計画はほとんど実現したことになるのである。ただし、上記のような経済的理由で自治体は原発立地に賛成することが多い。そのため原発立地過程において主要な問題となるのは土地買収と漁業権放棄の同意となる。
後二者の条件をクリアする上で、主導権を取るのは自治体自身であった。まず県知事を頂点とした地元政官界、商工業団体、農漁業団体の有力者たちの階層的ネットワークの上層部(自治体幹部、県議、市町村議など)との同盟関係を電力会社が事前に構築し、地権者・漁業権者への説得工作が展開される。同時に委託業者による用地買収工作が進められる。そうした水面下の根回し工作が十分に行われた上で、原発立地計画の正式発表がなされる。そして、用地買収問題の最終的解決と漁業補償問題については上記ネットワークによる利益誘導が行われるのである。
今回事故が起きた福島原発の立地に際しては、当時の県開発公社が両条件の実現を積極的に推し進めた。自治体は住民に対して原発とは明言せず、「大工場」を誘致するとして現地調査を行った後、予定地のに突然計画を告げた。そのうち毛萱は総会で全員反対の意思を示したが、隣の波倉が一人当たり一、二千万円の補償金をつかまされ、容認に回ってしまったため毛萱は孤立してしまった。毛萱内に条件(容認)派が生まれる中で代議士、県議、町議の強制収用などの威嚇を含んだ執拗な戸別訪問によって、ついに反対勢力もつぶされてしまったのである。ある酪農家は土地買収と引き換えに家族が東京電力で雇用されるという条件を飲んだという。賛成派住民には企業や自治体への就職が優遇されるが、反対派に対してはその道は閉ざされてしまうなどという形で利益誘導が行われる(鎌田慧『日本の原発危険地帯』参照)。
このように、日本における原発立地過程は極めて非民主主義的である。電力会社と自治体が一体となって誘致運動を進め、住民にはほとんど情報が与えられない中で原発賛成を強いられる。住民の同意を得るためにはカネや恫喝といったあらゆる手段を行使するのであった。これこそが社会情勢の変容にも関わらず、日本に54基もの原発が「安定的」に造られてきた背景であり、まさに迷惑施設を押し付けてきたのである。そして今回、押し付けられた原発によって福島の人々の生活領域は徹底的に破壊された。押し付けてきた者達の責任は相当に重い。徹底した責任追及と相応の処罰が求められよう。