
(独歩安を続ける日本の賃金 Economic Outlook より)
経団連は2013年1月21日に発表した今春闘の指針「経営労働政策委員会報告」で、基本給を底上げするベースアップ(ベア)を「実施する余地はない」と一蹴し、それどころか、年齢に応じて賃金が上がる定期昇給の延期や凍結の可能性にも言及しました。
経団連の米倉弘昌会長と連合の古賀伸明会長が1月29日都内で会談し、平成25年春闘が本格スタートしたのですが、会談で労働側がデフレ脱却には働く者の賃金や処遇改善が重要と訴えたのに対し、経営側は企業の存続と雇用の維持が最優先と主張しました。
賃上げしないと国民の購買力は上がらず、消費マインドは冷え切ったままで、結局お金を使えないので企業の業績も上がらないし、景気も良くならないし、デフレからも脱却できないという小学生でもわかる理屈だと思うのですが、守り一辺倒の経団連だけは思考停止したままでわからないようです。

(国民の賃金は目減りし続け、大企業の内部留保は増え続けた)
パナソニックなど電機産業が何千億円も赤字を出しているので、日本の大企業全体が儲かっていないかのようですが、実は、企業の内部留保は上のグラフのように265兆円、日銀統計によると、企業が抱える現預金は215兆円にも膨らんでいます。なんでそんなにお金を貯めているかというと、まず労働分配率が低いこと。労働分配率とは売上高から直接変動費を除いた付加価値高に人件費の占める割合です。
要は、企業の上げた売り上げからどれだけ賃金を支払っているかということです。下に、先進主要国の労働分配率のグラフを上げましたが、日本の企業ってケチというか、働いてくれた労働者に全然分配していないことがわかりますね。だから、冒頭のグラフのように企業の内部留保ばかり増えて、賃金は上がらないという構図になっているのです。
財界が消費税増税押しをした理由 消費税の輸出還付制度=戻し税を使った犯罪発覚

これ以上、雇用している人が賃金目減りに我慢できるわけないでしょう。だいたい、いくら労働者が我慢して企業の業績が上がっても、そのあと賃上げと言う形で報われる保証はまるでないということは冒頭の経団連の発言で明らかです。企業が雇用を増やす保証もありません。
いつまでもみんなが低賃金で働いていたらデフレ脱却なんてするわけないでしょう。
というか、デフレ脱却を含み、すべての経済政策は国民一人一人の生活が楽になるためにあるのに、この人の議論はデフレ脱却のために国民は我慢しろと言うのですから、本末転倒もいいところです。
なんとまあ、偉い学者の先生の浮世離れしたことか。
この浜田氏のトンデモ発言には、かつて浜田氏の講義を聴いたという新自由主義経済評論家の池田信夫氏でさえ、「デフレの原因は名目賃金の低下である」と真っ向から批判しています。

(賃金の目減りこそがデフレの原因であることは一目瞭然)
かつて、日本の労働分配率が最悪に低かったのは、上のグラフで分かるように実は第一次安倍内閣の2007年のことです。この時期、日本企業の多くは1990年代のバブル崩壊の後遺症に悩み、企業は成長することよりも不良資産の整理に必死でした。そのため、設備投資は抑え、正規職員を非正規に置き換え、 賃金コストの圧縮に専心しました。
この結果、拡大した企業収益は借金の返済に回され、あるいは内部に溜め込まれたため、戦後最長の景気回復の期間を通じて、賃金は下落し続けたのです。非正規労働者の割合は 高まり、労働分配率も下がり、ちょうど安倍内閣のときに最低水準に落ち込んだのでした。だからこそ、「実感なき景気回復」という言葉が流行ったのです。

(第一次安倍内閣のときに急速に拡大した非正規雇用)
そして、名目賃金の低下に次ぐ低下は 当然のことながらデフレスパイラルを生みました。第一次に続いて今回も同じ失敗を安倍内閣は繰り返そうというのでしょうか
そもそも、日本のGDP473兆円のうち賃金は52%の245兆円です。仮にこれを4%引き上げるとすれば、10兆円必要になりますが、他方、下のグラフのような企業の内部留保265兆円のうち現金・預金は215兆円ですから、その5%を使えば4%の賃上げは可能なのです。企業がため込んだ内部留保を少し使えば景気は良くなります。そんな思考も冒険もできないのが今の財界です。
賃金が上がらないのに、物価高になり、消費税増税され、生活保護費の切り下げとなったら、99%の国民は地獄ですよ。
逆に賃上げすれば預貯金にもまわりますが、賃上げが安定的に続くということがはっきりすれば一気に消費マインドは改善します。それで企業も儲かるのです。しかし、そのような好循環を作る能力が企業にないことはこの20年間で明白です。
労働契約法など労働法制の改正で非正規雇用から正規雇用へ。最低賃金法の改正で最低賃金の上昇。そして、強力な政治主導で定期昇給はもちろんのこと、産業界に大幅なベースアップを促すこと。
そういうアベノミクスなら私も賛成します。
政治家も学者も、国民の福利を基準に考える、それ1点で物事はよほどシンプルに解決するのに。
よろしかったら上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。
今年の春闘が29日、連合と経団連のトップ会談で始まった。安倍政権が「デフレ脱却」を掲げるなか、賃上げが実現するかどうかが最大の焦点。企業規模による格差や高齢者雇用、非正社員の待遇改善についても議論が白熱しそうだ。
●連合「収入増が不可欠」 経団連「まず企業の元気」
「デフレ経済から脱却ができるかどうかは、政府の適切な経済運営、財政運営に加え、春闘の交渉結果も、大きなカギを握る」(連合の古賀伸明会長)
「雇用を増大させていくか、給料を上げていくか、組合の方々と色々話し合った結果、決めていくのが、日本の労使の強みだ」(経団連の米倉弘昌会長)
今春闘の最大の焦点は賃上げの是非だ。
連合は「働き手の収入を増やし、国内総生産の6割を占める個人消費を盛り上げることがデフレ脱却に不可欠」(古賀会長)との立場だ。1997年から続く賃金の下落傾向に歯止めをかけるため、定期昇給とは別に、賃金や手当で1%目安の配分増を求めている。
一方、経団連側が21日に発表した春闘指針は「個人消費が落ち込む要因は将来不安。所得だけを増やしても預貯金に回る可能性が高い」と指摘。賃金水準を 上げるベースアップ(ベア)は「余地なし」、定期昇給は「実施の取り扱いが主要な論点」と踏み込んだ。会談を終えた米倉会長は「古賀会長は給料を上げるべ きだというが、やはり個々の企業が元気を出せる環境づくりを重視している」。景気を良くすることが優先で、働き手にお金が回るのはその次、という考えから だ。
両者の違いは中小企業の賃上げで、より明確だ。大手との格差是正のため、定昇とは別に1%相当の賃上げを求める連合に対し、経団連は「大手以上に厳しい 中小でベアは理解が得られない」と反発する。連合は会談のなかで、「賃上げがなければ、格差は広がるばかりだ」と再反論した。
●60歳超への対応、企業で差
今春闘では、4月に施行される改正高年齢者雇用安定法(高齢法)の対応も論点になる。65歳まで働きたい人全員の雇用確保を義務づけられる企業側は、人 件費は大幅に増やせないという姿勢が強く、経団連も「(賃金の上がり方を示す)賃金カーブの全体的な見直し」を提案する。実際、NTTグループは今秋、 65歳までの雇用確保と引き換えに60歳以前の賃金水準を見直す。
ただ企業の対応には差がある。サントリーホールディングスやIHIは4月、60歳以前の賃金水準は変えずに定年を延長する。トヨタ自動車は「お金がない と将来の不安が残り、消費も伸びない」(宮崎直樹・常務役員)とし、退職金制度を拡充するなど、60歳以降の生活費を補うための資産形成策に力を入れる。
労組側がまず求めるのは定年前の賃金水準の維持。高齢法には罰則がなく、再雇用されずに泣き寝入りを強いられる例があるため、高齢法の順守そのものも求 める。流通や繊維を中心に組織するUAゼンセンは「就業規則に希望者全員の再雇用を書き込む」(逢見直人会長)ことを目指す。
(山本知弘、米谷陽一)
●非正社員の待遇改善も論点
最近の春闘では、非正社員の待遇改善も課題になっている。働き手の3分の1を超え、その多くが年収200万円以下で働く。
連合は今春闘の闘争方針で、正社員にするルールや昇給制度の明確化、社会保険の適用拡大などを重点的に要求する項目として例示。「誰もが時給1千円」という賃金の目安も示した。
一方、経団連は「賃金水準の引き上げはかなり実現している」と主張し、総額人件費の増加を警戒する。
4月からは、通勤手当や食堂利用で正社員と差別することを禁じたり、無期雇用への転換を促したりする改正労働契約法が施行される。法の趣旨に沿うよう、職場ルールを見直すこともテーマになる。
安倍政権も企業の潤沢な資金の存在に気づいたのだろう。賃上げした企業の法人税負担を和らげる税制の導入を決めた。企業が貯蓄に励み、設備投資も賃上げも躊躇(ちゅうちょ)していてはデフレ脱却は危うい。
人件費を増やした企業は、その最大一割を法人税から差し引く。与党の自民、公明両党がまとめた二〇一三年度税制改正大綱に、企業の税負担を緩和す る新たな制度が盛り込まれた。企業の手元に積み上がっている巨額の内部留保を眠らせることなく、勤労者に移し替えて内需を盛り上げる。デフレ脱却に対する 安倍政権の意図が込められている。
だが、経団連の春闘方針「経営労働政策委員会報告」は、賃上げを「実施の余地はない」と一蹴、年齢などに応じて給与を引き上げる定期昇給も延期や 凍結があり得るとほのめかしている。法人税軽減というニンジンを見せられても、減税が時限措置ゆえに、やすやすとは応じられないと冷淡だ。
日本の経営者は一九九〇年代からの「失われた二十年」にうろたえ、すっかり内向きになってしまったようだ。分厚い手元資金に安心を求め、賃上げはおろか、設備投資さえためらっている。日銀統計によると、企業が抱える現預金は二百十五兆円にも膨らんだ。
経済界は「アジアの成長を取り込む」と勇んではいるが、海外子会社からの年三兆円に上る受取配当なども有効に活用しているか疑わしい。日本経済を むしばんでいる原因の一つは、十五~六十四歳の生産年齢人口減少に伴う内需縮小であり、企業はとりわけ消費性向が高い子育て世代にお金を回し、内需拡大に 転じることが求められていると言うべきだ。
経団連の企業行動憲章は「従業員のゆとりと豊かさを実現する」とうたっている。円高などの六重苦を嘆いてばかりいないで、日本再生への自助努力を受け入れる度量をしっかりと示すべきだ。
オバマ米大統領は二期目の就任演説で、米国の成功は復興しつつある中間層に支えられるべきだ-と訴えた。「なぜ1%が金持ちで、99%が貧乏なのか」を合言葉とした金融の中枢、ウォール街占拠への回答でもある。
購買力のある中間層の復活は日本も重い課題だ。格差拡大の原因にもなった製造業への派遣就労拡大を法制化したのは、かつての自民党政権ではなかったか。税制で賃上げを促そうとする安倍政権には、中間層復活に向け、経済界に協力を強く求める責務がある。
繰り返すな、6年前の誤り (1) - 安倍新総理は賃上げに動くべきだ -
2013年1月29日(火曜日)
安倍総理は太平洋戦争直後の吉田茂を除けば、戦後総理では唯一、2 回目のチャンスを与えられた総理である。1回目で失敗があるとすれば、それから教訓を学んで2回目に生かすことができる稀な総理だ。1回目は閣僚の不祥事 が相次ぎ、最後はご自身の健康問題も出て、誰が見ても無様な退陣を遂げてしまった。しかし第1次安倍内閣を退陣に追い込んだ最大の要因は2007年7月の 参議院選挙での大敗である。選挙で負ければ総理の政治生命は終わりだ。
1. 国民の関心は常に自分たちの暮らしぶり
なぜ安倍氏率いる自由民主党は、あの時点で選挙に大敗したのか? それを想い起すことは今の安倍総理にとって極めて重要である。先に結論を言えば、あの時、企業だけが豊かになり、国民の生活が良くならなかったからであ る。選挙で最大の争点は国、時代に関わりなく、いつも国民の生活ぶりだ。米国では “Are you better off ?”とか“It’s economy, stupid.”とか、大統領選挙戦中に吐かれた有名な台詞がある。前者はレーガン大統領(その時点では候補)のもので、「あなたの暮らしは良くなりまし たか?」という意味だが、彼は現職のカーター大統領の弱腰外交を批判することで支持を勝ち取ったのではない。国民の生活に対する不満に訴えたのだ。後者は クリントン氏のもので、意訳すれば「国民にとって大事なのは経済だ。そんなこともわからないのか、このばか者」という意味である。対抗する共和党のブッ シュ大統領(父)はイラク戦争で見事な勝利を収め、国民的人気も高かった。そのブッシュには勝てないのではないか、と質問されたときの彼の答えだ。いつの 時代も選挙の結果を左右するのは経済、なかんずく国民生活だ。
安倍氏は7月には参議院選挙を迎える。経済を良くしておくことは勝 利に向けての必須要件だ。彼は2006年9月に人気の高い小泉元総理から総理ポストを禅譲された。自ら勝ち取ったものではないから、翌年夏の参議院選挙は リーダーとしての資質を試す初めてのテストであった。結果は歴史的大敗となったが、この前後の日本経済をよく観察すると、なぜ選挙に負けたかだけでなく、 今の状況が6年前と次第に似てきていることがわかる。いくつかデータを見てみよう。
2. 日本経済の絶頂期に崩壊した第1次安倍内閣
日本経済は2002年1月から2008年2月までの73か月、戦後 最長の景気拡大を続けた。第1次安倍内閣の期間は2006年9月からの1年間で、その最も良い時期に該当する。景気回復を支えたのは円安であり、日本政府 による大規模な為替介入もあって、円は1ドル100円から120円くらいと長期間下落し続けた(【図1】なお赤印は第一次安倍内閣の在職期間を示す)。折 しも米国は住宅バブルの最中で需要が盛り上がり、また2001年にWTO への加入を果たした中国も経済成長が加速し、「中国特需」が盛り上がった。こうして日本は良好な外部環境の後押しもあって、2%を超える実質経済成長を続 けることができた(【図2】)。内需が低迷する中で外需依存の経済成長が実現できたのは、小泉、安倍政権にとってラッキーであった。この裏には、日本政府 の大規模為替介入を米国が黙認するという、強固な日米関係があったことは言うまでもない。昨年秋からの急激な円安に対してヨーロッパやアジア各国が懸念を 表明するのに対して、米国が今までのところ表立った反対をしていないのも、6年前と似ている。
【図1】円・ドルレート
【図2】実質GDP成長率
3. 絶好調でも良くならなかった国民生活
第1次安倍内閣の時期、企業収益も株価も持ち直した(【図3】、 【図4】)。特に株価(日経平均)は前任の小泉内閣の初期に8000円割れしたものが、その後上昇を続け、2007年5月には18000円の大台に達して いた。まさに選挙をやるには絶好のタイミングであった。だが、このような一見良好に見えた経済データの裏で国民の不満はむしろ高まっていた。何が起こって いたのだろうか?
【図3】営業利益
【図4】日本の株価
この時期、日本企業の多くは1990年代のバブル崩壊の後遺症に悩 んでいた。企業は成長することよりも、バランスシートの改善、言い換えれば不良資産の整理に必死であった。設備投資は抑え、正規職員を非正規に置き換え、 賃金コストの圧縮に邁進した。拡大した企業収益は借金の返済に回され、あるいは内部に溜め込まれた。これでは需要は盛り上がるはずがない。それでも成長で きたのは外需が堅調だからだ。【図5】はこの間の賃金の動向を示している。戦後最長の景気回復の期間を通じて、賃金は下落し続けた。非正規労働者の割合は 高まり(【図6】)、労働分配率も下がり、ちょうど安倍内閣のときに最低水準に落ち込んでいる(【図7】)。国民は企業サイドの好景気を一方で耳にしなが ら、自分たちの生活が一向に良くならないことに不満を感じ始めていたのである。
その頃「実感なき景気回復」という言葉が流行ったのはこのような事 情があったからだ。それでも小泉内閣の時代には郵政の民営化など、既得権と戦う姿勢も見られ、改革の効果がいずれ出てくるのではないかという期待もあっ た。しかし、安倍内閣になるに伴い、そのような改革への情熱は薄れ、代わりに安全保障など国民には必ずしも優先度の高くない課題に議論が移っていった。こ うして一見絶好調の経済情勢にありながら、民意は離反し、選挙では歴史的な敗北を喫してしまった。
【図5】日本の賃金動向
【図6】非正規労働者の割合
【図7】労働分配率
デフレ状況についても見ておこう。デフレとは消費者物価指数 (CPI:Consumer Price Index)の傾向的下落、つまり前年同月比でマイナスの状態を指す。これをグラフに示したのが【図8】であるが、これから明らかなように、1999年以 降、マイナスの年が多い。その中でも安倍氏が政権を率いた2006年から2007年は一時的にわずかながらインフレであった。だが、これは安倍内閣の功績 ではない。国際石油価格が上昇したのと、円安によるもので、国内での需要が盛り上がり、需給が逼迫して物価が上昇するということではなかったのである。所 得拡大を伴わないインフレは国民生活から見れば「悪いインフレ」で、決して評価されるモノではない。このところの円安に伴い国内物価の上昇が懸念される。 6年前と同じ状況が今また起こり始めている。
次回はアベノミクスの限界とそれを克服し、より確実な経済成長を達成するために賃金引き上げが不可欠であることを説明する。
【図8】日本の消費者物価(CPI)
シリーズ

根津 利三郎(ねづ りさぶろう)
【略歴】
1948年 東京都生まれ、1970年 東京大学経済学部卒、通産省入省、1975年 ハーバードビジネススクール卒業(MBA) 国際企業課長、鉄鋼業務課長などを経て、1995年 OECD 科学技術産業局長、2001年(株)富士通総研 経済研究所 常務理事、2004年(株)富士通総研 専務取締役、2010年 経済研究所エグゼクティブ・フェロー
【著書】
通商白書(1984年)、日本の産業政策(1983年 日経新聞)、IT戦国時代(2002年 中央公論新社) など
繰り返すな、6年前の誤り (2) - 安倍新総理は賃上げに動くべきだ -
2013年1月30日(水曜日)
3年間の民主党政権を含む5年の時間空白を挟んで再登場した第2次 安倍内閣では、経済問題こそが国民の支持を勝ち取るポイントである、という教訓が一部生かされたように見える。彼は持論である安全保障や歴史問題よりも、 国民が不満を持っている経済問題に焦点を当てた。特に金融政策を大胆に緩和することでデフレを脱却させるとともに、公共事業を通じて地方経済を活性化する という政策は、当面、為替や株価に顕著な影響を与え、経済に明るい期待を与えたことは評価されるべきだ。問題はこれからである。
1. 実は円安のメリットはゼロだ
仮に、もうしばらく円安、株高の効果が続くとしよう。経済全体への 影響はどうなるか? まず、円安を歓迎しているのは産業界だ。産業界は経団連を中心に「六重苦」を訴えてきた。その筆頭が円高だが、円安になることで直接 的に円安のメリットを受けるのは輸出企業である。逆に円安は原材料やエネルギーなど、わが国に国内生産が無く、全量輸入に依存しているような場合、円安の 分だけ円建て価格は上昇することになる。これを数字で見ると次のようになる。
2012年の日本の輸出金額は64兆円である。このうち円建てによ るものは40%で、この部分は為替変動の影響は直接的には受けない。残りは契約通貨ベースの価格を変えなければ円安分13%(79円→89円)だけ円建て 価格を引き上げることができ、5兆円ほど収益は改善する(64兆円×60%×13%)。これに対して、輸入額は70兆円、その78%は外貨建てであるが、 円安で円建て価格は13%上昇するから、円ベースでのコストアップ額は70兆円×78%×13%=7兆円となり、輸入面でのマイナスの方が輸出面のプラス を2兆円だけ上回ることになる。
円高は「悪」であるという考えは、日本の輸出が輸入額を大幅に上 回っていた前世紀の遺物であり、東日本大震災以降、燃料の輸入が急増し、輸入と輸出の大小関係が逆転した今日には当てはまらない発想だ。ただし、所得収 支、つまり海外に保有している子会社からの収益や外国の証券などからの配当、利子収入に対する影響もある。昨年、このような収入は18兆円あったが、ほと んどが外貨建てなので、これを円に換算する際、円安の方が2兆円だけ増えることになる。こうしてみると、円安の効果は全体としてプラス、マイナス合計でゼ ロだ。
安倍第1次内閣の次の福田内閣の経済財政担当大臣であった大田弘子 氏は2008年1月、国会での経済演説の中で、「日本は今や経済一流ではない。」と述べ、波紋を呼んだ。1人当たりのGDPがかつては世界3位だったもの が18位にまで落ち込んだことを受けての発言だったが、下落の原因の大半は円安だった。だから、その後の円高で順位は少し回復したが、このところの円安で 再下落しているだろう。為替レートは国力の指標で、際限のない為替の下落は外資による日本買占めなど、結局は惨めな経済をもたらす。安倍総理が「強い日 本」を目指すのであれば、この点は忘れるべきではない。
2. 円安で輸出は増えない
にもかかわらず、企業が円安を歓迎するのはなぜだろうか? 1つに は、輸出面のメリットは輸出企業を潤すのに対して、輸入面のコストアップは消費者に転嫁されるので、産業界に限ればプラスの効果が大きいことが挙げられ る。もう1つは、雇用への影響である。日本の輸出産業は自動車や家電など雇用効果の大きな産業が含まれている。円安になり、これらの輸出が増えれば、雇用 拡大に繋がる可能性がある。だが、このような議論が成り立つためには、価格を下げる(すなわち交易条件を悪化させる)ことにより、実際に輸出が増えること が前提だ。
過去のデータから輸出関数を推計してみると、輸出の決定要因は相手 国市場の所得水準、言い換えれば、輸出市場の景気動向が最も重要であり、価格の説明要因は極めて小さい。ブランド力がモノを言う耐久消費財では一般的に価 格弾性値は小さく、価格を多少下げたくらいで輸出は増えない。特にサプライチェーンのグローバル化の影響を忘れてはならない。近年、日本の輸出は完成品で はなく基幹部品や高機能原材料などが中心になっており、現地で組み立てられて最終商品になる。現地化はかなり進んでおり、日本からの部材の最終コストに占 める割合はかなり下がっている。輸出価格が10%程度下落したくらいで輸出が増えたり、新たな市場を獲得できるというような簡単な話ではなくなりつつあ る。
3. 株価上昇のメリットは外国人投資家が独占
株価の上昇はどのような効果をもたらすか。今、日本の株式市場で株 価を動かしているのは外国人投資家で、市場で売買される株式の3分の2は外人株である。日本の家計の金融資産のうち株式の割合は6%だ。米国の56%、 ヨーロッパの36%と比べて圧倒的に低く、仮に株価が上がっても、一般家計へのメリットはほとんどない。株は価格変動幅が大きく、リスク資産なので、国内 の金融機関や年金基金はほとんど持っていない。一般企業は関連会社の株を持っているが、これらは持ち合い株で売買されることはないので、実際の利益や キャッシュ・フローにはならない。3月末の決算で帳簿上の含み資産が多少増える程度であろう。株価の動向は総理が衆議院解散を決める際の重要な判断材料と 言われるが、昨年11月以降の急激な株価の上昇が国民一般にどれほどメリットがあるか極めて疑わしい。
このように考えると、今時点でのアベノミクスに対する高揚感はかな り実態のないもののように思われる。今日までのところは、何か大胆なことをやってくれるのではないか、という漠然とした「期待」で為替も株価も動いてきた が、実体経済への影響がはっきりするのはこれからであろう。最初に出てくるのは円安の物価への影響だ。すでに卸売物価は昨年11月から輸入品をはじめとし て上昇し始めており、末端市場でもガソリン価格は上昇している。これから電力やガス料金の上昇が避けられない。小麦粉などの食料原材料も1月から上昇して いる。
4. インフレ期待で消費は盛り上がらない
アベノミクスは、「インフレ期待が盛り上がれば、消費者は物価が上 昇する前にモノを買おうとするから、需要が盛り上がりデフレも収まる」という仮説に立っているが、本当だろうか? 筆者はむしろ逆ではないかと思う。日銀 が定期的に行っている「生活者の意識に関する調査(2012年9月)」によれば、国民の62%は1年先の物価は上がる、と見ている。インフレ期待はすでに 出来ているのだ。だが、それにより消費が盛り上がるという感じはない。人間の日々の消費行動は決まっており、インフレになりそうだから先に食べたり、遊ん だりすることはない。もちろん耐久消費財の場合、値上がりする前に買っておこう、という行為はあり得るが、それは消費の先食いで、一時的に盛り上がった後 に必ず反落する。昨年後半の景気後退はエコカーやエコ・ポイントといった消費促進措置が切れたことで起こった。逆に、長期的には将来物価が上がりそうだ、 と思えば、将来に備えてより貯金を増やす、つまり現在の消費を削減する、というのが普通の消費者の行動ではないか。こうしてみると、インフレ期待が出てく れば消費も回復する、と考えるのは極めて危険だ。
5. デフレ脱却の鍵は賃金の上昇
なぜ日本だけが長期のデフレに悩まされているのか? 答えは日本だ けが傾向的に賃金が下落し続けているからである。米国の場合、モノの価格は日本と同様、ディスインフレで物価上昇率はゼロに近いところまで下がっている。 だが、サービス価格はリーマン・ショック直後を除き、安定的に2%程度の上昇を続けている。その結果、モノとサービスを合計した消費者物価指数は年率 1.5~2%程度の緩やかな上昇となって、マイナスになることはない。欧州でもほぼ同様の傾向である。
「モノ」は国際貿易を通じて自由に移動するので、国ごとに価格の動 きが大きく異なることは稀だ。しかし、サービス価格は国によって動きが異なり、日本のサービス価格の下落は他の先進国では見られない特異な現象だ。消費者 物価指数のうちサービスの占める割合は先進国ではいずれも5割を超えるので、このサービス価格のインパクトは大きい。サービスの中身は公共料金や交通費、 家賃など多様だが、対人サービスに代表されるように、ほとんどが労働集約的であり、賃金の動きとサービス価格は連動する。ということは、日本のデフレは賃 金の低迷に起因する、と結論づけることが可能だ。したがって、いくら金融政策を緩和しても賃金が上昇しなければ、デフレ脱却はできない。
6. 分配率が下がると選挙に負ける
このようにアベノミクスは根拠の疑わしい論に基づいたものであり、 長続きしない可能性が高い。これをもっと力強い経済成長にするために必要なことは、賃金の引き上げである。政府は前哨戦が始まりつつある春闘に向けて経営 側の前向きな姿勢を引き出す必要がある。すでに円高の修正は相当程度実現した。日銀による大胆な金融緩和も実現した。次は、産業界がデフレ克服に向けて積 極的な貢献をすべき時だ。2%のインフレ目標を真面目に考えているのであれば、所得を2%以上拡大するための措置も並行してとらなければ、国民生活は実質 低下する。円安の効果も、このままではメリットは企業が手にし、負担は国民に転嫁されることになりそうだ。労働分配率はさらに下がるだろう。安倍総理が6 年前に参議院選挙で大敗した時、労働分配率は1960年代の高度成長期を除き、戦後最低であったことを忘れてはならない。今世紀に入ってからの国政選挙を 見ると、労働分配率の低下後には政権与党は勝てない、という傾向が明らかだ。
2013年度の税制改正の中に、雇用や給与を増やした企業には法人 税減税を行うという措置が含まれている。これは雇用者所得を増やすことの重要性を理解している証ではある。安倍総理肝いりのようだが、産業界は冷やかで、 これを機に雇用や賃金を増大させる様子はない。ベースアップや定期昇給といった、勤労者所得を安定的に引き上げていくことは議論にさえなっていない。
7. かつて自由民主党は経済界に賃上げ要請した
政府が賃金決定に介入するのは行き過ぎ、という意見もあろう。だ が、かかる要求は前例がある。それも自由民主党からだ。第1次安倍内閣の後を継いだ福田内閣の下での2008年8月の総合経済対策の中に「経済界に対する 賃上げ要請」が含まれている。これを受けて9月10日、当時の二階経済産業大臣が実際に御手洗経団連会長にかかる要請を行い、経団連会長もかかる方向で努 力することを約束した。筆者はこの席に同席した経済産業省の課長(当時)からこの話を直接聞いた。経済産業省の中にも企業が内部留保を溜め込むだけではな く、一部を賃金という形で還元し、国内需要を喚起すべきだ、という考えがあった。しかし、わずか5日後のリーマン・ショックですべてが水泡に帰した。翌年 の麻生内閣の時にも同様の要請は行われたが、産業界には無視され、2009年8月の総選挙で自由民主党は大敗し、民主党に政権を奪われた。
このような賃上げ要求は理不尽な話だろうか。日本のGDP473兆 円のうち賃金は52%の245兆円である。仮にこれを4%引き上げるとすれば、10兆円必要になる。他方、企業が保有している現金・預金は215兆円だ。 米国と比較しても、この数字は異常に大きい。株主の発言権が強い米国では、余分な金は株主に還元せよとの圧力が加わり、必要以上の金が企業の手元に留まる ということはない。コーポレート・ガバナンスが十分働かない日本では、政府が企業に対して賃上げや配当増加の要請をしても誤りではないと思う。
【図1】は日本企業の流動比率の動きを示したものだが、急速に高まっていることがわかる。仮に10兆円賃金に回したとしても、ほんの数ポイント下がるだけで、企業経営にまったく影響しないはずだ。
【図1】流動比率(当期末)【%】 
賃上げは貯蓄に回って消費は増えないという意見もある。麻生総理の 下で実施された定額給付金は3分の2が貯蓄に回ってしまった、と言われる。確かにボーナスや一時的な賃上げは消費者行動を変えるほどのインパクトはない。 しかし、収入が安定的に増えるということになれば、消費は拡大し、経済成長につながる。国民の過半数を占める勤労者の給与所得が拡大することで初めて本格 的な成長シナリオが描ける。
安倍新総理は円安、株高を演出することで、経済界に大きな貸しを 作った。日銀も金融緩和に向けて大胆に行動することを約束している。今度は産業界が安倍総理に協力すべきである。7月の参議院選挙に向けて、この貸しを返 してもらうには、今ほど良いタイミングはない。経済財政諮問会議や産業再生会議には産業界からの代表も多く含まれているが、今までのところ、産業界からの 「御用聞き」の場のように見える。これからは政府、日銀、産業界がそれぞれの役割を確認し、責任を持って行動し、その結果を確認する場として機能すべき だ。マクロ経済や財政状況に加えて、企業収益や賃金、労働分配率なども定期的に検証し、成長の成果が公正に配分されているかチェックするなど、強力な政策 展開が必要だが、安倍総理はそのための武器を手にしている。安倍さん、頑張れ!










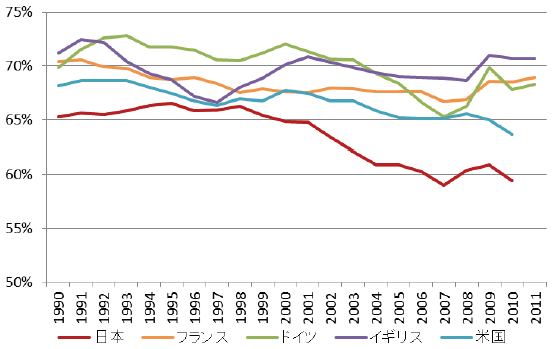






















内部留保を増やす気持ちもわからない訳ではありませんが、そこは政府がなんとかしてほしいものです。
賃金を上げて、労働時間を短縮するという、思い切りができないかぎりは、何も変わらず、悪い方へ向かうばかりだと思います。
どうも、こういうことらしいです。
バブル崩壊後、アメリカの圧力による金融ビッグバンと国際会計基準、グローバルスタンダードやらで、持ち合っていた株を市場に出すとともに外資規制を外し、平均株価が下がり、円安になったので、いわゆるハゲタカファンドが企業買収を繰り返すようになりました。自分の会社が買収されると、旧経営者は地位も権力も名誉も失って「ハダカ」になってしまいます。
法的に買収しやすくした日本で、自分の会社の買収を防ぐには(1)首切り、海外移転、非正規化で人件費をカットし、内部留保をひたすら溜め込み格付けを上げる(2)配当を上げる(3)自社株を時価で市場から買い戻すという倒錯を行う、という高株価策(と(3)とも関係しますが社員株主会・持ち合いの復活などの安定株主の強化、敗戦後の財閥解体で禁じた持株会社の復活)を行いました。
というわけで、単純な「経済」で言えば、儲けは、(1)値下げしてシェアを拡大して他社を潰し独占する(2)会社は出資した株主のためにあるので配当を増やす(3)研究開発・設備投資に回して、新製品の開発や生産コストを下げ、需要を獲得する(4)フォード主義で賃金に回して需要を拡大して経済のパイを大きくする・高賃金でロイヤリティとモラールを高めるとともに生産性の高い社員を集めるのが、教科書的正解です。
しかし、猿は木から落ちても猿ですが、社長たちはハゲタカに乗っ取られたら惨めです。そこで、自分が全てですから、買収さえされなければいい、1%以外がどうなろうと、日本経済がひどくなろうとブタ積みすることにしたわけです。で、ついでに自分の給料ほかはむちゃくちゃ増やしたと。
ですから、ブタ積み上げしている内部留保は自主的に崩すことはできないし、ありえません。積み上げないと死んじゃう病なのです。まして、賃金のために使うことはない。使えないお金を増やしてかえって自分の足(内需、未来)を食っているんだから全くグロテスクな話です。が、奴らは4半期、3ヶ月先までしか考えないそうですからその限りでは正解です。わが亡きあとに洪水よきたれ、です。
奴らの枕詞のように、企業の存亡をかけた厳しい国際(価格)競争があるなら、当然内部留保の代わりに値引きをしてお金が残るはずはないです。偉い人の給料だって、交際費だって黒塗りの車のお金だってほとんど出せません。ですから、「国際競争が厳しいから賃上げができない」は、全くの大嘘です。
斎藤貴男さんの本や「世界」の品川正治さんの連載を読むと、かつての会社の偉い人は、限界はあるにせよ、社員や会社、国全体のことを考えて会社を運営していたんだなあと思います。現在のエラそうなだけの経営者との違いに呆然とします。
正直、絶望街道まっしぐらいです
「自己責任!?」
「はい、自己責任です(爆)」
自分が社会の底辺になってみて気が付くのが(こういう言い方はよくないのですが、リアルに伝えたいのでご容赦ください)時給が安すぎて、生活が苦しいということです。
とくに、フルで8時間働いても自宅がなければ、日用品以外はまったくお金を使うことができません。LECに通ううこともできません(微笑)
年金もフルペンションで払っていないので老後も心配で、
生きてても意味がないなぁと思うこともあります。
とにかく、正社員さんもそうでしょうが非正規の賃金を上げないと消費することができません
「安倍様なんとかしてくだせぇー!!、おねげぇしますだぁ」
賃金の上昇も大事だが、まずは今現在失業中の方が職を見つけることのほうが優先順位は高い、という考え方が、それほどおかしいでしょうか?
インフレ期待上昇で消費が盛り上がらないというのも、もう一度考えなおされた方がいいと思います。皆さんローンを組んで家や車を買うときは金利を気にしますよね?そのとき考慮する金利は名目金利ではなくインフレ率を考慮した実質金利ですよね?(インフレ率5%のときに銀行の金利が5%だったら、あなたは喜びますか?)
実質金利=名目金利ー期待インフレ率
上記の関係から、インフレ期待が高まると実質金利が下がります。金利が下がれば家や車を買おうという人が増えるのは当たり前だと思うのですが、そうは思われないのでしょうか?
日本は物価が高すぎる。だから輸入でもOKなもの(生鮮野菜なんかは×)は、海外から安いものがどんどん輸入される。輸入品に価格競争で負けまいとすれば、国内企業はコストを削らざるを得ない。一番手をつけやすいのが(輸入相手国と比較して)高すぎる賃金。
企業の選択肢として海外で生産するのも有り。当然労働に対する需要が減り、結局これも賃金を押し下げる原因となる。
結局、諸外国(特にアジア圏)並みの賃金・物価になるまでデフレは続くと思います。(もしくは逆にアジア圏の賃金・物価が日本に近くなってもOK)TPPに参加したらもっとデフレのスピードが早くなるでしょう。
ただでさえ高い賃金を上げようなんて無謀です。残念ながら経団連のお偉いさんが言うとおり、国内産業は壊滅しますよ。より中小企業にダメージが集中しますが。
また、失業よりも雇用というという気持ちの切実さはわかるが、生活・命が続かないような安い上にひどい条件の雇用では意味がないと思う。実際、死んだり壊れたり、あるいは働き続けられなくなる人は少なくない。
賃金は受給で決まるわけだが、労働需要だけではなく、労働供給も増えるだろう。まず、いま製造業ほかで大量のリストラが行われている。生活保護基準の切り下げと働け圧力、インフレと国民負担率の上昇により、求職者も増える。すぐではないかもしれないが、最賃の例外を研修生や障害者から広げる動きがある。時給300円で働かされてはそうでない者にとっても賃下げ圧力で”迷惑”である。維新なんて最賃廃止!の本音を隠さないし。つまり、さらに賃下げ圧力が高まる。「NOと言えない労働者」によって賃下げ圧力が高まり、浮かした金で内部留保がブタ積み・死蔵(実際にはヘッジファンドに突っ込んで穴を開け税金で補填させたりするのだからもっと悪いが)されるくらいなら、生活保護を給付する方が金が回るし、賃下げ圧力が抑制されてなんぼかマシだ。
生活保護基準の切り下げに因って、安倍政権は僕らの”ハダカ”の価値、健康で文化的な最低限度生活の内容を値切りやがったわけだが、これは最賃や税・社会保険・医療費などの減免、各種給付と連動していている。つまり、一層可処分所得が減るが、それでも最低限度以上にしたわけだ。
アベノミクスで言えば、金利が上がり、輸入物価が上がり、連れて他の物物価上がり、賃金は上がらない。円安で電気料やその他公共料金も上がるだろう。金巡りの悪い人の国民負担率は上がり、給付は減るが、金持ちは贈与税(と相続税)が減る。国が突っ込むお金の少なくない部分は結局彼らの手元に積み上がり回転は悪いだろう。
さて、
>金利が下がれば家や車を買おうという人が増えるのは当たり前だと思うのですが、そうは思われないのでしょうか?
条件を切り縮めて考えれば、正しかろうが、
今の情勢では正解とは言えない。
貯金のない世帯が3割で、可処分所得が減る見通しなのだし、多くの人は家を借金して買った人たちがバブル崩壊後、どんな惨めで辛い目にあったかよく覚えている。家を借金して買った被災地の人たちがどんな苦しい目にあっているかは記憶に新しい。アラウンド失業者なら、とても新築・新車など考えられまい。空家は大量にあるし人口減で地価は低落トレンドだから、リスクを考えたら賃貸、せいぜい中古になる。車だって若い者は特にだが、中古でさえ維持費が出せないから持てずにいる。借金といえば、学生の半分は”奨学金”を借りているという。就職難と低賃金の中、”奨学金”は破産処理できないから(保証人が被る)、本人と家族の数百万の借金の負担は本当に大変だろう。意識している人はいないだろうが去年、政府の国家戦略会議 繁栄のフロンティア部会から、非正規を基本とした上で「40歳定年制」案が出ている。扱いが廃鶏や廃乳牛並だが、奴らは「家畜は潰したら金になるが、奴隷は殺しても経費がかかりやがる」と言いそうだ。郵政会社の非正規は定年がありクビになる。もう一度雇われた人もいるが給料の技能等級が振り出しに戻っていたそうだ。こうしたことを考えたら、目先のインフレ期待だけで地震が来ないことにして土地バブルの再来にでもかけない限り、家は買えないでしょ。でも、30年前後のスパンで見て、失業と、残債割れと、ETCを考えたら無理です。
あと、金持ちは家も車も現金もあるんで、金利が下がっても、借金して買おうとは思わない。賃貸用はあるかもしれないけど、供給が多いし客の支払い能力が低い上に下がるなら、借金してまではやりづらいんじゃないの。今、超低金利で、現金もあるのに溜め込んでいるというのはそういう事。
これから来るのは、目先はまだしも悪性のスタグフレーションというのが実態でしょう。
ま、イギリスの競馬に見られるようにバクチは所詮金持ちの遊びですよ。
>>物価が上がっても国民の賃金はすぐには上がりません。インフレ率と失業の相関関係を示すフィリップス曲線(インフレ率が上昇すると失業率が下がることを示す)を見てもわかる通り、名目賃金には硬直性があるため、期待インフレ率が上がると、実質賃金は一時的に下がり、そのため雇用が増えるのです。こうした経路を経て、緩やかな物価上昇の中で実質所得の増加へとつながっていくのです。
あなたの挙げた文章の前には上の文章が付いていますね。なぜこれを抜いたのでしょうか。
この前置きがあるのとないのでは、文章から受ける印象が変わりますね。
安倍憎しは分りますがミスリードはよくないですよ。
上の方もコメントに書かれていますが雇用が回復する事がそんなに悪い事ですかね。
物には順番があり雇用回復の後に賃金が上昇と言っているだけでしょう。
他に何かやり方ありますかね?
内部留保を使うべきだと言いますが、どのような政策でおこなうのですか?内部留保はしてはいけないと法律で定めますか?最低賃金を上げて厳しく施行していきますか?どちらにしろ倒産する会社が大量に出ますね。
しかし左巻の人はやたら内部留保を目の敵にしますが、会社の将来のためにお金を蓄えておく事がそんなにイケない事ですかね?
最低賃金の引上げや賃金の引上げを決めると、インフレ期待醸成に役立ちます。
>うーんさん
>物には順番があり雇用回復の後に賃金が上昇と言っているだけでしょう。
>他に何かやり方ありますかね?
リフレ派の議論で、リフレ政策自体は経済のパイを拡大する政策だからいろんな政策パッケージと両立できる、という説明がよくなされます。
しかし、実際はたとえ一時期でも実質賃金率が低下する時期があり得るわけです。それは、労働者のパイが一時期減ってしまい、損をする人も出るわけです。特に今回は生活保護水準の引き下げを伴っています。生活保護世代は苦しくなるでしょうね。
であるならば、雇用回復までの期間、実質賃金率が低下する期間の間には、それを補うための所得再分配政策とパッケージにしなければつりあいがとれないわけですが、それは生活保護水準や最低賃金率のインフレ率に合わせた上昇の設定を必要とします。
それとは別に、中央銀行がインフレターゲットを設定しても、誰がそれを信じるんだ?という点がどうしても残ります。賃金率の引上げが決まれば、それに応じてインフレ期待も高まるでしょう。
インフレ期待を確実に高めるために、賃金率上昇が効果的という議論もあるのです。「先に実質賃金率の低下が必ず必要」というわけでは無いです。
たしか、今週号の週刊現代の記事で、リフレ派の田中秀臣先生だか誰かが、賃金率の引き上げは効果的と言っている記事があったので、参考にしてみて下さい。
ともかく、インフレ政策をとるならば生活保護水準の引き下げは許容できない。筋が通らない。
2013/1/11 23:28
政府が緊急経済対策で打ち出した目玉となる数値が「60万人の雇用創出」だ。単純計算で完全失業率を約1%押し下げる目標だが、前提となる経済成長率の押し上げ効果には民間のエコノミストから疑問の声が上がっている。
60万人雇用の根拠となっているのは、今回の経済対策が2013年度の実質成長率を約2%高める見通しだ。実質国内総生産(GDP)の増加額を過去の統計データに基づく計算式に入れ、雇用拡大の予想を機械的にはじき出した。
しかし前提となる13年度の成長率の押し上げ効果については多くの民間エコノミストは0.5~0.8%程度とみている。政府が掲げる2%は「あまり現実的な数字ではない」(野村証券金融経済研究所の木下智夫チーフエコノミスト)との見方が多い。
2%の達成が難しい理由の一つは建設業の人材不足だ。東日本大震災後、当時の民主党政権が巨額の復興事業に取り組んだことで建設業の求人が急増。しかし少子化などの影響もあり、思うように現場の人材が集まらず、予算を円滑に消化できていないのが実情だ。
政府は予算を付けた公共事業がすべて実施される見込みで目標をつくるが、BNPパリバ証券の河野龍太郎チーフエコノミストは「この状態で新たに金を積んでも効果は限定的」と主張する。
2%達成が難しいもう1つの理由は波及効果の見込みの大きさにある。企業は投資や雇用の拡大に慎重だ。第一生命経済研究所の熊野英生首席エコノミストは「大きな波及効果を期待できない」と話す。今回の対策による雇用創出は「せいぜい15万人」(BNPパリバ証券の河野氏)との慎重な見方が多い。
政府は経済対策をまとめるため「楽観的な目標を立てやすい傾向がある」(ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査室長)との声もある。
同友会代表幹事「新税制で賃上げ進まず」
2013/1/16 19:37
経済同友会の長谷川閑史代表幹事は16日の記者会見で、2013年度税制改正で浮上している、従業員の平均給与を増やした企業の法人税を減税する新制度に「それで賃上げが進むとは思えない」と批判した。長谷川氏は「賃金は一度上げれば下げられない」と指摘。そのうえで「減税は一時的なものと考えると減税があるから賃上げしようとはならない」とした。
基本的にお金は、使えば使うほど増えるのが経済学の基本。にもかかわらず、偉い人の自己中な強欲で、実体経済に回らずに大企業と金持ちの懐に何百兆とブタ積みされている。企業も含めた富裕税も良いし、法人税に累進課税し、総合課税にして所得税の累進率を昔に戻し、相続税も累進率を上に伸ばす。消費税は昔のように物品税に戻す。かつてのように脱税を防ぐべく、「長者番付」を復活し、市民に情報提供を呼びかける。ついでに「納税愛国者法」でも作って、金持ちや企業の脱税や海外などへの税逃れを厳しく取り締まると共に「非国民」「売国奴」「反社会的分子」「テロリストより有害で卑劣」「人道に対する犯罪者」「絶対悪」「手を汚さぬ大量虐殺者」として晒して厳罰、海外に逃げたら逃げたでそれなりに落とし前をつけさせたらいいんじゃないの。ケチな生活保護の「不正受給」とは総額でも2~3桁違うんだからさ。で、高額納税・寄付者・企業は額に応じて紫綬報国勲章とか、愛国大勲位とか叙勲したらいい。名誉大蔵大臣とか、名誉日銀総裁もいいな。そうだ、額に応じた記念硬貨も発行してやろう。
で、税金を集めれば、(1)企業は利益にかかる税金を払うのが悔しいので利益を圧縮するべく、社員に配る方がまだマシだと賃金を増やす・保養所・社員寮とか雇用が増えるから福利厚生減税を増やすのも良い(バブル崩壊前はこうだったんだよ)、(2)経済好調な北欧のように、集めた税金を消費性向の高いすなわち金巡りの悪い人たちから順番に再配分するとともに、教育・保育・医療。福祉などに回す。
こうすれば、金が好循環し、雇用が増え、金が増える。銀行をはじめ、すべての金は偉い人の懐を何度も通るので、偉い人はもっと儲かる。また、(2)のようなことをしないと、才能のある人でさえ冒険できなくて新しい金儲けにつながらない。
あとは「企業は将来のために内部留保を貯めている」というのだけど、トヨタのように「全社員を何十年も草むしりさせていられる程、金を溜め込む」のは不自然でしょ。困ったときには脅せば国が兆の単位で税金を突っ込むし、投資で金が足りなければ、株でも社債でも出せばいい(儲けが見込めるから投資するんでしょ)し、直接・間接的に国・自治体に出させることもやってきた。消費税だって、輸出企業への体の良い補助策(戻し税が下請け泣かせでタダ取りに)としてフランスから輸入したんだし。円安誘導の為替介入も実質的にはむちゃくちゃ非効率な輸出企業への迂回補助金だからねえ。企業が輸出を増やせば円高に振れ、企業の手持ちのドルの価値が下がるのでドルを売るからますます円高になる。で、企業の都合が悪くなる。自業自得・自己責任なんだし、金があるんだから、輸出企業組合でも作って自分で為替介入すればよさそうなもんだが、それどころか差損が嫌だから、輸出で得た巨額のドルを売ってますます円高を拡大している。で、もっともらしい口実をつけてグルである政府を抱き込んで何兆もの差損を国民に付け回すのを前提に国に介入させると。いわゆる「利潤の私益化、費用の社会化」ですな。ついでに国内外のハゲタカさんも「日本の皆さん、ごっちゃんです!」
という訳で、巨額の内部留保を溜め込むのは、企業が将来の投資の必要ではなく、企業の偉い人の「将来」のために過ぎないのよ。
いわば金巡りが、”腸重積”を起こしているんだから、高圧浣腸の如き、強力な再配分策をやらないとハラワタが”壊死”して死んじまうよ。
安倍ら、偉い人がやっているのは、原因に目を背けて、それは自分たちの失敗とご都合主義・反道徳を見つめることだから自慰史観者には無理な相談だわな、「痛いのだからモルヒネを、苦しそうだから酸素吸入を、熱があるから解熱剤を」とやっていることに過ぎず、問題は悪化すれど、減速することさえできない。まあ、自分たちさえ当面良ければいいのだから、その意味では完璧な正解だけどね。でも、投資用資産が1億ある1%の金持ちでないのに、謎めいたこと言ってまで、こんなアベノミクスを擁護する人がいるのはなぜなんだろう。
まず、フィリップス曲線の理論は後付けです。実は統計的な相関関係のみで考えられたもので、因果関係は明確には分かっていません。
しかも、後付けされた理論も、時代遅れの完全なオールド・ケインジアンで、普通に考えたら無理があります。
確かに、短期フィリップ曲線の貨幣錯覚理論は、インフレによる実質賃金の低下によって雇用増加が起きると推定しています。しかし、いま賃金減による増益で雇用を増やすと思いますか?
貨幣錯覚理論では、資本と労働は完全に代替的で、労働価格が下がることで、企業が機械よりも人に投資することを想定しています。しかし、いまこの時代に、機械と人間が代替的で企業が「機械より人間が安いから人間を雇う」と思うでしょうか?
それに、今回家電メーカーがやばいのは、小泉景気とエコポイントで、過剰に生産設備に投資をしてしまったことも原因の一つと言われています。人を正社員にしようと思ったら、基本的には一生面倒を見る事を考えて雇います。正社員雇用によるコストのフローの増加は長期です。短期的な賃金の下落によって、生産要素への過剰投資という過ちを繰り返す企業はないでしょう。どうせ雇用が増えたって、契約社員。また派遣切りにあって、雇用は減るでしょう。
だから、長期フィリップスは、もともとの失業率水準に戻るのです。
浜田教授は経済"史"学者(古い理論の追求)という意味では優秀かもしれませんが、現代では役に立たない骨董品という謗りを免れません。