
『“グリムおばさん”とよばれてーメルヒェンを語りつづけた日々』
シャルロッテ・ルジュモン著 高野享子訳 こぐま社
そもそも私自身はなぜ昔話の魔力のとりこになったんでしたっけ?振り返ってみました
 。
。子どもの頃毎年もらっていたはずのサンタさんからプレゼント、大人になった今でも覚えているのはたった二つだけ!そのうちの一つが偕成社の全5巻のグリム童話全集でした
 。夢中になって何回も読み返したっけ。
。夢中になって何回も読み返したっけ。原作の挿絵を使っているこのグリム童話は話の内容も挿絵もかなりグロテスク。とにかく怖がりで、ちょっとでも暴力的な場面が少しでもでてくるとダメな私が、なぜあんなに残酷な場面オンパレードのグリム童話には惹きつけられたのか。自分でもずっと謎だったんです。だってねー、継母が男の子にりんごを取らせようとしてリンゴの箱のフタを閉めて、男の子の首ちょんぎっちゃったりするんですよ~!?!?。おいおいっ、でしょう?この「なぜ?」という思いが心のどこかにずーっとあったんでしょうね。
それから20年以上たち、子育てする中で知り合いになったあるママから
「グリム童話って実はすごいのよ!お薦めの本があるから読んでみて」
と言われ読んだのが『“グリムおばさん”とよばれて』だったんです。思えば、結構マニアックな本薦めてくれたなあ、このママさん(笑)。だって、一般には目にすることのない地下書庫に眠っているような本。彼女は元図書館員の方でした
 。
。で、この本がもうもう面白くて!昔話の持つ癒しの力にただただ驚きました
 。だってね、刑務所での受刑者たちや、野戦病院で傷ついた兵士たちの心をどんどん癒していくんですよー。すごくないですか!?昔を思い出してというのでなく、幼い頃昔話を聞いた思い出がない人まで!子どもだけで大人の心を癒していったという事実は読んだ当時は結構衝撃的でした
。だってね、刑務所での受刑者たちや、野戦病院で傷ついた兵士たちの心をどんどん癒していくんですよー。すごくないですか!?昔を思い出してというのでなく、幼い頃昔話を聞いた思い出がない人まで!子どもだけで大人の心を癒していったという事実は読んだ当時は結構衝撃的でした 。ゴメンナサイ!昔話の持つ力軽く考えすぎてましたー。ははー
。ゴメンナサイ!昔話の持つ力軽く考えすぎてましたー。ははー 、って感じ。
、って感じ。この本を皮切りに、松岡享子さん、脇明子さん、清水真砂子さんの本を読み漁り、色んなもやもやが解明されてスッキリ!河合隼雄さんが心理学の無意識の構造から昔話の魔力について解き明かしたのも面白かった(読んだそばから内容は忘れるけれど
 )。
)。学問的な解釈も面白いけれど、でもグリムおばさんの実績見て、みんなが癒されたというこの事実、この事実が昔話の持つ力のすべてを語っているように思います。
最近は、『桃太郎』なんかでも、鬼が改心して最後みんな仲良くなったり、いろんな改竄が見受けられます。でも、それをやっちゃいけない理由がこれらの本読むとよく分かる。
今では昔話の持つ力を当たり前のように思っている私ですが、そんな私でも、絵本による昔話の読み聞かせは未就学児までで、就学後は自分で読む、もっと長い物語にすぐ移行したほうがいいって思ってたんですよね(ほぼ忘れかけてたけど
 )。その考えが覆りました。今の子に足りないのって、物語、こういった昔話なんじゃないかと真剣に思う今日この頃。本当は絵本じゃなくて、“語り”がいいんですよねえ・・・まだそこまでの勇気はないので今度挑戦してみたいです。
)。その考えが覆りました。今の子に足りないのって、物語、こういった昔話なんじゃないかと真剣に思う今日この頃。本当は絵本じゃなくて、“語り”がいいんですよねえ・・・まだそこまでの勇気はないので今度挑戦してみたいです。









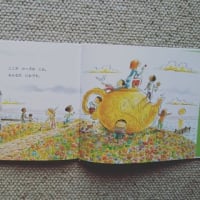

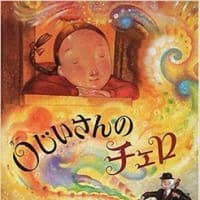
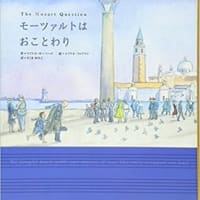
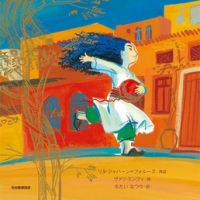
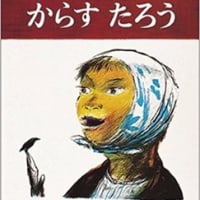
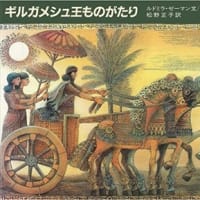



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます