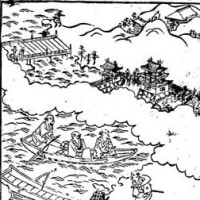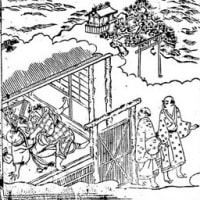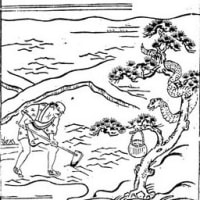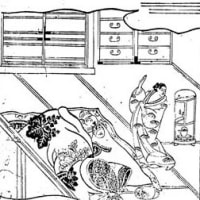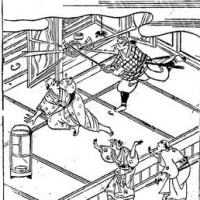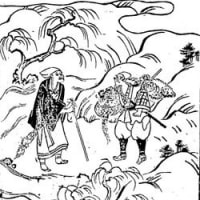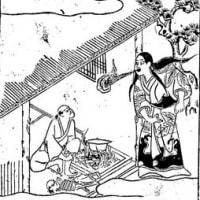ご訪問ありがとうございます→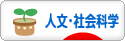 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
歴史の知識といえば、たいていは学生の頃に勉強した(詰め込んだ、と言うほうが適切かな)ことが全てで、その後、新しい知識を仕入れていない限り、何十年経っても、その知識が、その人の「常識」として留まっています。
さて、掲題の元寇ですが、学生時代を何十年か前に過ごした私と同年代の方にとっては、以下の内容が「常識」だろうと思います。
『2回にわたる元寇で、武器や戦法に勝れた元軍は、日本軍を散々悩ませましたが、2回とも、夜中に暴風が来て、船に戻っていた元軍は一夜にして壊滅しました。この暴風雨を、日本人は後々まで「神風」として崇めました』
この「2回とも」という部分が、私にとって長い間の疑問でした。
軍事により一大帝国を築いた元が、軍事上重要な情報である東シナ海の気象を知らないはずはなく、わざわざ台風の季節に艦隊を仕立ててやってくること自体、腑に落ちませんし、さらには、同じ間違いを二度も犯し、十数万の兵士を犠牲にして自滅するなど、どう考えても軍事大国らしからぬ過ちです。
それでも、天気予報などなかった時代、一度目は「読みが外れた」かとも解釈できますが、一度目が失敗した時点でその将軍は更迭(たぶん処刑)され、後任の将軍は前回の失敗をよく検討して事に臨むのが軍事というもので、こんな行き当たりばったりの、まるでわざと兵士を海に沈めるような作戦などあり得ない、という疑問です。
ところが、最近になって知ったのですが、やはり、元寇についての古い「常識」には、裏があったようです。
まずは、説明上、鍵となる事項を整理してみましょう。
1.文永の役では約3万、弘安の役では約15万の兵が来た
2.文永の役は1274年11月、つまり台風の季節ではない
弘安の役は1281年6~8月で、これは台風の季節
3.日本側の記録によると、文永の役では一夜にして元軍が引き上げたが、弘安の役では確かに暴風雨によって壊滅した
4.軍は、元軍単独ではなく、元および元が服属させた高句麗・南宋との連合軍であった。
特に弘安の役では、元以外の兵が10万を超えていた
以上から、最新の学説は次のようになっています。
1.兵力について
文永の役で、わずか3万の動員ということは、少なくとも文永の役においては、元に、本気で日本を征服する意図はなかったと思われる。それよりも15万を動員した弘安の役が本番で、文永の役は、日本側の防衛力を確認する前哨戦と見るのが適当。
ただ、一旦引き上げることで、元軍は自らの装備(てつはう・蒙古弓など)を明かしてしまうとともに、日本側に防衛体制増強(防塁など)の余裕を与えてしまっているのは、元軍戦略上の不手際だろうが、後述のとおり「日本侵略があまり本気ではなかった」としたら、日本側にわざとそうさせたのかもしれない。
2.台風について
文永の役は11月だから、台風が来ることは、まず、あり得ない。
また、文永の役が自主的な撤退であったのなら、弘安の役に際して、元軍が迂闊にも気象条件を考慮の外としたのは、まあ、不可解ではない。
さらには、これも前述のとおり、「わざと」の可能性さえある。
3.元軍撤退理由について
文永の役は前述のとおり「前哨戦」と見るべきなので、日本側の戦力を測るという目的が達成されれば長居は無用、さっさと引き上げるのが合目的的である。
弘安の役で台風が来たのは事実で、15万のうち10~12万が海に沈み、これは間違いなく敗戦である。
4.連合軍であったこと
元は高句麗・南宋を服属させたが、両国の残存が元におとなしく従うはずはなく、元にとってそのような不満分子は厄介者に過ぎない。
また攻略した国の者を、次の侵略戦争で尖兵として使うのは常套手段であるが、高句麗・南宋人にとっては、自分らの国を侵略した元に対しての忠誠心などあろうはずもなく、彼らの士気は極めて低く、戦役前の造船においても、日本での合戦においても、まるでやる気がなかった。
これらのことから導き出される結論は、
『元の日本侵略作戦は、あまり本気であったとは考えにくい。それでも、元からの国書を無視した日本を痛い目に合わせねば、元の威光に傷がつくから、勝敗に関わらず、攻めてみたものである。そして首尾よく日本を攻略できれば、それはそれで良し、もし攻略できなくても、不満分子である高句麗・南宋の兵は全滅するから、どっちに転んでも元にとっては都合がいい、という戦いであり、結局、後者の結果に落ち着いた。ただ、暴風雨によって、高句麗・南宋兵だけでなく、元軍そのものにも壊滅的な打撃が及んだのは計算外だったらしく、元は、海軍力の弱体化を招いた』
というものです。
これには目から鱗の落ちる思いがしたと同時に、私が、辻褄が合わないと思っていた点にも、なるほど高句麗・南宋という「捨て駒」での戦ならさもありなん、という明快な回答をくれるものでした。
さて、歴史上の事実はこれで整理がついたとしても、それではと湧き上がる疑問、「なぜ、歴史的事実が正しく伝わらず、歪曲された事実が伝わり、あまつさえ学校で検定教科書を用い、そう教え続けたのか」という点についてはどうでしょう?
これには、前記4つに続く鍵、
5.私の世代では、学校の先生(旧文部省というべきか)にも太平洋戦争経験者が多かった
という事実を、残念ながら、付け加えねばなりません。
圧倒的な軍事力を誇る元軍が、終始優勢に戦を進めていたにもかかわらず、一度ならず二度までも、偶然・・・つまり人智を超えた・・・暴風雨によって壊滅し敗退した、という事実(ではありませんが)からは、次の結論が導き出されます。
『日本は神国であり、たとえ夷敵が攻めてこようとも、最終的には「神風」が吹き、寸土も侵されることなく、わが国は勝利する』
これが、私たちの先生が少年時代を過ごしたであろう戦前の、国威高揚によるものであることに疑いの余地はありません。このように勇ましくも神々しい話は、軍国少年らの心に深く刻み込まれ、戦後、純粋な少年らが大人になって数十年経っても、その呪縛から解き放たれることはなかったのです。
戦前・戦時中の教育について知れば、まるで集団催眠とも言える教育ですが、私は、それは終戦とともに消え去り、戦後は民主的な教育に姿を変えたものとばかり思っていました。しかし、意図していなかったと信じたいですが、戦前教育の影は、戦後数十年にわたって影響を残し続けていたのです。
では、日本側の記録で明らかなように、そもそも文永の役では「神風」など吹いていないにもかかわらず、なぜ永きにわたって、吹いたことになっていたのでしょうか。
歴史編纂の際に資料とした、八幡神を喧伝する「八幡愚童訓」という書(宗教書であり、歴史を正しく伝えた書ではないことに留意してください)の中に、「2度とも神風が吹いた」という記述があるそうです。
これが、明治時代の富国強兵政策華やかなりし頃、歴史の教科書を編纂する際に都合よく利用されたであろうことは、想像に難くありません。
つまり、元寇という歴史を捻じ曲げてしまった「戦犯」は、この編者だったのです。
教科書の歴史が間違っていて、元軍が2度とも暴風で壊滅したと教えていたとしても、真実が詳らかになったのなら(もとから分かっていたことでしたが)、それは新しい事実を教えればいいわけですから、取り返しのつく過ちです。
しかし、根拠のない「神国」や「神風」を信じ込まされて、先の大戦で自暴自棄な作戦によって散華した若者たちの命は、取り返しがつきません。
それにしても、私も迂闊でした。
疑問を持ったのなら、とことん調べてみればよかったと、今になって悔しく思います。(もっとも、そんな力量などありませんでしたが)
しかし今なら、インターネットという方法で、居ながらにして簡単に調べることもできますから、歴史に限らず、疑問に思ったことは間を置かず調べる、という基本を実践したいものです。
たった一つの誤った歴史観が、かくも重大な結果を招くといった、「過ちは繰り返しませぬ」ように。
歴史の知識といえば、たいていは学生の頃に勉強した(詰め込んだ、と言うほうが適切かな)ことが全てで、その後、新しい知識を仕入れていない限り、何十年経っても、その知識が、その人の「常識」として留まっています。
さて、掲題の元寇ですが、学生時代を何十年か前に過ごした私と同年代の方にとっては、以下の内容が「常識」だろうと思います。
『2回にわたる元寇で、武器や戦法に勝れた元軍は、日本軍を散々悩ませましたが、2回とも、夜中に暴風が来て、船に戻っていた元軍は一夜にして壊滅しました。この暴風雨を、日本人は後々まで「神風」として崇めました』
この「2回とも」という部分が、私にとって長い間の疑問でした。
軍事により一大帝国を築いた元が、軍事上重要な情報である東シナ海の気象を知らないはずはなく、わざわざ台風の季節に艦隊を仕立ててやってくること自体、腑に落ちませんし、さらには、同じ間違いを二度も犯し、十数万の兵士を犠牲にして自滅するなど、どう考えても軍事大国らしからぬ過ちです。
それでも、天気予報などなかった時代、一度目は「読みが外れた」かとも解釈できますが、一度目が失敗した時点でその将軍は更迭(たぶん処刑)され、後任の将軍は前回の失敗をよく検討して事に臨むのが軍事というもので、こんな行き当たりばったりの、まるでわざと兵士を海に沈めるような作戦などあり得ない、という疑問です。
ところが、最近になって知ったのですが、やはり、元寇についての古い「常識」には、裏があったようです。
まずは、説明上、鍵となる事項を整理してみましょう。
1.文永の役では約3万、弘安の役では約15万の兵が来た
2.文永の役は1274年11月、つまり台風の季節ではない
弘安の役は1281年6~8月で、これは台風の季節
3.日本側の記録によると、文永の役では一夜にして元軍が引き上げたが、弘安の役では確かに暴風雨によって壊滅した
4.軍は、元軍単独ではなく、元および元が服属させた高句麗・南宋との連合軍であった。
特に弘安の役では、元以外の兵が10万を超えていた
以上から、最新の学説は次のようになっています。
1.兵力について
文永の役で、わずか3万の動員ということは、少なくとも文永の役においては、元に、本気で日本を征服する意図はなかったと思われる。それよりも15万を動員した弘安の役が本番で、文永の役は、日本側の防衛力を確認する前哨戦と見るのが適当。
ただ、一旦引き上げることで、元軍は自らの装備(てつはう・蒙古弓など)を明かしてしまうとともに、日本側に防衛体制増強(防塁など)の余裕を与えてしまっているのは、元軍戦略上の不手際だろうが、後述のとおり「日本侵略があまり本気ではなかった」としたら、日本側にわざとそうさせたのかもしれない。
2.台風について
文永の役は11月だから、台風が来ることは、まず、あり得ない。
また、文永の役が自主的な撤退であったのなら、弘安の役に際して、元軍が迂闊にも気象条件を考慮の外としたのは、まあ、不可解ではない。
さらには、これも前述のとおり、「わざと」の可能性さえある。
3.元軍撤退理由について
文永の役は前述のとおり「前哨戦」と見るべきなので、日本側の戦力を測るという目的が達成されれば長居は無用、さっさと引き上げるのが合目的的である。
弘安の役で台風が来たのは事実で、15万のうち10~12万が海に沈み、これは間違いなく敗戦である。
4.連合軍であったこと
元は高句麗・南宋を服属させたが、両国の残存が元におとなしく従うはずはなく、元にとってそのような不満分子は厄介者に過ぎない。
また攻略した国の者を、次の侵略戦争で尖兵として使うのは常套手段であるが、高句麗・南宋人にとっては、自分らの国を侵略した元に対しての忠誠心などあろうはずもなく、彼らの士気は極めて低く、戦役前の造船においても、日本での合戦においても、まるでやる気がなかった。
これらのことから導き出される結論は、
『元の日本侵略作戦は、あまり本気であったとは考えにくい。それでも、元からの国書を無視した日本を痛い目に合わせねば、元の威光に傷がつくから、勝敗に関わらず、攻めてみたものである。そして首尾よく日本を攻略できれば、それはそれで良し、もし攻略できなくても、不満分子である高句麗・南宋の兵は全滅するから、どっちに転んでも元にとっては都合がいい、という戦いであり、結局、後者の結果に落ち着いた。ただ、暴風雨によって、高句麗・南宋兵だけでなく、元軍そのものにも壊滅的な打撃が及んだのは計算外だったらしく、元は、海軍力の弱体化を招いた』
というものです。
これには目から鱗の落ちる思いがしたと同時に、私が、辻褄が合わないと思っていた点にも、なるほど高句麗・南宋という「捨て駒」での戦ならさもありなん、という明快な回答をくれるものでした。
さて、歴史上の事実はこれで整理がついたとしても、それではと湧き上がる疑問、「なぜ、歴史的事実が正しく伝わらず、歪曲された事実が伝わり、あまつさえ学校で検定教科書を用い、そう教え続けたのか」という点についてはどうでしょう?
これには、前記4つに続く鍵、
5.私の世代では、学校の先生(旧文部省というべきか)にも太平洋戦争経験者が多かった
という事実を、残念ながら、付け加えねばなりません。
圧倒的な軍事力を誇る元軍が、終始優勢に戦を進めていたにもかかわらず、一度ならず二度までも、偶然・・・つまり人智を超えた・・・暴風雨によって壊滅し敗退した、という事実(ではありませんが)からは、次の結論が導き出されます。
『日本は神国であり、たとえ夷敵が攻めてこようとも、最終的には「神風」が吹き、寸土も侵されることなく、わが国は勝利する』
これが、私たちの先生が少年時代を過ごしたであろう戦前の、国威高揚によるものであることに疑いの余地はありません。このように勇ましくも神々しい話は、軍国少年らの心に深く刻み込まれ、戦後、純粋な少年らが大人になって数十年経っても、その呪縛から解き放たれることはなかったのです。
戦前・戦時中の教育について知れば、まるで集団催眠とも言える教育ですが、私は、それは終戦とともに消え去り、戦後は民主的な教育に姿を変えたものとばかり思っていました。しかし、意図していなかったと信じたいですが、戦前教育の影は、戦後数十年にわたって影響を残し続けていたのです。
では、日本側の記録で明らかなように、そもそも文永の役では「神風」など吹いていないにもかかわらず、なぜ永きにわたって、吹いたことになっていたのでしょうか。
歴史編纂の際に資料とした、八幡神を喧伝する「八幡愚童訓」という書(宗教書であり、歴史を正しく伝えた書ではないことに留意してください)の中に、「2度とも神風が吹いた」という記述があるそうです。
これが、明治時代の富国強兵政策華やかなりし頃、歴史の教科書を編纂する際に都合よく利用されたであろうことは、想像に難くありません。
つまり、元寇という歴史を捻じ曲げてしまった「戦犯」は、この編者だったのです。
教科書の歴史が間違っていて、元軍が2度とも暴風で壊滅したと教えていたとしても、真実が詳らかになったのなら(もとから分かっていたことでしたが)、それは新しい事実を教えればいいわけですから、取り返しのつく過ちです。
しかし、根拠のない「神国」や「神風」を信じ込まされて、先の大戦で自暴自棄な作戦によって散華した若者たちの命は、取り返しがつきません。
それにしても、私も迂闊でした。
疑問を持ったのなら、とことん調べてみればよかったと、今になって悔しく思います。(もっとも、そんな力量などありませんでしたが)
しかし今なら、インターネットという方法で、居ながらにして簡単に調べることもできますから、歴史に限らず、疑問に思ったことは間を置かず調べる、という基本を実践したいものです。
たった一つの誤った歴史観が、かくも重大な結果を招くといった、「過ちは繰り返しませぬ」ように。