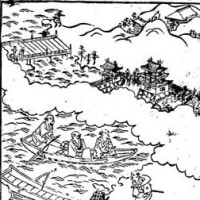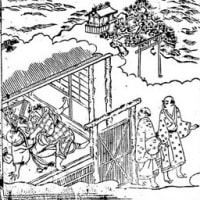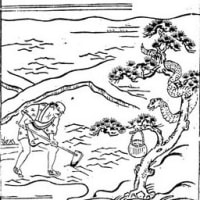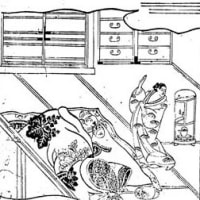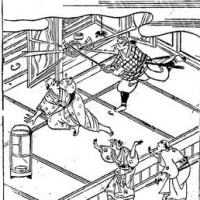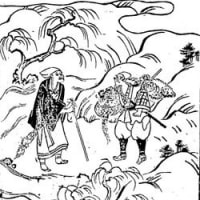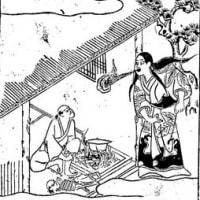ご訪問ありがとうございます→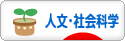 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
摂州難波の津、白髪町という所に住む阿積桐石とかいう人は、その昔は儒医として名高く、かつては仕官をも勤め、富貴の栄耀をも究めた人物であるが、さる仔細があって、この所に引っこんで逼塞の身となってから、今は世を渡る術もなくなり、今日の命を育むべき道もなかった。
だから、身命を保つには、学び得た儒の道を広めるより他はないと思い、昨今の、俗っぽいばかりで、鬼神の説に馴染み陰祀にまみれ、儒学の名を徒に称するだけで、釈迦の骨を有難がる者ばかりが数知れずいる世の中で、この輩の目を覚まさせて、正しい道へ進めさせるにはこれしかないと、自ら工夫して無鬼論というものを造り、書に著そうとした。
そうして執筆しているある日、桐石は、草稿半ばに至って気疲れがして心が倦むままに、しばらく卓に寄りかかって居眠りをしてしまった。すると夢か現か、忽然として桐石の側に人が立っていて、手を差し伸べて桐石の肘をしっかりと捉え、引き立てようとするので、振り仰いで見ると、何とも恐ろしく、背の丈は天井につかえるほどもあり、二つの眼は姿見の鏡(手鏡)に紅の網を懸けたように血走り、角は銅(あかがね)の榾木を並べたに生え、髪らしき物は、銀(しろがね)の針を散らしたように見え、左右に牙の生えた口が耳の辺りまで裂けた鬼が、屹(きっ)と目を見合わせて立っていたので、桐石は身の気が弥立ち手足は戦慄いて、人心地を無くして打ち伏していると、この鬼は、
「お前は生半可な儒学に迷い、道に背いて、鬼などはいない物だと勝手に決めつけ、猥りに後輩を欺き、世を惑わす説を流して、安易に飯の種にしようとした。鬼神などいないと考えているようだが、お前がいくら智のある奴だと言っても、孔子や孟子に及ぶわけではあるまい。だから、我がここに現れ、お前を連れて黄泉の庭に至り、善悪応報の道がある様を知らせてやろうぞ」
と言うと桐石の腕を取り、引提げて飛び上がった。

雲に乗り、風に従い、四五里程も行ったかと思うと、一つの大きな門に着いた。その構えは、例えるなら難波で見馴れた城のようであった。白い鬼や赤い鬼どもが鉄杖を取り、剣戟を構えて大庭に居並んでいる有様は、何とも言えないほど恐ろしい。連れて来た鬼は、桐石を階(きざはし)の基に引き据え、雷のような声を出し、
「武州大日本難波津の書生、桐石を召し捕って参りました」
と叫んだ。
しばらくあって、奥より、玉の冠を戴き牙の笏を取り、威儀を正した人が静かに歩み出て、玉扆(ぎょくい=玉座の屏風)に座し、その左右には侍衛や百官が、列を厳かにして座した。そしてこの王は桐石に詔して、
「汝は愚迷の才に驕り、みだりに無鬼の邪説をなした。この故に、今、汝を召し寄せて、その無知蒙昧な考えを改めさせるものである。速やかに帰って有鬼論をつくるべし。鬼らよ。こやつを率いて、地獄がある事を見せてやるがよい」
と宣いもあえぬに、獄卒が桐石を連れて、別の場所に至った。
そこは、たとえば仁徳の社のような構えに金銀をちりばめたようで、その宮中に五葉の花形をした鏡があって、玻璃の臺(うてな)に据えられていた。桐石が走ってこの鏡に向かおうとすると、鬼が、
「生ある者は、この鏡に向かってはならない。これはこれ浄玻璃である。人間が一生の間に犯した罪悪を悉く辿るから、もしお前がこれに向かって罪悪の相が現われたなら、お前は再び生きて娑婆に帰ることはできない」
と教えたので、桐石は身震いして控えた。
するとそこへ、男女の区別も判らないほど、手足は疲れ痩せて糸のようで、腹は茶臼山を抱えたような者が五人、四つん這いになって来たのを、情けを知らぬ獄卒どもが鉄杖で散々に打ち立て打ち立て、この鏡の前に追い進ませた。どうなることかと見ていたら、不思議に、この鏡の一葉毎に、五人の罪が各々現れた。それを見て桐石も、彼らが何者か悟った。彼らは最近、難波で男伊達と聞こえた五人の哀れ者の、なれの果てであり、桐石は、不憫に思って眺めていた。
この男伊達の親分で庄九郎という者の親は、ある時、田畑の事で近所の者と争いをし、庄屋を相手に訴訟をするべく、訴状を懐にして大坂の方へ赴いた道で、どうしたことか頻りに腹が痛みだし、曾根崎の天神に参って、しばらく拝殿で休んでいたが、いつとなく少し微睡んだ夢心に、数多の騎馬に乗った人が、この社に入り来て、
「三○村の地神、しばらくの間、雷を借り申したい由の御使いに参りました」
と言う。すると中から衣冠の人が四五人、小さな車を押し出して、使者に貸し与えている、というところで夢から覚めた。そこで、急いで帰って、近辺の村にも言い聞かせ、自分も、麦の頃だったので、急いで麦を悉く刈り込んだところ、二三日過ぎて大雨・雷電夥しく、洪水は逆巻いて、川も溢れるまでとなり、その洪水が村を襲ったので、庄九郎の親が言った言葉を信じて麦を早く刈り入れた者は、危うく難を逃れたが、この言葉を戯言だと思って麦を放っておいた者は、大きな被害を受けてしまった。
ところが、被害を受けた者たちは、庄九郎の親のことを悪く言い、庄屋に仇があるから、山伏を頼んで災難が起こるよう祈らせたのだ、などと言い触らしたので、かねて怨敵であった庄屋も、これに力を得て庄九郎の親を悪しざまに取りなした。
庄九郎親子は、住む所を追い立てられ、この難波の町に住むこととなったが、庄九郎の親は、この事が原因で病になって、ついに世を早くしてしまった。それで庄九郎も、世の人々を怨むようになり、この報いをするべく思い立ち、まず、同じ心を持つ友人と共に男伊達と号し、肘に入墨などして、悪の一党となった。庄九郎ら一党は、
「生きて父母の勘当を恐れず、死して獄卒の責めを恐れず。千人を殺して千の命を得たり」
とうそぶいて、明け暮れ、刀や暴力に身を任せるようになった。そして、どこへ行っても、三○村の者は見つけ次第に仇を取ってやろうと、常に大脇差を放さなかった。
彼らは、夜な夜な道頓堀のあたりを練り歩き、弱そうな奴や、少しでも粋がっている者がいれば、自分らの腕に任せて手ひどく当たれば、大抵は、平和な世の中で武器など扱ったことのない者ばかりであったので、たやすく餌食となった。
そして一党は髪形も奇妙なものに変え、着る物から腰の物まで珍奇な格好をして、女遊びも派手に浮世を謳歌し、また、被害にあった者も、後難を恐れて泣き寝入りするしかなかったので、庄九郎ら一党はいよいよ図に乗って、もはや自分たちに敵対する者はいないと笑い、いよいよ無法に募り、人が恐れるのを面白がって此処かしこにのさばった。

そんな具合だから、いつの間にか、親の仇を報せんと思い立った心ざしも忘れ、町のあちこちに出没して夜は廓に揚がり、悪事ばかりを働き回っていた、その刑罰に値する夕べまでの罪業、全て三千七百カ条の科が悉く鏡に現れ、後生を助かるべき善事はいささかもなかった。しかし、せめて死期に及んで前罪を悔い、念仏の功徳にすがる機会を与えられたので、この五人の者どもは真実に反省をして阿弥陀の名を唱えた。
しかし閻魔大王の沙汰は、死期に至って命懸けで念仏して、今までの悪心を翻すとの願を起こし、御助け頂きたいと、心底から唱えた念仏であっても、これまでの悪事を帳消しにすることはできない。ただ、この一遍の念仏によって、三千七百カ条のうち千七百カ条分の罪は赦され、阿鼻大城に落ちるべき罪人ではあるが、減刑して、彼らは畜生道に落ちて梟の身に生まれ変わり、二万劫を経てからもう一度、人間に返すべし、との判決になった。
それから獄卒どもは、かの五人を引き立て、また雲に乗って行くと見えたが、鶏の時を告げる声がして、大福院の鐘の響きに夢から覚めてみれば、白髪町の曙の中に、桐石は机にもたれながらうつ伏せなったままであり、妻は傍らでうたた寝をしている、元の通りであった。
摂州難波の津、白髪町という所に住む阿積桐石とかいう人は、その昔は儒医として名高く、かつては仕官をも勤め、富貴の栄耀をも究めた人物であるが、さる仔細があって、この所に引っこんで逼塞の身となってから、今は世を渡る術もなくなり、今日の命を育むべき道もなかった。
だから、身命を保つには、学び得た儒の道を広めるより他はないと思い、昨今の、俗っぽいばかりで、鬼神の説に馴染み陰祀にまみれ、儒学の名を徒に称するだけで、釈迦の骨を有難がる者ばかりが数知れずいる世の中で、この輩の目を覚まさせて、正しい道へ進めさせるにはこれしかないと、自ら工夫して無鬼論というものを造り、書に著そうとした。
そうして執筆しているある日、桐石は、草稿半ばに至って気疲れがして心が倦むままに、しばらく卓に寄りかかって居眠りをしてしまった。すると夢か現か、忽然として桐石の側に人が立っていて、手を差し伸べて桐石の肘をしっかりと捉え、引き立てようとするので、振り仰いで見ると、何とも恐ろしく、背の丈は天井につかえるほどもあり、二つの眼は姿見の鏡(手鏡)に紅の網を懸けたように血走り、角は銅(あかがね)の榾木を並べたに生え、髪らしき物は、銀(しろがね)の針を散らしたように見え、左右に牙の生えた口が耳の辺りまで裂けた鬼が、屹(きっ)と目を見合わせて立っていたので、桐石は身の気が弥立ち手足は戦慄いて、人心地を無くして打ち伏していると、この鬼は、
「お前は生半可な儒学に迷い、道に背いて、鬼などはいない物だと勝手に決めつけ、猥りに後輩を欺き、世を惑わす説を流して、安易に飯の種にしようとした。鬼神などいないと考えているようだが、お前がいくら智のある奴だと言っても、孔子や孟子に及ぶわけではあるまい。だから、我がここに現れ、お前を連れて黄泉の庭に至り、善悪応報の道がある様を知らせてやろうぞ」
と言うと桐石の腕を取り、引提げて飛び上がった。

雲に乗り、風に従い、四五里程も行ったかと思うと、一つの大きな門に着いた。その構えは、例えるなら難波で見馴れた城のようであった。白い鬼や赤い鬼どもが鉄杖を取り、剣戟を構えて大庭に居並んでいる有様は、何とも言えないほど恐ろしい。連れて来た鬼は、桐石を階(きざはし)の基に引き据え、雷のような声を出し、
「武州大日本難波津の書生、桐石を召し捕って参りました」
と叫んだ。
しばらくあって、奥より、玉の冠を戴き牙の笏を取り、威儀を正した人が静かに歩み出て、玉扆(ぎょくい=玉座の屏風)に座し、その左右には侍衛や百官が、列を厳かにして座した。そしてこの王は桐石に詔して、
「汝は愚迷の才に驕り、みだりに無鬼の邪説をなした。この故に、今、汝を召し寄せて、その無知蒙昧な考えを改めさせるものである。速やかに帰って有鬼論をつくるべし。鬼らよ。こやつを率いて、地獄がある事を見せてやるがよい」
と宣いもあえぬに、獄卒が桐石を連れて、別の場所に至った。
そこは、たとえば仁徳の社のような構えに金銀をちりばめたようで、その宮中に五葉の花形をした鏡があって、玻璃の臺(うてな)に据えられていた。桐石が走ってこの鏡に向かおうとすると、鬼が、
「生ある者は、この鏡に向かってはならない。これはこれ浄玻璃である。人間が一生の間に犯した罪悪を悉く辿るから、もしお前がこれに向かって罪悪の相が現われたなら、お前は再び生きて娑婆に帰ることはできない」
と教えたので、桐石は身震いして控えた。
するとそこへ、男女の区別も判らないほど、手足は疲れ痩せて糸のようで、腹は茶臼山を抱えたような者が五人、四つん這いになって来たのを、情けを知らぬ獄卒どもが鉄杖で散々に打ち立て打ち立て、この鏡の前に追い進ませた。どうなることかと見ていたら、不思議に、この鏡の一葉毎に、五人の罪が各々現れた。それを見て桐石も、彼らが何者か悟った。彼らは最近、難波で男伊達と聞こえた五人の哀れ者の、なれの果てであり、桐石は、不憫に思って眺めていた。
この男伊達の親分で庄九郎という者の親は、ある時、田畑の事で近所の者と争いをし、庄屋を相手に訴訟をするべく、訴状を懐にして大坂の方へ赴いた道で、どうしたことか頻りに腹が痛みだし、曾根崎の天神に参って、しばらく拝殿で休んでいたが、いつとなく少し微睡んだ夢心に、数多の騎馬に乗った人が、この社に入り来て、
「三○村の地神、しばらくの間、雷を借り申したい由の御使いに参りました」
と言う。すると中から衣冠の人が四五人、小さな車を押し出して、使者に貸し与えている、というところで夢から覚めた。そこで、急いで帰って、近辺の村にも言い聞かせ、自分も、麦の頃だったので、急いで麦を悉く刈り込んだところ、二三日過ぎて大雨・雷電夥しく、洪水は逆巻いて、川も溢れるまでとなり、その洪水が村を襲ったので、庄九郎の親が言った言葉を信じて麦を早く刈り入れた者は、危うく難を逃れたが、この言葉を戯言だと思って麦を放っておいた者は、大きな被害を受けてしまった。
ところが、被害を受けた者たちは、庄九郎の親のことを悪く言い、庄屋に仇があるから、山伏を頼んで災難が起こるよう祈らせたのだ、などと言い触らしたので、かねて怨敵であった庄屋も、これに力を得て庄九郎の親を悪しざまに取りなした。
庄九郎親子は、住む所を追い立てられ、この難波の町に住むこととなったが、庄九郎の親は、この事が原因で病になって、ついに世を早くしてしまった。それで庄九郎も、世の人々を怨むようになり、この報いをするべく思い立ち、まず、同じ心を持つ友人と共に男伊達と号し、肘に入墨などして、悪の一党となった。庄九郎ら一党は、
「生きて父母の勘当を恐れず、死して獄卒の責めを恐れず。千人を殺して千の命を得たり」
とうそぶいて、明け暮れ、刀や暴力に身を任せるようになった。そして、どこへ行っても、三○村の者は見つけ次第に仇を取ってやろうと、常に大脇差を放さなかった。
彼らは、夜な夜な道頓堀のあたりを練り歩き、弱そうな奴や、少しでも粋がっている者がいれば、自分らの腕に任せて手ひどく当たれば、大抵は、平和な世の中で武器など扱ったことのない者ばかりであったので、たやすく餌食となった。
そして一党は髪形も奇妙なものに変え、着る物から腰の物まで珍奇な格好をして、女遊びも派手に浮世を謳歌し、また、被害にあった者も、後難を恐れて泣き寝入りするしかなかったので、庄九郎ら一党はいよいよ図に乗って、もはや自分たちに敵対する者はいないと笑い、いよいよ無法に募り、人が恐れるのを面白がって此処かしこにのさばった。

そんな具合だから、いつの間にか、親の仇を報せんと思い立った心ざしも忘れ、町のあちこちに出没して夜は廓に揚がり、悪事ばかりを働き回っていた、その刑罰に値する夕べまでの罪業、全て三千七百カ条の科が悉く鏡に現れ、後生を助かるべき善事はいささかもなかった。しかし、せめて死期に及んで前罪を悔い、念仏の功徳にすがる機会を与えられたので、この五人の者どもは真実に反省をして阿弥陀の名を唱えた。
しかし閻魔大王の沙汰は、死期に至って命懸けで念仏して、今までの悪心を翻すとの願を起こし、御助け頂きたいと、心底から唱えた念仏であっても、これまでの悪事を帳消しにすることはできない。ただ、この一遍の念仏によって、三千七百カ条のうち千七百カ条分の罪は赦され、阿鼻大城に落ちるべき罪人ではあるが、減刑して、彼らは畜生道に落ちて梟の身に生まれ変わり、二万劫を経てからもう一度、人間に返すべし、との判決になった。
それから獄卒どもは、かの五人を引き立て、また雲に乗って行くと見えたが、鶏の時を告げる声がして、大福院の鐘の響きに夢から覚めてみれば、白髪町の曙の中に、桐石は机にもたれながらうつ伏せなったままであり、妻は傍らでうたた寝をしている、元の通りであった。