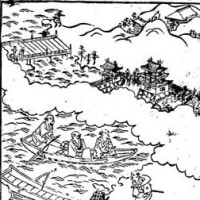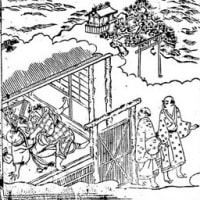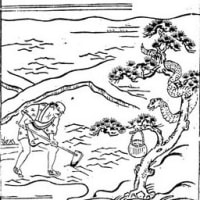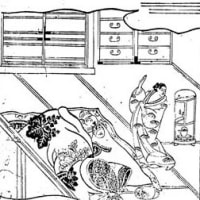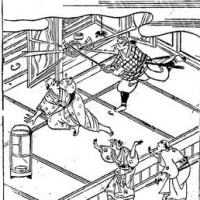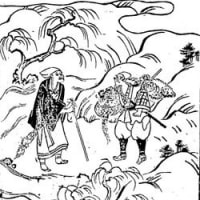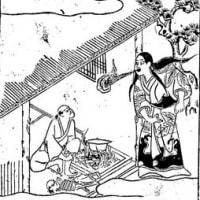ご訪問ありがとうございます→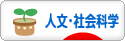 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
goo ニュースで、こんな記事がありましたので、再掲します。
会社はなぜ「有給休暇」を買い上げてくれないの?(R25) - goo ニュース
労働基準法
第24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(後略)
第39条
第1項
使用者は、(中略)労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
第2項
使用者は、(中略)継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。(後略)
法律で、「~なければならない」と書いてある場合の意味は、駄文「民法第752条 同居、協力及び扶助の義務」でも説明したとおり、必ずそうする義務があり、もし、そうしなかったならば、それは法律違反だぞ、という強制力を持つ規定です。
これを踏まえて、労働基準法第24条、第39条第1項・第2項をみると、いずれも「~なければならない」と書かれており、賃金を払わなかったり、勤続年数に応じた有給休暇を与えなかったら、それは法律違反だぞ、という厳しいものとなっていますから、これに反することは許されません。
さて、ネットのニュースでこんなのがありました。まずはご一読を。
有休の取得率47% 祝日多く取りにくい? 09年調査
働いた労働者には、当然、賃金が支払われます。そして、働いた労働者には、当然、有給休暇が与えられます。
すなわち、有給休暇は賃金と同じく、労働者が当然に受け取るべきものなのです。
ところが、その有給休暇の取得率が47%ということは、半分以上の有給休暇が、労働者に与えられていないことになります。
まさかあなたは、「私は、決められた賃金の半分を頂ければ、それで結構です」とは言わないでしょう?
それなのに、なぜ、有給休暇は半分以下しか与えられないのでしょう?
これには日本人独特の、働くことを美徳とし、休むことを悪徳・・・とまでは言わないにしろ、良しとしない感情が、大きく作用しています。
「休んだら、仕事に差し支えたり、他の仲間に迷惑がかかる」という意見はごもっともです。
しかし社長ならともかく、その社員が休んだぐらいで、仕事に差支えが出たり他の社員に迷惑がかかってしまうとすれば、会社の業務体制が問題であって、そうならないような人員配置や業務配分を考えるために、小さな会社では社長自ら、大きな会社では社長の命を受けた労務担当や管理職がいるのですから、社長以外が、そんな余計な心配をする必要はありません。
さて記事では、「厚生労働省は・・・有給休暇の・・・取得率の数値目標を設けることを努力義務にした」と続いています。
上にも書いたとおり、有給休暇は賃金と同等のものです。
であれば、先の記事を「厚生労働省は・・・賃金の・・・支払い率の数値目標を設けることを努力義務にした」と書き換えたらどうでしょう?
どんなに温厚な方でも、「ふざけるな。賃金は100%きっちり支払われるのが当然だ。最初から何割引かにするような『数値目標』などという発想自体、おかしいじゃないか」とおっしゃるでしょうね。
有給休暇も同じです。
100%きっちり与えられるのが当然で、『数値目標』とは笑止千万です。
おまけに、「『数値目標を設ける』ことを『努力義務』にした」に過ぎず、数値目標がどんなに低くても、設けさえすれば、努力義務を果たしたことになります。
また、設けられた低い数値目標さえも達成されなかったとしても、誰からも何のお咎めもありません。
さらに、努力義務ということは、結果的にできなくても、もっと言えば、そもそもそんな努力などしなくても、これまた何のお咎めもありません。
早い話が、これ自体、「ザル」を通り越して「有名無実」というわけです。
さて、もうお気づきの方もいるかと思いますが、ここまで私は、有給休暇が「与えられていない」と書いてきており、「取得されていない」とか「行使されていない」とは書いていません。
法的な理論(通常の感覚では、屁理屈と呼ばれます)から言えば、
「会社は有給休暇を与えているが、労働者がそれを取得していないに過ぎない」つまり、会社は義務を果たしているのに、労働者のほうが権利を放棄しているのだ、という理屈で、形としては、有給休暇は与えられていることになっています。
しかし、支払われたはずの賃金が、最終的に労働者の手に渡らなければ、支払われたことにはならないでしょう?
同じように、与えられたはずの有給休暇が、結局行使されていなければ、それは与えられていないのと同じではありませんか?
だから私は「与えられていない」と書いてきたのであり、それは、会社が、労働者が権利を放棄しているのに知らん顔をし、権利を正しく行使するような配慮を怠っている、つまり有給休暇の行使率が低いのは、偏に会社の責任である、という意味を込めています。
たとえば皆さんの中で、上司などから、「君の、今年度の有給休暇は、あと5日残っている。流れる前にきちんと取りたまえ」と言われた経験のある方はいらっしゃいますか?
まあ、いないでしょうね。私も、言われたことなどありません。
まさにその点が、私の言う「有給休暇が与えられていない」ということです。
厚生労働省は、冒頭に掲げた労働基準法第39条が名実ともに実現されるよう、「数値目標」だの「努力目標」だのではなく、「有給休暇の完全取得を義務化する」と言い切ってしまい、さらには、違反には罰則を課するなど、厳格に対処しなければ、
労働基準法 第1条
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
という目的は、到底達成されません。
さて蛇足ですが、なぜ日本人は、有給休暇の取得をためらう、言い換えれば、休むことに罪悪感を持つのでしょうか?
有給休暇なんかとらず、休まずにせっせと働く労働者のほうが、経営者にとっては都合のいい人材に決まっています。
そして労働者は、そうなるように教えられてきています。否、労働者が労働者になる前の段階、つまり学校に行っている間から、そうなるように教えられ続けています。
では、学校でそう教えるように決めているのは誰でしょうか?
さらに、そう決める権限のある者に、そう決めるよう仕向けたのは誰でしょうか?
もちろん、そうなることで最も利益を享受する者に決まっています。
それが誰かは言うまでもありませんね。
goo ニュースで、こんな記事がありましたので、再掲します。
会社はなぜ「有給休暇」を買い上げてくれないの?(R25) - goo ニュース
労働基準法
第24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(後略)
第39条
第1項
使用者は、(中略)労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
第2項
使用者は、(中略)継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。(後略)
法律で、「~なければならない」と書いてある場合の意味は、駄文「民法第752条 同居、協力及び扶助の義務」でも説明したとおり、必ずそうする義務があり、もし、そうしなかったならば、それは法律違反だぞ、という強制力を持つ規定です。
これを踏まえて、労働基準法第24条、第39条第1項・第2項をみると、いずれも「~なければならない」と書かれており、賃金を払わなかったり、勤続年数に応じた有給休暇を与えなかったら、それは法律違反だぞ、という厳しいものとなっていますから、これに反することは許されません。
さて、ネットのニュースでこんなのがありました。まずはご一読を。
有休の取得率47% 祝日多く取りにくい? 09年調査
働いた労働者には、当然、賃金が支払われます。そして、働いた労働者には、当然、有給休暇が与えられます。
すなわち、有給休暇は賃金と同じく、労働者が当然に受け取るべきものなのです。
ところが、その有給休暇の取得率が47%ということは、半分以上の有給休暇が、労働者に与えられていないことになります。
まさかあなたは、「私は、決められた賃金の半分を頂ければ、それで結構です」とは言わないでしょう?
それなのに、なぜ、有給休暇は半分以下しか与えられないのでしょう?
これには日本人独特の、働くことを美徳とし、休むことを悪徳・・・とまでは言わないにしろ、良しとしない感情が、大きく作用しています。
「休んだら、仕事に差し支えたり、他の仲間に迷惑がかかる」という意見はごもっともです。
しかし社長ならともかく、その社員が休んだぐらいで、仕事に差支えが出たり他の社員に迷惑がかかってしまうとすれば、会社の業務体制が問題であって、そうならないような人員配置や業務配分を考えるために、小さな会社では社長自ら、大きな会社では社長の命を受けた労務担当や管理職がいるのですから、社長以外が、そんな余計な心配をする必要はありません。
さて記事では、「厚生労働省は・・・有給休暇の・・・取得率の数値目標を設けることを努力義務にした」と続いています。
上にも書いたとおり、有給休暇は賃金と同等のものです。
であれば、先の記事を「厚生労働省は・・・賃金の・・・支払い率の数値目標を設けることを努力義務にした」と書き換えたらどうでしょう?
どんなに温厚な方でも、「ふざけるな。賃金は100%きっちり支払われるのが当然だ。最初から何割引かにするような『数値目標』などという発想自体、おかしいじゃないか」とおっしゃるでしょうね。
有給休暇も同じです。
100%きっちり与えられるのが当然で、『数値目標』とは笑止千万です。
おまけに、「『数値目標を設ける』ことを『努力義務』にした」に過ぎず、数値目標がどんなに低くても、設けさえすれば、努力義務を果たしたことになります。
また、設けられた低い数値目標さえも達成されなかったとしても、誰からも何のお咎めもありません。
さらに、努力義務ということは、結果的にできなくても、もっと言えば、そもそもそんな努力などしなくても、これまた何のお咎めもありません。
早い話が、これ自体、「ザル」を通り越して「有名無実」というわけです。
さて、もうお気づきの方もいるかと思いますが、ここまで私は、有給休暇が「与えられていない」と書いてきており、「取得されていない」とか「行使されていない」とは書いていません。
法的な理論(通常の感覚では、屁理屈と呼ばれます)から言えば、
「会社は有給休暇を与えているが、労働者がそれを取得していないに過ぎない」つまり、会社は義務を果たしているのに、労働者のほうが権利を放棄しているのだ、という理屈で、形としては、有給休暇は与えられていることになっています。
しかし、支払われたはずの賃金が、最終的に労働者の手に渡らなければ、支払われたことにはならないでしょう?
同じように、与えられたはずの有給休暇が、結局行使されていなければ、それは与えられていないのと同じではありませんか?
だから私は「与えられていない」と書いてきたのであり、それは、会社が、労働者が権利を放棄しているのに知らん顔をし、権利を正しく行使するような配慮を怠っている、つまり有給休暇の行使率が低いのは、偏に会社の責任である、という意味を込めています。
たとえば皆さんの中で、上司などから、「君の、今年度の有給休暇は、あと5日残っている。流れる前にきちんと取りたまえ」と言われた経験のある方はいらっしゃいますか?
まあ、いないでしょうね。私も、言われたことなどありません。
まさにその点が、私の言う「有給休暇が与えられていない」ということです。
厚生労働省は、冒頭に掲げた労働基準法第39条が名実ともに実現されるよう、「数値目標」だの「努力目標」だのではなく、「有給休暇の完全取得を義務化する」と言い切ってしまい、さらには、違反には罰則を課するなど、厳格に対処しなければ、
労働基準法 第1条
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
という目的は、到底達成されません。
さて蛇足ですが、なぜ日本人は、有給休暇の取得をためらう、言い換えれば、休むことに罪悪感を持つのでしょうか?
有給休暇なんかとらず、休まずにせっせと働く労働者のほうが、経営者にとっては都合のいい人材に決まっています。
そして労働者は、そうなるように教えられてきています。否、労働者が労働者になる前の段階、つまり学校に行っている間から、そうなるように教えられ続けています。
では、学校でそう教えるように決めているのは誰でしょうか?
さらに、そう決める権限のある者に、そう決めるよう仕向けたのは誰でしょうか?
もちろん、そうなることで最も利益を享受する者に決まっています。
それが誰かは言うまでもありませんね。