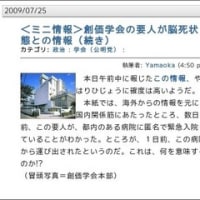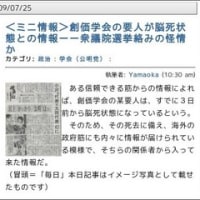備忘録 2005 NHK 日本の、これから ぼやきっくくり さんから

・・携帯の生アンケートの結果・・・
1.自分の立場を主張すべき 31216人
2.相手の立場を考えるべき 10131人
スタジオの回答とはかなりの差。
谷村新司
「グレーゾーンがかなりあると思う」
カン?(韓国人女性)
「私はあえて1にした。日本で本気で日本人と接した時に、韓国が普通に知ってる事実を日本は知らない。ここの人は知ってるが、普通に会った人は知らない。韓国人は日本人に片想いしているんだと思う。日本や日本人が嫌いなのではない」
?(20代女性)
「主張すべき立場がまだちゃんとしてない。何が譲歩できるのかわからないと話し合いできない。日本の中でコンセンサスができてない」
寺島実郎
「議論が混迷する理由、中国に行った経営者……日本という国の経済、産業、急速にアジアに依存して生きる体質になってる。我々自身が整理して、生産的な関係を構築していくか。頭と身体がバラバラ。アジアとのコミュニケーション深めないと生きていけないのに、まだ未整理」
谷村新司
「身体はアジアに埋まってるけど、頭はアメリカを向いてると?」
町村外相
「谷村さん、それはかなり偏った意見。確かに経済、依存関係はEUに近づいている。他方、安全保障、政治面では、依然として日米機軸。日米安定があるからアジアが安定してるという構造を理解してほしい。全ての基準をアジアに置くとはならない。テロ対策や海賊対策、地震対策とか、アジアでやっていくことはたくさんある。東アジア共同体というが、政治、安保は難しい。価値観違うから。が、これからサミットまでやろうとしてるから、テロ対策とか、それは進めていくべき」
?(30代女性)
「私もアメリカで仕事する経験があって、アメリカはアジアに対して目を向けている。中国系、インド系。アジアの中のハブは日本でなく、シンガポール、マレーシア。今の平和はアメリカとの保証にあったのは間違いないし、率直に感謝すべきだが、世界の中で重要なパワーを持つアメリカが、日本をアジアの中の日本と見てると思う。日本もアジアの中で何をするかを見ていくべきでは。ビジネスやってる中でそう思った」
?(80代男性)
「大臣は正直なことをおっしゃった。近現代史、教師はサヨク系統にならないように文部省が考えたというの、非常に正直な話。私は近現代史、マルクスはでなく事実に基づいた歴史を学校で教育してきた。韓国である一人の人が日韓友好の本を書いたら、反発があって彼は撤回したというが(「殴り殺される覚悟で書いた親日宣言」を書いたチョ・ヨンナムのこと。第二部で取り上げられた)、なぜかというと、潜在的に韓国では植民地時代の不満がある。それに対する不満が爆発した。そういう意味において、事実を申し上げます。松代大本営、強制連行して松代に防空壕作った、そういう事実があった」(だからそれは「徴用」では?(^_^;)
島村(20代女性)
「事実はひとつであっても、歴史解釈に正しいものはないと思う。私はオーストラリアの高校を卒業したが、オーストラリアの歴史200年を1年かけてやったが、いろんな資料集めて、一つの出来事でもこういう見方もあるよという、いろんな視点の教育があった。これが正しいとかじゃなく、いろんな見方を日本の歴史教育はとるべきだと思う」(会場拍手)
?(40代女性)
「今の方に同感。自分の頭で考える教育が必要。ひとつだけの答えを提供するのは歴史に関しては難しい。事実、主観がいろいろある。自分の主観を押し付けるのではなく、いろんな考えを。共同研究、合意が行われてないから教えないのでなく、それぞれの立場から考える素材を提供するのが必要。竹島のこと、独島も出してほしいと言ったの理解できる。扶桑社の教科書、アジア周辺諸国の問題のところで、『竹島は日本の領土であるにもかかわらず……』と書いてあるのは問題だと思った」
櫻井よしこ
「韓国の教科書は独島しか書いてないですね」
栗山尚一
「一つは、将来のためには近隣諸国と和解が必要。和解なくしては安定しない。どう達成するかは簡単ではない。辛坊強く両方で努力しないとできない」
李(20代男性)
「今日、日本のこれからということだが、日本のこれまでしか語ってないですね(会場笑い)。ということは、アジアの中の日本でなく、日本の中のアジアになってる。名分と実利だと思う。焦る必要ない。VTRやアンケートであったが、現在は未来の過去です。つまるところ今も歴史の一部。これからどうするかをとことんやらずにどうするんですか」
町村外相
「私は楽観的に考えてまして、お互いがお互いを必要とする環境ができてきてる。政治は別なんだと言っても仕方ない。一つの違い、靖国神社に反対だからこれで終わりだとなってはいけない。日米も70~80年代戦争と言われるような状態があった。日米関係は重層的な結びつきがあったからこうなってる。中国も韓国も日米摩擦が起きた時代のような状況にあると思うので、多少ぎくしゃくすることはあると思う。互いに認識し合うところで、どうマネージしていくのか。共通の認識を努力して増やしていくことができると思う」
司会
「皆さんにボードに書いてもらう。アジアの中の日本、一番皆さんが大切にしたいこと、外国の方は、大切にしてほしいことを」
・・・視聴者FAX&メール紹介・・・
女子アナ
「視聴者の方から17000通のご意見をいただきました」
東京都38才男性
「一人の人間であっても国家であっても、過去という荷物を背負いながら今を進むもの。日本は過去という荷物が存在しないように振る舞ってこなかったか?共同で荷物を考え直してみては?」
62才男性
「日本のほとんどの人は戦争に向かうことはないと思ってるだろうが、中国、韓国はそうは思ってない?歴史認識も一部の専門家以外知らない」
男性
「中国も韓国も日本を嫌ってるから、無理に仲良くするのは逆効果。アジアの国は韓国、中国、北朝鮮だけではない」(これ2ちゃんねらーか?(^_^;)
12才女性
「祖母は人間魚雷を作らされていた。今は平和。靖国参拝問題などでもめているのを恥ずかしいと思ってるはず。戦争を二度とやってほしくないと戦死者は思ってるはず」
36才主婦
「戦争は人を変えます。戦争は悲しみしか残さない。今日この日、本当の終戦記念日になることを祈っています」
紹介ここまで。
・出演者が書いたボード紹介(番組まとめ)
チョ(韓国人)
「『日本とアジアを理解する』」
ソウ(中国人?男性)
「『話し合いためらわずに』。イエスかノーかはっきり言えなかったが、はっきり言い合えば未来はピンク」
朱建栄
「『歴史認識は最大公約数を』。侵略戦争だったというのを最大公約数にすべき」
リー・ジョンウォン
「『国民から市民へ』。いま日本は市民から国民へ、国に戻ろうとしてる。中国、韓国は国民から市民になろうとしてる。国にとらわれない発想が必要」(この教授、もろプロ市民ですやん)
中村(30代男性)
「『対話のできる複数の回路を構築していく』。中国の女性の方が言葉のケンカをしようと言った。信頼関係があってこそ。彼女は身近な中国を伝えようと言うネットで活動しています」
五月女(50才男性教師)
「『事実を知る』。創始改名や南京大虐殺とか強制連行という熟語が出たが、きちんと事実を踏まえないままお互い話し合ってる気がする。そこに戻って、どこが事実か間違ってるかすり合わせた上で」
?(80代男性)
「『アジア人だったと気づくこと』。中国人らと旅行に行った日本人が『あなただけアジア人じゃなかったね』と言われたと。愕然としたと」
?(20代女性)
「『未来志向の日本人になる』。日本人ということを自分たちはきちんと考えていかないと」
?(20代女性)
「『複眼』。複合的視野という意味。歴史教育、島村さんが言ったみたいに、歴史教育や教科書の役割を考えないと。一つの解釈や何が正しいかを言うのでなく、メディア・リテラシーを教えるのが大切」
?(20代女性)
「『with love』。経済、メディア、いろんな問題あるが、人として仕事していく上で、意見や認識対立するが、お互い尊敬しあって愛情持って接するのが大事だと思う」
寺島実郎
「『親米入亜』。日本の役目だと思う」
町村外相
「『未来志向、世界の中の日本』。世界の中の日本という観点を忘れない。でないとアジアの皆さんとも付き合えない」
(まっちー、「志向」を「指向」って間違えて書いてて、最初にそれ、本人が訂正してたけど、ちょっと見てて恥ずかしかった(^_^;)
櫻井よしこ
「『相互の文化文明の尊重』」
(書かれた文字が小さすぎて、画面に寄ってる間に解説が終わってしまった(T^T))
栗山尚一
「『和解 アジア太平洋』。日本のアイデンティティを何処に求めるか?あまりアジアとのめりこんでいくのもどうか。アジアだけでは片づかない、太平洋も」
谷村新司
「『子供や孫の時代につなぐ』。カンさんがさっき、恋してるとちらっと言った。日本に恋してると。その人の日本の一挙手一投足が気になる。無関心ではいけない。向き合っていって声を伝えて行かねば」
第一部から通して読まれた方
いかがでしたか?
公正中立であるべきNHKが
どうも左がかっているんじゃないか?
と 疑問を持った番組でした。