
石井眞木:
・日本太鼓とオーケストラのための協奏曲「モノ・プリズム」 作品29
日本太鼓:鬼太鼓座
指揮:朝比奈隆
大阪フィルハーモニー交響楽団
・打楽器とオーケストラのための協奏曲「アフロ・コンチェルト」 作品50 ~バージョンA(2人の打楽器奏者のための)~
打楽器:百瀬和紀、山口多嘉子
指揮:岩城宏之
NHK交響楽団
VIctor: VDC-5512
今ではどうか知りませんが、そのむかし早稲田大学のオーケストラがよく演奏していたのが、レスピーギ「ローマの松」、ストラヴィンスキー「春の祭典」、そして本CDに収録されている石井眞木の「モノ・プリズム」で、私も何度か聞きにいったことがありました。「モノ・プリズム」とは作曲者の造語で、「モノ」はモノラルやモノクロの「モノ」で「単一の」と言う意味。「プリズム」はあの光の色を分解するプリズム。ここでは、「モノ」は日本太鼓の単一的な音色、「プリズム」はオーケストラから放射される多彩な音色を意味しており、これら全く異なる二つの楽器群の音がぶつかり合う曲です。
さて、このCDに収録されている「モノ・プリズム」と「アフロ・コンチェルト」はかなり類似したコンセプトの下に作曲された気がします。芸術作品は大抵の場合、その内外に対立構造を持っているものですが、協奏曲の場合にはそれが特に明確でしょう。この2曲はいずれもオーケストラに対する打楽器群の協奏曲のような作りで、変幻自在のオーケストラの音に対して、打楽器郡のある種不器用な音が浮かび上がるようになっています。
「モノ・プリズム」の場合は、アトモスフェリックなオーケストラの音を背景に、日本太鼓がくっきりと無心に打ち鳴らされます。両者は異なるレイヤーに存在し、その焦点距離さえも異なって聞こえます。そして距離が近づくでもなく主張し合い、最後まで融け合わずに終わるのですが、それでも両者の方向性を合わせることができたという満足感が得られます。また、日本太鼓の演奏者達には完全なシンクロが求められる曲ですが、そのことが演奏者達の人生までも感じさせるような気がするのです。
上の動画は岩城・N響の「モノ・プリズム」の演奏。ぜひ大音量でお聴きください。
一方の「アフロ・コンチェルト」では、それこそアフリカンドラムによるアフリカ的リズムの反復が病み付きになる音楽。ここではアフリカの民族楽器「バラフォン」も登場し、2人の打楽器奏者によるバージョンAの演奏。「モノ・プリズム」と比較して、オーケストラはよりリアルな大自然のような音を発するのに対し、打楽器はそれをしなやかに乗りこなす野生の人間のような存在に聴こえます。
二曲ともオーケストラ(西洋音楽)vs 打楽器群(東洋またはアフリカ音楽)という対立構造で、さらには人間 vs 大自然というもう一つの対立構造もあるように思われます。西洋音楽ではあまり大自然という概念はありませんが、それは恐らくキリスト教的な神という概念が大きくそびえ建っているからではないでしょうか。したがってこれら2曲は、まさに西洋のクラシック音楽では産みだされ得なかった音楽なのかも知れません。
クラシックCD紹介のインデックス










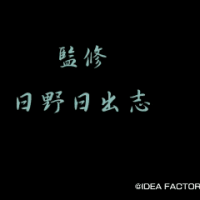
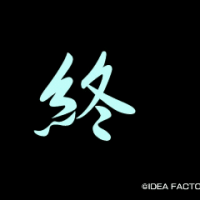
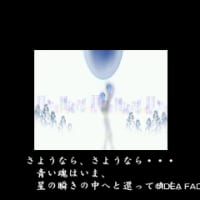


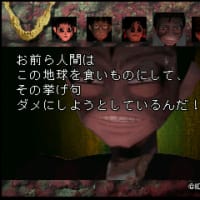

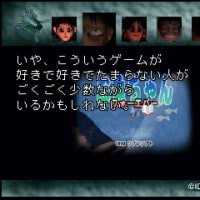

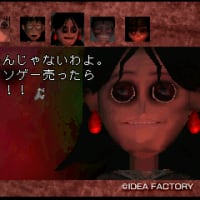
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます