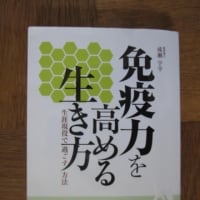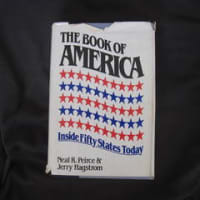今NHKのBS放送で成瀬巳喜男監督の映画を連続して放映している。数日前に私は「浮雲」を見た。この映画は昭和30年(1955年)の作品だということである。この映画は不思議に私は初めて見たものである。不思議だというのは、この時代の名作映画と言われているものは、その当時かそのごテレビでの再放送かは別にしてもほとんど見ているように思うのだが、この映画は見るのは初めてであった。
高峰秀子と森雅之が主演で、太平洋戦争中に当時の仏印で知り合った男女の終戦後の日本での交わりと最後に二人で行った屋久島で女が死ぬまでの二人を描いた、林芙美子原作の小説の映画化である。妻がいてしかも不実な男を追い続ける独身の若い女性との間の物語は、私はあまり惹かれなかったがその後私の手持ちの「日本映画ベスト150」を見ると、この映画は傑作だと論評してあった。150の日本映画の第5位にランクされてあった。
映画評論家の松倉郁夫氏は、この映画を見た昭和30年1月27日と日付まで正確に書いて、この映画を新宿で見て「終映は10時を廻っていたと思いますが、新宿駅東口へと通じる明るい道を避け、人影もまばらな南口の坂を登って帰途についたのを覚えています。とにかく涙が流れっ放しで、クシャクシャになった顔を人に見られたくなったからですが、改札口の近くまで歩いてもまだ嗚咽が止まらず、暫く暗闇にたたずんでいました。」と書いておられる。(日本映画ベスト150 文春文庫)
私はこの松倉氏の感受性を羨ましく思った。
私の本棚を探すと林芙美子の「浮雲」が出てきたので、映画の場面を思い出しながら拾い読みしているうちに段々と引き込まれて行った。そして、その結果、すでに録画していた映画「浮雲」を再度見直すことになった。
なるほど、面白いよく書かれた作品である。しかも女性でなければ書けないだろうと思う描写が随所にある。
戦時中の仏印のはなやかな生活の中での妻を日本において来た赴任者と日本人の若い女性(当時22歳)との交わり。終戦後の混乱の中でこの不実な男を追い求める若い女。そして妻を病気で失った後、心気一転離党屋久島の農林局へ赴任する男とそれに同行する女。そしてすぐに結核のために島で死ぬ女。男の慟哭。
最後のシーンは高峰秀子演ずる女の死顔である。若い時の松倉氏の感激がわかるような気もした。
私は、不実な男には単純に不快感を持ち、なおそれを追う女にも何ともやりきれない気持ちを持ってしまうのだが、これは私に文学的なセンスがないということなのかもしれない。
死んだ女を前に過去を思い出しながら嘆く男。私は小説「椿姫」のアルマンや小説「マノン・レスコー」の最後の場面を思い出していた。
画像:映画「浮雲」屋久島に落ちる男女(女は病身) 文春文庫「日本映画ベスト150」より