昨年の7月1日に、「夏近し。蛇ケ池や吉大夫さんの碑など」、と題して書いた記事で「知井村史」の甲賀三郎の八角鹿退治の伝説などを楽しんで読んでいると書いたのであるが、北さんからコメントを頂き、知りたい、とのことでした。書きます、とコメントを還しましたので、次に紹介したいと思います。
この伝説は、「京北の昔がたり」に、<八つ頭の大鹿退治>と題して、また「美山・伝承の旅」に、<大鹿退治>と題して記されています。これは「北桑田郡誌(大正版)」をもとに書かれているようです。京北の方は群誌よりももっと脚色されていますが、美山の方は群誌に近い形で書かれています。また「知井村史」には<八股角鹿>と題してこれに関する考察が記されていて読んでいくと楽しいものです。美山町誌にも記述があろうと思いますが、今我が手許にはありませんので省きます。
ここでは「北桑田郡誌・大正版」p588、知井村、土俗伝説に記された<甲賀三郎兼家猛獣退治の事>に従い紹介したいと思います。
--------------------------------
第42代元明天皇の和銅6年(713)、妖怪が都に出没して禁裏や農地に被害をもたらした。悩まれた天皇は占ってもらったところ、丹波北部の深山に八頭の巨鹿がいて、これが都に災いをもたらしているという。
命を受けた甲賀三郎兼家は猛者を従え丹波の国へと向かう。丹波についた兼家は、神社(1)で加護を祈り、弓矢の準備をしたのであるが(2)、一夜のうちに竹が繁茂したという(3)。準備を整えた兼家は山へと入るが、山深くどちらへ向かえばいいのか分からず困っていたところ、二人の童子が現れ、その案内で八丁山へと向かった。その途中、甲冑に身を固め(4)、更に佐々里川上流朽柳谷の深山へと進んでいった。
すると天地鳴動して八頭の大鹿が洞窟から飛び出し、兼家目がけて飛びかかってきたが、彼は怯まずに弓を放つと巨鹿に命中した。矢を負った鹿は山を下るまで逃げたがついに力尽き、血で岩や道をそめた(5)。追いつめた兼家は鹿を岩の上で斬った(6)。この岩は後の大水で唐戸まで流され、その付近を俎板淵という。
大鹿を退治した兼家は甲冑を脱ぎ(7)狩衣に着替え、佐々里の里へと下り、部下の安全を確認して休息した。そして祠をたてて八幡大明神を祀り神の加護に謝したが、これが今の知井八幡神社である。
(1)京北弓削の八幡宮社
(2)弓を削ったので弓削村の起源
(3)弓削村矢谷の集落
※竹藪が多かったそうです。「一的放弓居士」の碑について福山藩士との話を
以前書きました。
(4)ここで狩衣を掛けたので、ここを衣掛山という
※このキヌガケという呼称の起源については、澤潔さんは「北山を歩く」で衣笠
との関連で異説を述べられています。
(5)ここを赤石ケ谷という
(6)この岩を俎板岩と名付けた
(7)ここに鎧岩があるという
群誌では、「彼少しも屈せず直に矢を番えへ強弓を満月の如くに張り、ひようと放てば矢壺はたがわず彼の巨鹿に中りぬ。」などと文学表現も交えていて楽しいのですが、上では要点のみの記述にしました。
--------------------------------
なお群誌ではこの項の後、知井十苗の話に続きます。
兼家に従った家来の中にこの地に残ったものがいて、その子孫が知井十苗の先人と言われていて、十苗とは、林・勝山・高野・大牧・中田・東・長野・名古・中野・津元とされているとのことのことです。
甲賀三郎兼家は伝説の人物で、長野の諏訪神社や甲賀の里にいろいろな伝説に登場するようです。群誌にはこの項の最後に「鶴ヶ岡村の傅説にも之に酷似せるものあり、彼此對照せんには興味あるべし」と記してあり、鶴ヶ岡といえば諏訪神社、この神社の名前との関連も面白そうです。知井村史では数あるこの伝説には佐々里の地名が出てこないことや甲賀三郎を奈良時代のことと群誌に書かれていることに疑問を呈しておられます。また、八角の鹿とは当時八人の頭立った人達に治められていた先住民を征服したことの象徴かも知れない、などという記述があります。読んでいて楽しいものです。
そうですね、京都に近い人でないと、知井、佐々里、八丁ってどこ?と思われるでしょう。でも芦生の研究林と言えば大体分かるのではないでしょうか。芦生は京都大学が知井村(現南丹市)から研究林として借りているものです。地図で芦生の近くを探されればこういった地名が出てくると思います。
この伝説は、「京北の昔がたり」に、<八つ頭の大鹿退治>と題して、また「美山・伝承の旅」に、<大鹿退治>と題して記されています。これは「北桑田郡誌(大正版)」をもとに書かれているようです。京北の方は群誌よりももっと脚色されていますが、美山の方は群誌に近い形で書かれています。また「知井村史」には<八股角鹿>と題してこれに関する考察が記されていて読んでいくと楽しいものです。美山町誌にも記述があろうと思いますが、今我が手許にはありませんので省きます。
ここでは「北桑田郡誌・大正版」p588、知井村、土俗伝説に記された<甲賀三郎兼家猛獣退治の事>に従い紹介したいと思います。
--------------------------------
第42代元明天皇の和銅6年(713)、妖怪が都に出没して禁裏や農地に被害をもたらした。悩まれた天皇は占ってもらったところ、丹波北部の深山に八頭の巨鹿がいて、これが都に災いをもたらしているという。
命を受けた甲賀三郎兼家は猛者を従え丹波の国へと向かう。丹波についた兼家は、神社(1)で加護を祈り、弓矢の準備をしたのであるが(2)、一夜のうちに竹が繁茂したという(3)。準備を整えた兼家は山へと入るが、山深くどちらへ向かえばいいのか分からず困っていたところ、二人の童子が現れ、その案内で八丁山へと向かった。その途中、甲冑に身を固め(4)、更に佐々里川上流朽柳谷の深山へと進んでいった。
すると天地鳴動して八頭の大鹿が洞窟から飛び出し、兼家目がけて飛びかかってきたが、彼は怯まずに弓を放つと巨鹿に命中した。矢を負った鹿は山を下るまで逃げたがついに力尽き、血で岩や道をそめた(5)。追いつめた兼家は鹿を岩の上で斬った(6)。この岩は後の大水で唐戸まで流され、その付近を俎板淵という。
大鹿を退治した兼家は甲冑を脱ぎ(7)狩衣に着替え、佐々里の里へと下り、部下の安全を確認して休息した。そして祠をたてて八幡大明神を祀り神の加護に謝したが、これが今の知井八幡神社である。
(1)京北弓削の八幡宮社
(2)弓を削ったので弓削村の起源
(3)弓削村矢谷の集落
※竹藪が多かったそうです。「一的放弓居士」の碑について福山藩士との話を
以前書きました。
(4)ここで狩衣を掛けたので、ここを衣掛山という
※このキヌガケという呼称の起源については、澤潔さんは「北山を歩く」で衣笠
との関連で異説を述べられています。
(5)ここを赤石ケ谷という
(6)この岩を俎板岩と名付けた
(7)ここに鎧岩があるという
群誌では、「彼少しも屈せず直に矢を番えへ強弓を満月の如くに張り、ひようと放てば矢壺はたがわず彼の巨鹿に中りぬ。」などと文学表現も交えていて楽しいのですが、上では要点のみの記述にしました。
--------------------------------
なお群誌ではこの項の後、知井十苗の話に続きます。
兼家に従った家来の中にこの地に残ったものがいて、その子孫が知井十苗の先人と言われていて、十苗とは、林・勝山・高野・大牧・中田・東・長野・名古・中野・津元とされているとのことのことです。
甲賀三郎兼家は伝説の人物で、長野の諏訪神社や甲賀の里にいろいろな伝説に登場するようです。群誌にはこの項の最後に「鶴ヶ岡村の傅説にも之に酷似せるものあり、彼此對照せんには興味あるべし」と記してあり、鶴ヶ岡といえば諏訪神社、この神社の名前との関連も面白そうです。知井村史では数あるこの伝説には佐々里の地名が出てこないことや甲賀三郎を奈良時代のことと群誌に書かれていることに疑問を呈しておられます。また、八角の鹿とは当時八人の頭立った人達に治められていた先住民を征服したことの象徴かも知れない、などという記述があります。読んでいて楽しいものです。
そうですね、京都に近い人でないと、知井、佐々里、八丁ってどこ?と思われるでしょう。でも芦生の研究林と言えば大体分かるのではないでしょうか。芦生は京都大学が知井村(現南丹市)から研究林として借りているものです。地図で芦生の近くを探されればこういった地名が出てくると思います。










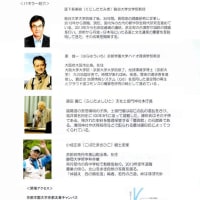
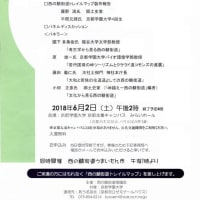
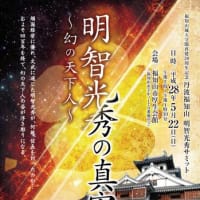


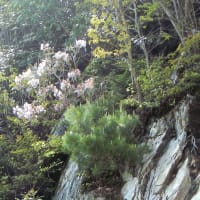


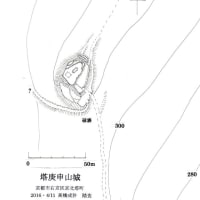


八頭の巨鹿がかってはいたのでしょうね。伝説や民話は小さな冊子になってお土産屋さんなどに売っていましたので、民話のありそうな土地に行きますと集めていました。今は止めてしまいましたが。。。
それにしてもどの様な強弓をつかわれたのでしょう? 私などは11キロの弓を引くのが精一杯でしたが???
芦生の森へ足を踏み入れるのは5月です。でも、忙しいのですよ。河鹿荘に一泊して翌日芦生の森を歩き、そのまま園部まで送っていただき、京都に泊まります。わたしは、葵祭りまで京都に滞在しますので、美山をノンビリ歩く日を一、二日過ごしてから京都へ向かいたかったのですが、連れの二人が「早く帰ろう。交通の便が悪くて動きが取れないから。」と言うものですから、、、団体行動をしないといけませんので。
来週も旅の帰りに京都に一泊して帰ります。桜が咲き始めていると良いのですが。
いずれにしても、佐々里は私の同級生(山国出身)が教師になって初めて赴任したのが佐々里分校でした。また、父も出張で出掛けたことがあり、その名前だけはかなり古くからから知っていました。一度は訪れたい場所です。
そうですね、折角芦生へ入られるなら、芦生の色々なコースを楽しまれたり、少し趣を変えて八丁界隈も宜しいのではないでしょうか。一泊だけではもったいない。
今年は桜が早く咲くのでしょうね。でも来週はまだ無理なのではないでしょうか。でも又々京都ですか、旨く時間が合えば京都に来られたときにあちこち案内させていただきますよ。京都市内はあまり興味がありませんので知りませんが、少し山里に入ったところなら任してください。
弓削や矢代、衣懸山、などの由来として説明されているのは上に書いたとおりです。仰るように八頭は八匹でなく、やつがしら、則ち八つの頭を持つ大鹿です。北桑田郡誌にしたがいますと、兼家のたどったのは、京都~京北の弓削~小塩~衣懸坂~八丁方面へ、そして大鹿が出て来たのは、郡誌では朽柳谷、美山伝承の旅では栃柳谷となっています)、矢を射られた大鹿が佐々里川沿いに逃げ、絶命したのが佐々里のあたりだ、ということなのでしょう。物語の筋書きはまあ色々ありますので語る人それぞれになるのではないでしょうか。そもそも甲賀三郎も伝説の人ですし。ただ八頭の鹿というのとヤマタの大蛇の八頭、などと結びつけたりして考えると面白いのではないでしょうか。鳥取県には八頭郡がありますしね。機会が有ればご案内させていただきます。
柳田国男さんも甲賀三郎について、その伝承を考察されているはずです。またお教え下さい。
北山は京の裏山、と間違って貼り付けてしまいました(*_*)失礼しました。