麻生総理が演説原稿の漢字を頻繁に読み間違えることがテレビなどでバカにされている。
未曾有を「みぞゆう」と読んだそうだが、なぜ未曾有が「みぞう」でなければならず、「みぞゆう」ではダメなのか。果たして麻生総理をバカにしている人の中で、その理由を理路整然と説明できる人はいるのだろうか。
なぜ有無は「うむ」であって「ゆうむ」ではいけないのか。保有は「ほゆう」であって、「ほう」ではいけないのか。
両方とも有の意味は同じである。どういう場合に「う」で、どういう場合に「ゆう」なのか規則性ははっきり言って存在しない。
未曾有、有無、保有はみな中国語にもある言葉だが、有の読み方ははどれもヨウであって同じである。
要するに、日本にその言葉が入ってきた時期によって華東地域の方言の発音が入ったり、長安の方言の発音が入ったりしたことによって読み方の区別が出てきたのである。有無の場合は関西弁で、保有の場合は関東弁で読むべし、と決めているようなもので、言葉の元祖である中国人から見れば何とも奇妙な光景であろう。
もともと中国語では1漢字1発音であることがほとんどである。1漢字に複数の発音があるケースは稀にあるが、はっきりと意味によって区分されている。それにしても大ざっぱなもので、例えば「給」は動詞として使う場合は「gei」だが、「供給」の時は「ji」というのが教科書的には正しいらしいが、8割以上の人が「供給」の場合も「gei」と発音している。
合理的な理由がないことで人をバカにする。何とも日本らしい首相イジメの光景である。
未曾有を「みぞゆう」と読んだそうだが、なぜ未曾有が「みぞう」でなければならず、「みぞゆう」ではダメなのか。果たして麻生総理をバカにしている人の中で、その理由を理路整然と説明できる人はいるのだろうか。
なぜ有無は「うむ」であって「ゆうむ」ではいけないのか。保有は「ほゆう」であって、「ほう」ではいけないのか。
両方とも有の意味は同じである。どういう場合に「う」で、どういう場合に「ゆう」なのか規則性ははっきり言って存在しない。
未曾有、有無、保有はみな中国語にもある言葉だが、有の読み方ははどれもヨウであって同じである。
要するに、日本にその言葉が入ってきた時期によって華東地域の方言の発音が入ったり、長安の方言の発音が入ったりしたことによって読み方の区別が出てきたのである。有無の場合は関西弁で、保有の場合は関東弁で読むべし、と決めているようなもので、言葉の元祖である中国人から見れば何とも奇妙な光景であろう。
もともと中国語では1漢字1発音であることがほとんどである。1漢字に複数の発音があるケースは稀にあるが、はっきりと意味によって区分されている。それにしても大ざっぱなもので、例えば「給」は動詞として使う場合は「gei」だが、「供給」の時は「ji」というのが教科書的には正しいらしいが、8割以上の人が「供給」の場合も「gei」と発音している。
合理的な理由がないことで人をバカにする。何とも日本らしい首相イジメの光景である。












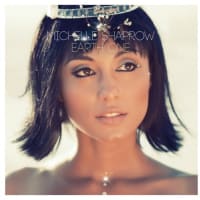

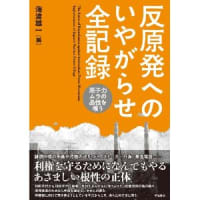



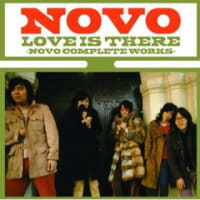

マルティン・ハイデッガーの主著「Sein und Zeit」は、岩波文庫、ちくま学術文庫、中公社版などでは『存在と時間』と訳されていますが、創文社が出している「ハイデッガー全集」版では『有と時』となっています。
僕は、永らくこれを音読みで「ゆうとじ」と読むべきものだと思っていました。しかし、先日、同訳書の扉に「うととき」と訓が振られているのを見つけて、ビックリしました。
http://www.sobunsha.co.jp/bookdates/ISBN978-4-423-19626-7.html
どうやら、道元の『正法眼蔵』の中にある「有時(うとき)」篇との関連で、訳者(辻村公一氏)が、そのような読みを採ったようです。
(河出書房の「世界の大思想」版も同様です。)
道元の著作も、なぜ「しょうぼうげんぞう」という読みをするのか説明するのは、なかなか大変な気がしますが、「有時」が、なぜ「ゆうじ」や「うじ」ではないのかも、分かりません。
こうしたことは、言葉の遣い手の歴史的社会的文化的環境に依存するのだと想います。
つまり、我が首相は、決して教養のレベルが低いわけではなく、我が国の文部科学省(あるいは内閣府)が推奨し標準化している歴史的社会的文化的な環境から、ややズレたところにいらっしゃるだけなんだと思います。
というコメントを書くつもりでいたら、今日は、我が首相が「シノギ」という「暴力団用語」を遣ったということが話題になっていましたね。
やはり「環境」の問題なんだと想います(笑)
それにしても"Sein und zeit"の日本語訳が「有と時」とは驚きます。Seinは英語でいうとBe動詞。これ以上ないシンプルな言葉で根源的問いかけをしようというのが原著の趣旨だと思うのだけれど、およそ日常語とはかけ離れた日本語?になっていて、もしハイデガーがあの世で日本語を習得していたら、「オレはそんなつもりではなかったんだけどなー」とぼやいているかもしれません。
英訳ではBeing and Time。原著のシンプルさをそのまま伝えられますが、日本語には名詞になるBe動詞がないので、「存在と時間」というように漢語頼みになってしまいます。ここはヤマト言葉で「あることととき」というのはどうでしょうか。
「あること、は最も普遍的で、最も空虚な概念だと言われ、無視されてきた」
この方が感じが出るではありませんか。
かつて「大企業」に勤めていたとき、文書管理の仕事をしていたことがありました。大きな官僚的組織では、表記の統一(標準・画一)化というのが要請されます。
戦後の文部省の「当用漢字」政策が始まったとき、諸手を挙げて賛同し、その定着に積極的な役割を果たしたのが大新聞社を中心としたマスコミ。彼らにしてみれば、使用漢字数の削減には、推進すべき合理性があったわけです。(「読み」の画一化については、放送局の利害かもしれませんが。)
「強者」が、「表記・表音」の標準からズレたとき、それを「叩く」理由は、日本のマスコミに固有の価値観の中にもあるかも知れません。そこには、「由来・起源」という意味での「reason」(理性)は不要なのでしょう。
ちなみに、僕は「でんべい」と「でんべえ」という読みについて統一を図っていません。画一化が嫌いなので(笑)
「標準化」とは、一定の明確な規則を定めることで、「有」の読み方の規則性は誰にも説明できない以上、それは標準化と呼ぶに値しません。熟語一つ一つに恣意的に「正しい読み方」が定められているのです。だから首相までもが間違ってしまったわけです。
有無の時は「うむ」なのに、なぜ「有償・無償」の時は「うしょう・むしょう」ではないのか? 規則性が乱れていることは明らかでしょう。
漢字の紀元がどーだろーが、日本人なら中学生でも読める常識的かつ当たり前の文字を読み間違えた麻生が馬鹿なことには変わりない
学生の頃にならった言葉を首相がまちがえる
これは、訂正されて当然でしょう
漢字の起源はともかく、首相が間違えた言葉を
大きく取り上げるマスコミにも問題ありでしょう
何がどうだっていちいち疑問に思ってたら、キリがないけどね。未曾有のレベルに限らず、貴方も昔から大半の事に気になってた訳でもないだろうしね。
それに麻生さんは未曾有の読み間違いがあった以降も間違いを多発した事がおかしいんだけどね。紙を見て喋ってるだけなのに・・・。
まぁ結果、mardinhoさんは綺麗事をぬかしてるだけです(^_^)