ロスの50万人デモ、DJ協力 スペイン語ラジオで動員
2006年 3月30日 (木) 21:34
50万人ものデモ参加者をどうやって動員したのか――。25日にロサンゼルスであった不法移民取り締まり法案に反対するデモについて、その規模に驚いた人々の間で動員の「謎」に関心が集まっている。主催者によると、デモ成功の陰にはスペイン語ラジオFM局のDJたちの全面的な協力があったという。http://news.goo.ne.jp/news/asahi/kokusai/20060330/K2006033004440.html
不法移民取り締まり法案に反対するデモについての古いニュースだが、今回は法案について論じるわけではなくラジオについて。
このデモは、ヒスパニック団体やカトリック関係者、人権団体などが連携し、約2カ月かけて平和的デモを準備したものだが、主催者が予測した動員数は数万人ほどだった。
しかし、デモ主催者がスペイン語FM局に出演したとき、番組のDJが趣旨に賛同し、他のスペイン語ラジオ局10局に声をかけ、他のラジオ局もデモ参加を呼びかけた。
DJ達は、主催者の意向である平和的デモを実現するため、「白を着て家族連れで参加すること」を呼びかけた。そして視聴者はその趣旨に賛同し、結果的に50万人もの人々がデモに参加した。テレビやインターネット全盛の時代に、意外にもラジオというメディアが大きな影響力が発揮した。
しかし、まったく逆の例もある。
1994年、アフリカのルワンダでは、ラジオがすさまじい凶器となった。
ルワンダで行われた虐殺は、ハビリマーナ大統領の政党系列の「千の丘自由ラジオ・テレビ」を通じて、ツチ族に対する憎悪をかきたてる煽動によって、実行を促された。http://www.issue.net/~sun/se/com20000123.html
ラジオは、ツチ族を繰り返し「ゴキブリ」と蔑称し、アフロ・ビートを伴った「ゴキブリをたたき殺せ」というメッセージを農村の隅々まで流した。素朴なフツ族農民が男も女も子どもたちも村をあげて、近くのツチ族めがけて農作業用のナタをふりおろした。また、民兵組織インタラアメは、ラジオが指名するツチ族系要人を直ちに現場で殺害することができた、という。
ルワンダでの虐殺において、ラジオが一定の影響力を持ったことは間違いはないが、もともとツチ族に対する反感や憎悪を掻き立てる政策が執られ続けていた。ラジオの突然の呼びかけだけで、フツ族民衆が虐殺に走ったわけではないようだ。ラジオがどこまでの役割を果たしたのかは議論が分れている。
NHKによって、「なぜ隣人を殺したか~ルワンダ虐殺と扇動ラジオ放送~」という番組も作られている。
ロサンゼルスとルワンダの例は、とても示唆的だが、大衆がメディアのメッセージで誘導できるという単純な結論にはならないだろう。
次ぎのような事例もある。
2002年のベネズエラだ。
メディアは嘘をつくこともまるでいとわず、「チャベスは独裁者だ」という固定観念を広め、世論を焚き付けた。ベネズエラには政治犯がまったくいないにもかかわらず、「チャベスはヒットラーだ」とする論調すらあった。スローガンはただ一つ、「あいつを倒せ!」http://www.diplo.jp/articles02/0206.html
ともするとプロパガンダに傾きがちなメディアは、仮想の民衆と実際の民衆とを混同した。4月11日のクーデタが仮想の民衆の名において行われたのに対し、実際の民衆は2日も経たないうちにチャベス大統領を政権に連れ戻した。
ベネズエラのチャベス大統領は、富を国民に分配することを掲げて、民主的選挙で大統領についた。ベネズエラの石油収入を独占している富裕層は、アメリカ政府にバックアップされ、チャベスを引き摺り下ろす計画を立てた。
2002年4月11日、クーデター未遂事件が発生した。ベネズエラのメディアのほとんどは富裕層に握られているため、メディアは打倒チャベスを叫び続けた。それはそのまま世界に流れた。しかし、クーデターは二日天下で終わった。ベネズエラの民衆は、富裕層に握られたメディアの言葉をまったく信用しなかった。
今日にいたるまで、ベネズエラのメディアとアメリカ政府は、反チャベス・キャンペーンを続けている。しかし、ベネズエラの民衆がこうしたプロパガンダに誘導されることはないようだ。
メディアを富裕層に握られているチャベス大統領が、いかにして民衆に呼びかけているのかは、興味のあるところだ。メディアの影響力が、まったく空振りし続けているという事例はそれほど多くはない。
50万人という平和的デモを実現したロサンゼルスのラジオ。
80万人もの人々を虐殺に追い込んだルワンダのラジオ。
民衆に意図を見透かされているベネズエラのメディア。
ここから学ぶものはとても多いのではないだろうか。
まず、メディアをどう捉えるかだ。
それによって、発信される情報の意図するものも見えてくる。
漫然と情報を受け取っていては、いいように誘導されてしまう。
一人ひとりがメディアとの付き合い方を考えることがたいせつだ。
















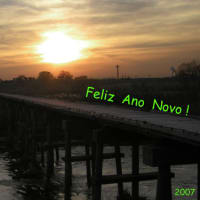
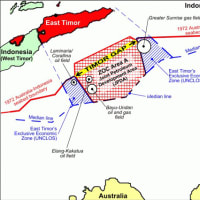


日本のテレビだって同じ事が言えると思うのです。各テレビ局によって、政治ニュースの伝え方が違う。どの局のニュースをメインで見るかによって、日本人それぞれの考え方も異なってくるのです。
私達は、一つの物を見るだけで判断しがちですが、それではいけないのだとつくづく思います。
何か情報を得ようと思うのであれば、それに対する批評を様々な角度から、沢山見聞きして、その中から自分で判断しなければならないと思いました。
日本のメディア、特にテレビ局は僕はあまり変わらないと思います。細かく言うと違うかもしれませんが、大別して変わらないと思います。どこのチャンネルも同じようなことばかり。
何故か日本ではアメリカのニュースばかりで南米やアフリカのニュースはほとんどやりません。最近のペルー大統領選の事もほとんどの人は知らない。
アメリカのことばかりニュースに出るというのも日本がアメリカと強いつながりを持っていると言う証なのでしょうか?
そういう意識があれば、情報に流されることはなくなります。
要はそれを意識するかしないかだと思います。
漫然と情報に接していると、かえって偏った情報が取り込まれ、あらぬ方向に流されてしまいます。
僕も、日本の各メディアの意図する方向はどこも同じだと考えています。
表面的な差はありますが、本質的には変わりはないでしょう。
現在の基本的な底流は、日本をアメリカの従属国にすることだと思います。
独立国の体裁をとった従属国です。
それが様々な形で進行していますが、メディアは報じません。
自らがこの底流に従属しているからでしょう。