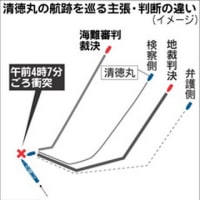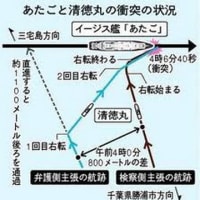この本の概要は「帯」の説明の通りである。そして凡例に《本書は李時明夫人張氏(1598-1680年)の手になる「飲食知味方」(別名「閨壷是議方」)と、徐有本夫人李氏(1759-1824年)の手になる「閨閤叢書」酒食篇、及び許筠(1569-1618年)の「屠門大嚼」を訳出したものである。(中略)前二書は、女性の手になるハングル古文の記録、最期のものは男性の著書で漢文である。》とある。
この前の月曜日、韓国・朝鮮語クラスが終わり、いつものように先生を囲んで「すっから・ちょっから」で食事をしている時に料理の話になり、私がこの本の話をしたところ先生に見せて欲しいと言われたので探し出してきた。まだ目を通していなかったので、この機会にパラパラとページをめくってみた。以下は編著者の「解説」および「あとがき」にもとづいての紹介である。
「飲食知味方(ウムシクチクミバン)」も「閨閤叢書(キュハブチョンソ)」も上層階級の両班(ヤンバン)の食生活を表したもので、当時の庶民階級の食生活のものではない。前著の成立した十六~十七世紀の頃、両班階級が旅行をする時は地方の両班家を相互に利用し合うのが習わしになっていて、旅行者がその地域の班家を訪ねて玄関で「自分はどこそこの何家の者だ」と名乗ると、主人は一度も会ったことのない人でも確かに両班だと知ると丁重に客室に案内し、酒食をもてなした。この接客態度が口伝えで広まっていくので、もてなしに家門の名誉をかけて心を配った。この当時のことゆえみな不意の訪問なので、常備の食料が何らかの形で用意されていなければならないし、また早造りもするのでそのためのテキストが必要になってくる。上層階級の班家の女性たちは読み書きにも洗練された教養を備えていたからこそ、このような料理書を書き残すことが出来たのである。
「飲食知味方」が発見されたのは1960年、現代語訳が現れたのは1966年以降で、2人の訳者がいるが、内容の見解について若干の相違がある。
《「若鶏の蒸しもの」料理で、孫正子氏は野菜の材料ににらととうがらしが用いられるかのように訳されている。黄慧性氏はとうがらしは省かれている。にらは염부추(ヨムブチュ)、あるいは부추(プチュ)とも呼ぶ。とうがらしは고추(コチュ)である。原文の염교(ヨムギョ)の表記を解釈する上で、このような差となったのではないかと思われる。原文を読んでみると、黄女史の方が正しいようである。それで本訳書ではとうがらしを省いた。もう少し掘り下げて考えるならば、この時代の料理にとうがらしが材料として使用されたかどうか、甚だ疑問だからである。
とうがらしが朝鮮や日本に伝来されたのは、十六世紀から十七世紀初頭にかけてである。もしこの書が張氏の手になるものであるならば、この料理内容は少なくとも十六世紀ごろ、いやそれ以前から、李家に連綿と受けつがれてきた伝統的な料理造りの方法が記されたものとみなければならない。つまり新しくこの時代に考え出された料理の書ではないのである。また、とうがらしがそのころに伝来したとしても、そんなに簡単に伝統料理にとり入れられることはまずないであろう。一般にとうがらしが朝鮮の家庭料理に広くとり入れられるようになるのは、十八世紀から十九世紀にかけてのことである。ここに記された班家の伝統料理に用いられたとみるのは早計だと考え、本訳書ではとうがらしはないものとしたのである。》
編著者の「解説」を長々と引用したのは理由がある。先日、朝日新聞が次のように報じた。
《「唐辛子、秀吉が持ち込み説」覆す 韓国研究所
【ソウル=牧野愛博】唐辛子は日本から豊臣秀吉が持ち込んだものではない――。韓国食品研究院は19日付で、こんな研究結果を発表した。
同院は、15年にわたって国内外の数百件の文献を研究。これまで唐辛子は秀吉によって、1592年に起きた第1次朝鮮出兵のときに朝鮮半島に持ち込まれたと信じられていたが、それ以前に発刊された「救急簡易方」などの文献に、唐辛子を意味する言葉が残されていたという。》(asahi.com 2009年2月22日6時0分)
私は長い間、唐辛子は朝鮮から日本にやって来たと思っていた。子供の頃、朝鮮で始めてあの唐辛子にお目にかかった印象が強かったのであろう。それに唐と名のつく品物が朝鮮を経て日本にやって来ることになんの違和感もなかったからである。それが逆に日本から朝鮮に持ち込まれたという話をなにかで知った時には奇異に感じた。だから私にとって「唐辛子は日本から豊臣秀吉が持ち込んだものではない」なんて、「ああ、やっぱり」で済む話なのである。しかし実際にとうがらしが朝鮮でどう使われていたのかには興味があり、それでたまたま上の解説に目が向いたのである。
鄭大聲氏の「解説(1982年)」に「とうがらしが朝鮮や日本に伝来されたのは、十六世紀から十七世紀初頭にかけてである」と記されているのみであるし、またこの本にまとめられた「食生活史参考年表」には《壬辰倭乱(豊臣秀吉の朝鮮侵略)。 とうがらしは、この戦争のときかそれ以前に伝来したとみられる。》とあって、「秀吉が持ち込み説」のあることを示唆しつつも、それ以外の可能性をも考慮に入れている。ただ鄭氏が「飲食知味方」からとうがらしを省くに至った推論の過程は私も納得できる。また壬辰倭乱の終結の年に生まれた張氏の「飲食知味方」に、とうがらしを使った料理の記載のないことは十六世紀から十七世紀初頭にかけて、朝鮮でとうがらしが一般的でなかったことの証と受け取れる。事実、十八世紀から十九世紀に記された李氏の「閨閤叢書」には섞박지(ソクパクチ、まぜ合わせ漬物)としていわゆるキムチの漬け方が出ているが、そこには《まず、大根、白菜累の水のきれたものを入れ、次いでなす・きゅうり・とうがんを入れた上に、塩辛を一重敷く。その上から青角(海藻のみる)・ねぎ・にんにく・とうがらしなどをいっぱいふるかける。》とあって、とうがらしが堂々とまかり通っている。
では「救急簡易方」にどのように「とうがらし」が現れるか、である。現代韓国語で唐辛子は고추である。それが「救急簡易方」では「椒」なる漢字に対応して現れるハングル文字고쵸が「とうがらし」のことと主張されている。しかし明らかに고추と異なる고쵸がどうして「とうがらし」でありうるのか、私にはこのあたりの論法が理解できないのである。

「椒」が「とうがらし」であることの根拠も私には分かりにくい。「椒」は「字通」によると《椒に草・木の二類があり、ともに辛気の強烈なものである。》とあるだけで、「山椒」が例に取り上げられているものの「とうがらし」はどこにも出てこない。「椒」が「とうがらし」でないのなら고쵸も「とうがらし」であり得るはずがなく、もし고쵸は明らかに現在のとうがらしを指す고추と同じものであるのなら、どこでどうなって고쵸が고추になったのか、文字の変遷についての説明が欲しいものである。
さらに言えば「救急簡易方」は1489年の書籍のようである。すなわちコロンブスがアメリカ大陸に辿り着く前である。と言うことは朝鮮にとうがらしがもともと自生していたことになる。私は唐辛子の原産地は中南米かと思っていた。下の本にはこのように出てくる。

《カリブ諸島があらゆる種類のトウガラシの原産地であることが推察される。アメリカの植民地化以降もトウガラシの品種は多様化しつづけた。(中略)スペイン人とポルトガル人はすぐにトウガラシを旧世界に持ち帰った。ヨーロッパではあまりにも刺激が強すぎてすぐには受け入れられなかったが、アフリカ、アラブ、アジアではまさに天啓のように歓迎された。人々はトウガラシを大量に使い、インド洋や太平洋の島々の住民もこれにならった。十六世紀にはあまりにも急激に普及したために、・・・》と中米産起源説を紹介している。
現在韓国で使われているとうがらしの起源が中米でなく朝鮮自生のものであることが生物学的に証明されたら、秀吉持ち込み説なんてかすんでしまうビッグニュースではないか。韓国の生物学者に国威発揚?のためにも頑張っていただきたいものである。明日「朝鮮の料理書」を先生にお見せする時に少し挑発してみよう。