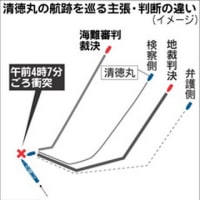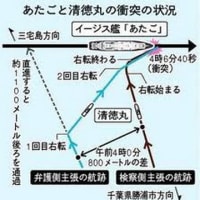先月九十五歳という高齢で亡くなった角田文衛さんの著書「平安の春」(朝日新聞社)の最後に収められた「女のいのち」に、延喜二年(902年)の阿波国板野郡田上郡戸籍や延喜八年の周防国玖珂郡玖珂郷戸籍などに女性の高齢者の多いことの指摘がある。そして後者から22人の八十歳以上の女性高齢者の名前が列記されている。最高齢者は百二歳である。角田さんは医療が発達し、平均寿命が高くなった現代でも、長生きできる限度は千年も前の昔とさほど変わっていないようであるとの感想を述べておられる。これは面白い指摘だと思い、講義の材料に取り入れたことがある。

翁に媼と言う言葉があるように、昔から高齢者は存在した。律令の規定にも年齢の区分があって、続日本紀の天平宝字二年(758年)七月三日の条に「今より以後、六十を老丁とし、六十五を耆老とすべし」とある。耆老を訓読みにすると「ふるきおきな」で、すでにこの頃にも老人を年齢によって老丁と耆老に分けている。今流で言えば初期高齢者と後期高齢者である。今のシステムのはしりのようだが、この年齢による区別に文句が出たとは思えない。なぜなら昔は高齢者がよりよく手厚い扱いを受けるための区分であったからだ。老丁になると二十歳以上の丁が負担する調と庸が半分になり、耆老は調庸が免除される。今でいえば税金を納めなくてもよくなるのである。その上まだ先がある。八十歳以上の高齢者と身体障害者には侍一人を、九十歳には二人を、百歳には五人を国が支給するというのである。侍とは今で言う介護者で、基本的には親族の課役が課せられる成人男性から選ぶようにと定められていた。また老人で子供のいない独り者とか自活不能社には賑給として米が年齢に応じて高齢者ほど多く支給されていた。高齢者までが介護保険を払わされる現代と大違いである。

上の話は服部早苗著「平安朝に老いを学ぶ」(朝日選書)に出ているもので、八世紀の頃からから1300年もなっているのに、国家による高齢者の扱いはかえって低下しており、人間の社会は進歩するばかりではないことがよく分かる。残されている史料によると、この当時、出雲国出雲郡漆沼郷の人口1500人のうち高齢者が60人、すなわち全人口の4%というから決して少ない数ではない。古代人人口を推計した研究結果では今の計算法に従うと平均寿命が三十歳に届かないとされているが、年齢別人口では十九歳以下が五割近くを占める一方、六十歳以上が全体の5.7%で、若年死亡率が現代に比べて非常に高いのが特徴的である。と言うことは二十歳まで生き延びると現代と同じくかなりの高齢にまで達するということになる。
ここで話が飛躍するが、この当時に今の日本に見かける医師免許を持った西洋医はもちろん居なかったし、先端医療なんておよそ縁のない原始医療の時代であった。それにもかかわらずちゃんと高齢者がそこそこ生きていたのである。病い、健康とのかかわりはどうだったのだろうか。
平安朝時代に入ると長寿法として露蜂房(ロイヤルゼリー)や枸杞を飲んだ貴族の話がこの本に出てくるが、健康法という意識がすでにあったのであろう。医師は治療を施し漢方薬を処方したが、外科手術などはおこなわなかった。自分なりの薬療法について医師の意見を尋ねる貴族がいたというから、自分のことは自分でという自立精神が一般的であったのかも知れない。この貴族とは「小右記」を残した藤原実資で、今でいうおたふく風邪が流行った時には60年前の記憶を呼び起こして「顔貌赤く腫れ、まず発熱し、後大いに腫れる。五六日を経て平復すと。療を加えざるを良となす」とアドバイスをしている。医者にかからない方がよいといっているのである。健康維持そして治療に対してさえ、当時の人は自分の判断を第一としていたようである。
時代は下って江戸時代に入っても高齢者は結構多い。下のグラフは速水融著「歴史人口学で見た日本」(文春新書)に記載(131ページ)のものである。幕末百年分残っている「宗門改帳」を元に調べたデータで、著者は《濃尾地方の農村における死亡年齢と比べた結果、濃尾地方では、幼児のころはたくさん死ぬが、十歳過ぎるとあまり死なず、六十から七十歳くらいまで生き延びているのに対し、奈良の場合は、もちろん子供のときにもたくさん死ぬけれども、それから先、濃尾地方ではめったに死なない二十代、三十代、四十代も同じように死んでしまう。簡単にいってしまえばいつ死ぬかわからない、いつ死んでもおかしくないという状況になっている。》(129ページ)とこのグラフを解析している。都市の住民の方が早死になのである。しかし六十歳を超える高齢者がとくに農村地帯で思いのほか多い事実は注目に値する。今以上に医者のいない「僻地」であっただろうに。

立川昭二著「病と人間の文化史」、「いのちの文化史」(ともに新潮選書)には江戸時代の高齢者の生き方が紹介されている。前者では七十歳を超えても矍鑠と「為すべきこと」に励んだ杉田玄白、小林一茶、滝沢馬琴、神沢杜口などが出てくるし、後者には伊能忠敬ともう一度神沢杜口が出てくる。よく知られていることであるが、伊能忠敬は数え年五十六歳で蝦夷地に入り七十四歳で世を去るまで日本全国を歩きつくして最初の日本全図を作成した。測量距離は四万キロ、地球一周分というから凄いの一言に尽きる。
その伊能忠敬は若いころから病弱であったという。立川さんはこう記している。《忠敬には持病があり、旅先では下痢や腹痛によくかかり、ときには「おこり」(マラリア)にもおそわれた。そんなときは常備薬を服用していたが、医者に診てもらったという記録はない。晩年に歯が一本になったときも、歯医者にかかり入れ歯を作ることはしなかった。自分のからだを信頼し、歯が無くなれば無いなりに生きていくという信念を持っていた。》(146ページ)そしてこの生き方を「いき」という江戸の美学に照らして評価する。
《病気や老化しても意地を保ち、足を知り、ものに執着せず、心豊かに自己の世界に自足し、そのうえでライフワーク完成の夢に生きる。それこそ「いき」という洗練された魅力(色っぽさ)のある生き方である。》(147ページ)
私は実は現代でもこのような生き方をしている高齢者が大勢いると思っている。ところがマスメディアの取り上げ方ではなぜか「弱者」としての高齢者が目立っている。最近の「後期高齢者医療制度」での取り扱いでもそうである。だから世間は高齢者といえばおしなべてそうであると錯覚してしまうのではなかろうか。
いざとなれば心置きなく医療のお世話になるためにも、日常は健康維持を自らの務めとして医者離れを心がけてはいかがだろうか。昔の人は定期健康診断にメタボ診断などなど余計なものがなかったから長生きできたのだと思えばよいのである。

翁に媼と言う言葉があるように、昔から高齢者は存在した。律令の規定にも年齢の区分があって、続日本紀の天平宝字二年(758年)七月三日の条に「今より以後、六十を老丁とし、六十五を耆老とすべし」とある。耆老を訓読みにすると「ふるきおきな」で、すでにこの頃にも老人を年齢によって老丁と耆老に分けている。今流で言えば初期高齢者と後期高齢者である。今のシステムのはしりのようだが、この年齢による区別に文句が出たとは思えない。なぜなら昔は高齢者がよりよく手厚い扱いを受けるための区分であったからだ。老丁になると二十歳以上の丁が負担する調と庸が半分になり、耆老は調庸が免除される。今でいえば税金を納めなくてもよくなるのである。その上まだ先がある。八十歳以上の高齢者と身体障害者には侍一人を、九十歳には二人を、百歳には五人を国が支給するというのである。侍とは今で言う介護者で、基本的には親族の課役が課せられる成人男性から選ぶようにと定められていた。また老人で子供のいない独り者とか自活不能社には賑給として米が年齢に応じて高齢者ほど多く支給されていた。高齢者までが介護保険を払わされる現代と大違いである。

上の話は服部早苗著「平安朝に老いを学ぶ」(朝日選書)に出ているもので、八世紀の頃からから1300年もなっているのに、国家による高齢者の扱いはかえって低下しており、人間の社会は進歩するばかりではないことがよく分かる。残されている史料によると、この当時、出雲国出雲郡漆沼郷の人口1500人のうち高齢者が60人、すなわち全人口の4%というから決して少ない数ではない。古代人人口を推計した研究結果では今の計算法に従うと平均寿命が三十歳に届かないとされているが、年齢別人口では十九歳以下が五割近くを占める一方、六十歳以上が全体の5.7%で、若年死亡率が現代に比べて非常に高いのが特徴的である。と言うことは二十歳まで生き延びると現代と同じくかなりの高齢にまで達するということになる。
ここで話が飛躍するが、この当時に今の日本に見かける医師免許を持った西洋医はもちろん居なかったし、先端医療なんておよそ縁のない原始医療の時代であった。それにもかかわらずちゃんと高齢者がそこそこ生きていたのである。病い、健康とのかかわりはどうだったのだろうか。
平安朝時代に入ると長寿法として露蜂房(ロイヤルゼリー)や枸杞を飲んだ貴族の話がこの本に出てくるが、健康法という意識がすでにあったのであろう。医師は治療を施し漢方薬を処方したが、外科手術などはおこなわなかった。自分なりの薬療法について医師の意見を尋ねる貴族がいたというから、自分のことは自分でという自立精神が一般的であったのかも知れない。この貴族とは「小右記」を残した藤原実資で、今でいうおたふく風邪が流行った時には60年前の記憶を呼び起こして「顔貌赤く腫れ、まず発熱し、後大いに腫れる。五六日を経て平復すと。療を加えざるを良となす」とアドバイスをしている。医者にかからない方がよいといっているのである。健康維持そして治療に対してさえ、当時の人は自分の判断を第一としていたようである。
時代は下って江戸時代に入っても高齢者は結構多い。下のグラフは速水融著「歴史人口学で見た日本」(文春新書)に記載(131ページ)のものである。幕末百年分残っている「宗門改帳」を元に調べたデータで、著者は《濃尾地方の農村における死亡年齢と比べた結果、濃尾地方では、幼児のころはたくさん死ぬが、十歳過ぎるとあまり死なず、六十から七十歳くらいまで生き延びているのに対し、奈良の場合は、もちろん子供のときにもたくさん死ぬけれども、それから先、濃尾地方ではめったに死なない二十代、三十代、四十代も同じように死んでしまう。簡単にいってしまえばいつ死ぬかわからない、いつ死んでもおかしくないという状況になっている。》(129ページ)とこのグラフを解析している。都市の住民の方が早死になのである。しかし六十歳を超える高齢者がとくに農村地帯で思いのほか多い事実は注目に値する。今以上に医者のいない「僻地」であっただろうに。

立川昭二著「病と人間の文化史」、「いのちの文化史」(ともに新潮選書)には江戸時代の高齢者の生き方が紹介されている。前者では七十歳を超えても矍鑠と「為すべきこと」に励んだ杉田玄白、小林一茶、滝沢馬琴、神沢杜口などが出てくるし、後者には伊能忠敬ともう一度神沢杜口が出てくる。よく知られていることであるが、伊能忠敬は数え年五十六歳で蝦夷地に入り七十四歳で世を去るまで日本全国を歩きつくして最初の日本全図を作成した。測量距離は四万キロ、地球一周分というから凄いの一言に尽きる。
その伊能忠敬は若いころから病弱であったという。立川さんはこう記している。《忠敬には持病があり、旅先では下痢や腹痛によくかかり、ときには「おこり」(マラリア)にもおそわれた。そんなときは常備薬を服用していたが、医者に診てもらったという記録はない。晩年に歯が一本になったときも、歯医者にかかり入れ歯を作ることはしなかった。自分のからだを信頼し、歯が無くなれば無いなりに生きていくという信念を持っていた。》(146ページ)そしてこの生き方を「いき」という江戸の美学に照らして評価する。
《病気や老化しても意地を保ち、足を知り、ものに執着せず、心豊かに自己の世界に自足し、そのうえでライフワーク完成の夢に生きる。それこそ「いき」という洗練された魅力(色っぽさ)のある生き方である。》(147ページ)
私は実は現代でもこのような生き方をしている高齢者が大勢いると思っている。ところがマスメディアの取り上げ方ではなぜか「弱者」としての高齢者が目立っている。最近の「後期高齢者医療制度」での取り扱いでもそうである。だから世間は高齢者といえばおしなべてそうであると錯覚してしまうのではなかろうか。
いざとなれば心置きなく医療のお世話になるためにも、日常は健康維持を自らの務めとして医者離れを心がけてはいかがだろうか。昔の人は定期健康診断にメタボ診断などなど余計なものがなかったから長生きできたのだと思えばよいのである。