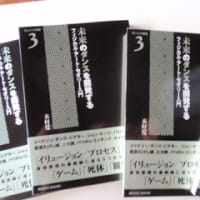昨日は、幸福なことにトークゲストで呼ばれ、なんだかとりとめなくべらべらとしゃべってしまいましたが、もしも舞台上で頭が真っ白になったら、、、と朝食中急に不安になり、午前中の1時間くらいで大急ぎで書いて会場で配った、ゲネプロ段階の公演内容を素材にした文章を、ここに掲載します。批評文なのか感想文なのかファンレターなのか判然としない異物ですが。ちょっとだけ修正してあります。
「幽霊」への感度
:小指値『霊感少女ヒドミ』Remix
ああ、なんとすげー作品を目の当たりにしてしまったことか!とイラダチにも似た歴史的感動に震える我が身を無理してちょっと脇にどかして、至ってクールに、作品に負けぬほどのクールを装いふり返るなら、いつものようにひっちゃかめっちゃかにぎやかに見えたこの舞台に、揺るぎないある一貫した「何か」がつねに漂っていた、そう切り出すのはどうだろう。
「何か」とは、例えば「幽霊」的な性格?実体から乖離した、ないし実体のない「幽霊」。もちろん霊感少女につきまとうサブローはその代表的存在だけれど、5人に分裂しちゃってるヒドミもいわば「幽霊」的な何かに相違ない。いや、考えてみれば、ヒドミの台詞のほとんどはブログという実体(書き手)のあやふやな文章から構成されているわけだし(そのブログの名称も「ヒトミ・ブログ」で、ヒドミの名から乖離しちゃってるし、それだから彼氏には見つからなかったわけだし)、そもそものそもそもとして、これ、ハイバイが2005年に公演した作品のRemixで、そういう意味でも作品自体が幽霊的な身分にあるわけで、例えば、もとの作品のソースがダイレクトに差し込まれたりするのも、そこにないはずのものが舞台に現前しちゃってる感がすごくあって、そういうあたりなんて誠にもって幽霊的なのだ。ヒドミがフリーターなのも、ナンパをきっかけにつきあっちゃうのも、そもそも自分が誰でどうしてそこに住んでいるのか分からないというヒドミの根本的な部分においても、揺るぎなくすべてが、例えばこう「幽霊」とでも呼んでみたくなる何かに貫かれている。
ぼくはゲネプロを見た段階で、この作品にいたく感動したのだけれど、その理由は、この作品が単に首尾一貫したものをもっているからなどではもちろんなく、この「幽霊」に強烈なリアリティがあったからだと、現時的では思っている。簡単に言えば、ぼくたちが付き合っているものたちすべては「幽霊」であると、というか、ぼくたち自身が紛れもない「幽霊」だと確認させられた、そのことにいたく感動したのだと思う。ネットの言説もiTuneも恋愛もセックス(自分自身の身体感覚)さえも、実感がどこか遠い、どこまでも遠い、ひと、もの、自分。
ところで、最近、ぼくより年長の大人たちがなぜか頼りにならないはずのぼくのところに人生相談をしてくる、なんて不思議なことがあった。一人じゃなく複数。彼らの心中にあるのは、聞き手の解釈で勝手にまとめてしまえば、自分のしたことに手応えが感じられない、何か先が見えてしまった気がするなどの空虚感。ぼくはその間、何度か小指値の稽古を見に行っていた。その異常なほどにハイテンションの(小学生のクリスマス・パーティのごとき)空間で構築されようとしていたのは、考えてみれば、まさに大人たちが感じている空虚感に似た「幽霊」なのであった。要は、誰もがいま、同じ境遇を生かされているのである。だから、大人だけじゃないぜ!と言いたくなる(そもそも実体なんてないのに実体らしきものを捏造せずにはおれない大人たちが弱虫なだけだぜ、なんて言って励ましたくなる)。要は、幽霊じゃなくなることを願うことではなく、幽霊であることを思いっきり遊ぶこと、なのではないだろうか。小指値がぼくたちに見せたのは、そういう遊びの一実例なのではないか。ポップで、失笑と爆笑とがない交ぜになった、カラッと瑞々しい遊びの空間。
稽古場で、ヒドミが5人あらわれる最初のシーンを繰り返し練習している彼らは傑作だった。「分身(ドッペルゲンガー)」というゲームを遊び、その遊びがどうなると最も面白いものになるかを真剣に組み立てている彼らは、まさに小学生みたいにふざけてて、しょーもない(とでも形容する他ない魅力的な)アイディアに大笑いしていて、真剣に「幽霊」的なものと遊んでいた。そうした遊びの実践がアゴラ劇場という演劇空間に出現し、そこで遊びが演劇となり(演劇と呼ばれるありもしない実体をひとつの単なるぼくたちの存在と等価な幽霊にしてしまい)、そうして幽霊を感知しそれを幽霊であるがままに招いてそれと遊ぶ時間を生成する(だから彼らこそ「霊感少女」なのだ)、そんな前代未聞の奇跡的な舞台をぼくは見たのだと思っている。(2008.2.9 ver.1.1)
「幽霊」への感度
:小指値『霊感少女ヒドミ』Remix
ああ、なんとすげー作品を目の当たりにしてしまったことか!とイラダチにも似た歴史的感動に震える我が身を無理してちょっと脇にどかして、至ってクールに、作品に負けぬほどのクールを装いふり返るなら、いつものようにひっちゃかめっちゃかにぎやかに見えたこの舞台に、揺るぎないある一貫した「何か」がつねに漂っていた、そう切り出すのはどうだろう。
「何か」とは、例えば「幽霊」的な性格?実体から乖離した、ないし実体のない「幽霊」。もちろん霊感少女につきまとうサブローはその代表的存在だけれど、5人に分裂しちゃってるヒドミもいわば「幽霊」的な何かに相違ない。いや、考えてみれば、ヒドミの台詞のほとんどはブログという実体(書き手)のあやふやな文章から構成されているわけだし(そのブログの名称も「ヒトミ・ブログ」で、ヒドミの名から乖離しちゃってるし、それだから彼氏には見つからなかったわけだし)、そもそものそもそもとして、これ、ハイバイが2005年に公演した作品のRemixで、そういう意味でも作品自体が幽霊的な身分にあるわけで、例えば、もとの作品のソースがダイレクトに差し込まれたりするのも、そこにないはずのものが舞台に現前しちゃってる感がすごくあって、そういうあたりなんて誠にもって幽霊的なのだ。ヒドミがフリーターなのも、ナンパをきっかけにつきあっちゃうのも、そもそも自分が誰でどうしてそこに住んでいるのか分からないというヒドミの根本的な部分においても、揺るぎなくすべてが、例えばこう「幽霊」とでも呼んでみたくなる何かに貫かれている。
ぼくはゲネプロを見た段階で、この作品にいたく感動したのだけれど、その理由は、この作品が単に首尾一貫したものをもっているからなどではもちろんなく、この「幽霊」に強烈なリアリティがあったからだと、現時的では思っている。簡単に言えば、ぼくたちが付き合っているものたちすべては「幽霊」であると、というか、ぼくたち自身が紛れもない「幽霊」だと確認させられた、そのことにいたく感動したのだと思う。ネットの言説もiTuneも恋愛もセックス(自分自身の身体感覚)さえも、実感がどこか遠い、どこまでも遠い、ひと、もの、自分。
ところで、最近、ぼくより年長の大人たちがなぜか頼りにならないはずのぼくのところに人生相談をしてくる、なんて不思議なことがあった。一人じゃなく複数。彼らの心中にあるのは、聞き手の解釈で勝手にまとめてしまえば、自分のしたことに手応えが感じられない、何か先が見えてしまった気がするなどの空虚感。ぼくはその間、何度か小指値の稽古を見に行っていた。その異常なほどにハイテンションの(小学生のクリスマス・パーティのごとき)空間で構築されようとしていたのは、考えてみれば、まさに大人たちが感じている空虚感に似た「幽霊」なのであった。要は、誰もがいま、同じ境遇を生かされているのである。だから、大人だけじゃないぜ!と言いたくなる(そもそも実体なんてないのに実体らしきものを捏造せずにはおれない大人たちが弱虫なだけだぜ、なんて言って励ましたくなる)。要は、幽霊じゃなくなることを願うことではなく、幽霊であることを思いっきり遊ぶこと、なのではないだろうか。小指値がぼくたちに見せたのは、そういう遊びの一実例なのではないか。ポップで、失笑と爆笑とがない交ぜになった、カラッと瑞々しい遊びの空間。
稽古場で、ヒドミが5人あらわれる最初のシーンを繰り返し練習している彼らは傑作だった。「分身(ドッペルゲンガー)」というゲームを遊び、その遊びがどうなると最も面白いものになるかを真剣に組み立てている彼らは、まさに小学生みたいにふざけてて、しょーもない(とでも形容する他ない魅力的な)アイディアに大笑いしていて、真剣に「幽霊」的なものと遊んでいた。そうした遊びの実践がアゴラ劇場という演劇空間に出現し、そこで遊びが演劇となり(演劇と呼ばれるありもしない実体をひとつの単なるぼくたちの存在と等価な幽霊にしてしまい)、そうして幽霊を感知しそれを幽霊であるがままに招いてそれと遊ぶ時間を生成する(だから彼らこそ「霊感少女」なのだ)、そんな前代未聞の奇跡的な舞台をぼくは見たのだと思っている。(2008.2.9 ver.1.1)