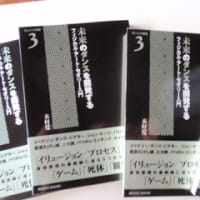昨日(1/14)は、王子小劇場でシベリア少女鉄道スピリッツ「もう一度、この手に」を見た。必見ですよ!(下記はネタバレ有り)
シベ少、結構久しぶりに見た。3年は前だ。面白かった。なんとなく、岡田チェルフィッチュがロスジェネ(死語?)世代の演劇代表と考えがちなんだけれど、5年前くらいを思い返せば、他にも若い面白い演出家が一杯横に並んでいて、いろいろな可能性のるつぼ状態だったわけで、そんなだったなあと思い出しながら見ていた(これはあくまでもぼくの問題、忘れていました)。
8本のショートが次々と上演される。暗転があり、タイトルがプロジェクトされる。けれども、かっちりと切れているわけではなく、ゆるくつながっていて、とくにそのつながりをつくっているのが、半分架空の「役者」の設定。後半からの町田マリーによる「ナレーション」によって明らかにされるのだが、この芝居には、役者に「役A」のみならず「役を演じる役者」という「役B」が与えられている。「役B」は、「ヨーロッパ企画の役者で京都出身」というリアルな内容の場合もあるし、「アンドロイド」とか「整形手術をした元男性」(これを女優・篠塚茜が演じている)とか、まったく非現実的な場合もある。「ヨーロッパ企画の役者で京都出身」は、さらに「台本がぐずぐすだし関西のお笑い感からしたらこれのどこがおかしいと感じて不満を抱いている」といったキャラ設定がされているので、「その不満から舞台に身が入らず携帯をいじったり漫画を読んだりする」ことになる。
それぞれの「役者=役B」は、「役A」を演じながらそれぞれの悩みを抱きつつ、舞台のストーリーとは別にその解決を模索する。だから、この「もう一度、この手に」は「8本のショート」作品ではなく、実は〈2階建て〉になっていて「8本のショートを演じることになった八人の役者たちのリアルストーリー」の作品なのだった。もちろん「リアルストーリー」ではないのだけれど、半分は実話なので、なんとなく錯覚も起こす。このあたりが本作のきわめてすぐれたところで、一緒に見に行ったKATの学生たちも、どこまでがリアルでどこまでが仕掛けられた(台本にある)演技なのかが分からなくなっていた。
それにしても土屋亮一は「伏線の名手」だ。冒頭の1話は、遺産争いをする異母兄妹がいつのまにかTV番組「ごきげんよう」をやってしまっている、というものなのだけれど、そのきっかけが四角い遺骨の箱を怒りに乗じて投げてしまうというところにあって、その瞬間、あまりのことにぞっとするのだが、そのあと「遺骨の箱」=「サイコロ」か、とわかるとその安堵とともに爆笑する。そこには充分「お笑い」の要素が含まれているのだけれど、実は、シベ少のすごさは、笑いよりもその手前にあった恐怖の方にあるのかもしれない。
前半から、「なんとなく」役者の動きがぎこちない。「整形手術をした元男性」は、後から見れば「女性としての自信がないのでもじもじとしてしまう」という人物設定がなされていたのかと分かるのだが、前半ではただもじもじとした演技が不自然に遂行されていた。「タネ」が明かされれば、安堵するにはするが、実は見せたいのは、「ネタ」が明かされる前の不穏さなのではないか。伏線の魅力というのは、伏線があるということに乗じて、ありえないおそろしいリミックスを平気で実行しうるところにあるのではないのか。
それにしても、篠塚茜はいいなあ。以前よく見ていた時にも思っていたのだけれど、声や振る舞いの漫画っぽさ。独特の抑揚があって、抑揚を曲線になぞらえれば、その曲線にはなぞるとひっかかり(フック)があったりして、そのひっかかりがとてもいいかんじなのだ。篠塚に匹敵するのは、ぼくのなかでは安めぐみ。金曜の夕方東京FMで彼女の司会番組があるんだけれど、いつも帰宅中の車で聴きながらひとり声真似しちゃってます。ポップなのだ、このポップさはとても貴重。
タイトルの「天安門」は、観劇後、KATの学生たちと行った中華料理屋。リアル中国が体感できる店。北東京はユニークないい店が多いとあらためて思う。
シベ少、結構久しぶりに見た。3年は前だ。面白かった。なんとなく、岡田チェルフィッチュがロスジェネ(死語?)世代の演劇代表と考えがちなんだけれど、5年前くらいを思い返せば、他にも若い面白い演出家が一杯横に並んでいて、いろいろな可能性のるつぼ状態だったわけで、そんなだったなあと思い出しながら見ていた(これはあくまでもぼくの問題、忘れていました)。
8本のショートが次々と上演される。暗転があり、タイトルがプロジェクトされる。けれども、かっちりと切れているわけではなく、ゆるくつながっていて、とくにそのつながりをつくっているのが、半分架空の「役者」の設定。後半からの町田マリーによる「ナレーション」によって明らかにされるのだが、この芝居には、役者に「役A」のみならず「役を演じる役者」という「役B」が与えられている。「役B」は、「ヨーロッパ企画の役者で京都出身」というリアルな内容の場合もあるし、「アンドロイド」とか「整形手術をした元男性」(これを女優・篠塚茜が演じている)とか、まったく非現実的な場合もある。「ヨーロッパ企画の役者で京都出身」は、さらに「台本がぐずぐすだし関西のお笑い感からしたらこれのどこがおかしいと感じて不満を抱いている」といったキャラ設定がされているので、「その不満から舞台に身が入らず携帯をいじったり漫画を読んだりする」ことになる。
それぞれの「役者=役B」は、「役A」を演じながらそれぞれの悩みを抱きつつ、舞台のストーリーとは別にその解決を模索する。だから、この「もう一度、この手に」は「8本のショート」作品ではなく、実は〈2階建て〉になっていて「8本のショートを演じることになった八人の役者たちのリアルストーリー」の作品なのだった。もちろん「リアルストーリー」ではないのだけれど、半分は実話なので、なんとなく錯覚も起こす。このあたりが本作のきわめてすぐれたところで、一緒に見に行ったKATの学生たちも、どこまでがリアルでどこまでが仕掛けられた(台本にある)演技なのかが分からなくなっていた。
それにしても土屋亮一は「伏線の名手」だ。冒頭の1話は、遺産争いをする異母兄妹がいつのまにかTV番組「ごきげんよう」をやってしまっている、というものなのだけれど、そのきっかけが四角い遺骨の箱を怒りに乗じて投げてしまうというところにあって、その瞬間、あまりのことにぞっとするのだが、そのあと「遺骨の箱」=「サイコロ」か、とわかるとその安堵とともに爆笑する。そこには充分「お笑い」の要素が含まれているのだけれど、実は、シベ少のすごさは、笑いよりもその手前にあった恐怖の方にあるのかもしれない。
前半から、「なんとなく」役者の動きがぎこちない。「整形手術をした元男性」は、後から見れば「女性としての自信がないのでもじもじとしてしまう」という人物設定がなされていたのかと分かるのだが、前半ではただもじもじとした演技が不自然に遂行されていた。「タネ」が明かされれば、安堵するにはするが、実は見せたいのは、「ネタ」が明かされる前の不穏さなのではないか。伏線の魅力というのは、伏線があるということに乗じて、ありえないおそろしいリミックスを平気で実行しうるところにあるのではないのか。
それにしても、篠塚茜はいいなあ。以前よく見ていた時にも思っていたのだけれど、声や振る舞いの漫画っぽさ。独特の抑揚があって、抑揚を曲線になぞらえれば、その曲線にはなぞるとひっかかり(フック)があったりして、そのひっかかりがとてもいいかんじなのだ。篠塚に匹敵するのは、ぼくのなかでは安めぐみ。金曜の夕方東京FMで彼女の司会番組があるんだけれど、いつも帰宅中の車で聴きながらひとり声真似しちゃってます。ポップなのだ、このポップさはとても貴重。
タイトルの「天安門」は、観劇後、KATの学生たちと行った中華料理屋。リアル中国が体感できる店。北東京はユニークないい店が多いとあらためて思う。