





1955年の冬、南部から、主を亡くしたパロンディ家の母親と4人の兄弟が、貧しさから脱却するべく、北部ミラノに住む長男を頼って出て来た。
しかし、同じ兄弟でも、故郷を捨てきれない者、都会に順応する者とに分かれ、また、子離れできない母親の激しい執着や、美しい娼婦との出会いや恋愛等が相まって、家族の間に亀裂が生じ、次第に埋めがたい溝となって行く。
一家のミラノでの生活は決して楽にはならないばかりか、崩壊へと向かうのである。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜
ちょっと、本作について書くには1回じゃ書き切れないので、3回に分けることにしました。
◆武蔵野館でのヴィスコンティ特集
現在、「ルキーノ・ヴィスコンティ-イタリア・ネオレアリズモの軌跡―」と題して、新宿武蔵野館でヴィスコンティ特集を行っています。本特集で上映されるのは『若者のすべて』『郵便配達は二度ベルを鳴らす』『揺れる大地』の3作品。
ちなみに、新宿武蔵野館は昨年の夏から秋にかけて一時閉館し、大規模改修を行っておりました。今回、どんくらい変わったのかしらん、とちょっと楽しみに行ったのですが、まあ、基本的な作り(スクリーンの配置や受付・トイレ等の配置)は以前と全く変わっておらず、内装が綺麗になって、劇場の椅子が新調されていました。しかし、いかんせん、座席の傾斜は以前のままなので、座る位置を間違えるとスクリーンが見づらいという点は改善されていなかったです。もう少し傾斜をつけてくれるとありがたいんですけどね、、、。まあ、あのビルの作りからいってそれはムリな望みなのは分かるんですが。一番大きなスクリーンの部屋は入っていないので分かりませんが、多分同じでしょう。
◆映画友の逆鱗に触れてしまった!
以前、『地獄に堕ちた勇者ども』の感想で、「お高く留まった映画」だの「単に耽美ってだけじゃなく、選民意識の匂いを嗅ぎ取る」だのと、罵りの文言を思うがままに書いたのですが、ほぼそれと同じことを、愚かにもヴィスコンティ好きの映画友に話したら、どうやら逆鱗に触れたようで「『若者のすべて』を見てから言え!」とぶった斬られました。
映画友曰く、『若者のすべて』を見れば、自分のヴィスコンティ評がいかに浅薄で本質を見誤っているかが痛いほど分かるはずだ、とのこと。
……まあ、そこまで言われれば見ない訳にも行きません。素直に見てみることにしました、しかもスクリーンで。
◆けたたましくて恐ろしい母親
映画友の言葉に対する自分なりの答えは後述するとして、まず内容に関する感想から。
イタリアは、ヨーロッパの中でも母子密着が強く、マンマが強いらしい。うろ覚えですが、ヨーロッパでは、イタリアの引きこもり率が高かったはず。そもそも“引きこもり”が可能なのは、大人になっても親の家から追い出されずに住み続ける文化がある場合だそうで、早くに自立を促される国では引きこもりではなく“ホームレス”になるとのこと。そういう意味で、日本や韓国での引きこもりは非常に多く、ヨーロッパではイタリアに多い、という調査結果が出ているのだとか。
本作を見て、その話が改めて説得力を持って私の脳裏に蘇りました。なるほどなぁ、、、と、パロンディ家を見ていて納得です。
ミラノに出てきた4人の息子のうち、末っ子(五男)のルーカは子どもですが、あとの3人は(四男のチーロは夜間大学の学生)皆大人です。イイ大人が3人も母親と一緒の部屋で寝ているっていう光景だけで(家が狭いからというのもあるけど)、ちょっとギョッとなりました。
母親のロザリアがですね、、、いろんな意味で怖いんです。とにかく、喋り方がけたたましい。声が異様に大きくて、まさしく機関銃のごとくまくし立てる。そんなにがなり立てなくても会話はできるでしょ、と言いたくなるけど、あれが多分彼女の普通の喋り方なんでしょう。正直、同じ空間にいるのが苦痛になりそうな女性です。
ただ、この母親像は、長男ヴィンチェンツォの婚約者ジネッタのお母さんも非常に似ているので、マンマの割と普遍的な像が描かれているのかも、と感じましたが、どーなんでしょうか。
仕事に行く大のオトナの息子たちに、やれ早く朝食を食べろだの、やれあの上着を着ろだの、とにかく世話を焼きまくる母親。その一方、ドアの呼び鈴が鳴ると息子に「ちょっと出て」などと言って甘える母親。
……嗚呼、子に母親が執着して、子が幸せになる話って見たことがない、、、、と序盤で既に先行きを想像して暗澹たる気持ちに、、、。
序盤の想像どおり、最後まで、生活の全てが息子たち中心に動いていました、この母親は。他にはなーんにもない。ホントに何にもないのです。夫が亡くなって、なおかつ、そういう時代だったとはいえ、それがますます恐ろしい。
◆パロンディ家の三男ロッコ=アラン・ドロン
本作の原題は、“Rocco e i suoi fratelli”。つまり、ロッコとその兄弟。
そのタイトルにもなっているロッコとは、パロンディ家の三男で、演ずるのはアラン・ドロン。本作は、このロッコと、二男シモーネの話を軸に進みます。
ミラノ移住後もなかなか定職が見つからない2人。ボクサーを目指すようになったシモーネと、バイト(?)するロッコですが、この2人が、時間差はあったとはいえ、一人の同じ女性を愛してしまうことから話がどんどん深刻な方向へ。
その女性は、ナディア(アニー・ジラルド)という美しい娼婦。シモーネは適当に遊ばれて捨てられるのだけど、2年後に再会したロッコとは真剣に愛し合うようになるのですよ。で、それを知ったシモーネは激怒するというわけ。
激怒して、シモーネがとった行動が、まあ一言で言えばサイテーです。ロッコとナディアのデート現場に手下数人を引き連れて踏み込み、ロッコの目の前でナディアをレイプする、、、んです。
もうね、、、見てられません、このシーン。もちろん、レイプの凄惨さもあるけれど、ロッコのとった行動が???なんです。「やめろ~~!」って叫ぶけど、体当たりしてでも止めようとはしないのね。おまけに、この事件の後日、ロッコとナディアは教会の屋上で会うのですが、その時、ロッコがナディアに言う言葉が目(字幕)を疑うものなのです。
「兄さん(シモーネ)はまだ君を愛してる。兄さんには君が必要なんだ。だからまた兄と一緒になってほしい。僕はいなくなるから」(セリフ正確じゃありません)
私は、正直、ナディアがこの時、教会の屋上から飛び降りてしまうんじゃないかと冷や汗が流れてドキドキしながら見ていました。それくらい、ナディアを絶望させるロッコの言葉です。幸い、ナディアは飛び降りることなく、泣きながら走り去るだけでしたが、、、。
シモーネとナディアは、肉体的・物理的にはよりを戻すのですが、ナディアの心はシモーネを絶対的に拒否し続ける。それが許せないシモーネは、遂に、彼女を刺し殺してしまう、、、。
ロッコの不思議さは、その後の展開でさらに度を極めて行きます。際限なく堕落していくシモーネの姿に、そうさせてしまったのは元はと言えば自分のせい(ナディアと付き合ったこと)だと嘆き、とことんシモーネのために犠牲になる道を選びます。シモーネよりもボクサーの才能があったロッコは、シモーネの多額の借金を返すため、ボクサーとしてジムと10年契約を結ぶんです。10年間ボクサーが大金を稼ぎ続ける、、、あまりにも非現実的です。
愛する女性を目の前でレイプしたシモーネを赦し、多額の借金をしてそれをロッコに肩代わりさせたシモーネを赦し、挙句の果てにはナディアを殺してしまったシモーネさえ赦そうとするロッコ。
……ロッコよ、あなたは一体、何なんだ? 白痴か神か。
(その②につづく)
★★ランキング参加中★★
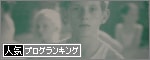














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます