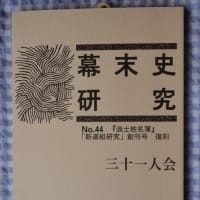三斗小屋宿跡の現況
2012年の5月19日から20日に掛けて、栃木県那須連峰内の三斗小屋宿跡と大峠を訪問してきました。今回の訪問は、昨年の秋に訪問した板室・大田原城址訪問の続きに当たります。戊辰野州戦争の際、会津中街道の宿場町である三斗小屋宿を拠点とした、大鳥圭介率いる旧幕府陸軍と会津藩兵の連合軍(以下、「会幕連合軍」と呼称)の第一大隊は板室・大田原方面への進出を意図するものの、新政府東山道軍に撃退され、三斗小屋宿に撤退します。と、ここまでが前回の訪問での行程です。
三斗小屋宿に後退した会幕連合軍は、以降は麓に降りてる事はなかったものの、8月21日に行われた新政府軍の母成峠攻撃に呼応したのか、白河城在城の新政府軍(黒羽藩兵・館林藩兵)が三斗小屋宿攻略を目指して出陣します。この新政府軍黒羽藩兵・館林藩兵と、三斗小屋宿を守る会津藩兵との間で繰り広げられたのが、三斗小屋宿攻防戦です。結局この戦いは新政府軍の勝利に終わり、更に進軍を続ける新政府軍を防ぐ為に、会津藩兵が布陣したのが会津と野州の国境である大峠です。
今回はこうした野州戦争終盤の戦いの舞台となった、三斗小屋宿跡と大峠の古戦場跡を訪問してきました。本来ならば、三斗小屋宿と大峠の戦いの説明を交えながら画像を紹介させて頂きたい所ですけれども、三斗小屋宿・大峠の両攻防戦はまだ調べた事がないので、今回は画像のみの紹介とさせて頂きます。
当日は沼原湿原の駐車場から出発。旧会津中街道と思われる道を辿って、三斗小屋宿跡を目指します。ただし旧会津中街道と、現在の登山道は異なっている部分が多く、これは旧会津中街道なのかと思いながら歩いて行きました。

そのような中で見つけた、道沿いに建つ地蔵。地蔵が建っていると言う事は、この道が旧会津中街道の可能性が高いと思い、嬉しくなりました。画像は地蔵と、旧会津中街道と重なっていると思われる登山道。

沢に架かる丸太橋。かなり流れの速い沢なので、心もとない橋なのですが、「橋が架かっているだけマシ」とその後実感する事になります・・・。

日本とは思えない、現実離れした美しい風景。一日目はまだ体力に余裕が有ったので、綺麗だなと思った風景を撮影する余裕がありました。

大きい沢である湯川に到着したら、昨年の震災の影響か、崖崩れにより橋が流されていました(汗)。しばし衝撃的な光景に目を疑いましたが、諦めて渡渉する事になります。水が冷たく、沢の流れに足を取られてしまいそうな危険な行為だったものの、非日常的な行為に内心ワクワクしていたりして(^^;)

難所を乗り越え、遂に三斗小屋宿跡に到着。板室側の宿場入口付近に建つ、戊辰戦死若干墓。

戊辰戦死若干墓と旧会津中街道

そして遂に辿り着いた三斗小屋宿跡。ここを訪れる為に、今回の旅に参加したと言っても過言はありません。画像を見て頂ければ判るとおり、決して広いスペースが在った訳ではありませんけれども、那須連峰内では貴重な平地ですので、宿場町が形成されました。
また現在の山道の左側に、かつての水路跡が伺えますが、同行した大山師匠によれば、当時の街道はこの水路の両脇に在ったと言う事です。この為に石灯籠が現在の山道脇ではなく、水路脇に建っているのが判ると思われます。

冒頭に書いたとおり、会幕連合軍の拠点となった三斗小屋宿は、新政府軍と会幕連合軍との戦いに巻き込まれて、その戦火で消失してしまいます。しかし住民の方達の懸命な努力によって一時は復興するものの、高度成長期の昭和32年に全ての住民が下山して廃村になります。当時の建物は全て失われてしまったものの、石灯籠や石仏が多く現存し、ここがかつての宿場町だったと言うのを実感させてくれます。

三斗小屋宿跡の会津側入口に建つ石仏と、白湯山神社(?)の鳥居。江戸時代までは白湯山信仰が盛んだったらしく、この信仰から三斗小屋宿に訪れる人も多かったらしいです。
その後九十九折を登って、本日の宿泊地となる三斗小屋温泉の「煙草屋」に到着。こちらは露天風呂が有名らしく、夜に星空を眺めながらの入浴を楽しむ人も多いらしいものの、疲れ果てていた私は六時には爆睡してしまいました。
さて翌20日、この日の目的は野州・会津(陸奥)の国境である大峠と言う事で、登山開始です。

三斗小屋温泉から大峠に至る山道。山から流れてきた水により、もはや山道なのか沢なのか判りません(汗)。ただしこのような物はまだマシと後に実感する事に・・・。

昨日の渡渉に続いての難所。画像を見ても判りづらいかと思いますが、断崖絶壁になっており、崖上から垂れ下がっているロープを使ってよじ登る事になります(汗)。ただこの時点ではまだ余裕があったので、「川口浩探検隊みたい」と楽しみながら登っていました(^^;)。

江戸時代の頃は石畳が綺麗に敷かれていた会津中街道だったのでしょうけれども、年月による風化により石の全体が露出するようになり、本来ならば歩行を容易にする為の石畳が、今や歩行を阻害する障害物になってしまっています。

石畳が無い道も在るものの、柔らかい土上の山道では、今度は木が生えて進行を阻害します。ところで所々石畳が在ったり無かったりする箇所がありました。これは石畳の無い箇所は、後年登山者が開拓した登山道と言う事なのかしら?。

そんなこんなで、やっとの事で大峠に到着です。右側には大峠の難所を越えようとして命を落とした旅人を弔う石仏が建っています。

大峠に残る塹壕跡。見づらいかもしれませんけれども、画像中央に二本の筋が有るのが見えるかと思います。この内右側が山道で、左側が会津藩兵が掘ったと思われる塹壕跡になります。この塹壕は大峠まで繋がる山道に「丁字」状に掘られており、一列縦隊で進む新政府軍を、横一線で銃撃出来るように掘られています。
こうして塹壕を掘って会津藩兵が布陣する大峠に、三斗小屋宿を占領した新政府軍は8月24日に攻撃を開始します。優れた陣地を築いた会津藩兵だったものの、この陣地を守る戦力は無く、殆ど防戦らしい戦いはせずに会津藩領へ撤退しました。
しかし会津藩兵がこの大峠で決死の防戦をしても、結果は同じだったかもしれません。あまり知られていませんが、この三斗小屋宿・大峠攻略戦に参加した下野黒羽藩兵は、優れた装備を持つ軍勢でした。前藩主が西洋軍事に注目していた事により、戊辰戦争には兵数こそ少ないものの、後装施条七連発銃のスペンサー銃を標準装備とする優良部隊を参加させています。三斗小屋宿・大峠攻防戦にはこの黒羽藩兵が3個小隊派遣されており、これは精神論重視で火力に劣る会津藩兵一個大隊に匹敵する戦力だと思われます。

大峠から南方面を見下ろして。肉眼では確認出来ませんでしたが、この光景の中に三斗小屋宿が在った筈です。

大峠の古戦場跡を確認したので、ここから三本槍岳を抜けるルートを辿る事になるのですけれども、私自身の体力の無さから、この撮影をした後は撮影をする気力が無くなったので、この以降の画像はありません。本当はこの後の三本槍岳~朝日岳~茶臼岳の行程が一番の難所であり、特に朝日岳は非現実的な美しい風景だったのですが、この時は半ば遭難を覚悟していたので、撮影する余裕はありませんでした。今、思えば無理をしてでも撮影しておけば良かったと後悔しているものの、当時は「無事生きて帰れるか」で頭がいっぱいだったので、そこまで頭が回りませんでした。尚、足を引っ張り続けて、それこそ遭難の危機に巻き込んでしまった友人二人には、心からお詫びさせて頂きたいと思います。
そのような訳で、三本槍岳~朝日岳~茶臼岳の画像は撮影出来なかったものの、無事生きて下山出来た事に感謝しながら、今回のレポートを書かせて頂きました。
訪問日
2012年05月19日~20日![]()
にほんブログ村