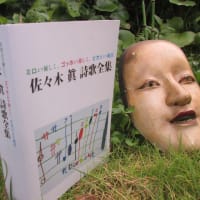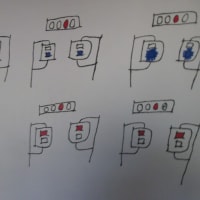照る日曇る日 第1030回
短歌の評論集などほとんど読んだことがなかったのですが、タイトルに魅せられて本書を手に取りました。
子規からアララギ、そして現在にいたる短歌の歴史を、時系列を逆にさかのぼって跡付ける、俯瞰的な書き下ろしの概論を期待していたのですが、そういう体系的なものではなく、私だけが知らない有名歌人への言及や多種多様な時論に混ざっての飛び石的遡行だったのがちょっと残念でした。
しかし短歌における「私性」の問題であるとか、岡井隆がどのようにしてアララギ派の先輩たちの文体との差別化を図ったか、塚本邦雄の前衛短歌において57577の定型がどのように「疎外」されているか、という具体的な分析、佐藤佐太郎の短歌の「あてどなさ」は何に起因しているか、前川佐美雄の戦争責任問題、萩原朔太郎がどういう道行で歌人から詩人に転換したか、等々の著者による論考は、問題提起の鋭さと結論までの明晰な論理展開の切れ味が抜群で、じつに読み応えがありました。
子規に戻ると、驚いたのは彼がはじめは「言文一致」に賛同していなかったということ。山田美妙のように文尾に「です/ます」を使えば、作者と同等もしくはそれ以下の階級の士人を、円朝を真似した二葉亭四迷だと聴衆に相対した落語の語り口になってしまう。文語が備えていたあらゆる人々に対するニュートラル性を失う、というのです。
その後子規は結局「言文一致」体を採用するにいたるのですが、その具体的な経緯についても知りたいと思ったことでした。
なおこの新版の巻末には、著者が選んだ子規の短歌150首がつけられていて久しぶりに通読したのですが、驚いたことにいつものような感動が湧き起ってこなかったことに一抹の寂しさを感じました。
どんな革新的な歌も、時代を超然と貫きながら光輝あまねくすることはやはり難しいのでしょうね。
神社から自宅までが間に合わずパンツに漏れたぞビチビチウンコ 蝶人