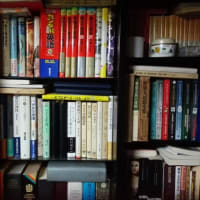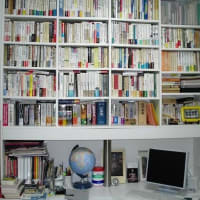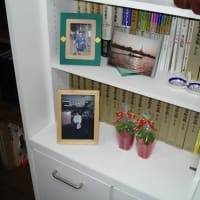下記(↓)前稿では<伝統>が社会的に生成される経緯を一瞥しました。本稿はその「復習」から書き起こし、世の移り変わりとともに変化しつつも<伝統>がその同一性を保持しながら再構築される構図を検討してみたいと思います。而して、<世間=社会>が<伝統>の同一性の基底であること、他方、その変化が臨界点を超える場合、<世間=社会>の変化は<伝統>を最早<伝統>ではないもの、すなわち、「生きられてある世界」を構成する風景の一部にしてしまう経緯を確認すること。これが本稿の獲得目標です。
・風景が<伝統>に分節される構図-靖国神社は日本の<伝統>か?
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/87aa6b70f00b7bded5b801f2facda5e3
【MV】僕たちは戦わない Short ver. / AKB48[公式]
◆再論-伝統生成の構図
蓋し、「何が伝統であり、何が伝統ではないのか?」「何が伝統として尊重されるべき事象であり、何がそうではないのか?」これらの問いに、自他共に納得できる解答を出すことはそう容易なことではありません。
例えば、ある論者は「日本は万世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠に存在する。この大義に基づいて億兆一心、忠孝の美徳を発揮するものだ。これこそ我が国体の精華であり、永遠不変、国史を貫く伝統である」と厳かに宣言される。他方、別の論者は「憲法9条は国是であり戦後日本を戦争から守ってきた伝統である」とのたまう。けれど、彼等は共に(そうは考えないという他者を納得させられる)根拠を何も提示することができない。
新カント派の方法二元論を持ち出すまでもなく「Sein-Sollen:事実-当為」の両者を巡る議論はその位相を異にする。ゆえに、(それらの主張が現在の歴史学や国際政治学の知見からは極めて怪しいことは別にしても)、たとえ2670年の間、あるいは、65年の間これらの論者の謂わゆる「国体」や「国是」なるものがこの社会で尊重されてきたとしても、その事実をもって明日も日本人がその「国体」や「国是」なるものを尊重すべきであるとは言えないのです。
では、「何が伝統か?」の問いに対してどのような構えで臨めばよいのか。蓋し、その要諦は、我々は<伝統>を巡る言語ゲームを通して、「何が伝統か」「誰が伝統と伝統以外のものを識別するのか」という<伝統>確定のルールを感得し体得するしかないということ。そして、そのルールは<物語の編み物>という形態を取りながら間主観性を帯びる公共的な性格のものであり、<私>にとって規範的拘束力をも持っているということです。而して、その理路は次の通り、
(甲)「何が伝統か」を感得できるのはこの世に私の自我たる<私>だけである
(乙)「何が伝統か」を感得するための資料は、<私>にとっての「生きられてある世界」(生活世界)内の、かつ、(その存在を最早疑いようもないと<私>に感じられる)不可疑性を帯びる事柄、畢竟、<伝統>を巡る言語行為に限られる
(丙)<伝統>を巡る言語行為を包摂する言語ゲームの中で<伝統>を確定するルールが生成され、しかる後、そのルールに則った新たな言語ゲームの中で次世代のルールが再生成され、このルール再生産のプロセスは順次継続していく
(丁)<伝統>を確定するルールは、「何が伝統か」を記述する1次ルールと、「誰がどのような手続でルールを制定・修正・解釈できるのか」を記述する2次ルールの結合として<私>の現前に立ち現われる
(戊)<伝統>を確定する2次ルールの内容は、「現象学に言う「他我構造」を通して、<私>が<我々>と看做す同じ<世間=社会>のメンバーの社会的意識として、すなわち、間主観性を帯びたものとして、かつ、言語ゲームを通して<私>に了解される」というもの
(己)<伝統>を確定する1次ルールの内容は、「ある<世間=社会>のメンバーとしての自己同一性を保持する<我々>が形成する、社会的意識に定礎された当該<世間=社会>コミュニティーメンバーの行為慣行」と言える
敷衍すれば、(甲)の独我論的の構えは<私>が霊能力者でも超能力者でもないことを前提にすれば不可避かつ唯一の出発点でしょう。「国体」なり「国是」なりがアプリオリにそれらの内容が普遍的に確定したものとしてこの日本列島の中空を漂っているわけではないのですから。ならば、(乙)~(丁)で述べた如く、<伝統>をこの社会の風景から切り取るためには、その存在や価値が<私>にとって疑いようもない言語ゲームの戯れを構成する言語行為の観察による他はないことになる。
而して、(戊)2次ルールと(己)1次ルールの確定作業の前哨として、ルールが<私>にとって規範的拘束力を及ぼし得るための条件は何かという検討が不可避になる。蓋し、<私>がその運命共同体のメンバーであると<確信>している<世間=社会>で、そのルールに従うことが<私>のアイデンティティーの根拠になるという契機を欠けば、<私>にとってそのルールは規範的拘束力も持ちえないという経緯がその条件であろうと私は考えています。
尚、(戊)の「他我構造」とは「他者も<私>に立ち現われる<私>の生活世界内の存在であり、かつ、他者は<私>が<私>と同型の「認識者-行為者」と「理解=解釈」した存在にすぎない」という程の意味です。畢竟、この「他我構造」を通して、<私>の「理解=解釈」に<私>は'''間主観性'''を覚えることになる(誤解なきように、「理解=解釈」が帯びる間主観性という性質は<私>にとっての評価に過ぎず、これまた、アプリオリにこの日本列島を間主観性を帯びた「国体認識」や「国是概念」が覆っているわけではないのです)。
◆伝統の可変性と同一性
前項の(丙)で述べた如く、<伝統>を巡るルールは言語ゲームの戯れの中で変化していく。蓋し、保守主義とは「伝統の恒常的な再構築の営みである」と私は考えていますが、(丙)の認識はこのことを<伝統>の側面から表現したものに他なりません。では、例えば、所謂「憲法改正の限界」の如き意味で<伝統>の変化に限界はないのでしょうか?
すなわち、刑事訴訟法や民事訴訟法では、訴訟対象論(訴因・公訴事実や訴訟物を巡る議論)において、証拠や新事実の発見、あるいは、法規解釈の修正にともない訴因や請求の変更があった場合、ある訴えが同一性を保持するかどうかが問題になりますが、事実の変化や<我々>の社会的意識の変遷が<伝統>の同一性を掘り崩したりそれを単なる風景の一部に格下げにすることはないのでしょうか。蓋し、
(a)甲子園の高校野球大会を、選手の健康と公平性を考えて、①出場校を64チームにして2回戦からの参戦組と1回戦からの登場組の不公平を解消する、②試合は1回戦から準々決勝までは、大阪・名古屋の2ドーム球場で行い、準決勝・3位決定戦・決勝の4試合は大阪ドームで行なう。(b)所謂「女系天皇」を認める。(c)捕鯨活動と鯨食を違法にする、等々。
例えば、これらの変化は<伝統>の同一性を失わせるものでしょうか。
結論から言えば、これら(a)~(c)が<伝統の再構築>であるか<伝統の破壊>であるかは、どこまでも「他我構造」の内部に置かれた<我々>が間主観性を覚えるこの日本社会の社会的意識の「理解=解釈」に収斂すると思います。蓋し、真夏の甲子園球場で繰り広げられるからこそ夏の甲子園大会は<伝統>として価値があると考える<我々>が少なくないからこそ現在に至るまでそれは続いてきているのでしょう。
いずれにせよ、ここで補足すべきは次の2点、
(α)<伝統>の重層性と相互連関性
それに直接係わる<我々>が少ないからといって、その事象が<伝統>ではないとは言えないということ
(β)<伝統>の体系性と民族国家性
近代国家成立以降の日本の<伝統>が、「日本国民=日本人」という国家規模の「間主観性=共同性」に底礎されている以上、日本の<伝統=物語の編み物>もまた、(単に(α)のエスニカルな契機だけではなく)ナショナル契機を帯びた国民国家の身の丈サイズの<伝統>ということ
蓋し、実は、高校野球に関心のない人々も稀ではない。まして、流鏑馬や薪能を演じたこと、否、見たことさえある日本人は極少数でしょう。しかし、それらが日本の<伝統>の一斑であることを否定する人もそう多くはないのではないか。畢竟、<伝統>の構成要素は単体で存立するものではなく、フッサールの言う意味での生活世界と伝聞の世界と神話的世界の三者を覆う広範な<物語の編み物>の一部なのです。而して、<伝統>の各要素はその編み物の内部で相互に連関しており、ならば、日本の<物語の編み物>にその座を占めている限りは、流鏑馬も薪能も、捕鯨と鯨食も日本の<伝統>と言えるのです。
他方、女系天皇の是非を定める<我々>の社会的意識は日本国を統合している<政治的神話=皇孫統べる豊葦原之瑞穂國のイデオロギー>と共鳴している。畢竟、皇室を巡る<伝統>は、それがナショナルな契機を媒介にしているがゆえに、日本の<伝統=物語の編み物>の中で要の位置を占めていることだけは明らかであろうと思います。尚、女系天皇を巡る私の基本的な考えについては下記拙稿をご参照ください。
・女系天皇は憲法違反か
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/3ab276729a79704d3dbe964193ad5261
・法とは何か☆機能英文法としての憲法学
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/da03dfc063c48a57b2332e17c3871d18
【MV full】ギブアップはしない / AKB48[公式]
最後に確認すべきは<伝統>の基底たる<世間=社会>の変遷と様相のこと。
而して、<伝統>とはそのコミュニティーを運命共同体と感じている<我々>の社会的意識とその社会的意識に定礎された行為慣行である。ならば、「大東亜戦争で沖縄は本土の犠牲になった」などとのたまう人々は、彼等が「沖縄≠日本」と考えているだろう段階で、すでに日本の<伝統>を確定する資格を有する<我々>ではない。畢竟、彼等は、運命共同体としての日本に帰属することに自己のアイデンティティーを感じる<我々>ではなくなっており、よって、<伝統>を遵守尊重することで自己のアイデンティティーを確認する<我々>でもないということです。
蓋し、人口に膾炙している「沖縄には在日米軍基地の70%がある」というのは「沖縄には在日米軍専用施設の44%、(自衛隊との共同利用施設等々も算入すれば)、在日米軍の全施設の18%がある」の間違いであることを不問に付すとしても、このような論法は、「東京には国会議事堂の100%がある」という命題同様それ自体としてはなんら、同盟国アメリカと自衛隊員諸君に対して無礼極まりない沖縄の「非日的-反日的」の社会意識を正当化するものではない。地勢も歴史も非対称的な現在の都道府県の領域が単一の国民国家を形成した以上、沖縄県民の戦中と戦後もまた、日本人たる沖縄県民がその「地政学的条件-歴史的背景」からして必然的に甘受するしかなかった体験であったと言えるだろうからです。
ならば、「沖縄は独立するべきだ」と多くの沖縄県民が考えるのならば、沖縄が<我々>の<世間=社会>でなくなるのなら、日本の<伝統>を担う意志も資格も欠いている彼等に対しては、「どうぞご自由に」と言う他はない。と、感情的な排除の論理からではなくそう私は考えます。再見沖縄?
・刺青慕情-<伝統>の伝播と盛衰を考えるための覚書
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/c58d92ace7518c147ec060e4020253d8